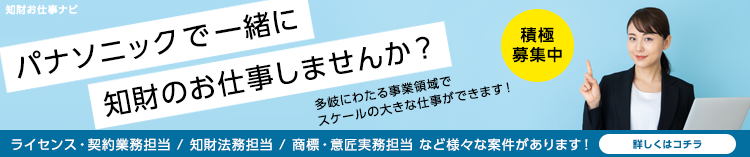| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
平成
30年
(ネ)
10061号
不当利得返還請求控訴事件
|
|---|---|
|
控訴人(一審原告 )X 被控訴人(一審被告) 株式会社マコメ研究所 同訴訟代理人弁護 士伊藤真 平井佑希 丸田憲和 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2019/01/15 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成28年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
1 事案の経緯等 (1) 本件は,控訴人が,①被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,②控訴人はテクノ東郷から前記①の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2) 原判決は,①本件特許権の権利者であるテクノ東郷は本件特許を被控訴人が実施することについて黙示に許諾していたと認められ,また,②控訴人がテクノ東郷から特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の譲渡を受けたとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 (3) 控訴人は,原判決を不服として控訴した。 2 前提事実 本件の前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)は,原判決3頁3行目~5行目を,次のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2に記載のとおりである。 「 イ テクノ東郷は,平成23年12月8日,控訴人に対し本件特許権の持分2分の1を譲渡した(甲10,11)。 本件特許権は,平成25年12月7日,年金不納付により消滅した(甲11)。 テクノ東郷と控訴人は,平成28年8月4日,テクノ東郷が控訴人に対し本件特許権の持分2分の1を無償で譲渡する旨の「特許権の持分譲渡契約書」に署名捺印した(甲9)」 。 3 争点 本件の争点は,原判決4頁21行目の「損害」を「損失」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2)及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決9頁5行目に「原告は」とあるのを「原告が」と改める。 イ 原判決9頁7行目に「損害」とあるのを「損失」と改める。 ウ 原判決9頁13行目~14行目に「1800万となる(特許法102条3項)」とあるのを「1800万円であり,被告はこれと同額の利益を受け,その 。 ために原告は同額の損失を被った。」と改める。 エ 原判決9頁17行目に「支払を求める。」とあるのを「支払を求めることができる。」と改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 争点(3)(特許権者による無償実施許諾の有無)について (ア) 原判決は,控訴人が,平成17年5月の時点においてイ号物件が本件発明の構成要件を充足すると認識していながら,その後もイ号物件の製造に主導的に関与し,平成19年2月に同物件が完成し,納入された後までその製造の中止や実施料の支払を求めていないことによると,控訴人は被控訴人が本件特許を実施することについて黙示に許諾していたと認めるのが相当であると判断したが,次のとおり,その認定・判断は誤りである。 a 原判決は,平成17年5月30日に控訴人が被控訴人に対しイ号物件の仕様書案の「観測機器の製作」等の部分の補充を指示し,同月31日に被控訴人が控訴人に対し補充後の仕様書案を送付し,控訴人がこれを見てイ号物件が本件発明の構成要件を充足し本件特許の実施に当たることを認識したと認定した。 しかし,控訴人が静岡県が発注を決めたイ号物件の詳細を知らされたのは,平成18年6月2日である(甲2)。被控訴人は,静岡県の担当者と共にイ号物件の仕様書案を作成して控訴人に送付したことから,遅くとも同年3月頃にはイ号物件の技術の詳細等を把握し,特許権者の許諾を得る義務が課されていた事実を認識できたはずである。その時期は控訴人がイ号物件の技術の詳細を知る約3か月前であったが,被控訴人は特許権者の許諾を得ようとはしなかった。非は被控訴人にある。 b 原判決は,控訴人が,被控訴人に対し,菊川観測点に設置する歪計,傾斜計については新型センサーユニットを採用し,このセンサーユニットを装着できる歪計ユニットをテクノ菅谷に製作させ,部品レベルで被控訴人に納入させることを指示したなどと認定した。 しかし,センサーユニットの採用は,「イ号物件特有の技術の採用」ではなく,他の製品(南ア用や核燃料サイクル機構用等)に使用する汎用のセンサーユニットである。被控訴人は,イ号物件になくてはならない特別な技術であるとの主張はしていない。 c 原判決は,控訴人が,平成18年4月27日の菊川観測点向け「デジタル式2連地殻活動総合観測装置」についての打合せにおいて,データロガーのデータを転送する場合,電波若しくは光通信で切り離しておいてほしいなどと依頼したと認定した。 しかし,イ号物件にはデータロガーはないから,イ号物件にかかわる事実との認定は誤りである。南ア用(立命館大学の発注品)のデータロガーにかかわることである。 d 原判決は,控訴人が平成18年6月頃に菊川観測井向け模擬試験の項目について指示を与えるなどしたこと,控訴人が同年9月27日~10月3日の2回目の模擬試験で代替品の使用を承認するなどしたこと,控訴人が同年12月13日及び20日の中間検査に立ち会ったことを黙示の許諾の判断の基礎とした。 しかし,これらはイ号物件の設置工事にかかわることであり,本件訴訟の対象で あるイ号物件の製造・販売とはかかわりがない。 e 原判決は,「みなし公務員であった控訴人に対し,民間企業の代理人として営利活動ができたのであるが営利活動をしなかった」として,非が控訴人にあると判断したが,みなし公務員であった控訴人に対し「職務に専念する義務」を放棄し,テクノ東郷の代理人として「実施料の支払いを求める」等の営利活動をするべきであった,すなわち,控訴人が犯罪を犯すべきであったとするのは誤りであり,この「犯罪を犯すことを奨励するような判断」は訂正されなければならない。 (イ) 原判決は,①テクノ東郷の代表者が控訴人の実兄であること,②控訴人が平成13年頃にテクノ東郷の有する他の特許権の通常実施権の許諾に係る契約に関与しており,この当時からテクノ東郷が控訴人にその有する特許権の行使を委ねていたことがうかがわれること,③控訴人が被控訴人に対しイ号物件が本件特許権を侵害する旨の平成21年1月22日付け通告書を送った際も,テクノ東郷の代理人である旨を明示していること,④テクノ東郷も被控訴人に対し平成22年1月6日付け書面において,本件特許権等に関する問題は控訴人に委任しており,今後は控訴人に連絡するよう求めていることなどに照らすと,テクノ東郷は,イ号物件の製造当時において,本件特許の実施に関する意思決定を控訴人に包括的に委ねていたものと認めるのが相当であると判断したが,次のとおり,その認定・判断は誤りである。 a 原判決は,控訴人が平成13年1月31日付けのテクノ東郷・被控訴人間の契約書原案を作成し被控訴人に交付したと認定した。 しかし,原案の交付者はテクノ東郷であり,控訴人は,原案を手渡したにすぎない。控訴人が手渡した原案をテクノ東郷の代表者と被控訴人の代表者が修正後,契約書として完成させて署名捺印したのである。 また,テクノ東郷が,平成13年1月31日以降,その有する特許権に関する問題を全て控訴人に委任していた旨の被控訴人の主張は,立証されていない。控訴人 は,平成13年当時は公務員であり,「職務に専念する義務」を課され副業は禁じられていたから,特許権に関する実施の許諾等の委任を受けるはずがない。 さらに,上記契約書は,本件特許権とは無関係な技術にかかわる契約書であって,被控訴人がイ号物件を製造販売した平成19年2月から約6年前に作成されたものであるから,本件特許権に関する問題を全て控訴人に委任していた旨の根拠にはならない。 b 原判決は,控訴人作成の平成21年1月22日付け通告書,テクノ東郷作成の平成22年1月6日付け書面を,イ号物件の製造当時の控訴人に対する委任の根拠とした。 しかし,これらは,いずれも控訴人が名古屋大学を退職し,民間人となった平成20年3月以降に作成された書類である。イ号物件が製造販売された平成19年2月当時は,控訴人はみなし公務員であり,民間企業の営利活動をすることは禁じられていた。これらの書類により,時間的な前後関係を逆転させ,控訴人がみなし公務員であった時期の証拠とすることは,不当である。 イ 争点(4)(テクノ東郷から原告への不当利得返還請求権の譲渡の有無)について 控訴人は,特許原簿記載のように特許権者であるテクノ東郷から持分を譲渡され,その際に,持分に相当する不当利得返還請求権も譲り受けた。また,特許原簿に移転登録できない特許権者の持分に係る上記請求権も,公証人の面前で特許権の持分と共に譲り受けた(甲9~11)。これらの事実は,新たに提出した甲18から明らかである。 (3) 被控訴人の主張 ア 争点(3)(特許権者による無償実施許諾の有無)について (ア) 控訴人は,原判決が,控訴人に対し職務専念義務を放棄し,テクノ東郷の代理人として実施料の支払を求める等の営利活動をするべきであったとしたことは誤りであるなどと主張する。 しかし,控訴人は,イ号物件が本件特許権の侵害に当たると認識したのであれば,被控訴人に対する指示を行う立場から,本件特許権の侵害という結果を避けるために,被控訴人に対して設計の変更を促すなどして本件特許権を侵害する態様での製造を中止させたり,実施料の支払を行う必要がある旨を指摘するなどして,実施料の支払を促すことができた。 また,控訴人がテクノ東郷の代理人として被控訴人に対して製造の中止や実施料の支払を求めたとしても,無報酬で行えば,営利活動にはならない。 (イ) 控訴人は,控訴人が平成20年3月まで職務専念義務を負っていたから,テクノ東郷から特許権に関する実施の許諾等の委任を受けるはずがないなどと主張する。 しかし,控訴人が本件特許権の実施に関する意思決定を業として行っていたのかどうかや,本件特許権の実施に関する意思決定を行うことが,職務専念義務に違反するかどうかは明らかでないし,そのような義務や義務違反の存否と黙示の許諾の有無は無関係である。 公務員として職務専念義務を負うことから,その者が職務専念義務をすべからく遵守することが導かれるわけではない。また,職務専念義務の内容は,勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用いるというものであるから,控訴人がテクノ東郷から本件特許権の実施に関する意思決定を包括的に委ねられることが必ずしも職務専念義務に反することにはならない。 (ウ) 控訴人は,平成13年1月31日付けのテクノ東郷・被控訴人間の契約書(乙11)は,本件特許権とは無関係な技術にかかわる契約書であり,本件特許権に関する問題を全て原告に委任していた旨の根拠にはならないなどと主張する。 しかし,原判決は,乙11を交付したことのみをもって黙示の許諾を認定しているわけではない。また,乙11は,テクノ東郷が保有していた,本件特許権とは別の特許権に関する,テクノ東郷と被控訴人との間の契約書案であり,これを控訴人 が被控訴人に交付した事実からは,テクノ東郷が保有する他の特許権の通常実施権の許諾に係る契約に関与していたことが理解できるから,テクノ東郷が控訴人に対しテクノ東郷が保有する特許権の行使を委ねていたことをうかがわせる証拠となり得る。 (エ) 控訴人は,控訴人作成の平成21年1月22日付け通告書,テクノ東郷作成の平成22年1月6日付け書面により,時間的な前後関係を逆転させ,イ号物件が製造販売された平成19年2月当時の証拠とすることは,不当であるなどと主張する。 しかし,イ号物件が製造販売された以降に作成された文書であっても,そこから本件に関係する事実を認定することはできる。 イ 争点(4)(テクノ東郷から原告への不当利得返還請求権の譲渡の有無)について 控訴人が主張する甲9~11,18により,控訴人が不当利得返還請求権の譲渡を受けたことを認めるには足りない。 |
|
|
当裁判所の判断
当裁判所も,イ号物件が製造・販売された平成19年当時の本件特許権の特許権者であったテクノ東郷は,被控訴人がイ号物件の製造・販売において本件特許を実施することについて黙示に許諾していたと認められるから,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。その理由は,下記1のとおり原判決を補正し,下記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を示すほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第4の1及び2(9頁26行~17頁23行)に記載のとおりである。 1 原判決の補正 (1) 原判決11頁26行の「構成を採ること」の直後に「に」を加える。 (2) 原判決13頁9行に「仕様書」とあるのを「仕様書案」と改める。 (3) 原判決15頁19行目の「その製造の中止や実施料の支払を求める」を 「テクノ東郷をして,その製造の中止や実施料の支払を求めさせる」と改める。 (4) 原判決15頁23行目~24行目の「イ号物件の製造の中止や実施料の支払を求める」を「テクノ東郷をして,イ号物件の製造の中止や実施料の支払を求めさせる」と改める。 (5) 原判決16頁11行目~12行目の「納入された後までその製造の中止や実施料の支払を求めていない」を「納入された後まで,テクノ東郷をして,その製造の中止や実施料の支払を求めさせていない」と改める。 (6) 原判決16頁21行目の「関与しており,」を「関与していること」と改め,同行目の「この当時から」から同頁23行目の「こと」までを削る。 (7) 原判決17頁17行目~19行目の「原告は本件特許権の実施料の支払を請求し得る立場にあったというべきであり,」を削る。 2 当審における控訴人の補充主張に対する判断 (1) 控訴人は,被控訴人が本件特許を実施することについて控訴人が黙示に許諾していたとの認定・判断は,誤りであると主張する。 しかし,次のとおり,理由がない。 ア 証拠(甲14の1・2,乙10)によると,平成17年5月30日に控訴人が被控訴人に対しイ号物件の仕様書案の「観測機器の製作」等の部分の補充を指示したこと,同月31日に被控訴人が控訴人に対し補充後の仕様書案を送付したことが認められる。そして,証拠(原告本人〔6頁〕)によると,控訴人は,イ号物件の仕様書を見たときに,イ号物件が本件発明の構成要件を充足することを直ぐに認識したというのであり,その時期も,平成19年2月から遡って1年半ぐらい前であるというのであるから,控訴人は,平成17年5月31日に送付された仕様書案を見て,イ号物件が本件発明の構成要件を充足すると認識したと認められる。 イ 証拠(乙6)によると,控訴人が,被控訴人に対し,菊川観測点に設置する歪計,傾斜計については新型センサーユニットを採用し,このセンサーユニットを装着できる歪計ユニットをテクノ菅谷に製作させ,部品レベルで被控訴人に納 入させることを指示したことが認められる。この事実は,控訴人がイ号物件の開発,製造に対して関与したことを基礎付けるものであり,そのことは,センサーユニットがイ号物件特有の技術であるかどうかで左右されるものではない。 ウ 証拠(乙5の7)によると,控訴人が,平成18年4月27日の菊川観測点向け「デジタル式2連地殻活動総合観測装置」についての打合せにおいて,データロガーを転送する場合,電波若しくは光通信で切り離しておいてほしいなどと依頼したことが認められる。乙5の7は,被控訴人従業員作成の業務日報であって,日常業務の一環として作成されたものであるところ,その体裁は,打合せ毎に,その参加者,打合せの内容が区別して記載されているものである。そして,上記依頼は,同日に行われた立命館大学の関係者らとの「南アフリカ向け3成分歪計及びデータロガー」についての打合せではなく,菊川観測点向け「デジタル式2連地殻活動総合観測装置」についての打合せとして記載されているのであるから,その内容は十分信用することができる。 エ 控訴人が平成18年6月頃に菊川観測井向け模擬試験の項目について指示を与えるなどしたこと,控訴人が同年9月27日~10月3日の2回目の模擬試験で代替品の使用を承認するなどしたこと,控訴人が同年12月13日及び20日の中間検査に立ち会ったことは,控訴人が平成17年5月31日頃にイ号物件が本件発明の構成要件を充足すると認識した後も,イ号物件について,これを製造・販売した被控訴人と複数回にわたり現に接触していたにもかかわらず,イ号物件の製造の中止や実施料の支払を求めるなどの行動に及んだことがないことを示すものであるから,上記事実がイ号物件の設置工事にかかわることであることは,控訴人が黙示の許諾をしていたとの判断を左右するものではない。 オ(ア) 前記補正して引用する原判決が判示するとおり,控訴人が発明者であり,テクノ東郷が特許権者となっている特許権は,本件特許の他にも複数あるが(乙17),これは,控訴人が所属していた名古屋大学が,控訴人が職務上した発明について,職務発明として同大学が特許を取得するのではなく,控訴人が個人と して特許を取得することを容認していたこと,しかし,控訴人個人で特許の維持コストを負担することが困難であったことから,特許の維持コストを負担してくれる企業を探したものの見つからず,実兄が経営するテクノ東郷に特許の維持コストを負担してもらうことが多かったことによるものである(乙1,27,原告本人〔4頁〕。そして,名古屋大学は,同大学が特許を取得せず,控訴人が個人として特許 )を取得する場合には,その特許の実施料を得ることを制限していなかった(甲13,乙1,原告本人〔15頁〕。 ) (イ) 控訴人は,みなし公務員であったから,テクノ東郷の代理人として本件特許権の実施料の支払を求める等の活動をすることはできなかったと主張する。 しかし,本件特許権は,前記(ア)で認定したようなものであり,また,控訴人は,イ号物件が本件発明の構成要件を充足すると認識していた。それにもかかわらず,控訴人は,長期間にわたり,テクノ東郷をして,イ号物件の製造の中止や実施料の支払を求めさせなかったのであるから,このことは,控訴人において被控訴人がイ号物件の製造・販売に当たり本件特許を実施することについて黙示に許諾していたことを基礎付けるというべきであって,テクノ東郷をして,イ号物件の製造の中止や実施料の支払を求めさせることが控訴人のみなし公務員としての職務専念義務に違反するということはできない。なお,イ号物件は,控訴人がその当時所属していた名古屋大学において,控訴人が主たる責任者となっていた観測に使用するものであったこと(原告本人〔1頁~2頁〕)も,控訴人による黙示の許諾に沿うものということができる。 (2) 控訴人は,テクノ東郷が,イ号物件の製造当時において,本件特許の実施に関する意思決定を控訴人に包括的に委ねていたとの認定・判断は,誤りであると主張する。 しかし,次のとおり,理由がない。 ア 証拠(乙1,11~13)によると,テクノ東郷・被控訴人間の平成13年1月31日付け契約書(乙11)は,控訴人が発明者である発明についての特 許権(特許権者はテクノ東郷)に関するもので,控訴人が原案を作成して被控訴人に交付するなど控訴人が「仲立ちをして」締結されたものであることが認められ,控訴人が,単にテクノ東郷の使者として,契約書原案を被控訴人に手渡したにすぎないとは認められない。 そして,上記契約書は,控訴人が発明者であり,テクノ東郷が特許権者となっている特許権を対象とする点において,本件特許権と共通の性質を有する対象を扱うものであって,前記(1)オの事実を併せ考慮すると,控訴人においてイ号物件が本件発明の構成要件を充足すると認識した平成17年5月頃から約4年前の平成13年の事実であるものの,控訴人が,その当時からテクノ東郷が特許権者となっている特許権の行使に深くかかわっていたことを示すものということができ,テクノ東郷が,イ号物件の製造当時において,本件特許の実施に関する意思決定を控訴人に包括的に委ねていたことを推認することができる重要な事実ということができる。 イ 控訴人作成の平成21年1月22日付け通告書(乙15の1),テクノ東郷作成の平成22年1月6日付け書面(乙14)は,いずれも,それらの書面作成当時,テクノ東郷が有する本件特許権の行使が控訴人に委ねられていたことを内容とするものであるから,それ以前にも本件特許権の実施に関する意思決定が控訴人に委ねられていたことに沿うものであって,テクノ東郷が,イ号物件の製造当時において,本件特許権の実施に関する意思決定を控訴人に包括的に委ねていたことを推認することができる重要な事実ということができる。 ウ 前記(1)オの事実に照らすと,テクノ東郷が本件特許権の実施に関する意思決定を控訴人に包括的に委ねていたからといって,そのことが直ちに控訴人の職務専念義務に違反するということはできない。 |
|
|
結論
以上によると,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 森義之 |
|---|---|
| 裁判官 | 森岡礼子 |
| 裁判官 | 古庄研 |