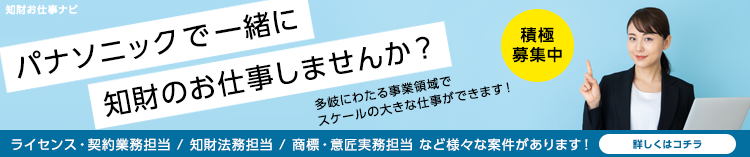| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行ケ)
10022号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
5 原告沢井製薬株式会社 同訴訟代理人弁護士 小松陽一郎 大住洋 10 千葉あすか 小山秀 中田健一 被告科研製薬株式会社 15 同訴訟代理人弁護士 末吉剛 高橋聖史 瀬戸一希 同訴訟代理人弁理士 山口晶子20 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 25 特許庁が無効2023-800002号事件について令和6年2月7日にした審 決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。争点 は、進歩性に関する認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 5 被告は、平成11年7月28日(以下「本件優先日」という。)に出願された特許出 願(特願平11-214369号。以下「基礎出願」という。)に基づく国内優先権を 主張して、発明の名称を「病原微生物および抗微生物剤の検出法、抗微生物剤の薬効 評価法ならびに抗微生物剤」とし、平成12年7月11日を出願日(以下「本件出願 日」という。)とする特許出願をして(以下、出願時の願書に添付した明細書、特許請 10 求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。また、以下、 【】の記号を用いた ものは、本件明細書等に記載された特許請求の範囲の請求項の番号、発明の詳細の説 明の段落番号又は図面の番号を示す。、平成21年11月27日、特許権の設定登録 ) (特許第4414623号。請求項の数1。以下、この特許を「本件特許」という。) を受けた(甲107、112)。 15 原告は、令和5年1月11日、本件特許につき無効審判請求をした(甲94。無効 2023-800002号事件)。 被告は、上記無効審判請求事件において、令和5年4月6日付けで、本件特許の特 許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(甲95。以下、この訂正を「本件訂正」 という。。 )20 特許庁は、令和6年2月7日、本件訂正を認めた上で、「本件審判の請求は、成り 立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月16日、 原告に送達された。 原告は、令和6年3月11日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載 25 本件訂正後における本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりで ある(以下、訂正後の請求項1記載の発明を「本件訂正発明」という。また、本件訂 正発明のうち、化学名(一般的名称:エフィナコナゾール。甲68)の部分を「KP- 103」ということがある。。 ) 「(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペ リジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール-1-イル)ブタン- 5 2-オールまたはその塩を有効成分として含有する外用爪真菌症治療剤であって、爪 真菌症が爪白癬である、前記治療剤。」 3 本件審決の理由の要旨 本件審決は、原告が主張する無効理由1(甲1の1(Abstracts of the 36th ICAAC, 1996, p.113, F78-F80)を主引用例とする進歩性欠如)及び無効理由2(甲1の2(特 10 許第2768830号公報)を主引用例とする進歩性欠如)のいずれも理由がないと した。その理由の要旨は、次のとおりである。 (1) 優先権主張の効果について 本件特許については基礎出願に基づく国内優先権が主張されている。しかし、基礎 出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に本件訂正発明が記載されているとはいえな 15 いから、本件訂正発明は、基礎出願に基づく優先権主張の効果を享受することはでき ない。したがって、本件訂正発明の進歩性の判断の基準日は、本件優先日ではなく、 本件特許の現実の出願日である平成12年7月11日(本件出願日)となる。 (2) 本件出願日当時の周知技術及び技術水準の認定 ア 表在性白癬は、真菌の一つである皮膚糸状菌(皮膚糸状菌のうちトリコフィト20 ン属のものが白癬菌)が毛髪、爪及び皮膚角質層で増殖することにより生じる疾患で、 頭部白癬、体部白癬、股部白癬、足白癬、手白癬、爪白癬などがあること、爪白癬の ほとんどは、トリコフィトン・ルブルム(8割強)及びトリコフィトン・メンタグロ フィテスが原因菌であることは、本件出願日当時、いずれも周知であった(以下「技 術常識A」という。。 ) 25 イ 本件出願日当時、爪と毛髪が、いずれも硬ケラチンを含み、アミノ酸組成も互 いに類似することは周知であった(以下「技術常識B」という。。 ) ウ 本件出願日当時、外用剤による爪白癬の治療を効果的に行うためには、抗真菌 剤を爪甲の角質内に浸透させ、爪白癬の原因菌が存在する爪甲下層と爪床へ抗真菌剤 を送達させる必要があるところ、爪甲は、皮膚と比べて硬く、厚く緻密であり、抗真 菌剤がその内部まで浸透(透過)しにくいことから、爪白癬の外用剤での治療は非常 5 に困難で、一般的に無効であるとされ、そのような状況下、爪白癬の治療には内服薬 が第一選択になっていた(以下「技術常識C」という。。 ) (3) 無効理由1(甲1の1を主引用例とする進歩性欠如)について ア 甲1-1発明の認定 甲1の1には、次の発明(以下「甲1-1発明」という。)が記載されている。 10 「新規外用抗真菌剤トリアゾールである、以下の化学構造を有するKP-103を有効成 分として含有し、皮膚への塗布により投与して皮膚糸状菌症に対する治療効果を有す る溶液であって、皮膚糸状菌症が足白癬である、溶液。 」イ 相違点1の認定 15 本件訂正発明と甲1-1発明を対比した結果、両発明は次の点において相違する (以下「相違点1」という。。 ) 「治療対象が、本件訂正発明では「爪真菌症」である「爪白癬」と特定されている のに対し、甲1-1発明では「皮膚糸状菌症」である「足白癬」と特定されている点。」 ウ 相違点1についての検討 20 (ア) 本件出願日当時の外用爪白癬治療剤に関する技術水準を検討する。 爪白癬は難治性の疾患として知られ、経口剤では肝障害等の副作用の問題があった ため、外用剤の開発が望まれてきた。 しかし、先に認定した技術常識Cを考慮すると、抗真菌剤であるチオコナゾールに つき外用で爪真菌症に有効であることが報告され、塩酸アモロルフィンなどの抗真菌 5 剤の爪浸透性を高めることのできる被膜形成性抗真菌剤組成物が知られ、抗真菌剤の 爪浸透性を高める手法が提案されていたとの事情を考慮しても、爪白癬の外用剤での 治療は非常に困難で、一般的に無効であると当業者は認識していたといえることか ら、甲1-1発明のKP-103という特定の抗真菌剤が、爪の内部まで浸透(透過)でき、 治療効果を奏する外用剤として爪白癬に適用できることを当業者が予測することは、 10 困難であったといえる。 (イ) 次に、KP-103について知られていた知見についてみる。 甲8(Chem. Pharm. Bull., Vol.47, No.10, p.1417-1425 (1999))及び甲27 (Abstracts of the 36th ICAAC, 1996, F792)の記載によると、本件出願日当時、 KP-103は、毛髪ケラチンの存在下でも活性が低下しないことから、KP-103は毛髪ケラ 15 チンとの親和性が低いことが知られていたといえる。 しかし、皮膚の角質層の抗真菌剤への影響を検討するために毛髪を使用し得ること が知られていることや、先に認定した技術常識Bを考慮しても、抗真菌剤の爪浸透性 を検討するために毛髪を使用し得ることは知られていなかったことから、甲8や甲2 7の記載に接した当業者が、KP-103の爪浸透性についての知見を取得するとは認め難 20 い。また、抗真菌剤の爪浸透性は、薬剤の水溶解度といった因子が影響を及ぼすと考 えられ、抗真菌剤と硬ケラチンとの親和性のみで決定されるとはいえないので、KP- 103と毛髪ケラチンとの親和性が低いことが知られていたとしても、KP-103の爪浸透 性は不明であったというほかない。 そうすると、甲8及び甲27の上記記載を考慮しても、KP-103を、治療効果を奏す 25 る外用剤として爪白癬に適用する動機付けがあったとはいえない。 (ウ) したがって、甲1-1発明のKP-103が、治療効果を奏する外用剤として爪白癬 に適用できることを当業者が容易に想到することができたとはいえない。 エ 本件訂正発明の効果 本件明細書等の記載は、本件訂正発明の外用のKP-103の爪白癬の効果を推察させる ところ、この効果は、技術常識Cを考慮すると、当業者が予測できたものということ 5 はできない。 オ 小括(無効理由1) 以上のとおり、本件訂正発明は、甲1-1発明及び周知技術に基づいて、当業者が 容易に発明をすることができたものとはいえない。 (4) 無効理由2(甲1の2を主引用例とする進歩性欠如)について 10 ア 甲1-2発明の認定 甲1の2には、次の発明(以下「甲1-2発明」という。)が記載されている。 「(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペ リジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール-1-イル)ブタン- 2-オール又はその酸付加塩を有効成分として含有する、トリコフィトン・メンタグ 15 ロフィテス(KD-04)に対する抗真菌活性を有する、外用皮膚真菌症治療剤。」 イ 相違点2の認定 本件訂正発明と甲1-2発明を対比した結果、両発明は次の点において相違する (以下「相違点2」という。。 ) 「真菌症について、本件訂正発明では「爪白癬」である「爪真菌症」と特定される 20 のに対し、甲1-2発明では「皮膚真菌症」と特定される点。」 ウ 相違点2についての検討、本件訂正発明の効果 甲1-2を主引用例としても、上記(3)ウと同様の理由により、KP-103が、治療効 果を奏する外用剤として爪白癬に適用できることを当業者が容易に想到することが できたとはいえない。 25 また、上記(3)エのとおり、本件訂正発明の効果は、当業者が予測できたものとい うことはできない。 エ 小括(無効理由2) 以上のとおり、本件訂正発明は、甲1-2発明及び周知技術に基づいて、当業者が 容易に発明をすることができたものとはいえない。 第3 原告主張の審決取消事由 51 取消事由1(甲1の1を主引用例とする進歩性判断の誤り) (1) 本件審決の認定について ア 本件審決による甲1-1発明の認定は、「皮膚糸状菌症が足白癬である、」との 点が「皮膚糸状菌症が皮膚白癬である、」と認定されるべき点を除き争わない。相違 点1についても、甲1-1発明の治療対象を「皮膚白癬」と認定すべき点を除き争わ 10 ない。 イ 本件審決による技術常識A及びBの認定は争わない。 ウ 本件審決による技術常識Cの認定のうち、「爪白癬の外用剤での治療は非常に 困難で、一般的に無効であるとされ、」との部分は、次のとおり、誤っている。 本件出願日当時、確かに、爪甲は、皮膚と比べて硬く、厚く緻密であり、抗真菌剤 15 がその内部まで浸透(透過)しにくいために外用の抗真菌剤が効果を発揮しにくいと いう問題が当業者に知られていたことは事実であるが、技術常識Aのとおり、皮膚白 癬と爪白癬は、いずれも皮膚糸状菌が患部で増殖することで生じる疾患であり、病態 や治療のための抗真菌剤の作業機序は同じである。 そして、本件出願日当時、経口剤によると肝機能障害等の副作用の問題があること 20 から、外用爪白癬治療剤の開発が切望されており、皮膚白癬治療剤を爪白癬治療剤に 適用するための研究が多数行われ、実際に適用することも周知であった。具体的には、 本件出願日当時、皮膚白癬と爪白癬の両方で使用されている抗真菌剤は多く(甲2 9) 外用皮膚真菌症治療剤を外用爪真菌症治療剤に適用することが周知であった 、 (甲 4~6、29、52)ほか、爪甲への浸透性の問題を意識し、浸透性を高めるために、 25 病爪部を除去して塗布し、又は密封療法や尿素軟膏と併用することで爪への吸収促進 を図る工夫等もされ、抗真菌剤が活性を保ったまま患部に到達しさえすれば一定の有 効性が期待されることが技術常識となっていた(甲3、20、30、108)。 本件審決や被告が技術常識Cの根拠として挙げる証拠(甲28、48、50、乙3 ~5)は、いずれも、爪白癬について標的部位に到達すれば有効であることを前提と するもののほか、爪白癬の外用療法の有効性を必ずしも否定しないものであるから、 5 これらによっては、爪白癬の外用剤での治療が「一般的に無効である」(全く効果が ない)ということはできない。 したがって、本件出願日当時、「爪白癬の外用剤での治療は非常に困難で、一般的 に無効である」(全く効果がない)などという技術常識は存在しなかったというべき であり、本件審決による技術常識Cの認定の一部は誤っている。 10 (2) 相違点1に係る容易想到性判断の誤り ア 進歩性判断における「動機付け」とは、主引用発明に副引用発明を「適用しよ うとすることを試みる」ことであって、その適用を試みることもない、あるいは試み ようとすると阻害要因がある場合に「動機付け」がないということになる。医薬品の 研究開発において、新たな治療薬を探すために試行錯誤するのは常道であるから、ニ 15 ーズが存在する限り、主引用発明に副引用発明の適用を試みることまで否定する(開 発を完全に諦める)ことは考えられない。 また、特許庁の審査ハンドブックでは、医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用 途と異なる場合に、出願時の技術水準から両者間の作用機序の関連性が導き出せる場 合には、有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常、請求項に係 20 る医薬用途発明の進歩性は否定されるとしている。 本件審決は、本件出願日当時の技術常識として、従来の外用真菌症治療剤について 爪白癬への適用を試みることが行われていたこと、爪白癬を様々な工夫を加えた外用 抗真菌剤によって治療する試みもされていたこと、短期間で爪白癬を治癒させかつ経 口剤と比較し全身性の副作用の少ない外用剤の開発が切望されていたことをそれぞ 25 れ認定している。そうすると、甲1-1発明と爪白癬の治療剤とは、技術分野が共に 白癬という皮膚科疾患である点、課題も皮膚又はその付属器官に関わる表在性真菌症 の治療剤の提供という点、作用・機能も少なくとも皮膚組織の真菌症を治療するとい う点で、それぞれ共通しているといえ、これらに照らすと、甲1-1発明のKP-103を 外用の爪白癬治療剤に適用しようと試みること、すなわち動機付けは当然に認められ るべきである。 5 さらに、本件出願日当時、爪は皮膚の一部であり、白癬の典型症状として爪白癬が 周知であること、真菌症治療において、従来の外用真菌症治療剤を外用爪真菌症治療 剤として用いることは当業者において周知であったこと、爪と毛髪がいずれも硬ケラ チンを含み、アミノ酸組成も互いに類似すること、KP-103は皮膚への浸透性が高く、 硬ケラチン存在下でも高い活性を維持できるため、皮膚の角質層で抗真菌活性が良く 10 保たれることが知られていたこと(以上につき、甲1、3~11、15~23、27 ~29、47、48、52、63)も併せ考慮すると、甲1-1発明のKP-103を、外 用の爪白癬治療剤に適用しようとする動機付けは、優に認められるというべきであ る。 イ これに対し、本件審決は、技術常識Cを強調して、「KP-103という特定の抗真 15 菌剤が、爪の内部まで浸透(透過)でき、治療効果を奏する外用剤として爪白癬に適 用できることを当業者が予測することは困難であった」などと結論付けている。 しかし、上記(1)のとおり、技術常識Cのうち、 「爪白癬の外用剤での治療は非常に 困難で、一般的に無効である」といった技術常識は認められない。 仮に、技術常識Cのうち、「爪白癬の外用剤での治療は非常に困難」という限度で 20 技術常識が認められるとしても、前記アのとおり、本件出願日当時、外用での爪白癬 治療剤が切望されている状況にあり、実際に皮膚真菌症治療剤を爪白癬につき適用す るための研究や臨床上の工夫が多数されていたのであるから、外用での爪白癬治療に 適する可能性のある抗真菌剤が見つかった場合に、当業者において、適用を想到すら せず最初から開発を諦めるという選択をするほどに強い阻害要因とはなり得ない。 25 (3) 本件訂正発明の効果も予測できない顕著なものではないこと ア 本件出願日当時、毛髪を用いて、抗真菌剤とケラチンの吸着性や吸着による薬 効への影響が検討されており、一般に抗真菌剤は、ケラチンに吸着することで抗真菌 活性が低下することが周知技術又は技術常識であった(甲8、24~26)。また、 本件審決も認定するとおり、本件出願日当時、KP-103は、毛髪ケラチンの存在下でも 活性が低下しないことから、毛髪ケラチンとの親和性が低いことが知られていた。そ 5 して、爪と抗真菌剤が結合することで、抗真菌剤の活性が低下するとともに、浸透を 妨げる一因となること(甲28の1)、爪甲に存在するケラチンのペプチド鎖間のジ スルフィド結合を切断することで、薬剤がケラチン蛋白の隙間を通過しやすくして爪 への浸透性を高めることは多く行われていたこと(甲47)など、本件出願日当時の 技術常識を考慮すると、当業者であれば、KP-103がケラチン存在下でも爪に浸透でき、 10 しかも高い活性を維持した状態で患部に到達できることで、爪白癬の外用剤としてあ る程度の治療効果があることまでは当然に予想されるといえる。 この点について本件審決は、抗真菌剤の爪浸透性は、硬ケラチンとの親和性のみで 決定されるとはいえないと指摘するが、種々の要因が爪浸透性に影響を与えるとして も、少なくともKP-103が硬ケラチンとの親和性が低く、そのためにケラチン存在下で 15 も薬効が低下しないということは、爪浸透性を評価するうえでプラス材料というべき であり、爪白癬への治療効果を期待するのに十分である。 イ また、本件明細書等に記載された効果も、何ら顕著なものとはいえない。すな わち、 【0085】【図3】には、外用基剤、KP-103液剤、アモロルフィン液剤、ター 、 ビナフィン液剤、経口基剤及びタービナフィン経口剤の各被検体について30日間治 20 療の結果が記載されているが、どの群でも「爪内菌陰性化足数」は10件中1件もな かった。 「爪内平均菌数」では、KP-103液剤は、外用基剤、経口基剤、タービナフィン 経口剤に対しては有意に菌数が減ったとされているが、KP-103液剤とタービナフィン 経口剤とは投与経路や薬液濃度が異なるから、単純にKP-103液剤が顕著な効果を奏す るとは判断できない。また、KP-103液剤は、他の外用液剤(アモロルフィン液剤及び 25 タービナフィン液剤)に対しては有意差が見られないのであるから、やはり顕著な効 果を奏するとはいえない。 (4) 被告の主張する事情等への反論 ア 被告は、平成26年時点で、足白癬、体部白癬及び股部白癬を適応症とする多 数の外用薬が承認されていたのに、爪白癬を適応症とする承認を得られていなかった として、このことは、皮膚の白癬の外用薬を爪白癬の外用薬に転用することが困難で 5 あり、転用したとしても効果を示さなかったことを示すと主張する。 しかし、治療剤としての認可の有無は、有効性の有無だけで決められるものではな く、ビジネス判断など様々な要因を踏まえて決定されるものであるから、承認の有無 や治療実績の蓄積は、進歩性の判断とは無関係である。進歩性の有無を判断するに当 たっては、あくまでも当業者が従来の外用真菌症治療剤を爪白癬の外用剤として用い 10 得ることを認識していたか否かが問題とされるべきである。 イ 被告は、化学的抜爪や外科的抜爪と組み合わせて抗真菌剤を使用する態様は、 本件訂正発明の「外用爪真菌症治療剤」に当たらないと主張する。 しかし、本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は、あくまで「爪白癬治療剤」と記 載されるにとどまり、爪白癬の型や重症度、投与方法、治療上の位置付け等について 15 は何ら限定されていない。したがって、化学的抜爪や外科的抜爪と組み合わせて抗真 菌剤を使用する態様も、本件訂正発明の「外用爪真菌症治療剤」に当たるというべき である。 そして、本件訂正発明のこのような特許請求の範囲の記載を前提にすると、本件出 願日当時、表在性白色爪真菌症(WSO)や軽度の遠位爪甲下真菌症(DSO)に対 20 しては外用での治療が有効とされていたこと、爪白癬の再発防止の観点から外用剤を 経口剤と併用することを推奨する知見があったこと、全身療法(経口剤による治療) では治療できなかった患者に有効であった事例もあったこと(以上につき、甲6、5 2、110、111)等に照らし、本件訂正発明が進歩性を欠くことは明白である。 (5) 小括 25 以上のとおり、本件訂正発明は、本件出願日当時、当業者が甲1-1発明に基づい て容易に発明をすることができたものであるから、特許を受けることができない。こ れと異なる本件審決は、進歩性の判断を誤った違法があるから、取り消されるべきで ある。 2 取消事由2(甲1の2を主引用例とする進歩性判断の誤り) 本件審決による甲1-2発明及び相違点2の認定については争わないが、前記1に 5 おいて甲1-1発明に基づく進歩性判断について主張したのと同様の理由により、本 件訂正発明は、本件出願日当時、当業者が甲1-2発明に基づいて容易に発明をする ことができたものであるから、特許を受けることができない。これと異なる本件審決 は、進歩性の判断を誤った違法があるから、取り消されるべきである。 第4 被告の反論 10 1 取消事由1(甲1の1を主引例とする進歩性判断の誤り)について (1) 技術常識の認定について 原告は、本件審決による技術常識Cのうち、「爪白癬の外用剤での治療は非常に困 難で、一般的に無効である」との認定を争うが、次に述べるとおりの本件優先日当時 及び本件出願日当時の技術常識に照らすと、本件審決による上記認定は正当である。 15 ア 爪は、爪甲上層、爪甲中層及び爪甲下層の三層で構成されている(甲42)。 爪白癬は、多くの場合、皮膚糸状菌が爪甲の遠位部又は側縁部から爪甲下(爪床と の隙間)に侵入して生じるため(甲51)、その感染部位は爪床及び爪甲下層である。 しかし、外用剤の治療では、感染部位に直接塗布することができず、外用剤を爪甲上 層の表面に塗布するほかない。外用剤の有効成分は、爪甲を透過して、感染部位であ 20 る爪甲下層及び爪床に到達する必要がある。 ところが、爪の厚さは、皮膚の角質層の約25~80倍に当たり(甲43、46)、 このことが、爪における有効成分の拡散性が極めて悪いことの理由とされてきた(甲 47)。また、爪は、親水性のゲル膜と考えられており、爪と皮膚とは、正反対の性質 を有すると指摘されていた(甲22、23、47)。さらに、爪を構成する上記三層 25 は、それぞれ固有の物理化学的特徴を有しており、薬物透過性も異なり得るところ(甲 47、56)、爪白癬の有効成分は、これら三層全てを透過する必要がある。 このように、爪と皮膚とでは、構造及び組織が大きく異なり、アミノ酸組成も同一 ではない(甲23)など、爪透過性と皮膚での透過性は異なる。そのため、皮膚での 透過性から爪透過性を予測することは困難であった(甲61)。 イ このような爪白癬の特殊性から、少なくとも真菌症治療の分野では、爪と皮膚 5 とは明確に区別され、白癬の治療薬の分野でも、効能・効果について、足白癬、体部 白癬及び股部白癬と爪白癬とは、明確に区別されてきた。そして、本件優先日当時、 多数の文献が、爪白癬の外用薬は臨床的治癒をもたらさないことを指摘していた(甲 48、49)。また、本件優先日及び出願日以後においても、爪白癬は、抗真菌薬の対 象疾患としても皮膚の白癬と区別され(甲59)、平成26年時点でも、多数の外用 10 薬が足白癬、体部白癬及び股部白癬を適応症として承認されていたのに対し、爪白癬 を適応症とする承認は得られていなかった(甲60)。このように、皮膚の白癬の外 用剤を爪白癬の外用剤に転用することは困難であり、転用したところで効果を示さな かった。 なお、本件優先日当時及び本件出願日当時、欧州及び米国において、塩酸アモロル 15 フィン及びシクロピロックスを有効成分とするネイルラッカー剤(爪の表面に被膜を 形成するタイプの外用剤)が上市されていたが、これらの効果は、実際には不十分で あった(甲52、64、65、67、83、110)。 ウ 上記ア及びイの事情から、本件優先日当時及び本件出願日当時、外用薬による 爪白癬の治療は、一般的に無効と認識されており、その旨が多数の文献に明記されて 20 いた(甲28、48、50、乙3~5)。 以上のとおりであるから、本件審決による技術常識Cの認定は正当である。 (2) 容易想到性の検討について ア 原告は、進歩性判断における「動機付け」について、主引用発明に副引用発明 を「適用しようとすることを試みる」ことであり、その適用を試みることもない、あ 25 るいは試みようとすると阻害要因がある場合に「動機付け」がないということになる として、医薬品の研究開発では新たな治療薬を探すために試行錯誤するのは常道であ るから、ニーズが存在する限り、主引用発明に副引用発明の適用を試みることまで否 定することは考えられないと主張する。 しかし、原告の主張は、何らかの容易想到性の評価根拠事実があれば動機付けを肯 定するというに等しく、進歩性判断における動機付けが総合判断により導かれる規範 5 的要件であることを看過しており、不当である。 そして、上記(1)のとおり、爪白癬の特殊性により、外用薬での治療は一般に無効 と認識されていたことに加えて、本件出願日当時、日本において、足白癬には多数の 外用薬が承認されていたにも関わらず、爪白癬の外用薬の承認はなかったことからす ると、足白癬の外用薬を爪白癬に転用しようと試みても、失敗に終わったことを示し 10 ているから、KP-103を外用の爪白癬治療剤に適用する動機付けは欠如していたという べきである。 イ 原告は、爪と毛髪がいずれも硬ケラチンを含み、アミノ酸組成も互いに類似す ること(技術常識B)に加えて、甲8に依拠して、 「KP-103は皮膚への浸透性が高く、 硬ケラチン存在下でも高い活性を維持できるため、皮膚の角質層で抗真菌活性が良く 15 保たれることが知られていた」と主張し、KP-103を外用の爪白癬治療剤に適用しよう とする動機付けが優に認められると主張する。 しかし、甲8は、エフィナコナゾール(KP-103)について、皮膚の白癬治療を主題 として行われた研究論文であり、そこで示されている「経皮吸収に加えて経毛包吸収 でも皮膚に容易に浸透する」という特性は、角質層や毛包が存在しない爪甲の透過性 20 とは無関係である。毛髪添加の実験も、皮膚の角質層内や生毛部での活性に及ぼすケ ラチンの影響を評価するモデルの一つとして行われたにすぎない。 また、本件優先日当時及び本件出願日当時、ケラチン親和性のみならず、分子サイ ズ(分子量)、電荷及び親水性-親油性など、薬剤の様々な性質が、爪甲での透過性 に影響を及ぼすことが知られており(甲42、47)、爪用外用剤の設計には、これ 25 らの要素をバランスよく考慮する必要があった。 したがって、ケラチン親和性のみから、爪甲の透過性や、爪白癬の外用剤としての 有用性を予測することは困難であったというべきである。 ウ 本件訂正発明の効果は、予測できない顕著なものであった。 本件訂正発明の発明者は、爪白癬の動物モデルにおける薬効の適切な評価法を新た に開発した。モルモット爪白癬モデルの試験において、当該評価法を使用し、薬効を 5 評価したところ(実施例4)、KP-103投与群では、外用基剤群のほか、タービナフィ ン液剤投与群及びアモロルフィン液剤投与群と比べて、爪内平均菌数を明確に下げて いる(【図3】。タービナフィン及びアモロルフィンは、いずれも足白癬、体部白癬 ) 及び股部白癬の外用薬として承認された薬剤であるが、本件明細書等記載の爪白癬モ デルに対して効果を示さなかった。これに対して、本件訂正発明のKP-103は、爪内平 10 均菌数を大幅に低下させて優れた薬効を示しており、この効果は予測できない顕著な ものである。 なお、従来の爪白癬を含む真菌症に対する抗真菌剤の薬効評価法では、薬効の適切 な評価が困難であり、特定の成分を実験的動物モデルで評価しようとしても、新たな 薬効評価法なしには正確にその薬効を評価できなかったのであるから、当該成分が爪 15 白癬に対して治療効果を発揮することを見いだしたとしたら、その効果は予想外かつ 顕著であるというべきである。 エ 以上によると、本件訂正発明は、本件出願日当時、甲1-1発明及び周知技術 等に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。本件審決に 誤りはなく、原告の主張する取消事由1には理由がない。 20 2 取消事由2(甲1の2を主引例とする進歩性判断の誤り)について 取消事由1について主張したのと同様の理由により、本件訂正発明は、本件出願日 当時、甲1-2発明及び周知技術等に基づき、当業者が容易に発明をすることができ たものとはいえない。本件審決に誤りはなく、原告の主張する取消事由2には理由が ない。 25 第5 当裁判所の判断 1 本件訂正発明の概要 本件訂正後における本件特許の特許請求の範囲は前記第2の2のとおりであり、こ れに加え、本件明細書等の記載によると、本件訂正発明の概要は、次のとおりと認め られる。 (1) 本件訂正発明は、病原微生物の検出法、病原微生物に対する抗微生物剤の薬効 5 評価法及び抗微生物剤の検出法に関するとともに、当該薬効評価法に基づいて得られ る抗微生物剤及び爪真菌症治療剤に関する。【0001】 () (2) 真菌症の一種である白癬は皮膚糸状菌が皮膚(角質層)、爪及び毛髪等のケラ チン質に寄生することによって引き起こされる表在性の皮膚疾患であるが、特に、爪 に生じる爪白癬は、白癬による皮膚疾患の中でも難治性の疾患として知られる。爪白 10 癬の治療には経口剤(グリセオフルビン、タービナフィン等)が用いられるが、爪白 癬の完全な治癒には、半年以上といった長期間の服用を要し、不規則な服用や中断、 さらには肝毒性等の副作用が報告されている。このため、短期間で爪白癬を治癒させ、 かつ経口剤と比較し全身性の副作用が少ない外用剤の開発が切望されている。しか し、現在の外用抗真菌剤を爪甲に単純塗布した場合では、薬剤が爪甲の厚い角質に十 15 分に浸透できず、爪内の真菌に対して抗真菌効果を発揮することはできなかった。 (【0009】【0010】 、) (3) 本件訂正発明は、動物又は生体試料の病原微生物感染部位に残留する抗微生物 剤の影響を受けず、正確に該抗微生物剤の薬効を評価できる抗微生物剤の薬効評価法 に基づいて得られる抗微生物剤、具体的には、強力な抗真菌活性に加え、爪甲におい 20 て良質な浸透性と貯留性、高い活性を保持することで、外用塗布で爪白癬に効果を発 揮し、市販の経口剤と比較しても短期間で爪白癬を治癒することができ、また、治療 上必要な量を十分に投与しても副作用を発現することのない効果的な爪真菌症治療 剤を提供することを目的とする。【0012】【0015】 (、) (4) 本件訂正発明の発明者らは、実施例4として、次の実験を行った。 25 白癬の原因となる皮膚糸状菌の一種であるトリコフィトン・メンタグロフィテスを 培養させて接種菌液とし、モルモット爪白癬モデル(Hartley系5週齢雄性モルモッ トの趾間部に前記接種菌液を浸漬したペーパーディスクを挿入し固定して、感染21 日後に除去。感染60日後に爪甲内への白癬菌の感染を確認)を作成した。【002 ( 3】【0024】【0056】【0057】【0076】【0077】 、、、、、) 被検物質として、液剤はKP-103、アモロルフィン及びタービナフィンをそれぞれ 5 1%濃度に溶解し調製した。タービナフィン経口剤は40mg/kgになるようにカ プセルに分注し調製した。感染60日目から1日1回、連日30日間、液剤は0.1 mLを1足の足裏皮膚及び爪に塗布し、タービナフィンのカプセル剤は1カプセル (40mg/kg)を経口投与した。 【0078】 () 爪白癬の薬効は、次の方法により評価した。すなわち、最終治療の2日後に後足1 10 足分の爪(3個)を切り出して切り刻み、ホモジナイズ後に14日間透析を行った後、 原液又は希釈液を培地に塗布して培養した。培養後、全ての培地に菌のコロニーが観 察されない場合を菌陰性化とし、爪内菌陰性化足数を求めた。培地上にコロニーが出 願した場合はそのコロニー数(CFU)を計測し、希釈率を乗じて1足当たりの爪内 菌数を算出した。爪内菌数はクラスカル-ワーリス検定を行った上で、チューキー法 15 に基づく多重比較を行い、群間の有意差を解析した。それらの結果を図3に示し、そ れを表3にまとめた。図3においては、各処置群の爪内菌数をプロットし、それらの 平均菌数を横線及び数値で表した。【0079】【0080】 (、) (【図3】) (【0084】) 図3及び表3に示すように、いずれの群においても30日間治療では爪内菌陰性化 足は観察されなかった。しかし、KP-103は外用基剤と比較して有意に爪内菌数を減少 させ、その治療効果は経口タービナフィンと比較し有意に優れていた。一方、アモロ 5 ルフィン及びタービナフィン(外用、経口)では基剤と比較して有意な殺菌効果は認 められず、治療効果を発揮することはできなかった。以上より、KP-103は外用塗布で 爪白癬に対して効果を発揮し、経口タービナフィンと比較し早期に爪白癬を治癒でき ることが示唆された。【0085】 () (5) KP-103は、従来の外用抗真菌剤では効果が得られなかった爪真菌症に対して単 10 純塗布で優れた治療効果を発揮することが明らかとなった。外用塗布であるため、経 口剤にみられる全身性の副作用がなく、短期間で爪真菌症を治癒させるため、爪真菌 症治療剤として産業上大変有益である。【0091】 () (6) 本件訂正発明は、(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3 「 -(4-メチレンピペリジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール 15 -1-イル)-ブタン-2-オール」(KP-103)又はその塩を有効成分として含有す る外用爪真菌症治療剤であって、爪真菌症が爪白癬である、前記治療剤である。【請 ( 求項1】) 2 本件出願日当時の技術水準等 基礎出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に本件訂正発明が記載されているとは いえず、本件訂正発明の進歩性判断の基準日が本件出願日となる旨の本件審決の認定 (第2の3(1))は正当である。 そして、掲記の証拠(断りのない限り、枝番号の表記は省略した。)及び弁論の全 5 趣旨によると、本件出願日当時の技術水準等に関し、次の事実が認められる。 (1) 白癬 白癬とは、真菌の一つである皮膚糸状菌のうち、トリコフィトン属のもの(白癬菌) の寄生により発症する疾患で、表在性(浅在性)白癬と深在性白癬とに分類される。 このうち、表在性白癬は、白癬菌が表皮角層にとどまっているもので、その感染部位 10 に応じて、頭部白癬、体部白癬、股部白癬、足白癬、手白癬、爪白癬等に分類される。 爪白癬の原因菌の大半は、トリコフィトン・ルブルム(8割強)、次いでトリコフィ トン・メンタグロフィテスであるが、これらの原因菌は、足白癬の原因菌としても大 半を占めている。これらのことは、本件出願日当時、周知であった。 (甲3、20、3 3、50) 15 (2) 爪白癬の治療 ア ヒトの爪甲は、一般に上層、中層及び下層の三層構造からなるとされる。爪白 癬においては、トリコフィトン・ルブルム等の白癬菌が、主として爪甲下層又は爪床 (爪甲の下の表皮で構成される組織)中のケラチンに感染していることが確認され る。感染部位である表皮角層が露出している足白癬等と異なり、爪白癬の感染部位は、 20 上記のとおり爪甲下層や爪床であるため、外用剤による爪白癬の治療を効果的に行う には、抗真菌剤を爪甲の角質内に浸透させ、爪甲下層や爪床等の感染部位に送達させ る必要がある。しかし、爪甲は、手指爪で厚さ0.5~0.6mm、足趾爪で厚さ1. 38~1.65mmと、表皮角層(表皮全体の厚さは0.06~0.2mm、うち角 層のみの厚さは20μm)よりも厚く、また硬く緻密であることから、抗真菌剤がそ 25 の内部まで浸透、透過しにくいという障害がある。このため、爪白癬の治療において、 外用剤での治療は非常に困難とされ、経口剤(内服薬)が第一選択となっていた。も っとも、経口剤には肝障害等の副作用の問題があり、局所製剤(外用剤)の開発が待 たれる状況にあった。これらのことは、本件出願日当時、周知であった。そして、こ れに関連して、次のように、爪白癬の外用剤での治療を「一般に無効」「 、(一般的に) 効果がない」と表現する文献等もあった。 (次の各書証のほか、甲3、7、32、42 5 ~47、53、乙6) (ア)「皮膚糸状菌に有効な外用剤はいくつかあるが、単剤療法として用いられた場 合、たとえ長期の塗布をしても、真菌性の爪疾患をほとんど治癒しない。(甲29、 」 71:Clinical Microbiology Reviews, Vol.12, No.1, p.40-79 (1999)) (イ) 「爪白癬の治療は古くから試みられてきたが、現在まで、成功例は限られてい 10 た。…初期の治療法は外用剤であった。局所皮膚糸状菌感染症の治療に広く用いられ ている外用薬には、…がある。しかし、これらの外用薬は爪の真菌感染症に対して、 爪全体に浸透して感染を根絶することができないため、一般に効果がない(generally ineffective)」 。(甲48:Clinical Microbiology Reviews, Vol.11, No.3, p.415- 429 (1998)) 15 (ウ) 「外用剤は一般に無効」(甲50の1:「医真菌学」(金原出版、平成5年)) (エ) 「現在使用されている外用薬は、足白癬…などの限局性の皮膚糸状菌感染症の 治療には非常に有効であるが、真菌性爪感染症の大多数の治療には有効ではない。」 (甲57:JAOA, Vol.97, No.6 (1997)) (オ) 「外用抗真菌薬は、爪?離と併用した場合でも、通常、真菌性爪感染の治療に 20 は効果がない。(乙3:Journal of the American Academy of Dermatology, Vol.35, 」 S2-S5 (1996)) (カ) 「本症(爪白癬)は外用薬による治療ではまず完治させることができない。ま た、抜爪も無益である。(乙4: 」 「治療」74号169頁(平成4年)) イ 本件出願日当時、我が国において、爪白癬を適応症として承認された外用薬は 25 なかった。 ウ 爪白癬の治療において、外用抗真菌剤を感染部位に送達させるための試みとし て、 「ネイルラッカー剤」と呼ばれる、爪甲の表面に被膜を形成する外用剤の開発(有 効成分はシクロピロックス又は塩酸アモロルフィン。甲4、29、52、109、1 10、乙2)や、尿素等により爪甲を化学的に除去し又は外科的に抜爪した上で抗真 菌剤を塗布し、密封包帯法(ODT)等を併用する(甲20、30~32、47、5 5 0、108、111、乙7、8、11)等の試みがされていた。 エ 甲6、16の1(Clinicaland Experimental Dermatology, 10, p.111-115 (1985))には、抗真菌剤であるチオコナゾールについて、爪白癬の治療のための外用 溶液剤としての効果を、オープン試験(以下「甲6試験」という。)により評価した結 果が記載されている。甲6試験では、爪真菌症の患者合計27名(うち、皮膚糸状菌 10 症感染患者は18名)に対し、感染爪上にチオコナゾール(28%)爪用溶液を1日 2回塗布するように指示し、少なくとも3か月間、最長12か月にわたって治療を継 続し、感染範囲及び臨床的改善の評価を行った。その結果は次のとおりである。 皮膚糸状菌感染症について寛解がみられた4例は、いずれも手指の爪に感染のある 15 患者であった。うち3例は、足の爪にも感染がみられたものの、足の爪については治 療に反応しなかった。 (3) 爪と毛髪の類似性 本件出願日当時、爪と毛髪が、いずれも硬ケラチンを含み、アミノ酸組成も互いに 類似することは周知であった(本決審決の認定した技術常識B。甲9~11、19、 21、23)。 (4) KP-103の特性 甲1の1(甲15はその抄訳。以下同じ。(Abstracts of the 36th ICAAC, 1996, ) p113, F78-F80)には、KP-103の1%溶液をモルモットの皮膚糸状菌症モデル(体部 5 白癬、足白癬、趾間型足白癬)に1日1回局所投与した場合の治療効果が、ネチコナ ゾールよりも優れており、ラノコナゾール及びブテナフィンとほぼ同等であったこ と、この優れた効果は、高い活性と、角質層での長い保持時間に起因すると考えられ ること等が記載されている。 甲8、16の2(Chem. Pharm. Bull. Vol.47, No.10, p.1417-1425 (1999))に 10 は、KP-103を含む化合物群を調製し、それらの抗真菌活性を外用薬として評価したこ と、一般的に、大半の外用抗真菌剤の活性は、ケラチンへの吸着により大幅に低下し、 対照薬剤であるクロトリマゾールやネチコナゾールでも、ヒト毛髪(ケラチン)の添 加により実質的に抗トリコフィトン・メンタグロフィテス活性が低下したが、KP-103 ではそのような低下が見られなかったこと、KP-103は、経皮吸収に加えて、経毛包吸 15 収でも皮膚へ容易に浸透することが確認されたこと、KP-103の優れた効果は、抗真菌 活性に加えて、皮膚における良好な浸透性と、活性の低下が少なかったことに起因す ると考えられること等が記載されている。 甲27(Abstracts of the 36th ICAAC, 1996, F792)には、KP-103について、ラ ノコナゾール及びブテナフィンと比べて、ケラチンに対する低い吸着と、ケラチンか 20 らの高い遊離を示したことが記載されている。 (5) 毛髪を使用した抗真菌剤の角質吸着性、吸着時の抗菌活性の研究 甲25(「基礎と臨床」30巻1号123頁(平成8年))には、外用抗真菌剤の薬 効発現部位である角質層の抗菌活性に及ぼす影響を調べる目的で、角質の材料として ヒト毛髪を用い、ラノコナゾールの角質への吸着性と吸着時の抗菌活性をインビトロ 25 で調べ、他の抗真菌剤と比較した実験結果が記載されている。 甲26(「西日本皮膚科」52巻3号545頁(平成2年))には、ヒト毛髪粉末を 用いて、外用抗真菌剤である塩酸ブテナフィンの角質への吸着性及び角質と吸着した ときの抗真菌活性の低下につき他の抗真菌剤と比較した実験結果が記載されている。 3 取消事由1(甲1の1を主引用例とする進歩性判断の誤り)について (1) 本件訂正発明、主引用発明、一致点及び相違点の認定 5ア 本件訂正発明は、次のとおりである。 「(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペ リジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール-1-イル)-ブタン -2-オールまたはその塩を有効成分として含有する外用爪真菌症治療剤であって、 爪真菌症が爪白癬である、前記治療剤。」 10 なお、本件明細書等の記載に基づき前記1に認定した本件訂正発明の概要によると、 本件訂正発明における治療剤は、爪甲に単純塗布した場合に、爪甲に透過、貯留し、 かつ高い活性を保持する特性により、爪白癬に対する治療効果を発揮することを特徴 とするものと認められる。 イ 甲1の1には、本件審決が認定したとおり、次の甲1-1発明が記載されてい 15 るものと認められる。 「新規外用抗真菌剤トリアゾールである、以下の化学構造を有するKP-103を有効成 分として含有し、皮膚への塗布により投与して皮膚糸状菌症に対する治療効果を有す る溶液であって、皮膚糸状菌症が足白癬である、溶液。 」20 この点について、原告は、甲1-1発明の治療対象を、足白癬ではなく「皮膚白癬」 と認定すべきと主張する。しかし、甲1の1には「皮膚白癬」の語は記載されておら ず、皮膚糸状菌症のうちに「皮膚白癬」と称される分類があることを認めるに足りる 証拠もない。また、甲1の1には、足白癬のほかに、体部白癬、趾間型足白癬を実験 の対象としたことが記載されているが、証拠(甲3、7、50)によると、本件出願 5 日当時、足白癬は、その原因菌のほとんどがトリコフィトン・ルブルムとトリコフィ トン・メンタグロフィテスである点で他の表在性白癬よりも爪白癬と共通し、足白癬 と爪白癬が合併する場合もよくみられることが知られていたと認められる。そうする と、本件審決が、治療対象を爪白癬とする本件訂正発明と対比すべき主引用発明の認 定に際し、治療対象を皮膚糸状菌症中の足白癬と認定した点は正当である。 10 ウ 本件訂正発明と甲1-1発明を対比すると、両発明は、「KP-103又はその塩を 有効成分として含有する外用真菌症治療剤であって、真菌症が白癬である、前記治療 剤。」である点において一致し、本件審決が認定したとおり、次の相違点1が認めら れる。 「治療対象が、本件訂正発明では「爪真菌症」である「爪白癬」と特定されている 15 のに対し、甲1-1発明では「皮膚糸状菌症」である「足白癬」と特定されている点。」 (2) 相違点1についての検討 ア 主引用例中の記載 主引用例である甲1の1には、KP-103について、足白癬の原因菌であるトリコフィ トン・ルブルム及びトリコフィトン・メンタグロフィテスに対する抗真菌作用を有す 20 ること、また、KP-103の皮膚糸状菌症に対する優れた効果は、高い活性と、角質層で の長い保持時間に起因すると考えられることが記載されている。 イ 本件出願日当時の技術水準等 (ア) 前記2(1)~(3)のとおり、本件出願日当時、①トリコフィトン・ルブルム及び トリコフィトン・メンタグロフィテスが足白癬と同様に爪白癬の原因菌の大半を占め 25 ていること、②外用剤による爪白癬の治療を効果的に行うには、抗真菌剤を爪甲の角 質内に浸透させ、感染部位に送達させる必要があるが、爪甲の性質上、抗真菌剤がそ の内部まで浸透、透過しにくいという障害があって、爪白癬の外用剤での治療は非常 に困難とされていた一方、経口剤にも副作用の問題があり、外用剤の開発が待たれて いたこと、③爪と毛髪が、いずれも硬ケラチンを含み、アミノ酸組成も互いに類似す ることは、いずれも周知であった(以下、丸番号の数字に応じて「技術常識①」など 5 という。。) 次に、前記2(2)、(4)及び(5)のとおり、本件出願日当時、④外用抗真菌剤を感染 部位に送達させるための試みとして、ネイルラッカー剤の開発や、爪甲を化学的又は 外科的に除いて抗真菌剤を塗布し、密封包帯法(ODT)と併用する治療等が行われ ていたこと、⑤抗真菌剤であるチオコナゾールを外用爪白癬治療剤として評価する甲 10 6試験が実施されたこと、⑥KP-103は、ヒト毛髪(ケラチン)を添加しても、抗トリ コフィトン・メンタグロフィテス活性が減少せず、ケラチンに対する低い吸着、高い 遊離といった性質を有すること、⑦抗真菌薬の角質への吸着性と角質吸着時の活性の 低下について、ヒト毛髪を用いて評価する研究があったことが、それぞれ知られてい た(以下、丸番号の数字に応じて「技術的知見④」などという。 。) 15 (イ) 原告は、本件審決が本件出願日当時の技術水準として「爪白癬の外用剤での治 療は非常に困難で、一般的に無効であるとされ、」と認定した点について、 「一般的に 無効である」という語を「全く効果がない」と読み替え、あるいは同義と解釈した上 で、そのような技術常識は存在しなかったと主張する。 しかし、前記2(2)のとおり、本件出願日当時、感染部位である表皮角層が露出し 20 ている足白癬等とは異なり、爪甲の厚さ、硬さ及び緻密さから、爪白癬の治療のため に爪甲に抗真菌剤を塗布したとしても、抗真菌剤が爪甲の内部まで透過、浸透しにく いという障害があって、爪白癬の外用剤の治療は非常に困難とされていたことは周知 であったと認められる。そして、これに関連して、爪白癬の外用剤での治療を「一般 に無効」「 、(一般的に)効果がない」と表現する文献等が複数あったことも、前記の 25 とおりである。これらの文献は、爪白癬の外用剤での治療が「全く効果がない」とは 表現しておらず、爪白癬では、足白癬その他の白癬のように外用抗真菌剤を単純に塗 布しても、所望の治療効果を期待することができない旨を記載しているとみるのが相 当である。本件審決による「爪白癬の外用剤での治療は非常に困難で、一般的に無効 であるとされ、」との認定は、本件出願日当時のそのような技術水準を認定する趣旨 のものとして正当ということができる。 5ウ 相違点に係る容易想到性の検討 (ア) 主引用例である甲1の1には、KP-103について、トリコフィトン・ルブルム及 びトリコフィトン・メンタグロフィテスに対する抗真菌作用を有し、その活性は強く、 また、角質層での保持時間が長いと考えられることが記載されている。そして、外用 剤の開発が待たれる爪白癬の原因菌の大半はトリコフィトン・ルブルム及びトリコフ 10 ィトン・メンタグロフィテスであることは周知であった(技術常識①、②)。 他方で、本件出願日当時、外用剤による爪白癬の治療を効果的に行うには、抗真菌 剤を爪甲の角質内に浸透させ、感染部位に送達させる必要があるところ、爪甲の性質 上、抗真菌剤がその内部まで浸透、透過しにくいという障害があり、爪白癬の外用剤 での治療は非常に困難とされていたこともまた周知であった(技術常識②)。 15 したがって、本件出願日当時、甲1-1発明の外用真菌性治療剤の治療対象を「爪 白癬」とし、相違点1に係る本件訂正発明の構成とすることが当業者において容易に 想到できたというには、当時の技術水準等に照らし、当該治療剤を爪甲に単純塗布し たときに、その有効成分であるKP-103が爪甲の内部まで浸透、透過し、感染部位であ る爪甲下層及び爪床に送達され、治療効果を発揮することが合理的に期待できること 20 を要するというべきである。 (イ) そこで、本件出願日当時の技術水準について検討する。 a 本件出願日当時、外用抗真菌剤を感染部位に送達させるための試みとして、ネ イルラッカー剤の開発や、爪甲を化学的又は外科的に除いて抗真菌剤を塗布し、密封 包帯法(ODT)と併用する治療等が行われていたことが知られていた(技術的知見 25 ④)。 しかし、本件出願日当時に知られていたネイルラッカー剤による爪白癬の治療効果 は限定的であった。例えば、甲29、71には「予備データ(Preliminary data)に よれば、アモロルフィンかチオコナゾールの何れかを含むネイルラッカー剤は増大し た効果を提供するかもしれない( suggestthat ... may offer increased efficacy)」とあり、甲52、109は爪白癬の局所治療としてネイルラッカー剤を 。 5 紹介するものの要約(Summary)には「局所療法は局所薬剤が爪甲を透過しないため しばしば無効(often ineffective)である。」とある。 密封包帯法(ODT)についても、乙7(「治療薬ガイド1999~2000」 (文 光堂・平成11年))に「肝機能障害などで内服不可能なときは尿素軟膏との併用あ るいは密封療法を行うがその効果は弱い。」とあるように、知られた効果は限定的で 10 あった。 また、爪甲を化学的又は外科的に除いて抗真菌剤を塗布する方法は、治療剤を爪甲 に単純塗布するものではない。 このように、技術的知見④に係る試みは、いずれも、抗真菌剤を爪甲に単純塗布し た場合に、その有効成分が爪甲の内部まで浸透、透過し、感染部位である爪甲下層及 15 び爪床に送達され、治療効果を発揮することを示唆するものとはいえない。 b 本件出願日当時、抗真菌剤であるチオコナゾールを外用爪白癬治療剤として評 価する甲6試験が実施されたことが知られており(技術的知見⑤)、甲6には、皮膚 糸状菌感染症患者18名のうち8名に著明な改善、4名に臨床的及び真菌学的寛解の 効果が得られた旨が記載されている(前記2(2))。 20 しかし、前記2(2)エのとおり、甲6試験は、オープン試験であって、対照群との 比較も行われていないほか、対象患者も18名にとどまり、かつ、寛解に至ったのは 爪白癬のうちでも比較的治癒しやすい手指の爪の感染4例のみ(うち3例は足の爪に も感染がみられたが、完治しなかった。)というものである。そうすると、当業者は、 甲6の記載のみをもっては、抗真菌剤であるチオコナゾールが有効成分として爪甲の 25 内部まで浸透、透過し、感染部位である爪甲下層及び爪床に送達され、治療効果を発 揮することを合理的に期待するには至らず、ましてやその知見をKP-103に適用できる と考えるには至らないというべきである。 c 本件出願日当時、KP-103について、ヒト毛髪(ケラチン)を添加しても抗トリ コフィトン・メンタグロフィテス活性が減少せず、ケラチンに対する低い吸着、高い 遊離といった性質を有すること(技術的知見⑥)、抗真菌薬の角質への吸着性と角質 5 吸着時の活性の低下について、ヒト毛髪を用いて評価する研究があったこと(技術的 知見⑦)が、それぞれ知られていた。 しかし、本件出願日当時、表在性白癬とは白癬菌が表皮角層にとどまるものである こと、感染部位である表皮角層が露出している足白癬等とは異なり、爪白癬の感染部 位は主として爪甲下層及び爪床であり、抗真菌剤が容易に浸透、透過しにくい爪甲の 10 存在が、爪白癬の外用抗真菌剤による治療を困難にしていたことは周知であった(技 術常識②、前記2(1)及び(2))。また、爪白癬の局所薬物治療効果を高めるためには、 抗真菌剤の選択において、その水溶解度、分子量、解離定数、製剤のpH及び白癬菌 に対する最小阻止濃度を考慮する必要があるとの知見があった(甲35)。しかると ころ、技術的知見⑦に係る研究(甲25、26)は、いずれも爪ではなく、皮膚への 15 抗真菌剤の浸透性(吸着性)及び浸透(吸着)時の活性についての研究結果であるか ら、技術常識B(爪と毛髪が、いずれも硬ケラチンを含み、アミノ酸組成も互いに類 似すること)及び技術的知見⑥(KP-103はヒト毛髪を添加しても活性が減少せず、ケ ラチンに対する低い吸着、高い遊離といった性質を有すること)を併せても、これら の知見は、KP-103が皮膚への高い浸透性(吸着性)を持ち、浸透(吸着)時に高い活 20 性を保持するであろうことを示唆するにすぎず、これを超えて、当業者において、外 用真菌性治療剤として爪甲に単純塗布したときに、KP-103が爪甲の内部まで浸透、透 過し、感染部位である爪甲下層及び爪床に送達され、治療効果を発揮することまで示 唆するものとはいえない。 (ウ) 以上に検討したところによると、甲1の1の記載と本件出願日当時の技術常識 25 その他の技術的知見を考慮したとしても、本件出願日当時、当業者において、甲1- 1発明の外用真菌症治療剤の治療対象を爪白癬とし、相違点1に係る本件訂正発明の 構成とすることが容易に想到できたということはできない。 エ 原告の主張について (ア) 原告は、進歩性判断における「動機付け」とは、主引用発明に副引用発明を「適 用しようと試みる」ことであり、その適用を試みることもない、あるいは試みようと 5 すると阻害要因がある場合に「動機付け」がないことになるとして、医薬品の研究開 発において新たな治療薬を探すために試行錯誤するのは常道であり、ニーズが存在す る限り、主引用発明に副引用発明の適用を試みることまで否定する(開発を完全に諦 める)ことは考えられないから、従来の外用真菌症治療剤について爪白癬への適用を 試みることが行われていたこと、爪白癬を様々な工夫を加えた外用抗真菌剤によって 10 治療する試みもされていたこと、短期間で爪白癬を治癒させかつ経口剤と比較し全身 性の副作用の少ない外用剤の開発が切望されていたこと等、本件審決も認定した事情 からすると、当然に甲1-1発明のKP-103を外用の爪白癬治療剤に適用しようと試み ること、すなわち動機付けが当然に認められると主張する。 しかし、原告の主張が、医薬に係る発明の進歩性を肯定するためには、当業者が医 15 薬品の開発を完全に諦めていることが必要とする趣旨であるとすると、このような見 解は採り得ない。ある発明が主引用発明に基づいて容易に発明をすることができたか は、引用例の記載内容や出願日当時の技術水準等に基づく総合判断であって、原告が 主張するような製品開発のニーズや試みがされていたという辞書的な意味での動機 付けがあるとしたときに、阻害要因がなければ直ちに進歩性が否定されるかのような 20 主張は、論理に飛躍があって採用することができない。 (イ) 原告は、特許庁の審査ハンドブックにおいても、医薬発明の医薬用途が引用発 明の医薬用途と異なる場合に、出願時の技術水準から作用機序の関連性が認められる 場合には、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常、請求項に係る医薬用途発 明の進歩性は否定されるとした上で、甲1-1発明と本件訂正発明の各治療剤は、技 25 術分野が共に白癬という皮膚科疾患である点、課題も皮膚又はその付属器官に関わる 表在性真菌症の治療剤の提供という点、作用・機能も少なくとも皮膚組織の真菌症を 治療するという点で、それぞれ共通しているといえるから、本件訂正発明の進歩性は 否定されると主張する。 しかし、両治療剤について、技術分野が白癬の治療剤という点で共通し、機能も抗 真菌剤の作用による白癬の治療という点で共通するとはいえるものの、感染部位であ 5 る表皮角質が露出している足白癬とは異なり、爪白癬では、厚く、硬く緻密である爪 甲が障害となって外用抗真菌剤を感染部位に直接塗布できないという課題があった 点、また、作用機序という点でも塗布部位から感染部位に抗真菌剤を送達させること に困難があった点において異なっているのであるから、上記のとおり技術分野や機能 の一部が共通しているとしても、これらをもって直ちに本件訂正発明の進歩性を否定 10 することはできない。 (ウ) 原告は、①爪は皮膚の一部であり、②白癬の典型症状として爪白癬が周知であ ること、③真菌症治療において、従来の外用真菌症治療剤を外用爪真菌症治療剤とし て用いることは当業者において周知であったこと、④爪と毛髪がいずれも硬ケラチン を含み、アミノ酸組成も互いに類似すること、⑤KP-103は皮膚への浸透性が高く、硬 15 ケラチン存在下でも高い活性を維持できるため、皮膚の角質層で抗真菌活性が良く保 たれることが知られていたことなども、本件訂正発明の進歩性を否定する事情として 主張する。 しかし、前記ウ(ア)及び(イ)のとおり、①について、爪甲は表皮角層と同様にケラチ ンを含む点においては共通するが、本件出願日当時、感染部位である表皮角層が露出 20 した足白癬等には外用抗真菌剤の塗布による治療が容易であったのに対し、爪白癬の 場合には爪甲が抗真菌剤の感染部位への送達を困難にしていたのであるから、「爪は 皮膚の一部」といった抽象的な共通点を挙げても進歩性を否定する事情とはなり得な い。②が周知であることは既に認定したとおりであるが、③について、本件出願日当 時、爪白癬の外用剤での治療は非常に困難とされていたことが周知であったところ、 25 これを前提に、外用抗真菌剤を感染部位に送達させるための試みとして、ネイルラッ カー剤、爪甲の除去、密封包帯法(ODT)等の試みがされていたことは認められる ものの、これらの試みによる効果として知られていたものはいずれも限定的であり、 また、爪甲の除去は爪甲に抗真菌剤を直接塗布することとは異なるのであるから、甲 6試験の存在を考慮しても、「従来の外用真菌症治療剤を外用爪真菌症治療剤として 用いることは当業者において周知であった」と認めることはできない。④及び⑤につ 5 いて、これらの知見は、KP-103が皮膚への高い浸透性(吸着性)を持ち、浸透(吸着) 時に高い活性を保持するであろうことを示唆するにすぎず、外用真菌症治療剤として 爪甲に単純塗布したときに、KP-103が爪甲の内部まで浸透、透過し、感染部位である 爪甲下層及び爪床に送達され、治療効果を発揮することまで示唆するものとはいえな い。 10 (エ) したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。 (3) 本件訂正発明の効果 ア 前記1に認定したとおり、本件明細書等には、実施例4として、モルモット爪 白癬モデルを作成し、外用KP-103液剤の薬効を評価したところ、図3及び表3に示す ように、いずれの群においても爪内菌陰性化足は観察されなかったが、KP-103は外用 15 基剤と比較して有意に爪内菌数を減少させ、その治療効果は経口タービナフィンと比 較し有意に優れていたこと、アモロルフィン及びタービナフィン(外用、経口)では 基剤と比較して有意な殺菌効果は認められず、治療効果を発揮することはできなかっ たことが記載されている。 ここで、KP-103液剤の治療効果は、爪内平均菌数において、外用基剤、経口基剤及 びタービナフィン経口剤との関係では有意差が示されたものの、アモロルフィン液剤 及びタービナフィン液剤との関係では有意差は示されていない。しかし、有意水準が 5 0.01%に設定されていること、アモロルフィン及びタービナフィン(外用、経口) は基剤との関係でも有意差は示されていないこと、KP-103液剤の爪内平均菌数はアモ ロルフィン及びタービナフィン各液剤と比較して約10分の1(Logスケールで約1 減)となっていることがそれぞれ認められることに加え、表3のプロットからしても、 KP-103液剤の治療効果は、アモロルフィン液剤及びタービナフィン液剤と比べて、優 10 れているものと評価することができる。 そして、この効果は、既に述べているとおり、本件出願日当時、爪白癬の治療につ いて、抗真菌剤が爪甲の内部まで浸透、透過しにくいという障害があるため、外用剤 での治療は非常に困難とされていたことが周知であったことからすると、当業者にお いて予測することが困難であったというべきである。 15 イ この点について、原告は、一般に抗真菌剤は、ケラチンに吸着することで抗真 菌活性が低下することが周知技術又は技術常識であった上、KP-103が毛髪ケラチンと の親和性が低く、毛髪ケラチンの存在下でも活性が低下しないこと、爪甲に存在する ケラチンのペプチド鎖間のジスルフィド結合を切断して、薬剤がケラチン蛋白の隙間 を通過しやすくして爪への浸透性を高めることが多く行われていたこと(甲47)等 が知られていたから、当業者であれば、KP-103がケラチン存在下でも爪に浸透し、高 い活性を維持した状態で患部に到達して、爪白癬の外用剤としてある程度の治療効果 があることまでは当然に予想されると主張する。 5 しかし、前記(2)ウ(イ)cのとおり、原告が挙げる知見は、KP-103が皮膚への高い浸 透性(吸着性)を持ち、浸透(吸着)時に高い活性を保持するであろうことを示唆す るにすぎないものである。また、甲47に記載されているジスルフィド結合を切断す る方法は、スルフヒドリル基を含んだ化合物を角質溶解薬とともに使用するなどの試 みが紹介されているにすぎず、そのような併用なしに爪甲に単独塗布した場合に効果 10 を奏し得ることを示してはいない。 また、原告は、本件明細書等に記載された効果も何ら顕著なものとはいえないと主 張するが、本件明細書等に記載された効果が予測し得ないものであったことは、前記 アのとおりである。 (4) 小括 15 以上によると、主引用例の記載及び周知技術等を考慮しても、本件訂正発明は、本 件出願日当時、当業者が甲1-1発明に基づいて容易に発明をすることができたとは いえない。これと同旨の本件審決は正当であり、原告の主張する取消事由1には理由 がない。 4 取消事由2(甲1の2を主引例とする進歩性判断の誤り)について20 (1) 本件訂正発明、主引用発明、一致点及び相違点の認定 ア 本件訂正発明については、前記3(1)アのとおりである。 イ 甲1の2には、次の甲1-2発明が記載されているものと認められる。 「(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペ リジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール-1-イル)ブタン- 25 2-オール又はその酸付加塩を有効成分として含有する、トリコフィトン・メンタグ ロフィテスに対する抗真菌活性を有する、外用皮膚真菌症治療剤。」 ウ 本件訂正発明と甲1-2発明を対比すると、両発明は、「KP-103又はその塩を 有効成分として含有する外用真菌症治療剤。」である点において一致し、本件審決が 認定したとおり、次の相違点2が認められる。 「真菌症について、本件訂正発明では「爪白癬」である「爪真菌症」と特定される 5 のに対し、甲1-2発明では「皮膚真菌症」と特定される点。」 (2) 進歩性についての検討 主引用例である甲1の2には、KP-103が、皮膚真菌症の原因菌であるトリコフィト ン・メンタグロフィテスに対して高い活性を示すことが記載されている。 そして、取消事由1について前記3(2)、(3)で述べたところによると、甲1の2の 10 記載と本件出願日当時の技術常識その他の技術的知見を考慮したとしても、本件出願 日当時、当業者において、甲1-2発明の外用真菌症治療剤の治療対象を爪白癬であ る爪真菌症とし、相違点2に係る本件訂正発明の構成とすることが容易に想到できた ということはできず、本件訂正発明の効果は、本件出願日当時、当業者において予測 することが困難であったというべきである。 15 (3) 小括 以上によると、主引用例の記載及び周知技術等を考慮しても、本件訂正発明は、本 件出願日当時、当業者が甲1-2発明に基づいて容易に発明をすることができたとは いえない。これと同旨の本件審決は正当であり、原告の主張する取消事由2には理由 がない。 20 5 結論 以上のとおり、原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく、本件審決にこれ を取り消すべき違法はないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判 決する。 25 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 5本多知成 10 裁判官 天野研司 裁判官遠山敦士は、てん補のため署名押印することができない。 15 裁判長裁判官 本多知成 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/04/23 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
|