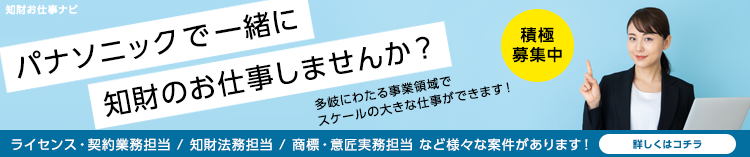| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(ネ)
10043号
損害賠償請求控訴事件
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/05/08 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
|
判例全文
令和7年5月8日判決言渡 令和6年(ネ)第10043号 損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第22564号、令和4年(ワ)第160 85号) 5 口頭弁論終結日 令和7年3月11日 判 決 控訴人兼被控訴人 株式会社ジィ・シィ企画 (以下「第1審原告」という。) 10 同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二 同 木 村 広 行 同補佐人弁理士 野 本 裕 史 15 被控訴人兼控訴人 株 式 会 社 モ ビ リ テ ィ (以下「第1審被告モビリティ」という。) 被控訴人兼控訴人 Y 20 (以下「第1審被告Y」といい、第1審被告モビリティと併せて 「第1審被告ら」という。) 上記両名訴訟代理人弁護士 寒 河 江 孝 允 主 文 1 第1審原告の控訴を棄却する。 25 2 第1審原告の当審における追加請求を棄却する。 3 第1審被告らの控訴を棄却する。 1 4 第1審原告の控訴に係る控訴費用及び当審における追 加請求に係る訴訟費用は第1審原告の負担とし、第1審 被告らの控訴に係る控訴費用は第1審被告らの負担とす る。 5 事 実 及 び 理 由 (略語は、本判決で定めるもののほか、原判決の例による。) 第1 控訴の趣旨 1 第1審原告 (1) 原判決中、第1審原告の敗訴部分を取り消す。 10 (2) 第1審被告モビリティは、第1審原告に対し、4190万6167円及 びこれに対する令和3年9月25日から支払済みまで年3%の割合による金 員(ただし、第1審被告Yと4190万6167円及びこれに対する同年1 0月19日から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を 支払え。 15 (3) 第1審被告Yは、第1審原告に対し、第1審被告モビリティと連帯して、 4190万6167円及びこれに対する令和3年10月19日から支払済み まで年3%の割合による金員を支払え。 2 第1審被告ら (1) 原判決中、第1審被告らの敗訴部分を取り消す。 20 (2) 第1審原告は、第1審被告Yに対し、2000万円及びこれに対する令 和4年7月6日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え、もしく はこれに代えて謝罪せよ。 (3) 第1審原告は、第1審被告モビリティに対し、3000万円及びこれに 対する令和4年7月6日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え、 25 もしくはこれに代えて謝罪せよ。 第2 事案の要旨 2 1 本件は、次の本訴及び反訴から成る事案である。 (1) 原審本訴事件は、第1審原告が、岡三証券を主幹事会社として、マザー ズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、岡三証券に 対し、第1審原告の製造又は販売する製品は第1審被告モビリティが当時有 5 していた本件特許(特許第4789092号)に係る本件特許権を侵害して いるとの理由で別件訴訟を提起した旨の通知書を送付した行為(原判決では 「本件通知書」 「本件通知行為」の略語が用いられていたが、当審において 、 は、以下「本件通知書1」 「本件通知行為1」という。 、 )が、不正競争行為 (不正競争防止法2条1項21号)、不法行為又は取締役がその職務を行う 10 についての悪意若しくは重過失による任務懈怠に該当し、本件通知行為1に より第1審原告に損害が生じたと主張して、第1審被告らに対し、4503 万7856円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるもの である。 (2) 原審反訴事件は、第1審被告らが、本件通知行為1は、第1審被告らに 15 よる正当な義務の履行としてされたものであり、第1審原告による本訴提起 は、故意又は過失によって第1審被告らの権利又は法律上保護される利益を 侵害し、第1審被告らは、これにより有形及び無形の損害を被ったと主張し て、第1審原告に対し、第1審被告Yにつき2000万円、第1審被告モビ リティにつき3000万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払 20 を求めるものである。 2 原審は、第1審原告の本訴請求及び第1審被告らの反訴請求をいずれも全 部棄却する判決をしたところ、これを不服とする第1審原告及び第1審被告 らが控訴を提起した。ただし、第1審原告は、当審において、第1の1記載 のとおり、4190万6167円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め 25 る限度で不服を申し立てた。 3 第1審原告は、当審において訴えの追加的変更を行い、第1審被告モビリ 3 ティが、株式会社日本取引所グループに対し、令和3年6月24日頃、上記 同旨の内容の通知書(乙3。以下「本件通知書2」といい、本件通知書1と 併せて「本件各通知書」という。)を送付した行為(以下「本件通知行為2」 といい、本件通知行為1と併せて「本件各通知行為」という。)も上記同様に 5 不正競争行為等に該当し、第1審原告に損害が生じたと主張して、損害賠償 を求めるとともに、第1審被告モビリティの責任原因として会社法350条 に基づく責任を予備的に追加した。 【第1審原告の請求の法的根拠】 第1の1(2)について 10 ・ 主請求 ・ 主位的請求:不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求 ・ 予備的請求:不法行為に基づく損害賠償請求 ・ 更なる予備的請求:会社法350条に基づく損害賠償請求 ・ 附帯請求:遅延損害金請求(起算日は訴状送達日の翌日、利率は民 15 法所定) 第1の1(3)について ・ 主請求 ・ 主位的請求:不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求 ・ 予備的請求:不法行為に基づく損害賠償請求 20 ・ 更なる予備的請求: 会社法429条1項に基づく損害賠償請求 ・ 附帯請求:遅延損害金請求(起算日は訴状送達日の翌日、利率は民 法所定) 【第1審被告らの請求の法的根拠】 第1の2(2)及び(3)について 25 ・ 主請求:不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに代わる民法723条 に基づく謝罪請求(選択的併合) 4 ・ 附帯請求:遅延損害金請求(起算日は反訴状送達日の翌日、利率は民法 所定) 第3 前提事実 前提事実は、原判決「事実及び理由」の第2の1(5)オ(8頁~)の項の末 5 尾に改行して以下の補正を加え、同1(5)「カ」 「キ」の見出し符号をそれぞ 、 れ「キ」 「ク」と改めるほかは、原判決「事実及び理由」の第2の1(3頁~) 、 に記載するとおりであるから、これを引用する。引用部分中、本件特許、これ に係る特許請求の範囲及び本件各通知書の内容を摘記する。 【原判決の補正】 10 「カ 第1審被告モビリティは、本件通知行為1と同日である令和3年6月2 4日、株式会社日本取引所グループに対し、本件通知書1と同じ内容を記載 した「特許裁判に関する通知書」と題する本件通知書2(乙3)を送付した (本件通知行為2)。本件通知書2には、本件通知書1と同じ内容が記載され ていた。」 15 1 本件特許 第1審被告モビリティは、平成14年4月17日(優先日平成13年4月1 7日、優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002-58 4251号)の一部を分割して、平成20年5月7日、本件特許の特許出願を し、平成23年7月29日、本件特許権の設定登録(請求項の数6)を受けた 20 (特許第4789092号)。 2 本件特許に係る特許請求の範囲 第1審被告モビリティは、平成30年12月6日及び令和2年3月6日、特 許庁に対し、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請 求をし(訂正2018-390195号、訂正2020-390021号)、 25 これらの訂正を認める審決(前者につき平成31年1月29日付け、後者につ き令和2年6月30日付け)が確定しているところ、本件特許に係るこれらの 5 訂正後の特許請求の範囲の請求項1、3、4及び5の各記載は、以下のとおり である(このうち、請求項5に係る発明が本件発明である。 。 ) 【請求項1】 RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のス 5 イッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信される トリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、 保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける 受付手段と、前記トリガ信号に応答して、RFIDインターフェースを有す るRバッジに対してRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信 10 号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け 取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う 比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付け た前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記 アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比 15 較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経 過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯 電話。 【請求項3】 請求項1記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイ 20 スドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加 および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 【請求項4】 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、 クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設の 25 チケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つであることを特徴とす る請求項3記載の携帯電話。 6 【請求項5】(本件発明) 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェー スを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携 帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断 5 手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報で あると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする 受信装置。 3 本件各通知書の内容 「・・・当職は、株式会社モビリティ…の代理人として、2021年6月23日 10 (水)付けにて、東京地方裁判所に、株式会社ジィ・シィ企画を被告として、 特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提訴したことを通知いたします。 なお、通知人は株式会社ジィ・シィ企画(以下、被告という)に対して、被 告製品が通知人会社保有の特許権を侵害していることを指摘し、被告に対し、 その事実を認めること及び正当な対価を支払うことを請求し、そのための誠意 15 ある協議を求めて、数回に渡り内容証明書などで通知しているにも拘わらず、 何らの回答も無いまま現在に至っております。 ・・・被告は、2021年7月7日にマザーズ市場に上場予定の企業であり、 日本取引所グループの上場審査基準である「投資者保護の観点から当取引所が 必要と認める事項」(有価証券上場規程)及び「公益又は投資者保護の観点で 20 適当と認められること」(上場審査等に関するガイドライン)に定められてい る「新規上場申請者の企業グループが、経営活動や業績に重大な影響を与える 係争又は紛争等を抱えていないこと。」に該当するもの…であり、かかる紛争 の事実は、被告の上場の適格性に影響を及ぼすものと思料し、被告の「新規上 場」の承認については慎重に再審査されるべきであると思料します。・・・ 25 記 東京地方裁判所令和3年(ワ)第16255号 7 ①東京地方裁判所 民事第47部(知財部) ②原告 株式会社モビリティ 代表取締役 Y ③被告 株式会社ジィ・シィ企画 代表取締役 Z ④訴訟金額 金4億9388万円 5 以上」 第4 争点及び争点に関する当事者の主張 1 本件の当審における争点は、以下のとおりである。 【当審における争点】 (1) 本件特許権侵害についての虚偽告知の有無(争点1) 10 ア 充足論(争点1-1) イ 無効論(争点1-2) ウ 訂正の再抗弁の成否(争点1-3、当審で追加された争点) エ 訂正発明に係る無効の抗弁の成否(争点1-4、当審で追加された争点) オ 第1審被告らによる虚偽告知の内容(争点1-5) 15 (2) 第1審被告らと第1審原告との間の競争関係の有無(争点2) (3) 第1審被告らの故意又は過失の有無(争点3) (4) 第1審被告Yの悪意又は重過失による任務懈怠の有無(争点4) (5) 第1審原告の損害発生の有無及び損害額(争点5) (6) 本訴提起による不法行為の成否(争点6) 20 (7) 第1審被告らの損害発生の有無及び損害額(争点7) 2 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者双方の主張は、当審における当事者の補充的主張を別紙 のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」の第3(11頁~)に記載のと おりであるから、これを引用する(ただし、当審での争点1-5は、原判決で 25 は「争点1-3」である。 。 ) 第5 当裁判所の判断 8 1 当裁判所は、第1審被告モビリティがした本件各通知行為は、不正競争防 止法2条1項21号の「虚偽の事実を告知」するものであるとは認められな いから(争点1-5)、その余の点について検討するまでもなく、第1審原告 の本訴請求には理由がなく、また、本訴提起による不法行為も成立しないか 5 ら(争点6)、第1審被告らの反訴請求も理由がないと判断する。その理由は、 以下のとおりである。 2 争点1-5(第1審被告らによる虚偽告知の内容)について 事案に鑑み、争点1-5から判断する。 (1) 第1審原告は、第1審被告らが、別件訴訟を提起した旨を本件各通知書 10 に記載し、岡三証券ないし株式会社日本取引所グループに通知したところ (本件各通知行為)、第1審原告は第1審被告らの本件特許権を侵害してい ないから、本件各通知行為が不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実 を告知」するものに当たると主張する。 (2) しかし、前記引用に係る前提事実(5)オ及びカのとおり、本件各通知書 15 の内容は、①第1審被告モビリティが別件訴訟を提起したこと、②第1審被 告モビリティは、第1審原告に対し、第1審原告の製品が本件特許権を侵害 していることを指摘し、第1審原告に対し、その事実を認め、正当な対価を 支払うことを請求し、そのための誠意ある協議を求めて、数回にわたり内容 証明書などで通知しているにもかかわらず、何らの回答がないまま現在に 20 至っていること、③第1審原告は、マザーズ市場に上場予定の企業であり、 上記のような紛争の事実は、第1審原告の上場の適格性に影響を及ぼすから、 新規上場の承認については慎重に再審査されるべきであると思料すること、 ④別件訴訟の裁判所事件番号、訴訟係属裁判所、当事者名、訴訟金額、を通 知するというものである。 25 上記の点のうち、①及び④は別件訴訟提起の事実そのものを伝えるもので あり(上記引用に係る前提事実(5)エ)、③は慎重な再審査を要望している 9 ことを伝えるものであるにすぎず、何ら虚偽の事実を告知するものではない。 上記②の内容も、第1審原告の製品が本件特許権を侵害しているという事実 を断定的に言及するものではなく、その文脈に鑑みれば、これは訴訟前の紛 争の経緯を伝えるものであり、そうした紛争があったこと自体は事実である 5 (同前提事実(5)イ及びウ)。なお、上記②の内容のうち、何らの回答がな いまま現在に至っているとする部分については、第1審原告は、本件特許権 侵害の指摘に対して回答書を送付するなどして対応しているから(同前提事 実(5)ウ)、厳密にいえば事実と異なるといえる。しかし、当該記載は上記 ②の一部にすぎず、その文脈に鑑みれば、これは、第1審原告において第1 10 審被告モビリティが要求する正当な対価の支払を認める回答をしなかったこ とを誇張して表現したものと理解できなくもないから、この点のみをもって 上記②を虚偽の事実を告知するものであると認めることはできない。 以上に加え、裁判という事柄の性質上、別件訴訟において、最終的に第1 審被告モビリティの請求が認められるかは定かではなく、そのことは本件各 15 通知書を受け取った者においても了解可能であることを考慮すると、上記内 容の本件各通知行為をもって、虚偽の事実を告知したことになると解するの は相当ではない。 そして、仮に、本件各通知書を受け取った者が、第1審原告が別件訴訟 の当事者となったことを考慮して何らかの対応を取り、それによって第1審 20 原告が損害を被ることがあったとしても、上記の判断は左右されるものでは ない。 (3) 以上に関し、第1審原告は、別件訴訟が取り下げられたことにより、当 該訴訟は初めから裁判所に係属していなかったとみなされるから(民事訴訟 法262条1項)、別件訴訟が提起されなかったことになり、本件各通知行 25 為が虚偽の事実を告知したことになると主張するが、訴えの取下げの効果と、 別件訴訟の提起という事実の存否を混同するものであり、採用することはで 10 きない。 なお、第1審被告モビリティは、別件訴訟を提起した際、訴状に収入印 紙を貼付しておらず(同前提事実(5)エ)、第1審原告の新規上場が中止と なった後に別件訴訟を取り下げているが(同前提事実(5)キ及びク)、こう 5 した事情によって、上記内容の本件各通知行為自体が虚偽の事実を告知した ことになるわけでもない。 (4) 以上により、本件各通知行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚 偽の事実を告知」するものであるとは認められない。 よって、その余の点について検討するまでもなく、第1審原告の主位的請 10 求は理由がない。そして、第1審原告のその余の請求も、本件各通知行為が 虚偽の事実の告知に当たることを前提とするものであるから、その前提を欠 き、結局、第1審原告の本訴請求はいずれも理由がない。 3 争点6(本訴提起による不法行為の成否)について 訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提 15 訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、 提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り 得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目 的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られると解するのが相 当である(原判決「事実及び理由」第4の6(68頁)の11~21行目に同 20 旨)。 本件では、前記のとおり、本件各通知行為が虚偽の事実の告知に当たらない にもかかわらず、第1審原告による本訴提起がされているが、本件各通知行為 が虚偽の事実の告知に当たるかについては、当審と原審で判断が分かれている ように、法的評価を伴う微妙な判断が必要になるものである。そうすると、本 25 件において、第1審原告が、本訴請求が事実的、法律的根拠を欠くものである ことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるの 11 にあえて訴えを提起したなどとはいえないのであり、第1審原告による本訴提 起が不法行為になるとは認められない。 よって、第1審被告らの反訴請求も理由がない。 第6 結論 5 以上によれば、第1審原告の本訴請求及び第1審被告らの反訴請求をいずれ も棄却した原判決は結論において相当であり、第1審原告の控訴及び第1審被 告らの控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、第1審原告の 当審における追加請求も理由がないから、これを棄却することとして、主文の とおり判決する。 10 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 増 田 稔 15 裁判官 本 吉 弘 行 20 裁判官 岩 井 直 幸 12 (別紙) 当審における当事者の補充的主張 1 争点1-2-5(甲32文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如)に ついて 5 【第1審被告らの主張】 (1) 原判決は、請求項5の構成の中から請求項1の構成(特徴)の記載部分 (構成要件A~G)を全て除外して、請求項5のみの構成要件J~Kを認定 した上で、無効の抗弁を認めたが、これは、請求項に関する「一部無効」論 に基づく判断であり、特許法123条1項柱書後段の法理に明確に違反する 10 ものである。 (2) 本件発明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード 情報」を意味していることは明らかであり、当業者であれば、「個別情報」 をカードの種別を示す情報であると理解する。これに対し、甲32発明の 「チケットデータ」とは、自動改札を通過するだけにのみ必要なデータ(す 15 なわち、定期券や乗車券に相当するデータ)であって、チケットデータごと に異なる通し番号が割り振りされるものである。したがって、甲32発明は、 本件発明の「発信手段」や「判断手段」に対応する構成について何ら開示も 示唆もしていない。 よって、甲32発明から、本件発明の「受信装置」には容易に想到せず、 20 進歩性欠如の無効理由は認められない。 2 争点1-2-6(訂正前の本件発明に関する甲29文献を主引用例とする 進歩性欠如)について 【第1審被告らの主張】 (1) 甲29発明は「非接触ICカード」を開示しているだけであり、「携帯 25 電話」について何ら開示も示唆もしていない。そして、甲32発明では、自 動改札機13が携帯通信端末11から「チケットデータ」を受信しているの 13 に対し、甲29発明では、自動改札機として機能するリーダ/ライタ400 が、非接触ICカード100から「所定のレスポンス信号」を受信しており、 受信するデータ(信号)が明らかに異なる技術内容である。このように受信 するデータ(信号)が異なっているので、当業者であっても、甲29発明の 5 「非接触ICカード」の代わりに、甲32発明の「携帯通信端末」を用いる ことはあり得ず、動機付けがないことが明らかである。 (2) また、甲29発明では、「所定のレスポンス信号」とは、リーダ/ライ タ400と非接触ICカード100との間で「相互認証処理」を実行するた めの契機となる(トリガとなる)信号であって、その「所定のレスポンス信 10 号」それ自体を用いて「相互認証処理」を行っていない。しかし、本件発明 では、「個別情報」それ自体を用いて認証を行っている。よって、甲29発 明の「所定のレスポンス信号」は、本件発明の請求項5の「個別情報」に相 当せず、たとえ甲29発明と甲32発明を組み合わせたとしても、当業者は 本件発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認め 15 られない。 (3) さらに、甲29発明において、「乱数A」とは、「乱数a」を暗号化鍵を 用いて変換して得られた数であり、「非接触ICカード100」の種別を示 す情報(数)ではない。これに対して、本件訂正発明における「個別情報」 はカードの種別を示す情報であり、明らかに異なるものである。よって、た 20 とえ甲29発明と甲32発明を組み合わせたとしても、当業者は本件発明の 「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認められない。 3 争点1-2-7(訂正前の本件発明に関する甲30文献を主引用例とする 進歩性欠如)について 【第1審被告らの主張】 25 (1) 甲30発明は「B型カード」を開示しているだけであり、「携帯電話」 について何ら開示も示唆もしていない。そして、甲32発明では、自動改札 14 機13が携帯通信端末11から「チケットデータ」を受信しているのに対し、 甲30発明では、ICカードの重要なパラメータを情報領域に含めてリーダ に「ATQB」が伝送されるのであり、受信するデータ(信号)が異なって いるので、当業者であっても、甲30発明の「B型カード」の代わりに、甲 5 32発明の「携帯通信端末」を用いることはあり得ず、動機付けがないこと が明らかである。 (2) また、甲30発明の「ATQB」は、「Answer to Request B」であって、 ICカードの重要なパラメータを情報領域に含めてリーダに伝送されるもの であり、「カードの種別」を示す情報ではない。これに対して、本件発明に 10 おける「個別情報」はカードの種別を示す情報であり、明らかに異なるもの である。しかも、甲30文献には、単に「リーダがカードからATQBを誤 りなく受信すると、直ちに、特定の目的に一致したカードを選択することが 可能になる。 (甲30・186頁)と記載しているだけで、その判断基準に 」 ついて一切開示・示唆していない。よって、甲30発明は、本件発明の「発 15 信手段」や「判断手段」に対応する構成について何ら開示も示唆もしていな い。 (3) よって、たとえ甲30発明と甲32発明を組み合わせたとしても、当業 者は本件発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は 認められない。 20 4 争点1-2-8(訂正前の本件発明に関する、ソニーがFeliCaカー ドのユーザーに提供した「FeliCaカード ユーザーズマニュアル V ersion 2.02」と題する書面(甲36文献)又は甲36文献に記 載された発明の公然実施品(甲36製品)を主引用例とする進歩性欠如)に ついて 25 【第1審被告らの主張】 (1) 甲36発明は、Felicaカードである非接触ICカード」を開示し 15 ているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない。そ して、甲32発明では、自動改札機13が携帯通信端末11から「チケット データ」を受信しているのに対し、甲36発明では、リーダ/ライタが非接 触ICカードから「カードの製造ID(IDm)と製造パラメータ(PM 5 m)」を受信しており、受信するデータ(信号)が明らかに異なる。このよ うに受信するデータ(信号)が異なっているので、当業者であっても、甲3 6発明の「非接触ICカード」の代わりに、甲32発明の「携帯通信端末」 を用いることはあり得ず、動機付けがないことが明らかである。 (2) また、甲36発明の「IDm」それ自体は、1つの「個別情報」に対応 10 するかもしれないが、甲36発明は、1つのFelicaカードである「非 接触ICカード」を特定するための1つの「IDm(PMm)」を開示して いるにすぎない。このため、甲36発明は、取得した「IDm(PMm)」 が要求したIDmであるか否かを判断していない。一方、本件発明の「個別 情報」は、カードの種別を示す情報であり、本件発明の「受信装置」は、そ 15 の「個人情報」が何であるのか、カードの種別を判断している。 (3) よって、たとえ甲36発明と甲32発明を組み合わせたとしても、当業 者は本件発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は 認められない。 5 争点1-2-9(訂正前の本件発明に関する甲45文献を主引用例とする 20 進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲45文献には、次の構成を有する発明(以下「甲45発明」という。) が記載されていると認められる(以下、甲45発明の構成を「甲45j」な どという。以下の発明においても同様に構成を表記する。 。 ) 25 甲45j 非接触ICカードとの間で送受信するためのセンサ部を有し、 甲45k 運賃を引き去るのに十分な残額を要求するトリガ信号を前記非接 16 触ICカードに発信する発信手段と、 甲45l 前記非接触ICカードから受信した残額が、運賃を引き去るのに 十分な残額であるか否かを判断する判断手段とを有し、 甲45m 前記判断手段で受信した残額が、運賃を引き去るのに十分な残額 5 であると判断されたときに、残額から運賃を引き去った結果を新 しい残額として前記非接触ICカードに送信する 甲45n ことを特徴とする改札装置。 (2) 本件発明と甲45発明は、高々、次の点で形式的に相違し、その余で一 致する。 10 (相違点) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲45発明では「非接触ICカード」である点。 (3) 本件特許優先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触IC カードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する機器 15 が、携帯電話と非接触で送受信を行うものとすることが広く行われており、 受信装置を、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェース を備えるものとすることは、甲第27、32~35号証に記載の事項であっ て、周知技術になっていることが明らかであった。甲45文献に触れた当業 者は、こうした周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用す 20 ることで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、甲第27、32~3 5号証のいずれかに記載の事項を適用することで、相違点に係る本件発明の 構成に容易に想到する。仮に、その他、何らかの相違があるとしても、当業 者が適宜設計する程度のものであって、本件発明は、甲45発明に基づき容 易に想到できたものであるから、進歩性欠如の無効理由を有する。 25 【第1審被告らの主張】 第1審原告の主張は争う。甲45文献は、「非接触ICカードを用いた乗車 17 券システム」に関する発明を開示しているだけであり、甲45発明は「携帯電 話」について何ら開示も示唆もしていない。 6 争点1-2-10(訂正前の本件発明に関する甲46文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 5 【第1審原告の主張】 (1) 甲46文献には、次の構成を有する発明(以下「甲46発明」という。) が記載されていると認められる。 甲46j ICカードとの間で送受信するためのアンテナ及びリーダ/ライ タを有し、 10 甲46l 前記ICカードから受信したチェックコードが、正しいICカー ドのチェックコードであるか否かを判断する判断手段とを有し、 甲46m 前記判断手段で受信したチェックコードが、正しいICカードの チェックコードであると判断されたときに、前記ICカードから のデータの読み出しを行う 15 甲46n ことを特徴とする自動改札機。 (2) 本件発明と甲46発明は、次の点で相違し、その余で一致する。 (相違点1) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲46発明では「ICカード」である点。 20 (相違点2) 本件発明では、「個別情報の発信要求を・・・発信する発信手段」(構成要件 K)を有するのに対し、甲46発明では、そのような構成を備えているのか 否かが明らかではない点。 (3) 甲47文献には、自動改札機において、自動改札機と無線カードとの間 25 では、無線カードから個別情報の読み出しを行う際に、自動改札機のリーダ ライタから無線カードへの呼び掛けが行われ、それに対して無線カードから 18 個別情報の送信が行われることが開示されているから(3.5.1、図3)、 甲47発明は「個別情報の発信要求を・・・発信する発信手段」(構成要件 K)に相当する構成を備えているといえる。また、甲47文献は、無線カー ド(非接触ICカード)を用いた自動改札機という甲46発明と同じ技術に 5 関する文献であるから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについ て十分な動機付けがある。そして、両者を組み合わせることにつき、阻害事 由はない。 よって、甲46発明の自動改札機に甲47発明の上記構成を組み合わせ ることにより、相違点2に係る本件発明の構成に想到することは当業者に 10 とって容易である。 また、甲46発明に触れた当業者は、周知技術に動機付けられ、当該周 知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付け られ、甲27、32~35号証のいずれかに記載の事項を適用することで、 相違点1に係る本件発明の構成に容易に想到する。 15 したがって、本件発明は、甲46発明、甲47発明及び周知技術に基づ いて当業者が容易に発明することができたものであり、進歩性欠如の無効理 由を有する。 【第1審被告らの主張】 第1審原告の主張は争う。甲46文献は、「ICカードを利用した自動改札 20 システム」に関する発明を開示しているだけであり、甲46発明は「携帯電話」 について何ら開示も示唆もしていない。本件発明における「個別情報」とは、 クレジットカードなどの「カード情報」を意味していることは明らかであると ころ、甲46発明の「チェックコード」は、そのカードが正しいか否かを認証 するためのコードであるから、本件発明における「個別情報」に該当しない。 25 同様に、甲47文献も、自動改札機に係る発明を開示しているだけであり、 「携帯電話」に対応する構成要素を何ら開示も示唆もしていない。 19 よって、たとえ甲46発明と甲47発明を組み合わせたとしても、本件発明 を進歩性欠如の理由で無効にはできない。 7 争点1-2-11(訂正前の本件発明に関する甲48文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 5 【第1審原告の主張】 (1) 甲48文献には、次の構成を有する発明(以下「甲48発明」という。) が記載されていると認められる。 甲48a 第1の電波信号送受信装置を有する携帯電話であって、 甲48b 当該携帯電話の電源またはキーを押すことを、携帯電話を使用可 10 能な状態にするための要求として受け付ける、 甲48c 電源又はキーを押すことに応答して、第2の電波信号送受信装置 を有するIDカードに対してIDカードにあらかじめ記憶された データ9を要求する電波信号Aを送信する、 甲48d 前記IDカードよりデータ9を受け取って、該受け取ったデータ 15 9と前記携帯電話に記憶されているデータ10およびデータ11 との比較を行う、 甲48e 比較結果に応じて携帯電話を使用可能な状態にするための要求を 許可または禁止する(すなわち携帯電話を使用可能または使用不 可能にする)、 20 甲48f 携帯電話を使用可能な状態にするための要求を許可する(すなわ ち携帯電話を使用可能にする)という比較結果が得られた場合は、 一定時間が経過するまでは携帯電話を使用可能な状態にするため の要求を許可し続ける(すなわち携帯電話を使用可能にし続ける) 甲48g 携帯電話。 25 (2) 仮に、本件発明の構成要件Jについて「請求項4記載の(携帯電話)」 という事項を考慮すべきであるとしても、本件特許優先日当時において、甲 20 48発明が、本件発明との相違点1(「請求項1記載の」に対応する構成を 備えていない点)、相違点2(「アプリケーションプログラムやデバイスドラ イバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および /または更新する手段を有する」に対応する構成を備えていない点)及び相 5 違点3(「前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッ ドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメ ント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つである」に 対応する構成を備えていない点)で相違するとしても、甲48発明に、甲第 27、29、30、32、36、45、46号証のそれぞれに記載の各発明 10 や公然実施発明や、甲49~52、63~65の周知の技術的事項を組み合 わせて、本件発明に容易に想到することができたから、進歩性欠如による無 効理由が認められる。 【第1審被告らの主張】 第1審原告の主張は争う。甲48文献は、訂正前の請求項1が無効であると 15 して引用された証拠であり、甲49文献~甲52文献は、訂正前の請求項3及 び4が無効であるとして引用された証拠であるが、本件訂正に係る訂正の再抗 弁の主張により、訂正後の請求項1、3及び4の「携帯電話」特許発明を無効 にはできない。 8 争点1-2-12(訂正前の本件発明に関する甲53文献を主引用例とす 20 る拡大先願違反)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲53文献(特開2001-245354)は、本件特許優先日(平成 13年4月17日)の前である平成12年3月1日に出願日を有し、本件特 許優先日後の平成13年9月7日に公開されている。甲53文献に係る発明 25 (以下「甲53発明」という。)の発明者は、本件発明の発明者と同一でな く、かつ、甲53発明に係る出願人は、本件発明の出願人と同一でない。 21 (2) 甲53文献には、次の構成を有する甲53発明が記載されていると認め られる。 甲53a ロック解除コード送信部および認証演算結果受信部を有する携帯 電話機であって、 5 甲53b 当該携帯電話機のキー操作によるデータの入力に対応する操作内 容を、メモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等の操作を行う ための要求として受け付ける、 甲53c 前記操作内容に応答して、ロック解除コード受信部および認証結 果送信部を有するロック解除装置に対して、ロック解除装置に記 10 憶されているID情報に応じた認証演算結果(第2の認証演算結 果)を要求するロック解除コードを送信する、 甲53d 前記ロック解除装置より認証演算結果(第2の認証演算結果)を 受け取って、該受け取った認証演算結果(第2の認証演算結果) と当該携帯電話機に予め記録してある認証演算結果(第1の認証 15 演算結果)との比較を行う、 甲53e 比較結果に応じてメモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等を 許可または禁止する、 甲53f メモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等を許可するという比 較結果が得られた場合は、一連の処理が完了するまではメモリダ 20 イヤル等の個人情報へのアクセス等を許可し続ける 甲53g 携帯電話機。 (3) 仮に、本件発明の構成要件Jについて「請求項4記載の(携帯電話)」 という事項を考慮すべきであるとしても、本件特許優先日当時において、甲 53発明が、相違点1(「アプリケーションプログラムやデバイスドライバ 25 をインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/ま たは更新する手段を有する」に対応する構成を備えていない点)、相違点2 22 (「前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカー ド、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施 設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つである」に対応す る構成を備えていない点)及び相違点3(「携帯電話との間で送受信するた 5 めのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話 に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別 情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判 断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話 との間で処理を行うことを特徴とする受信装置」に対応する構成を備えてい 10 ない点)で本件発明と形式的に相違するとしても、これらの相違点は課題解 決のための具体化手段における微差(周知技術の付加等であって、新たな効 果を奏するものではないもの)にすぎず、甲53発明と本件発明とは実質同 一であるから、本件発明は拡大先願違反の無効理由を有する。 【第1審被告らの主張】 15 上記5(争点1-2-11)【第1審被告らの主張】に同旨(ただし、甲4 8文献を甲53文献とする。) 9 争点1-2-13(訂正前の本件発明に関する甲54文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 20 (1) 本件発明の要旨認定においては、本件発明の構成要件Jの「請求項4記 載の(携帯電話)」という事項を除外するべきであることについては、原判 決「事実及び理由」の第3の8「(原告の主張)」の(1)(18頁)に記載の とおりである。 (2) 甲54文献には、次の構成を有する発明(以下「甲54発明」という。) 25 が記載されていると認められる。 甲54j 電子マネー端末であって、 23 甲54k 当該電子マネー端末に設けられた入力部の操作によって、電子マ ネー関連情報(カードID、個人公開鍵、個人認証情報、残高) の送信を要求する信号を当該電子マネー端末に挿入された電子マ ネーカードに送信する手段と、 5 甲54l 前記電子マネーカードから受信した電子マネー関連情報が正当で あることを確認する手段とを有し、 甲54m 前記受信した電子マネー関連情報が正当であると確認されたとき に、前記電子マネーカードとの間で処理を行う 甲54n ことを特徴とする電子マネー端末。 10 (3) 本件発明と甲54発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点1) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲54発明では「電子マネーカード」である点。 (相違点2) 15 本件発明では、「RFIDインターフェースを有する」のに対して、甲5 4発明では、電子マネーカードが電子マネー端末に挿入され、「RFIDイ ンターフェース」の開示がない点。 (4) 甲49文献には、POSシステムなどの外部システムとやり取りするス マートカード(すなわち、電子マネーカード)用の電子部品をセルラ電話 20 (すなわち、携帯電話)に内蔵することによって、携帯電話に電子マネー カードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行う、という発明(以 下「甲49発明」という。)が開示されており、相違点1及び2に相当する といえる。 そして、甲49文献は、POSシステムなどの外部システムとやり取り 25 するスマートカード(電子マネーカード)という甲54発明と同じ技術に関 する文献であり、また、甲49文献には、可撓性プラスチック・スマート 24 カードに伴う問題点や欠点を克服するため、スマートカードに関連する電子 部品を別のハウジング構成内に組み込むこと、トランザクションを実行する ために、外部リーダとの接触を必要としないスマートカードを提供すること が課題として記載されており(【0002】~【0005】 、当該記載は、 ) 5 甲54発明に甲49発明を適用することについて、示唆しているものといえ るから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付 けがある。また、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。 よって、甲54発明に甲49発明を組み合わせることにより、相違点1 及び2に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 10 (5) また、本件特許優先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触 ICカードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する 機器が、携帯電話と非接触で送受信を行うものとすることが広く行われてお り、受信装 置を、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインター フェースを備えるものとすることは、甲第27、32~35号証に記載の事 15 項であって、周知技術になっていることが明らかであった。 よって、甲54文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、 当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動 機付けられ、甲第27、32~35号証のいずれかに記載の事項を適用する ことで、相違点1及び2に係る本件発明の構成に容易に想到する。 20 【第1審被告らの主張】 甲54文献は、電子マネーシステムに関する発明を開示しているだけであり、 「携帯電話」や「RFIDインターフェース」について何ら開示も示唆もして いないから、本件発明を進歩性欠如の理由で無効にはできない。 10 争点1-2-14(訂正前の本件発明に関する甲55文献を主引用例とす 25 る進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 25 (1) 本件発明の要旨認定について、上記9(争点1-2-13)【第1審原 告の主張】(1)に同じ。 (2) 甲55文献には、次の構成を有する発明(以下「甲55発明」という。) が記載されていると認められる。 5 甲55j 非接触データキャリアとの送受信を行うアンテナ部を有する自動 販売機システムであって、 甲55k 自動販売機システムに設けられた商品選択ボタンの押下によって、 ID、残金読取り要求を自動販売機システムに近づけられた非接 触データキャリアに発信する手段と、 10 甲55l 非接触データキャリアから受信した残金が利用金額以上の残金で あるか否かを判断する手段とを有し、 甲55m 非接触データキャリアから受信した残金が利用金額以上の残金で あると判断されたときに、非接触データキャリアとの間でプリペ イド残金の書き換え処理を行う 15 甲55n ことを特徴とする自動販売機システム。 (3) 本件発明と甲55発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲55発明では「非接触データキャリア」である点。 20 (4) 甲55文献の「非接触データキャリア」は、非接触ICカードを含むと ころ(【0008】 、甲49文献には、POSシステムなどの外部システム ) とやり取りするスマートカード(すなわち、ICカード)用の電子部品をセ ルラ電話(すなわち、携帯電話)に内蔵することによって、携帯電話にIC カードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行う、という発明が開 25 示されており、上記相違点に相当するといえる。 そして、甲49文献については上記9【第1審原告の主張】(4)に記載の 26 とおりであり、甲49文献の記載は、甲55発明に甲49発明を適用するこ とについて示唆しているといえるから、当業者にとっては、両者を組み合わ せることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることに つき、阻害事由はない。 5 よって、甲55発明に甲49発明を組み合わせることにより、上記相違 点に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 (5) また、上記9【第1審原告の主張】(5)と同様に、甲55文献に触れた 当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用 することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、甲第27、32~ 10 35号証のいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件 発明の構成に容易に想到する。 【第1審被告らの主張】 甲55文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示して いるだけであり、「携帯電話」や「RFIDインターフェース」について何ら 15 開示も示唆もしていないから、本件発明を進歩性欠如の理由で無効にはできな い。 11 争点1-2-15(訂正前の本件発明に関する甲56文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 20 (1) 本件発明の要旨認定について、上記9(争点1-2-13)【第1審原 告の主張】(1)に同じ。 (2) 甲56文献には、次の構成を有する発明(以下「甲56発明」という。) が記載されていると認められる。 甲56j 非接触型プリペイドカードとの間で送受信を行うメータ側無線受 25 信部及び無線送信部を有するガスメータであって、 甲56k ガスメータに設けられた料金投入スイッチの押下によって、ID 27 番号及びプリペイド金額の発信要求をガスメータに近づけられた 非接触型プリペイドカードに発信する手段と、 甲56l 非接触型プリペイドカードから受信したID番号が一致するか否 かを判断する手段とを有し、 5 甲56m 非接触型プリペイドカードから受信したID番号が一致すると判 断されたときに、非接触型プリペイドカードとの間で残金の払い 戻し処理を行う 甲56n ことを特徴とするガスメータ。 (3) 本件発明と甲56発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。 10 (相違点) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲56発明では「非接触型プリペイドカード」である点。 (4) 甲49文献については上記9【第1審原告の主張】(4)に記載のとおり であり、甲49文献の記載は、甲56発明に甲49発明を適用することにつ 15 いて示唆しているといえる。当業者にとっては、両者を組み合わせることに ついて十分な動機付けがあり、両者を組み合わせることにつき阻害事由はな い。 よって、甲56発明に甲49発明を組み合わせることにより、上記相違 点に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 20 (5) また、上記9【第1審原告の主張】(5)と同様に、甲56文献に触れた 当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用 することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、甲第27、32~ 35号証のいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件 発明の構成に容易に想到する。 25 【第1審被告らの主張】 甲56文献は、非接触型プリペイドカード方式メータに関する発明を開示し 28 ているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないから、 本件発明を進歩性欠如の理由で無効にはできない。 12 争点1-2-16(訂正前の本件発明に関する甲57文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 5 【第1審原告の主張】 (1) 本件発明の要旨認定について、上記9(争点1-2-13)【第1審原 告の主張】(1)に同じ。 (2) 甲57文献には、次の構成を有する発明(以下「甲57発明」という。) が記載されていると認められる。 10 甲57j 非接触データキャリアとの間でデータ送受信を行うためのリーダ ライタを有する自動販売機システムであって、 甲57k 自動販売機システムに設けられた購入金額選択ボタンの押下に よって、ID及び残高の読取要求を自動販売機システムに近づけ られた非接触データキャリアに発信する手段と、 15 甲57l 非接触データキャリアから受信した残高が選択金額以上の残高で あるか否かを判断する手段とを有し、 甲57m 非接触データキャリアから受信した残高が選択金額以上の残高で あると判断されたときに、非接触データキャリアとの間で残高書 換え処理を行う 20 甲57n ことを特徴とする自動販売機システム。 (3) 本件発明と甲57発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲57発明では「非接触データキャリア」である点。 25 (4) 甲57文献の「非接触データキャリア」は、非接触ICカードを含むと ころ(【0008】 、甲49文献には、POSシステムなどの外部システム ) 29 とやり取りするスマートカード(すなわち、ICカード)用の電子部品をセ ルラ電話(すなわち、携帯電話)に内蔵することによって、携帯電話にIC カードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行うという発明が開示 されており、上記相違点に相当するといえる。 5 そして、甲49文献については上記9【第1審原告の主張】(4)に記載の とおりであり、甲49文献の記載は、甲57発明に甲49発明を適用するこ とについて、示唆しているといえる。当業者にとっては、両者を組み合わせ ることについて十分な動機付けがあり、両者を組み合わせることにつき阻害 事由はない。 10 よって、甲57発明に甲49発明を組み合わせることにより、上記相違 点に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 (5) また、上記9【第1審原告の主張】(5)と同様に、甲57文献に触れた 当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用 することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、甲第27、32~ 15 35号証のいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件 発明の構成に容易に想到する。 【第1審被告らの主張】 甲57文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示して いるだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないから、本 20 件発明を進歩性欠如の理由で無効にはできない。 13 争点1-2-17(訂正前の本件発明に関する甲58文献を主引用例とす る進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 本件発明の要旨認定について、上記9(争点1-2-13)【第1審原 25 告の主張】(1)に同じ。 (2) 甲58文献には、次の構成を有する発明(以下「甲58発明」という。) 30 が記載されていると認められる。 甲58j 送受信回路を有する現金自動取引装置であって、 甲58k 現金自動取引装置に設けられたリクエストスイッチの押下によっ て、第1識別情報の発信を求める第1のリクエスト信号を現金自 5 動取引装置に近づけられたカードに発信する手段と、 甲58l カードから受信した第1識別情報が要求した第1識別情報である か否かを判断する手段とを有し、 甲58m カードから受信した第1識別情報が要求した第1識別情報である と判断されたときに、カードとの間で第2のリクエスト信号に関 10 連する処理を行う 甲58n ことを特徴とする現金自動取引装置。 (3) 本件発明と甲58発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点) 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの 15 に対して、甲58発明では「カード」である点。 (4) 甲58文献の「カード」は、電波により外部と交信する送受信回路とマ イクロコンピュータを保持しており(2頁右下欄14行~3頁左上欄8行)、 ICカード(スマートカード)といえるところ、甲49文献には、POSシ ステムなどの外部システムとやり取りするスマートカード(すなわち、IC 20 カード)用の電子部品をセルラ電話(すなわち、携帯電話)に内蔵すること によって、携帯電話にICカードの機能を持たせ、RFインタフェースで通 信を行うという発明が開示されており、上記相違点に相当するといえる。 そして、甲49文献については上記9【第1審原告の主張】(4)に記載の とおりであり、甲49文献の記載は、甲58発明に甲49発明を適用するこ 25 とについて示唆しているといえるから、当業者にとっては、両者を組み合わ せることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることに 31 つき、阻害事由はない。 よって、甲58発明に甲49発明を組み合わせることにより、上記相違 点に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 (5) また、上記9【第1審原告の主張】(5)と同様に、甲58文献に触れた 5 当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用 することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、甲第27、32~ 35号証のいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件 訂正発明の構成に容易に想到する。 【第1審被告らの主張】 10 甲58文献は、現金自動取引装置に関する発明を開示しているだけであり、 「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないから、本件発明を進歩性欠 如の理由で無効にはできない。 14 争点1-2-18(訂正前の本件発明に関する甲59文献を主引用例とす る新規性・進歩性欠如)について 15 【第1審原告の主張】 (1) 本件発明の要旨認定について、上記9(争点1-2-13)【第1審原 告の主張】(1)に同じ。 (2) 甲59文献には、次の構成を有する発明(以下「甲59発明」という。) が記載されていると認められる。 20 甲59j セルラホン(cellular phone)と結合した携帯用 電子装置との間で変調されたRF信号またはIR識別信号を送受 信する ための 送信 手 段およ び受信 手段 を 有する 現金登 録装 置で あって、 甲59k 現金登録装置に設けられた“送信”キーの押下によって、UPC 25 データ(を含む識別信号IDS)の発信を求める呼び出し信号C ASを現金登録装置に近づけられたセルラホン(cellula 32 r phone)と結合した携帯用電子装置に発信する手段と、 甲59l セルラホン(cellular phone)と結合した携帯用 電子装置から受信した(識別信号IDSに含まれる)UPCデー タが要求したUPCデータであるか否かを判断する手段とを有し、 5 甲59m セルラホン(cellular phone)と結合した携帯用 電子装置から受信した(識別信号IDSに含まれる)UPCデー タが要求したUPCデータであると判断されたときに、携帯用電 子装置との間で処理を行う 甲59n ことを特徴とする現金登録装置。 10 (3) 本件発明は、甲59発明と同一であるから、新規性欠如の無効理由を有 する。 (4) 仮に、本件訂正発明と甲59発明は、次の点で相違し、その余の点で一 致するとしても、進歩性欠如の無効理由を有する。 (相違点) 15 本件発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるの に対して、甲59発明では「携帯用電子装置」である点。 (5) 甲59文献には、「携帯用電子装置100は・・・セルラホン(cel lular phone)・・・と結合し得る。」と記載されているのであるか ら、かかる記載に動機付けられて、(甲27、32~35、49も考慮すれ 20 ば)携帯用電子装置100を携帯電話とすることは容易に想到する。 また、甲49文献には、POSシステムなどの外部システムとやり取り するスマートカード(すなわち、ICカード)用の電子部品をセルラ電話 (すなわち、携帯電話)に内蔵することによって、携帯電話にICカードの 機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行う、という発明が開示されて 25 おり、上記相違点に相当するといえる。 そして、甲49文献は、POSシステムなどの外部システムとRFイン 33 タフェースでやり取りするという甲59発明と同じ技術に関する文献であり、 また、甲59文献には、「携帯用電子装置100は・・・移動通信装備 のポ ケットベル及びセルラホン(cellular phone)・・・と結合し得 る。 (5頁右上欄6~9行)と記載されており、当該記載は、甲59発明に 」 5 甲49発明を適用することについて示唆しているといえるから、当業者に とっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。また、 両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。 よって、甲59発明に甲49発明を組み合わせることにより、上記相違 点に係る本件発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。 10 (6) また、本件特許優先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触 ICカードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する 機器が、携帯電話と非接触で送受信を行うものとすることが広く行われてお り、受信装置を、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインター フェースを備えるものとすることは、甲第27、32~35号証に記載の事 15 項であって、周知技術になっていることが明らかであった。 よって、甲59文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、 当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動 機付けられ、甲第27、32~35号証のいずれかに記載の事項を適用する ことで、上記相違点に係る本件発明の構成に容易に想到する。 20 【第1審被告らの主張】 甲59文献は、電子識別システムに関する発明を開示しているだけであり、 「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないから、本件発明を進歩性欠 如の理由で無効にはできない。 15 争点1-3(訂正の再抗弁の成否)について 25 【第1審被告らの主張】 (1) 本件特許に係る訂正審判請求及び無効審判請求等 34 ア 第1審被告モビリティは、本件訴訟の第1審係属中(口頭弁論終結後、 判決言渡し前)である令和6年1月24日、本件特許の特許請求の範囲 及び明細書の訂正を求める訂正審判請求をした(訂正2024-390 011)。これに対し、第 1 審原告は、同年3月5日、本件特許について 5 の無効審判請求(無効2024-800018)をしたところ、特許庁 は、同年6月25日付けで、上記訂正審判請求を先に審理するとして、 上記無効審判請求の手続を中止する旨の通知を行った。そして、特許庁 は、同年10月22日付けで、上記訂正審判に係る訂正(以下「本件訂 正」という。)を認める旨の審決をし、同審決は確定した。 10 イ 本件訂正の訂正事項は、以下の特許請求の範囲の訂正を含むものであり、 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1、4及び5の記載は、以下のと おりである(下線部は訂正による訂正箇所を指す。本件訂正後の請求項 5に係る発明を「本件訂正発明」という。 。 ) 【請求項1】 15 RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話の スイッチを押すことで生成されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者 が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情 報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号 に応答して、RFIDインターフェースを有するRバッジに対して当該 20 Rバッジの製造時に書き込まれた書換不可能な識別情報であってRバッ ジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段 と、前記Rバッジより前記識別情報を受け取って、該受け取った識別情 報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段 と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前 25 記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記 アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するとい 35 う比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定 時間が経過する前に前記被保護情報へのアクセスがなされた場合には当 該アクセスを許可し、前記所定時間が経過した後に前記被保護情報への アクセスがなされた場合には当該アクセスを禁止することを特徴とする 5 携帯電話。 【請求項4】 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカー ド、クレジットカード、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、 公共施設のチケットのうち少なくとも1つであって、それらの中から1 10 つが選択され得ることを特徴とする請求項3記載の携帯電話。 【請求項5】(本件訂正発明) 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインター フェースを有する受信装置であって、当該受信装置に設けられた読み取 りスイッチの押下によって、前記選択した1つの新たな機能に対応する 15 個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信 する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情 報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で前記受信 した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記 携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。 20 (2) 本件訂正における訂正要件の充足 第1審被告モビリティは、本件訂正を行っているところ、これは、訂正 前の請求項5に記載された受信装置を限定するものである。 また、訂正前の請求項4において、新たな機能から「定期券、乗車券」 を削除するとともに、「それらの中から1つが選択され得る」と減縮訂正し 25 たことにより、訂正後の請求項5の「前記選択した1つの新たな機能に対応 する個別情報」に対する明瞭な「特定」がされている。 36 さらに、請求項1に関する訂正も、訂正前の請求項1の「アクセス制御 手段」の動作の意義を明瞭にするものである。 よって、本件訂正は訂正要件を満たす。 (3) 本件訂正による無効理由の解消 5 本件訂正により、訂正前の本件発明について主張されていた記載要件違反、 新規性・進歩例の欠如の無効理由については、全て解消される。 (4) 原告各製品が本件訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること ア 本件訂正発明の構成要件の分説 本件訂正発明(請求項5)は、次の構成要件に分説することができる。 10 下線部は本件訂正による訂正箇所を指す。以下の構成要件は、本件訂正 前の本件発明の構成要件JからNまでに対応するものである。 【請求項5】 J’請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDイン ターフェースを有する受信装置であって、 15 K’当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、前記 選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を当該受信 装置に近づけられた前記携帯電話に発信する発信手段と、 L 前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否 かを判断する判断手段とを有し、 20 M’前記判断手段で前記受信した個別情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う N ことを特徴とする受信装置。 イ 本件訂正発明の構成要件のうち、J’、Nについては、原告各製品がこ れを充足することについて、当事者間に争いがない。 25 ウ 構成要件K’については、例えば、原告各製品の所有者である客がSu icaでの決済を依頼すると、店員はタッチパネルによりSuicaに 37 対応した決済方法を表示させることになり、店員の選択により、被控訴 人各製品は、タッチパネルで選択された決済方法に応じてPollin gコマンドを、スマホ(「AUthentiGate Android ICカード認証パッケージ」スタンドアロンライセンスインストール済 5 みのAndroid3.2以降のNFC対応端末として、SHARP製 AQUOS R(NTTドコモ)のこと。以下「対象スマホ」という。) に発信する手段を有する。よって、原告各製品は本件訂正発明の構成要 件K’を有する。 エ 構成要件Lについては、Pollingコマンドに対象スマホが応答し 10 なければ、原告各製品の処理は中断され(中断するという判断手段を有 する。 、Pollingコマンドに対象スマホが応答すれば、原告各製 ) 品はスマホからIDmとPMmを受信する。そして、IDmの製造者 コード等で個別情報(原告各製品では、店員が設定した電子マネー・ク レジットカード等の個別情報)かどうかが判断される。原告各製品は、 15 以上のような判断手段を有するので、構成要件Lを満たす。 オ そして、原告各製品は、受信した個別情報が要求した個別情報であると 判断したときに、スマホとの間で処理を行うので、構成要件Mも満たす。 カ 以上のとおり、原告各製品は、本件訂正発明の技術的範囲に属するもの である。 20 (5) 第1審原告による時機に後れた攻撃防御方法の主張については、争う。 【第1審原告の主張】 (1) 第1審被告らの訂正の再抗弁に関する主張は、本件各通知行為について 不正競争防止法等に基づく損害賠償請求が成立するかについて、本件各通知 行為後の事情を考慮すべきとするものであり、失当である。 25 仮に、上記の点を措くとしても、以下に述べるように、第1審被告らの主 張は理由がない。 38 (2) 訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当たること 第1審原告は、原審における審理計画に従って無効の抗弁を主張してい るところ、第1審被告らは訂正の再抗弁を主張することが可能であったにも かかわらず、1年以上にわたって訂正の再抗弁を一切主張しなかった。しか 5 も、第1審被告らは、控訴審になって初めて本件訂正に係る訂正の再抗弁を 主張したが、原告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属することを具体的 に主張立証せず、第1審原告において反論を尽くすことが必要となり、訴訟 の完結が遅延されることになることは明らかである。よって、本件訂正に係 る訂正の再抗弁は、時機に後れたものであるとして、却下されるべきである。 10 (3) 本件訂正発明の非充足について 第1審被告らが主張するように、仮に、本件訂正発明の「請求項4記載 の(携帯電話)」が、訂正後の請求項5に係る本件訂正発明(受信装置)の 構造、機能等を特定するものであったとしても、第1審被告らが主張する侵 害根拠である対象スマホは、訂正前の請求項4の構成要件を充足しないから、 15 同様の理由で、訂正後の請求項4の構成要件を充足しない。 そして、第1審被告らは、原告各製品のうち、具体的にいずれの構成を もって本件訂正発明の技術的範囲に属するというのか不明であるし、この点 を措くとしても、原告各製品は、訂正前の請求項5の構成要件を充足しない から、少なくとも、同様の理由で、訂正後の請求項5の構成要件を充足しな 20 い。 16 争点1-4-1(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・本件訂正の訂正要件 が認められないこと)について 【第1審原告の主張】 本件訂正は訂正要件を満たしておらず、本件訂正発明に係る本件特許には特 25 許法123条1項8号の無効理由があるから、第1審被告らの訂正の再抗弁に 関する主張は全て失当である。 39 (1) 訂正事項3について 訂正前の請求項1の文言は、それ自体意味が明瞭であり、2つの解釈が なされ得るようなものではない。よって、同請求項を訂正する訂正事項3は、 明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当せず、目的外訂正であって、 5 認められるものではない。 また、上記訂正は、「所定時間」の間の期間に被保護情報へのアクセスが あれば、そのアクセスから継続するアクセスは、「所定時間」を経過した後 であっても許可される態様を含むものであるところ、本件明細書には、この ような態様について記載も示唆もされていないから、訂正事項3は新規事項 10 を追加する訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正でも あるから、認められるものではない。 そして、訂正事項3が特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないこ とから、訂正事項9(本件明細書段落【0011】における請求項1の記載 に関して上記同様に訂正するもの。)も明瞭でない記載の釈明を目的とする 15 ものに該当しない。 (2) 訂正事項5について 本件明細書には、受信装置60において、携帯端末10で選択した1つ の新たな機能に対応する個別情報の発信要求を携帯端末10に発信すること は記載も示唆もされておらず、むしろ、受信装置60にあらかじめ指定され 20 ている機能(カード)の個別情報(カード情報340)の発信要求を携帯端 末10に発信することが記載されているのであるから、訂正事項5は、新規 事項を追加する訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正 でもあるから、認められるものではない。 そして、訂正事項5が認められないから、訂正事項11(本件明細書段 25 落【0015】における請求項5の記載に関して上記同様に訂正するもの。) も認められない。 40 【第1審被告らの主張】 争う。本件訂正が訂正要件を満たすことについては、上記15における【第 1審被告らの主張】のとおりである。 17 争点1-4-2(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・サポート要件違反) 5 について 【第1審原告の主張】 (1) 訂正前の本件発明に関するサポート要件違反(無効理由2)のうち、原 判決「事実及び理由」の第3の6(争点1-2-2。15頁~) (原告の主 「 張)」(2)(「第三者による不正使用を確実に防止する」との課題が解決でき 10 ると認識できない。)に同旨。 (2) 訂正後の請求項5の「前記選択した1つの新たな機能に対応する個別情 報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」に関し、本件明細書には、受 信装置60にあらかじめ指定されている機能(カード)の個別情報(カード 情報340)の発信要求を携帯端末10に発信することが記載されているの 15 みであり、受信装置60において、携帯端末10で選択した新たな機能に対 応する個別情報の発信要求を携帯端末10に発信することは記載も示唆もさ れていないから、訂正後の請求項5は、発明の詳細な説明に記載された発明 ではない。 よって、訂正後の請求項5に係る発明(本件訂正発明)はサポート要件 20 違反の無効理由を有するから、訂正の再抗弁は成り立たない(無効理由13 のうちのサポート要件違反1)。 (3) 仮に、控訴人らの解釈のとおり、本件訂正発明の構成要件J’について 「請求項4記載の(携帯電話)」という事項を考慮すべきであるとしても、 訂正後の請求項5の記載は、当業者が課題を解決できると認識できる範囲に 25 はないから、本件訂正発明はサポート要件違反の無効理由を有する(無効理 由13のうちのサポート要件違反2)。 41 【第1審被告らの主張】 争う。 18 争点1-4-3(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・実施可能要件違反) について 5 【第1審原告の主張】 (1) 訂正前の本件発明に関する実施可能要件違反(無効理由3)のうち、原 判決「事実及び理由」の第3の7(争点1-2-3。17頁~) (原告の主 「 張)」の3段落目(過度の試行錯誤に関する主張)に同旨。 (2) 訂正後の請求項5の「前記選択した1つの新たな機能に対応する個別情 10 報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」に関し、本件明細書には、携 帯端末10で選択した機能(カード)が何であるのかが、携帯端末10から 受信装置60へと通知されることは記載も示唆もされておらず、受信装置6 0では、携帯端末10で選択した機能(カード)が何であるのかを知り得な い。受信装置60において、携帯端末10で選択した1つの新たな機能に対 15 応する個別情報の発信要求を携帯端末10に発信することは不可能であり、 当業者は、訂正後の請求項5の受信装置を作ることができない。 よって、訂正後の請求項5に係る発明(本件訂正発明)は実施可能要件 違反の無効理由を有する(無効理由14のうちの実施可能要件違反1)。 (3) 仮に「請求項4記載の」という事項を考慮すべきであるとしても、第1 20 審被告の解釈を前提とすれば、訂正後の請求項5の受信装置は、当業者が課 題を解決できると認識できる範囲にはないから、本件発明の目的(かかる課 題解決)を達成するためには、少なくとも過度の試行錯誤を要することは明 らかである。よって、本件訂正発明は実施可能要件違反の無効理由を有する (無効理由14のうちの実施可能要件違反2)。 25 【第1審被告らの主張】 争う。 42 19 争点1-4-4(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲27文献を主引用 例とする新規性又は進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 本件訂正発明の要旨認定(「請求項4記載の(携帯電話)」の除外)、甲 5 27発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び 理由」の第3の8(争点1-2-4。18頁~) (原告の主張) 「 」に同旨。 なお、本件訂正発明の要旨認定において、構成要件J’の「請求項4記載の (携帯電話)」を除外すべきであることについては、後記のいずれの無効の 抗弁においても同じである。 10 (2) 甲27発明・甲27’発明と、本件訂正発明を対比すると、仮に相違点 があるとしても、これまでに述べた相違点のほか、本件訂正によって生じる 相違点があるとしても、高々、次の点にとどまる。 (相違点1) 本件訂正発明は、「当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下に 15 よって、・・・発信要求を・・・発信する発信手段」を備えているのに対し て、甲27発明・甲27’発明は、受信装置に設けられた読み取りスイッチ の押下によって発信要求を発信する発信手段を備えているといえない点(あ るいはこの点が不明である点)。 (相違点2) 20 本件訂正発明は、「発信要求を当該受信装置に近づけられた」通信対象に 「発信する発信手段」を備えているのに対して、甲27発明・甲27’発明 は、かかる構成を備えているか不明である点。 そして、相違点1に関して、装置一般において、何らかの動作について、 スイッチの押下によって当該動作を行わせるように構成することは、一般常 25 識ともいえる技術常識であることは顕著な事実であって、相違点1は具体化 手段における微差にすぎず、実質的な相違点ではない。 43 仮に、実質的な相違点であるとしても、甲27発明ないし甲27’発明 において、「発信要求を・・・発信」し続けることによる電力の消費という自 明の課題等に動機付けられて、かかる技術常識に基づき、同発明において、 「当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、・・・発信要 5 求を・・・発信する発信手段」に相当する構成を備えるものとすることは容易 に想到する。 また、相違点2に関して、甲27発明・甲27’発明は、受信装置に相 当する構成が、携帯電話その他の通信対象と無線通信を行うものであり、無 線通信が可能な距離は限られるのは当然であるから、「発信要求を当該受信 10 装置に近づけられた」通信対象に「発信する発信手段」に相当する構成を本 来的に備えている。したがって、相違点2は、実質的な相違点ではない。仮 に、実質的な相違点であるとしても、当業者が適宜設計する事項にすぎず、 容易に想到るものである。 よって、本件発明は、甲27発明・甲27’発明によって無効であると 15 ころ、本件訂正により本件訂正発明との間で生じる相違点は、実質的な相違 点ではないか、容易に想到できるものであるから、本件訂正によって無効理 由を解消することができない。よって、訂正の再抗弁は、成り立たない。 (3) さらに、仮に、第1審被告らの主張のとおり、本件訂正発明の構成要件 J’について「請求項4記載の(携帯電話)」という事項を考慮し、甲27 20 発明・甲27’発明と本件訂正発明に以下の形式的な相違点3又は相違点3’ があるとしても、具体化手段における微差にすぎないか、少なくとも容易に 想到できるものにすぎない(この点は、後記(20)~(27)、(28)~(33)の各 主引用例との関係でも同様である。 。 ) (相違点3) 25 本件訂正発明は、「請求項1記載の」の点を除き、請求項3の発明特定事 項及び請求項4の発明特定事項を前提とする「前記選択した1つの新たな機 44 能に対応する・・・(個別)情報の発信要求を・・・発信する発信手段」との構 成を有するのに対して、甲27発明・甲27’発明は、かかる構成を備えて いるか不明である点 (相違点3’) 5 本件訂正発明は、「前記選択した1つの新たな機能に対応する・・・(個別) 情報の発信要求を・・・発信する発信手段」との構成を有するのに対して、甲 27発明・甲27’発明は、かかる構成を備えているか不明である点 【第1審被告らの主張】 本件訂正発明の請求項5記載の「受信装置」は、訂正後の請求項4記載の 10 「携帯電話」を引用する(従属する)「受信装置」の発明であり、本件訂正発 明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード情報」を意味 していることは明らかである。これに対し、甲27発明の「駅識別番号及び端 末識別番号」は、駅の識別番号及び端末の識別番号であり、明らかにカードの 種別を示す情報ではない。よって、当業者は、甲27 発明から、本件訂正発明 15 の「受信装置」には容易に想到せず、進歩性欠如の無効理由は認められない。 20 争点1-4-5(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲32文献を主引用 例とする新規性又は進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲32発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事 20 実及び理由」の第3の9(争点1-2-5。25頁~) (原告の主張) 「 」に 同旨 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲32) 【第1審被告らの主張】 25 本件訂正発明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード 情報」を意味していることは明らかであり、当業者であれば、「個別情報」を 45 カードの種別を示す情報であると理解する。これに対し、甲32発明の「チ ケットデータ」とは、自動改札を通過するだけにのみ必要なデータ(すなわち、 定期券や乗車券に相当するデータ)であって、チケットデータごとに異なる通 し番号が割り振りされるものである。したがって、甲32発明は、本件訂正発 5 明の「発信手段」や「判断手段」に対応する構成について何ら開示も示唆もし ていない。 よって、甲32発明から、本件訂正発明の「受信装置」には容易に想到せず、 進歩性欠如の無効理由は認められない。 21 争点1-4-6(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲29文献を主引用 10 例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲29発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事 実及び理由」の第3の10(争点1-2-6。30頁~) (原告の主張) 「 」 に同旨 15 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲29) 【第1審被告らの主張】 無効理由が成立しないことについて、上記2(争点1-2-6)【第1審被 告らの主張】に同旨 20 22 争点1-4-7(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲30文献を主引用 例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲30発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事 実及び理由」の第3の11(争点1-2-7。35頁~) (原告の主張) 「 」 25 に同旨 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 46 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲30) 【第1審被告らの主張】 無効理由が成立しないことについて、上記3(争点1-2-7)【第1審被 告らの主張】に同旨 5 23 争点1-4-8(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲36文献又は甲3 6製品を主引用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲36発明・甲36製品の認定及び引用例との一致点・相違点について、 原判決「事実及び理由」の第3の12(争点1-2-8。38頁~) (原告 「 10 の主張)」に同旨 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲36) 【第1審被告らの主張】 無効理由が成立しないことについて、上記4(争点1-2-8)【第1審被 15 告らの主張】に同旨 24 争点1-4-9(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲45文献を主引用 例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲45発明の認定、引用例との一致点・相違点について、上記5(争点 20 1-2-9)【第1審原告の主張】に同旨 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)に同旨(ただし、主引用例は甲45) 【第1審被告らの主張】 上記5(争点1-2-9)【第1審被告らの主張】に同旨(本件訂正発明の 25 請求項5記載の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に対応す る個別情報の発信要求」についても何ら開示も示唆もしていない。) 47 25 争点1-4-10(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲46文献を主引 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 甲46発明の認定、引用例との一致点・相違点について、上記6(争点 5 1-2-10)【第1審原告の主張】に同旨 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)に同旨(ただし、主引用例は甲46) 【第1審被告らの主張】 上記6(争点1-2-10)【第1審被告らの主張】に同旨(本件訂正発明 10 の請求項5記載の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に対応 する個別情報の発信要求」についても何ら開示も示唆もしていない。) 26 争点1-4-11(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲48文献を主引 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 15 (1) 甲48発明の認定、引用例との一致点・相違点について、上記7(争点 1-2-11)【第1審原告の主張】に同旨。ただし、本件訂正発明の請求 項3及び請求項4に記載の事項も本件特許優先日当時に周知の技術事項で あったことについて、甲第49、50、63~65号証を追加する。 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 20 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲48) 【第1審被告らの主張】 無効理由が成立しないことについて、上記7(争点1-2-11)【第1審 被告らの主張】に同旨 27 争点1-4-12(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲53文献を主引 25 用例とする拡大先願違反)について 【第1審原告の主張】 48 (1) 甲53発明の認定、引用例との一致点・相違点について、上記8(争点 1-2-12)【第1審原告の主張】に同旨。ただし、本件訂正発明の請求 項3及び請求項4に記載の事項も本件特許優先日当時に周知の技術事項で あったことについて、甲第49、50、63~65号証を追加する。 5 (2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記19(争点1-4- 4)【第1審原告の主張】(2)及び(3)に同旨(ただし、主引用例は甲53) 【第1審被告らの主張】 無効理由が成立しないことについて、上記8(争点1-2-12)【第1審 被告らの主張】に同旨 10 28 争点1-4-13(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲54文献を主引 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1)ア 受信装置が、携帯電話で選択した1つの新たな機能に対応する個別情 報の発信要求を携帯電話に発信することは、本件明細書に記載も示唆もさ 15 れていない。むしろ、本件明細書には、受信装置にあらかじめ指定されて いる機能の個別情報の発信要求を携帯電話に発信することが記載されてい る。したがって、構成要件K’の「前記選択した1つの新たな機能に対応 する」の部分は、本件明細書に開示がないから、ないものとして解釈し、 本件明細書の段落【0092】に受信装置側の構成として開示されている 20 「読み取りスイッチの押下によって」個別情報の発信要求を行う構成と解 釈する場合のみ、訂正要件を充足する。したがって、仮に請求項5に対し ての本件訂正が認められるとしても、構成要件K’について、次のとおり の構成要件K’’と解釈して検討すべきである。 「K’’当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、個別 25 情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信する 発信手段と、」 49 イ また、この点を措くとしても、仮に、「前記選択した1つの新たな機能」 とは、請求項4記載の携帯電話において選択された新たな機能を意味す るとすれば、「前記選択した1つの新たな機能」の部分は「他の装置」に 関する事項であって、この点においても、本件訂正発明は、二つ以上の 5 装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる 情報処理装置(受信装置)の発明であるから、サブコンビネーション発 明と解される。そして、本件訂正発明の受信装置が「個別情報の発信要 求を・・・前記携帯電話に発信」するとしても、かかる受信装置の発信要求 がどのような意味を有するかは(前記選択した1つの新たな機能に対応 10 する個別情報の発信要求であるか否かは) 前記携帯電話の構成に依存す 、 る。したがって、「前記選択した1つの新たな機能に対応する」との部分 は、本件訂正発明に係る受信装置の構造、機能等を何ら特定していない から、これを除外して本件訂正発明の要旨を認定すべきであって、構成 要件K’’を前提として、無効理由を検討すべきものである。 15 ウ よって、本件訂正発明において、上記の「前記選択した1つの新たな機 能に対応する」を除外して発明の要旨を認定すべきである。 (2) 甲54発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい ては、上記9(争点1-2-13)【第1審原告の主張】(2)から(5)までに 同旨 20 【第1審被告らの主張】 上記9(争点1-2-13)【第1審被告らの主張】に同旨(本件訂正発 明の請求項5記載の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に 対応する個別情報の発信要求」についても何ら開示も示唆もしていない。) 29 争点1-4-14(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲55文献を主引 25 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 50 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記28(争点1-4-13)【第 1審原告の主張】(1)に同旨 (2) 甲55発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい ては、上記10(争点1-2-14)【第1審原告の主張】(2)から(5)まで 5 に同旨 【第1審被告らの主張】 (1) 甲55文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示 しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだ けでなく、本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1 10 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら 開示も示唆もしていない。本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」 は、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信す るためのものであるのに対し、乙30文献に記載の「商品選択ボタン210」 は、商品を選択するためのボタンであって、「選択した1つの新たな機能に 15 対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。 よって、甲55発明は、構成要件K’の「発信手段」を備えていない。 (2) また、本件訂正発明の請求項5の「個別情報」とは、複数種類の複数の カード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、甲 55発明の「電子マネーの残金情報」は、明らかに「カードの種別を示す識 20 別情報」ではあり得ない。つまり、構成要件K’の「個別情報」は、甲55 発明の「電子マネーの残金情報」には該当せず、甲55発明は本件訂正発明 の構成要件Lの「判断手段」の構成を備えていない。 (3) さらに、甲49文献も、「読み取りスイッチ」 「発信手段」及び「判断 、 手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。 25 (4) よって、本件訂正発明について、甲55発明を主引用例とし、甲49発 明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には 51 できない。 30 争点1-4-15(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲56文献を主引 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 5 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記28(争点1-4-13)【第 1審原告の主張】(1)に同旨 (2) 甲56発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい ては、上記11(争点1-2-15)【第1審原告の主張】(2)から(5)まで に同旨 10 【第1審被告らの主張】 (1) 甲56文献は、非接触型プリペイドカード方式メータに関する発明を開 示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない だけでなく、本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した 1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何 15 ら開示も示唆もしていない。 (2) すなわち、甲56文献の「非接触型プリペイドカード1」は、本件訂正 発明の「携帯電話」と異なり、1つの機能(電子マネーとしての機能)しか 有していない。また、本件訂正発明の「前記選択した1つの新たな機能に対 応する個別情報の発信要求」と、甲56発明の「ガスメータ7側から発信さ 20 れた起動用電波」とは明らかに異なる。さらに、本件訂正発明の請求項5の 「個別情報」(構成要件K’)とは、複数種類の複数のカード類から選択した 1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙31発明の「ID番号 とプリペイド金額」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあり 得ない。 25 したがって、甲56発明は構成要件Lの「判断手段」の構成を備えていな い。 52 (3) さらに、甲56発明の「料金投入スイッチ13」は、プリペイドカード を使用して料金の支払を行うためのスイッチであるところ、本件訂正発明の 請求項5記載の「読み取りスイッチ」は、「前記選択した1つの新たな機能 に対応する個別情報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」ためのもの 5 であるから、明らかにその使用目的や働き・作用が異なる。 よって、甲56発明は、本件訂正発明の構成要件K’の「発信手段」も備 えていない。 (4) さらに、甲49文献も、「読み取りスイッチ」 「発信手段」及び「判断 、 手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。 10 (5) よって、本件訂正発明について、甲56発明を主引用例とし、甲49発 明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には できない。 31 争点1-4-16(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲57文献を主引 用例とする進歩性欠如)について 15 【第1審原告の主張】 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記28(争点1-4-13)【第 1審原告の主張】(1)に同旨 (2) 甲57発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい ては、上記12(争点1-2-16)【第1審原告の主張】(2)から(5)まで 20 に同旨 【第1審被告らの主張】 (1) 甲57文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示 しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだ けでなく、本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1 25 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら 開示も示唆もしていない。 53 (2) すなわち、本件訂正発明の請求項5に記載の「読み取りスイッチ」は、 「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するた めのものであるのに対して、甲57文献に記載された「購入金額選択ボタン」 は、購入金額を選択するためのボタンであって、「選択した1つの新たな機 5 能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。 よって、甲57発明は、本件訂正発明の構成要件K’の「発信手段」も備 えていない。 (3) さらに、本件訂正発明の請求項5の「個別情報」とは、複数種類の複数 のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、 10 甲57発明の「残高」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあ り得ない。つまり、構成要件K’の「個別情報」は、甲57発明の「残高」 には該当せず、甲57発明は本件訂正発明の構成要件Lの「判断手段」の構 成を備えていない。 (4) さらに、甲49文献も、「読み取りスイッチ」 「発信手段」及び「判断 、 15 手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。 (5) よって、本件訂正発明について、甲57発明を主引用例とし、甲49発 明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には できない。 32 争点1-4-17(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲58文献を主引 20 用例とする進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記28(争点1-4-13)【第 1審原告の主張】(1)に同旨 (2) 甲58発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい 25 ては、上記13(争点1-2-17)【第1審原告の主張】(2)~(5)に同旨 【第1審被告らの主張】 54 (1) 甲58文献は、現金自動取引装置に関する発明を開示しているだけであ り、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂 正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に 対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もして 5 いない。 (2) すなわち、本件訂正発明の請求項5に記載の「読み取りスイッチ」は、 「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するた めのものであるのに対して、甲58文献に記載された「リクエストスイッチ」 は、第1識別情報を読み出すために第1のリクエスト信号を送出するための 10 スイッチであって、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信 要求」を発信するためのものではない。 よって、甲58発明は、本件訂正発明の構成要件K’の「発信手段」も備 えていない。 (3) さらに、本件訂正発明の請求項5の「個別情報」とは、複数種類の複数 15 のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、 甲58発明の「第1識別情報」は、甲第58号証の3頁下段に「また第1識 別情報は、例えば全ての利用客が所有するカード2について同じ内容であり」 と記載されているとおり、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあ り得ない。つまり、構成要件K’の「個別情報」は、甲58発明の「第1識 20 別情報」には該当せず、甲58発明は本件訂正発明の構成要件Lの「判断手 段」の構成を備えていない。 (4) さらに、甲49文献も、「読み取りスイッチ」 「発信手段」及び「判断 、 手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。 (5) よって、本件訂正発明について、甲58発明を主引用例とし、甲49発 25 明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には できない。 55 33 争点1-4-18(訂正発明に係る無効の抗弁の成否・甲59文献を主引 用例とする新規性・進歩性欠如)について 【第1審原告の主張】 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記28(争点1-4-13)【第 5 1審原告の主張】(1)に同旨 (2) 甲59発明の要旨認定、本件訂正発明との対比及び相違点の判断につい ては、上記14(争点1-2-18)【第1審原告の主張】(2)から(5)まで に同旨 【第1審被告らの主張】 10 (1) 甲59文献は、電子識別システムに関する発明を開示しているだけであ り、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂 正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に 対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もして いない。 15 (2) すなわち、本件訂正発明の請求項5に記載の「読み取りスイッチ」は、 「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するた めのものであるのに対して、甲59文献に記載された「“送信”キー」は、 呼び出し信号CASを送り出すためのキーであって、「選択した1つの新た な機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。 20 よって、甲59発明は、本件訂正発明の構成要件K’の「発信手段」も備 えていない。 (3) さらに、本件訂正発明の請求項5の「個別情報」とは、複数種類の複数 のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、 甲59発明の「UPCデータ」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」 25 ではあり得ない。つまり、構成要件K’の「個別情報」は、甲59発明の 「UPCデータ」には該当せず、甲59発明は本件訂正発明の構成要件Lの 56 「判断手段」の構成を備えていない。 (4) したがって、本件訂正発明について甲59発明を主引用例として新規性 欠如の理由により無効にはできない。 (5) さらに、甲49文献も、「読み取りスイッチ」 「発信手段」及び「判断 、 5 手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。 よって、本件訂正発明について、甲59発明を主引用例とし、甲49発明 の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効にはで きない。 34 争点1-5(第1審被告らによる虚偽告知の内容)について 10 【第1審原告の主張】 本件各通知行為による損害主張として、原判決「事実及び理由」第3の13 「(原告の主張) (43頁)記載に同旨である。 」 【第1審被告らの主張】 第1審原告の本件通知行為2に関する主張も争う。 15 35 争点3(第1審被告らの故意又は過失の有無)及び争点4(第1審被告Y の悪意又は重過失による任務懈怠の有無)について 【第1審原告の主張】 第1審原告は、原判決が判断した無効理由である甲32文献を主引用例とす る新規性欠如(争点1-2-5の一部)の主張のみならず、多数の無効理由を 20 主張しており、これら全てを前提に本件各通知行為が「虚偽の事実を告知」す るものであり、不正競争行為に該当すると主張しているのであるから、第1審 被告らの故意・過失などについても、これら全ての無効理由を判断した上で認 定されるべきである。本件ではこれら全ての無効理由が認められるべきであり、 第1審被告らの故意・過失などは当然に認められる。 25 【第1審被告らの主張】 争う。 57 36 第1審原告の損害発生の有無及び損害額(争点5)について 【第1審原告の主張】 (1) 第1審被告モビリティに対する請求については、本件通知行為1に係る 請求において4503万7856円の損害賠償を優先的に求め、当該請求に 5 より認められない損害部分について、本件通知行為2に係る請求をする。 (2) 第1審被告Yに対する請求についても、上記同様、本件通知行為1に係 る請求において4503万7856円の損害賠償を優先的に求め、当該請求 により認められない損害部分について、本件通知行為2に係る請求をする。 【第1審被告らの主張】 10 争う。 58 |