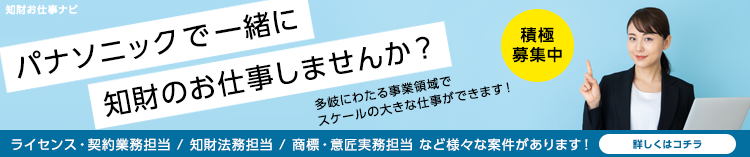| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
5年
(ネ)
10040号
損害賠償請求控訴事件
|
|---|---|
|
令和7年3月19日判決言渡 令和5年(ネ)第10040号 損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第5905号) 口頭弁論終結日 令和7年1月27日 5判決 控訴人株式会社東海医科 同訴訟代理人弁護士 大野聖二 10 多田宏文 同訴訟復代理人弁護士 亀山和輝 被控訴人Y 15 同訴訟代理人弁護士 越野周治 高本紗斗美 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/03/19 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1503万2196円20 及び別紙1認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金額に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合による金銭を支払え。 3 控訴人の当審におけるその余の追加請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを8分し、そ25 の7を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 -1-5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
5 1 控訴の趣旨 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人は、控訴人に対し、1億円及び別紙2請求額一覧表の「各月請求 額」欄記載の各金額に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済 みまで年3%の割合による金銭を支払え(控訴人は、当審において、原審に10 おける元本1000万円及びこれに対する遅延損害金の請求を、このように 拡張した。)。 2 控訴の趣旨に対する答弁 (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。 15 第2 事案の概要 本判決の本文中で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、別紙3略 語一覧のとおりである。また、本判決において、特許法を「法」という。 1 請求の要旨 控訴人は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」20 とする本件特許の特許権者である。被控訴人は、医師であって、令和元年頃か ら令和4年頃にかけて、本件クリニックにおいて、豊胸手術等の美容医療サー ビスを提供していた者である。 本件は、被控訴人が平成31年(令和元年)から令和4年3月10日(訴え 提起の日)までの間、血液豊胸手術に用いるために複数の薬剤を調合して一の25 薬剤としたことは本件特許権を侵害する行為に当たるとして、控訴人が、原審 において、民法709条に基づき、被控訴人に対し、損害賠償金1000万円 及びこれに対する令和4年4月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで 民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 原審の判断 原審は、被控訴人が複数の薬剤を調合して本件発明の技術的範囲に含まれる5 薬剤を製造したとは認められないとして、控訴人の請求を棄却した。 3 控訴の提起と請求の拡張 控訴人は、原判決を不服として控訴を提起し、当審において、被控訴人が複 数の薬剤を調合して一の薬剤とすることに加えて、被控訴人が複数の薬剤を 別々に被施術者に注射して体内においてこれらの薬剤を混ざり合わせることも、 10 本件特許権(又は独占的通常実施権)を侵害する行為であると主張を追加した。 また、控訴人は、当審において、請求の対象期間を平成31年1月1日から令 和6年5月24日までとした上で、損害賠償金1億円(ただし、具体的主張と しては、少なくとも令和2年5月から令和3年7月にかけて受けた損害額と主 張する2億2269万7768円の一部請求)及びこれを各月に発生した損害15 額に応じて割り付けた額に対する当該月末日の翌日(翌月1日)から支払済み までの民法所定の年3%の割合による遅延損害金の請求(第1の1(2))へと拡 張し、法102条2項又は3項の適用を主張する。 |
|
|
前提事実
1 本件特許権等20 (1) 本件特許及び本件発明(甲2) 本件特許は、Aが、平成24年2月24日、A自身を発明者として特許出 願し、平成25年1月25日に設定登録がされたものである。 本件発明(特許請求の範囲の請求項4記載の発明のうち、請求項1記載の 発明を引用する発明)は、次のとおりである。 25 「自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳 剤を含有してなることを特徴とする、豊胸のために使用する、皮下組織増加 促進用組成物。」 (2) 本件特許権の帰属等(甲1、16、乙10) 控訴人は、医療機器の販売・賃貸等を目的とする株式会社である。 控訴人は、Aから本件特許権の譲渡を受け、平成26年11月12日付け5 で、その移転登録がされた。 本件特許権については、令和3年1月25日を納付期限の末日とする第9 年分の特許料不納付を原因として、令和4年7月13日に抹消登録がされた が、錯誤発見を原因として、令和5年1月10日に回復登録がされた。この ため、法112条の3第2項1号の規定により、本件特許権の効力は、令和10 3年7月26日から令和5年1月9日までの間にされた本件発明の実施行為 には及ばない。 2 被控訴人の行為等(甲3、4、9、乙31、40、41) 医師である被控訴人は、令和元年6月10日に本件クリニックを開設し、令 和4年10月頃までのうちの一定の期間、同所において、「無細胞プラズマジ15 ェル」を用いた「3WAY血液豊胸」という名称の本件手術を提供していた。 被控訴人が本件手術に用いていた薬剤の成分のうち、「トラフェルミン(販売 名:フィブラスト) は本件発明の 」 「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」 に、「イントラリポス」は本件発明の「脂肪乳剤」に相当する。 3 債権譲渡通知(甲30(以下、特記しない限り、書証の枝番号の表記は省略20 する。)、弁論の全趣旨) Aの代理人弁護士は、令和6年5月22日、被控訴人に対し、Aのためにす ることを示して、被控訴人による本件特許権侵害を理由とするAが有する損害 賠償請求権及び不当利得返還請求権並びにこれらに対する利息請求権を控訴人 に全て譲渡した旨の通知をした。 25 第4 争点 1 構成要件充足性に関する争点 本件では、主要な争点の一つとして、被控訴人が本件手術に用いる薬剤を製 造したことが、本件発明の実施行為としての「生産」に当たるかが問題となっ ている。 そこで、まず、①被控訴人が用いた薬剤の一成分である「無細胞プラズマジ5 ェル」が本件発明の「自己由来の血漿」に相当するか(争点1-1)が問題と なる。 次に、事実認定上の争点として、被控訴人による本件手術の態様に争いがあ り、②被控訴人が、本件手術に用いる薬剤として、被施術者に投与する前に、 血漿、トラフェルミン及びイントラリポスという三成分を混合した一の薬剤(組10 成物)を製造したか(争点1-2)が問題となる。 被控訴人は、本件手術の態様として、血漿及びトラフェルミンを含む「A剤」 と、イントラリポスを含む「B剤」とを別々に被施術者に投与していたと主張 するが、仮に本件手術がこのような態様であったと認められるとしても、被施 術者の体内で「A剤」と「B剤」とが混ざり合うから、③被控訴人が「A剤」15 と「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生 産」に当たるか(争点1-3)が問題となる。 2 特許有効性に関する争点 被控訴人は、特許無効の抗弁(法104条の3)を提出する。 本件発明は「豊胸用組成物」という「物の発明」として特許されている。し20 かし、被控訴人は、当該組成物について、その製造のために被施術者の体内(人 体)から血液を採取する必要がある上、これをそのまま被施術者の皮下(人体) に投与することが前提となっているから、本件発明は、「物の発明」の形であ りながら、実質的には「豊胸手術のための方法の発明」であり、現に、被控訴 人が行う医療行為である本件手術が実質的に特許権行使の対象になっていると25 主張する。 そこで、①本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条1 項柱書き)に違反した無効理由があるか(争点2-1)が問題となる。 また、被控訴人は、本件特許の無効理由として、②サポート要件違反(争点 2-2)及び③明確性要件違反(争点2-3)も主張する。 3 特許権の効力が及ばない範囲に関する争点5 被控訴人は、本件特許権の効力は、被控訴人の行為には及ばないと主張する。 具体的には、①試験又は研究のための実施の免責規定(法69条1項)の適 用(争点3-1)、②調剤行為の免責規定(同条3項)の適用(争点3-2) 及び③権利の濫用等(争点3-3)を主張し、その適否が問題となる。 4 損害に関する争点10 被控訴人による本件特許権(又は独占的通常実施権)の侵害が認められたと きは、被控訴人が賠償すべき損害額が問題となる。控訴人は、まず法102条 2項による損害額の計算を主張するから、本件において同項が適用されるかが 問題となる(争点4-1)。また、控訴人は、選択的に、同項により算定され る損害額のほか、同条3項により算定される損害額も主張するから、これらの15 算定による損害額(争点4-2)が問題となる。 |
|
|
当事者の主張
1 争点1-1(「無細胞プラズマジェル」は本件発明の「自己由来の血漿」に 相当するか)について (控訴人の主張)20 本件明細書等には、本件発明の「血漿」の意義は定義されていない。明細書 の技術用語は学術用語を用い、用語はその有する普通の意味で使用するとされ ているから、生化学分野における辞書等を参照すると、「血漿」とは、「血液 から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体」、「血液中から血球を取除い た成分」とある。被控訴人が用いていた「無細胞プラズマジェル」は、被施術25 者から採取した血液を遠心分離して細胞成分を完全に除いた血漿というのであ るから、本件発明の「自己由来の血漿」に相当する。 被控訴人は、出願時における出願人の意見書等(乙3、4)に基づき、本件 発明の「自己由来の血漿」は「乏血小板血漿(PPP)」に限定して解釈され るべきであり、被控訴人が本件手術で使用していた「無細胞プラズマジェル」 は、細胞成分を完全に除いた血漿(NCP)から製造したものであるから、本5 件発明の「血漿」に当たらないと主張する。しかし、上記の出願人の意見は、 本件発明の実施態様の一つである乏血小板血漿(PPP)と引用文献に記載さ れた多血小板血漿(PRP)とは区別される旨を述べるにとどまり、「自己由 来の血漿」が「乏血小板血漿(PPP)」に限定されるとは述べていない。か えって、「血漿」につき、「血液から血球成分である赤血球、白血球並びに血10 小板を取り除いた血液に含まれる液体成分である」と述べており、これは控訴 人の上記解釈に整合的である。したがって、被控訴人の解釈は誤りである。 (被控訴人の主張) 審査時に出願人が提出していた意見書等(乙3、4)には、出願人の意見と して、「本願発明の血漿は、血液から血球成分である赤血球、白血球並びに血15 小板を取り除いた血液に含まれる液体成分である乏血小板血漿(PPP: Platelet Poor Plasma)であり、乏血小板血漿とは血小板を殆ど含まない血漿 である」との記載がある。したがって、本件発明における「自己由来の血漿」 とは「乏血小板血漿(PPP)」のみを意味すると限定して解釈されるべきで ある。被控訴人が用いていた「無細胞プラズマジェル」は、被施術者から採取20 した血液を遠心分離して細胞成分を完全に除いた血漿(NCP)から製造され るものであって、血小板が残っているPPPとは異なるから、本件発明の「自 己由来の血漿」には当たらない。一般に、豊胸手術にPPPを用いると、施術 後にしこりが発生することが知られているため、被控訴人は本件手術にPPP を用いていない。 25 2 争点1-2(被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合 した組成物を製造したか)について (控訴人の主張) (1) 次に述べる事情を総合すると、被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイ ントラリポスを混合して一の薬剤とし、これを被施術者に投与していたこと が認められる。 5 ア 本件手術に用いた成分を記録していた薬剤ノート(甲29、乙60、6 2)は、被控訴人が本件手術前に被施術者の状態をみてどの薬剤を入れる かを指示し、これに基づき看護師又は准看護師が記載した上で調合のため に利用していたものであるが、同薬剤ノートは、被施術者ごとに、 「血液」、 「ガナハ」(ヒアルロン酸)、「フィブラスト」(トラフェルミン)、「A10 APE」(成長因子)、「イントラ」(イントラリポス)、「メルス」(プ ラセンタ)、「抗」(抗生物質)の順で成分の分量が記載されており、被 控訴人の主張によるとB剤として別剤となるはずの「イントラ」が、特に 区別して記載されていない。これは、薬剤ノートに記載された成分があら かじめ全て混合された上で被施術者に投与されていたことを強く推認させ15 るというべきである。 イ 被控訴人は、本件クリニックのウェブサイトにおいて「INJECTION 注入 薬剤について…当院では無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤 を組み合わせております。」と、これらの成分が混合されている趣旨の説 明をしている(甲3)。 20 ウ 被控訴人は、本件手術を実際に受けたBに対し、「自己の血液を…採取 し、血球成分を除去したものをジェル化し、胸に戻し豊胸する手術です… 充填剤として成長因子と一部ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使 用します」、「乳房再生豊胸ではトラフェルミン○を使用しますが、この R 薬剤に含まれるエデト酸によるアレルギーがあります。また、イントラリ25 ポスには…卵黄からの脂質が含まれ、アレルギーを起こすことが知られて います」等との記載がある 「注入式豊胸手術承諾書および申込書(誓約書)」 用紙や説明書面を交付している。また、Bは、本件手術の内容が、被控訴 人主張のように、血漿と成長因子等からなるA剤と乳化剤・栄養剤等から なるB剤を別々に投与したというものとは全く異なっていたと陳述する (甲6)。 5 エ 本件クリニックに勤務していたC看護師及びD准看護師は、いずれも、 本件手術に用いられる薬剤は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポス を混合したものであり、A剤、B剤といった区別はしていなかったと陳述 又は証言する(甲12、15、証人Cの証言)。D准看護師が上記成分を 混合する様子を撮影した映像もある(甲13)。 10 (2) 被控訴人は、全ての成分を混合すると薬剤が凝固するという自らの実験結 果(乙12、13)を示した上で、被控訴人は、本件手術において、NCP と成長因子等からなるA剤と、乳化剤・栄養剤等からなるB剤とを別々に投 与していたと主張する。 しかし、まず、被控訴人による上記実験は、本件明細書等に記載された方15 法に従うことなく組成物を製造しているから、本件発明に係る組成物が投与 前に凝固してしまうことの根拠とはならない。また、被控訴人は、本件手術 に際してA剤、B剤と呼ばれるものが院内でどのように呼ばれていたのか、 施術時にどのように看護師等に薬剤の交換の指示をしていたのか、2種類の 薬剤を投与することについて看護師等や被施術者に説明していたのか等につ20 いて一貫した説明ができていない。したがって、本件手術においてA剤とB 剤とを別々に投与していたという被控訴人の主張は事実に反する。 (被控訴人の主張) (1) 本件手術に先立ち、被控訴人は、被施術者から血液を採取しNCPを製造 する。次に、NCPと成長因子その他の薬剤を混合した薬剤(A剤)と、乳25 化剤(イントラリポス)や栄養剤等を混合した薬剤(B剤)をそれぞれ製造 する。本件手術では、まずA剤を胸の奥の方に投与し、次にB剤を胸の皮膚 表面近傍に投与し、さらに、その中間の区間にA剤、B剤を交互にグラデー ション状に投与するという三段階により行われる。したがって、被控訴人は、 血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合した組成物を製造してはい ない。 5 (2) 控訴人は、被控訴人が血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを全て混 合していたと主張するが、次のとおり事実ではない。 ア 上記成分を被施術者の体外で全て混合すると、薬剤が凝固し、被控訴人 の用いる機器では投与ができない。仮にできたとしても、施術後に体内で しこりが生じてしまう。このことは、被控訴人作成の実験報告(乙12、 10 13)からも裏付けられる。また、A剤とB剤を体外で混合して投与する と、豊胸効果が1日も持たない。このため、被控訴人は、A剤を投与した 後の被施術者の胸の状態を確認した上で、B剤の種類、量、注入箇所を選 択するようにしている。 イ 薬剤ノートには、使用することのある薬剤が列挙されているだけであっ15 て、薬剤の並び順にも特段の意味はない。被施術者の属性等に応じて薬剤 の種類を選択しているから、薬剤ノートに記載された薬剤の全てを使用す るわけではなく、ノートに記載されていない薬剤も使用している。 ウ 被控訴人のウェブサイトには「組み合わせております。」と記載されて いたが、これは手術の方法を説明したものではないから、成分を全て混合20 して一度に投与することの証拠とはならない。 エ Bは、施術時に静脈麻酔を使用していたから、本件手術の具体的内容を 記憶しておらず、Bの陳述は信用できない。 オ D准看護師は、本件クリニックにおいて、顧客から受領した代金を横領 し、被控訴人から懲戒解雇処分を受けている者であって(乙16~18)、 25 D准看護師の陳述は信用できない。また、C看護師が本件手術で使用する 薬剤を製造していたと証言する令和2年2月から同年5月までの時期は、 被控訴人が豊胸モニターを募集し始める前であって本件手術を行ってお らず、さらに、C看護師も本件クリニックにおける横領行為の主犯格であ る本件クリニックに勤務していた他の看護師から多大な利益を受けるな どしていた者であることからすると、C看護師の証言も信用できない。 5 3 争点1-3(被控訴人が、血漿及びトラフェルミンを含む「A剤」とイント ラリポスを含む「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係 る組成物の「生産」に当たるか)について (控訴人の主張) 仮に被控訴人がA剤とB剤とを別々に被施術者に投与していたとしても、特10 許発明に係る物の「生産」とは、当該特許発明の技術的範囲に属する物を新た に作り出す行為をいうところ、被施術者の体内に投与されたA剤とB剤は、そ の後体内で混ざり合うことによって、本件発明の技術的範囲に属する組成物と なるのであるから、被控訴人は、本件発明の技術的範囲に含まれる組成物を新 たに作り出していたもので、すなわち「生産」していたことに変わりはない。 15 したがって、この場合でも、被控訴人による本件特許権の侵害が生じていた というべきである。 (被控訴人の主張) (1) 「組成物」の一般的な語義、本件明細書等における実施例の記載等に照ら すと、本件発明に係る組成物が生産されたというには、被施術者の体外にお20 いて、三つの成分(血漿、b-FGF、脂肪乳剤)が含有された組成物が生 産されることを要すると解すべきである。本件手術は、異なる薬剤であるA 剤及びB剤を別々に投与するものであり、上記三つの成分からなる何らかの 実体をもったひとまとまりの組成物が、被施術者の体内において生産される とはいえない。 25 (2) 本件発明は組成物という「物の発明」であるところ、被施術者の体内で結 果的に成分が混ざり合った場合にも「組成物が生産された」と解釈すること は、医療行為そのものである本件手術に特許権の効力を及ぼすこととなり、 実質的に、本件発明を「方法の発明」として保護し、医療方法に特許を認め ることに等しくなるから、不当であって許されない。 4 争点2-1(本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条5 1項柱書き)に違反した無効理由があるか)について (被控訴人の主張) 本件発明は、「豊胸用組成物」に係る発明であるが、これを製造するには、 医師が被施術者から血液を採取して「自己由来の血漿」を得る必要がある上、 製造された組成物は、医師がそのまま被施術者の皮下に投与することが前提と10 なっている。そうすると、本件発明は、実質的には、採血、組成物の製造及び 投与という連続して行われる一連の行為、すなわち豊胸手術のための方法の発 明と異なるものではない。 ここで、医療行為は「産業上利用することができる発明」(法29条1項柱 書き)に当たらないと解するべきである(東京高裁平成12年(行ケ)第6515 号同14年4月11日判決参照)から、実質的に豊胸手術のための方法の発明 というべき本件発明は、医療行為に当たるものとして、産業上利用することが できる発明には当たらない。 したがって、本件発明に係る特許は、特許無効審判により無効にされるべき ものであり、控訴人は、本件特許権を行使することができない。 20 (控訴人の主張) 本件発明は、組成物に関する物の発明であって、医療行為そのものを対象と する方法の発明ではない。医薬やその調合方法といった発明は、昭和50年法 律第46号による法改正により不特許事由から除外されているから、本件発明 が、現行法の下で特許性を有することは明らかである。 25 法2条3項1号に規定する「生産」とは、発明の構成要件を充足しない物を 素材として発明の構成要件を充足する物を新たに作り出す行為をいう。本件で は、医師が採取した血液を素材として、本件発明の技術的範囲に含まれる物(豊 胸用組成物)を新たに作り出す行為が「生産」に当たり、これは医師以外の者 でも行うことができる。ここで、血液を採取する医師の行為は「生産」行為の 対象に含まれない。 5 5 争点2-2(本件発明に係る特許は、サポート要件(法36条6項1号)に 違反した無効理由があるか)について (被控訴人の主張) 本件発明の「自己由来の血漿」は、文理上、あらゆる血漿を含むように記載 されているが、前記1(被控訴人の主張)のとおり、本件特許の出願人は、出10 願経過において、「自己由来の血漿」が「乏血小板血漿(PPP)」である旨 を主張していた。そうすると、本件発明の技術的範囲を「乏血小板血漿(PP P)」以外の血漿を構成要素とする組成物全般についてまで拡張ないし一般化 することはできず、本件発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない から、本件発明に係る特許は、サポート要件(法36条6項1号)の規定に違15 反してされたものとして、特許無効審判により無効にされるべきものである。 したがって、控訴人は、本件特許権を行使することができない。 (控訴人の主張) 被控訴人によるサポート要件違反の主張は、本件発明の「自己由来の血漿」 が乏血小板血漿(PPP)に限定されるとの解釈を前提としているところ、前20 記1(控訴人の主張)のとおり、被控訴人の解釈は誤りであるから、被控訴人 の主張は前提を欠くものであって理由がない。 6 争点2-3(本件発明に係る特許は、明確性要件(法36条6項2号)に違 反した無効理由があるか)について (被控訴人の主張)25 本件発明の「自己由来の血漿」は、その構造又は特性が明記されていないと ころ、これを製造する時点で、被施術者が誰であるかは医師の内心にしかなく、 その物の構造又は特性を客観的に判断することができないから、本件発明に係 る特許は、明確性要件(法36条6項2号)の規定に違反してされたものとし て、特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって、控訴人は、 本件特許権を行使することができない。 5 (控訴人の主張) 争う。 7 争点3-1(本件特許権の効力が、試験又は研究のための実施の免責規定 (法69条1項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について (被控訴人の主張)10 (1) 令和元年6月から令和2年5月までの被控訴人の行為について 被控訴人は、令和元年6月10日に本件クリニックを開業(乙31)して から令和2年5月にかけて、血液豊胸手術を行うための研究、具体的には、 自身から採取した血液を使用した試験管内等による生体外実験(in vitro) を行い、知人等に対して試験的な施術をした。その過程において、被控訴人15 は、多血小板血漿(PRP)や乏血小板血漿(PPP)に含まれている血小 板が豊胸手術後のしこりの原因となると考え、血液から細胞成分を完全に除 いた血漿であるNCPを得る条件を見いだし、法規制の対象とならないこと も確認し、令和2年5月に本件手術の方法をある程度確立した。上記期間に おける被控訴人の行為は、試験又は研究のためにするものであって、本件特20 許権の効力は及ばない(法69条1項)。 (2) 令和2年5月頃から同年11月頃までの被控訴人の行為について 被控訴人は、上記のとおり本件手術の方法をある程度確立したことから、 その効果を検証するために、令和2年5月頃から、本件手術のモニター募集 を始め、同月27日以降、本件手術を実施してその効果を確認し、モニター25 の了承を得てウェブサイト等に掲載していた。被控訴人は、撮影等に了承し たモニターには料金を割引し、データ収集、解析等のために追加人件費を支 払っていた上、モニターにも、何度も通院してもらう等の負担があった。こ のように、臨床実験(モニター)期間は、その後に施術方法を確立した以降 の期間とは異なる事情があった。 したがって、この間の被控訴人の行為も、試験又は研究のためにするもの5 であって、本件特許権の効力は及ばない(法69条1項)。 (控訴人の主張) 控訴人は、被控訴人が生体外実験をする行為については、特許権侵害行為と して主張していない。 被控訴人は、令和2年8月には、「3WAY血液豊胸」を美容医療のメニュ10 ーの一つとして掲げ、通常時と変わることのない料金を設定して表示していた のであるから(甲9、10)、被控訴人による本件手術のための組成物の製造 は、試験又は研究のためにするものとは認められない。モニターを対象として いるからといって、試験又は研究のためにする実施であるということは困難で ある。 15 8 争点3-2(本件特許権の効力が、調剤行為の免責規定(法69条3項)に より、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について (被控訴人の主張) 本件発明は美容医療に関するところ、美容医療は、身体的特徴の再建、修復 又は形成による心身の健康や自尊心の改善に寄与する分野であり、治療並びに20 身体の構造又は機能に影響を及ぼすものである。したがって、本件発明は、「二 以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。 以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬につい ての発明」(法69条3項)に当たる。 ここで、被控訴人が「処方せんにより」調剤しているか否かが問題となり得25 るが、処方せんは、薬の種類、服用量、投与方法等、すなわち処方を文書化し た書面にすぎず、その有無により、医師による調剤行為の性質が変化するもの ではない。法69条3項の趣旨が、医療現場に支障が起こることを防ぐことに あることからすると、現実に処方せんが発行されていることは同項の本質的要 件ではなく、医療法規に基づいて適法に行われる調剤行為であれば、免責が認 められるべきである。仮に、被控訴人が血漿(NCP)、トラフェルミン及び5 イントラリポスを本件手術に先立ち混合した薬剤を製造していたとしても、同 行為は調剤行為といえるから、法69条3項により、本件特許権の効力は、同 行為には及ばない。 (控訴人の主張) 法69条3項において、「医薬」とは「人の病気の診断、治療、処置又は予10 防のため使用する物」と定義されている。「病気」について、特許法には定義 がないが、一般には生物が生理・精神機能に異常を来し、正常の機能が営めず、 諸種の苦痛や不快感を伴う現象をいう。豊胸を希望する者は、生理状態等に異 常や障害を来してはおらず、正常の機能、健康な生活等を営むことが困難にな っているわけではない。したがって、本件発明は、法69条3項の「医薬の発15 明」には当たらない。 また、法69条3項の適用を受けるためには、「処方せんにより調剤する医 薬」という要件を満たす必要があるところ、被控訴人の行為が処方せんの発行 なく行われていることに争いはない。したがって、同規定の適用をいう被控訴 人の主張は失当である。 20 9 争点3-3(本件特許権の行使は権利の濫用等に当たり許されないか)につ いて (被控訴人の主張) 控訴人による本件特許権の行使は、被控訴人が、医師として、被施術者から 血液を採取してNCPを製造し、これを用いて製造した薬剤を被施術者に投与25 する一連の医療行為に対する特許権の行使にほかならない。また、本件手術に 用いる混合薬剤は豊胸を目的とするものであるが、身体的コンプレックスで精 神を病む場合もあるので、豊胸も医療行為といえ、これに用いる混合薬剤の製 造に特許権の効力が及ばないとすることは、公共の利益、福祉に合致する。 医師が、医療行為を行うに際して常に特許権侵害の可能性を恐れる状況に追 い込むことは妥当でないから、医療行為に対して特許権を行使することは、権5 利の濫用として許されないか、端的に医療行為には特許権の効力が及ばないと 解するべきである。 したがって、控訴人の請求は、権利の濫用等により許されないというべきで ある。 (控訴人の主張)10 控訴人は、被控訴人による豊胸用組成物の生産行為を問題としているのであ って、これとは別個の行為である採血や投与は問題としていない。豊胸用組成 物の生産行為は、医師以外の第三者が行うこともできるから、これを偶然医師 である被控訴人が行ったとしても、医療行為として免責されるべき理由とはな らない。 15 10 争点4-1(本件の損害額の算定に当たり、法102条2項を適用できる か)について (控訴人の主張) (1) Aからの損害賠償請求権の譲渡 控訴人は、平成26年11月12日、Aから本件特許権を譲り受けるとと20 もに、Aに対して本件特許権についての独占的通常実施権を設定した(甲3 0~32)。 控訴人は、本件特許権についての独占的通常実施権者であるAから、被控 訴人に対する損害賠償請求権の譲渡を受けた。Aは、東京都内で美容クリニ ックを営む者であるから、被控訴人による本件特許権の侵害がなければ利益25 を受ける立場にあったものであり、その損害額の算定に当たって、法102 条2項を適用することができる。 被控訴人は、控訴人が通常実施権設定の募集をしていたことが、Aが本件 特許権についての独占的通常実施権の設定を受けていたことと矛盾すると主 張する。しかし、特許権者は、独占的通常実施権を設定した場合でも、独占 的通常実施権者の同意があれば、第三者に対して更に実施権の許諾が可能で5 あり、控訴人が通常実施権設定の募集をしていたことは、Aが独占的通常実 施権の設定を受けていたことと矛盾するものではない。Aは、独占的通常実 施権者として、本件特許権につき、同意なく第三者に実施許諾されない法的 地位を有していた。 (2) 控訴人グループとしての利益10 控訴人は、その発行済株式の100%をAが保有し、A式豊胸術を広めて いくため、本件特許権を保有するなど、知的財産権を管理する立場にある。 そして、Aがクリニックを経営して本件発明を実施し、利益を得る体制とな っている。そうすると、控訴人とAとは経済的に一体の関係にあり、控訴人 はAを通じて本件発明を実施して利益を得ているといえるから、仮に控訴人15 とAとの間に独占的通常実施権の設定があったと認められないとしても、控 訴人には、被控訴人による特許権侵害行為がなければ利益を得られたであろ う事情があるといえる。 したがって、控訴人が受けた損害額の算定に当たって、法102条2項を 適用することができる。 20 (被控訴人の主張) (1) Aが独占的通常実施権の設定を受けていたとの主張について 控訴人は、Aに独占的通常実施権を設定したと主張するが、控訴人は、少 なくとも平成30年2月3日から令和2年12月26日までの間、自身のウ ェブサイト上で、本件特許権についての通常実施権の設定を勧誘、募集して25 いた事実が認められることに照らすと(乙42)、控訴人の主張は事実では ない。 (2) 控訴人グループとしての利益との主張について 控訴人は、医療機器の販売・賃貸等を目的とする株式会社であり、本件発 明を実施するような業務を行っていない。控訴人には、「特許権侵害行為が なかったならば利益が得られていたであろう事情」は存在せず、法102条5 2項を適用することはできない。 11 争点4-2(損害額)について (控訴人の主張) (1) 法102条2項により算定される損害額 令和2年5月から令和3年7月25日までに被控訴人が実施した豊胸手術10 の売上高は、別紙2の「豊胸代金(オプション込)」欄記載のとおり、少な くとも合計2億2269万7768円である。なお、被控訴人は、値引き分、 オプション料金、返金分は売上高から控除されるべきと主張するが、値引き や返金は被控訴人側の事情であって考慮されるべきではないし、オプション 料金は、本件発明を実施したからこそ得ることができたものであるから、売15 上高に含めて計算されるべきである。 被控訴人は、経費を立証していないので、上記売上高の全額が被控訴人の 利益とみるべきである。これに、消費税相当額10%、弁護士費用相当額1 0%をそれぞれ加算すると、控訴人の損害額は、少なくとも2億6723万 7321円となる。 20 本件では同額のうち1億円を請求し(月ごとの請求額の内訳は別紙2の「各 月請求額」欄記載のとおりである。)、損害の発生した月ごとに、各月請求 額に対する翌月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める。 (2) 法102条3項により算定される損害額 法102条3項により控訴人の損害額を計算すると、令和2年5月から令25 和3年7月25日までに被控訴人が実施した豊胸手術の売上高は、前記(1) のとおり少なくとも合計2億2269万7768円である。相当な実施料率 としては、バイオ・製薬分野におけるライセンス料の相場が6.0%となっ ているところ、本件発明によってこそ効果的な血液豊胸が可能となること、 被控訴人は血液豊胸を積極的にアピールして顧客を獲得しており、本件特許 の寄与は大きいといえること、被控訴人が故意に本件特許権を侵害していた5 と認められること等の事情に照らし、相当な実施料率は売上高の30%を下 回ることはない。 上記期間中の被控訴人の売上高の30%に相当する額6680万9330 円に加えて、消費税相当額10%、弁護士費用相当額10%をそれぞれ加算 すると、控訴人の損害額は合計8017万1196円を下らない。また、損10 害の発生した月ごとに、損害額に対する翌日1日から支払済みまでの遅延損 害金の支払を求める。 (被控訴人の主張) (1) 法102条2項が適用される場合の損害額 ア 「生産」によって利益を得ていないこと15 控訴人は、被控訴人による特許権侵害行為として組成物の「生産」を問 題とするが、被控訴人は、薬剤の生産のみによっては利益を得ておらず、 仮に法102条2項が適用されるとしても、被控訴人の受けた利益の額は 零であるから、損害額もまた零ということになる。 イ 値引き分、オプション料金、返金分は控除されるべきこと20 控訴人は、被控訴人の売上高を計算するに際して、値引き分、オプショ ン料金及び返金分を考慮していない。これらは、豊胸手術の売上高とはい えないから控除されるべきである。 ウ 損害額算定の基礎となる売上期間について 前記7(被控訴人の主張)(2)のとおり、被控訴人による施術のうちの令25 和2年5月27日から同年11月末日までの期間は、臨床実験(モニター) 期間であって、試行錯誤を繰り返しながら、実験として施術をしていた期 間であり、本件特許権の効力が及ばないため、同期間の売上げは損害額算 定の基礎とはならない。 (2) 法102条3項が適用される場合の損害額 前記(1)のとおり、被控訴人の売上高を計算するに際して、値引き分等は控5 除されるべきであるし、令和2年5月から同年11月までのモニターに対す る施術の売上げは考慮されるべきではない。また、豊胸の代替手段としては、 シリコンバッグ注入、ヒアルロン酸注入、脂肪注入など多種多様な方法があ り、加えて、血漿や線維芽細胞を使用した豊胸を行っているクリニックも多 数あるから、本件発明の代替可能性は高いといえる。 10 相当な実施料率については、全技術分野の平均値である3.8%程度にと どまるというべきである。 |
|
|
当裁判所の判断
1 争点1-1(「無細胞プラズマジェル」は本件発明の「自己由来の血漿」に 相当するか)について15 (1) 本件発明の概要 本件明細書等の記載(甲2:特許公報)によると、本件発明の概要は、次 のとおりと認められる(【】は本件明細書等の段落番号を指す。)。 ア 技術分野 本件発明は、乳腺周囲等に皮下組織又は脂肪組織を生成、増加させるこ20 とにより、乳房等の皮下に皮下組織、脂肪組織の蓄積、増大を図る皮下組 織増加促進用組成物に関する。(【0001】) イ 背景技術 主として乳腺と脂肪組織により構成される乳房を維持するためには、脂 肪細胞における脂肪合成を促進させて脂肪組織の増大、蓄積を促し、加え25 て皮下組織を増大させることが望ましい。(【0002】) 従来の豊胸術のうち、乳房インプラント、脂肪移植、ヒアルロン酸やコ ラーゲン等を注入する方法等には、それぞれ安全性の問題があるほか、効 果も十分ではない等の課題があった。(【0003】~【0008】) 他方、肌問題を改善する方法として、自己由来の白血球を含有する多血 小板血漿(PRP:Plate Rich Plasma)と、成長因子を組み合わせ混合注5 入して細胞組織の増加を促進させる方法が提案されている。これは、豊胸 術にも適用の余地があるが、PRPとして分離される血漿は採血した血液 の10分の1から20分の1程度であり、数十から数百mLを必要とする 豊胸には実用的でない。(【0009】) ウ 本件発明10 発明者は、このような現状下において、自己由来の血液成分の中でも、 その半数を占める液体成分である血漿に着目し、血漿と、成長因子の中で も塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)を組み合わせて乳房の皮下組 織に注入すれば、皮下組織の蓄積、増大を図ることができ、血漿として脂 質が不十分な場合には人工脂質(脂肪)を補充することで、極めて効果的15 に乳房の皮下に脂肪組織の蓄積、増大を図り、豊胸効果が得られることを 確認し、本件発明に至った。(【0010】) 本件発明は、従来の豊胸術が有していた安全性等の問題を回避し、乳房 の皮下に皮下組織、脂肪組織の蓄積、増大を図る安全で自然な方法による 自己組織の回復、容貌の回復が得られる皮下組織増加促進用組成物である20 豊胸用組成物を提供することを課題としたものである。具体的には、自己 由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含 有してなることを特徴とする、豊胸のために使用する皮下組織増加促進用 組成物である。(【0012】、【0013】、【0016】、【請求項 1】、【請求項4】)25 エ 発明を実施するための形態 豊胸を行おうとするヒトの血液を採取し、好ましくは3000~400 0rpmの範囲内で遠心分離して血漿を分離し、抗凝固薬であるヘパリン 又はクエン酸を添加し、ゲル状の自己由来の血漿を調製できる。塩基性線 維芽細胞増殖因子(b-FGF)は、「トラフェルミン」の一般名、「フ ィブラストスプレー」の販売名で上市されているものをそのまま用いるこ5 とができる。より脂肪組織を生成、増加させるために、脂肪乳剤の形態で 脂肪を同時に投与する。脂肪乳剤は、静注用脂肪乳剤として提供されてい る「イントラリピッド輸液」製剤を使用することができる。(【0025】 ~【0032】) (2) 本件発明の「自己由来の血漿」の意義について検討する。 10 ア 本件明細書等のうち特許請求の範囲には、「血漿」の意義を具体的に定 義する記載はないところ、生化学分野における代表的な辞典には、「血液 から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体を血漿といい、単にプラズ マ(plasma)とも略す」(甲7の1:岩波理化学辞典(第4版))、「血 液中から血球を取除いた成分」(甲7の2:生化学辞典(第4版))との15 記載がある。 本件明細書等の発明の詳細な説明には、「自己由来の白血球を含有する 多血小板血漿(PRP:Plate Rich Plasma)…が提案されている…。…P RPとして分離される血漿は採血した血液量の十分の一から二十分の一程 度であり、…数十から数百mLを必要とする豊胸には実用的でな(い)」20 (【0009】)、「本発明者は、かかる現状下のもとに、自己由来の血 液成分の中でも、その半数を占める液体成分である血漿に着目し、…血漿 中に含まれるタンパク質をはじめとする脂質、ブドウ糖、ホルモン、特に 脂質がb-FGFの作用と相俟って…」(【0010】)等の記載があり、 また、発明を実施するための形態に関する部分ではあるが、「自己由来の25 血漿としては、自己の血液を採取し、常法、遠心分離して得た血漿であり、 血液の約55%を占める液体成分である」(【0025】)との記載もあ る。 上記の記載や前記(1)の本件発明の概要によると、本件発明の「自己由来 の血漿」とは、「被施術者から採取した血液から赤血球その他の細胞成分 を取り除いた液体成分」という意義を有するものと解するのが相当である。 5 イ これに対し、被控訴人は、本件特許の出願経過等に照らすと、本件発明 の「自己由来の血漿」 「乏血小板血漿 は (PPP:Platelet Poor Plasma)」 の意義に限定して解釈すべきであり、被控訴人が本件手術に用いていた被 施術者から採取した血液を遠心分離して細胞成分を完全に除いた血漿(N CP)はこれに含まれないと主張する。 10 この点につき、本件特許の出願に対する拒絶査定に対して出願人が提出 した審判請求書(乙4)には、「本願発明で使用する血漿(Plasma)は、 自己由来の血漿であり、血液から血球成分である赤血球、白血球並びに血 小板を取り除いた血液に含まれる液体成分である。すなわち、引用文献1 (判決注:特開2009-235004号公報。甲8)の段落番号[0015 04]の記載における、バフィーコートの上層に分離されたPPP(乏血 小板血漿:Platelet Poor Plasma)と呼ばれる上澄みの液体画分であり、 要するに、血小板を殆ど含まない血漿である。」との記載がある。 しかし、同記載は、審査官による拒絶理由のうち「本願発明で使用する 血漿は、引用文献1に記載のPRPと区別できるものではない」との認定20 に対し、血小板をほとんど含まない「自己由来の血漿」は、血小板が豊富 に含まれる引用文献1のPRPとは区別できる旨を述べたものにすぎない。 そして、同記載中では、 「血小板を殆ど含まない血漿である」とする一方、 血小板が含まれることの積極的意義については何ら記載がないことに照ら すと、「血小板を殆ど含まない血漿」との記載をもって、「血小板を全く25 含まない血漿」を除外する趣旨であるとはにわかに認めることはできない。 被控訴人主張の「細胞成分を完全に除いた血漿(NCP)」と「乏血小板 血漿(PPP)」との関係は必ずしも明らかではないが、少なくとも、上 記審判請求書の記載によっては、「自己由来の血漿」から「血小板を全く 含まない血漿(血小板を完全に除去した血漿)」が除外されたと解するこ とはできず、本件明細書等や出願経過をみても、他にそのように解すべき5 根拠は見当たらない。 したがって、本件特許の出願経過等を根拠に本件発明の「自己由来の血 漿」の意義を限定して解釈すべき旨の被控訴人の主張は採用することがで きない。 (3) 小括10 被控訴人が本件手術に用いていた「無細胞プラズマジェル」は、本件手術 に先立って採取した被施術者の血液から細胞成分を完全に除去した血漿であ るから(乙25、被控訴人本人)、上記(2)アのとおり「被施術者から採取し た血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体成分」という意義を有 する本件発明の「自己由来の血漿」に相当するといえる。 15 2 争点1-2(被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合 した組成物を製造したか)について (1) 認定事実 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。 ア 本件クリニックの開設等20 医師である被控訴人は、令和元年6月10日、東京都中央区に、診療科 目を美容外科及び美容皮膚科とする本件クリニックを開設した。乙31) ( イ 本件手術の提供に向けた準備 (ア) 被控訴人は、令和2年1月頃から、フィブラストスプレー及びイント ラリポスを購入し始めた。(乙35、36)25 (イ) 被控訴人は、この頃、自らの採取した血液を遠心分離するなどしたほ か、厚生労働省の担当者に対して、細胞成分が含まれない血漿を用いた 医療サービスの提供が再生医療等の安全性の確保等に関する法律による 規制の対象となるかについて照会するなどした。(乙7、8) (ウ) 被控訴人は、弁理士に対し、仮定した施術方法が本件特許権を侵害し ないかについて調査を依頼し、令和2年2月27日付けで、弁理士から5 本件特許に関する見解書を受領した。その内容は要旨次のとおりであっ た。(乙32) a 本件特許は、産業上の利用可能性、進歩性、サポート要件の各要件 に違反してされたものであり、無効理由がある。 b 行為A「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離する10 ことで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した 「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーと、 イントラリピッド輸液を混合した組成物(組成物1)を作製する。該 患者に対して、豊胸目的で、組成物1を投与する。」は、形式的には 本件発明の技術的範囲に属するが、医療行為に該当する実施態様には15 特許権の効力が及ばないと解されるから、本件特許権を侵害しない。 c 行為B「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離する ことで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した 「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーを混 合した組成物(組成物2)を作製する。該患者に対して、豊胸目的で、 20 組成物2とイントラリピッド輸液とを、別々に投与する。」は、組成 物2とイントラリピッド輸液の各投与が行われた時点で、本件発明に 係る物の生産が行われたと解する余地があるが、人体内部では様々な 物質が存在し相互作用していることからすると、組成物2とイントラ リピッド輸液とを別々に投与した場合は、本件発明に係るひとまとま25 りの組成物を投与する場合と同一の効果が得られるとは限らず、本件 特許権を侵害しない。 ウ 本件手術の提供 被控訴人は、本件クリニックにおいて、令和2年5月27日から同年1 1月末頃まではモニター期間としてモニターとして募集した者を対象とし、 モニター期間後の同年12月からは一般募集をした者を対象として、いず5 れも対価を得て本件手術を提供した。(乙45、47、52~58) 被控訴人による本件手術は、「自己由来の血漿」を「細胞成分を除いた 血漿(NCP)」とし、ヒアルロン酸やプラセンタ等を加えたほかは、本 件明細書等に実施例として記載されている方法を用いたものであった。 エ 薬剤ノートの記載10 本件クリニックでは、遅くとも令和3年1月27日の本件手術の施術分 から、被控訴人が看護師又は准看護師に対し、被施術者に投与する薬剤の 各成分量を口頭で指示し、これを受けて、看護師又は准看護師が被施術者 に投与する薬剤の成分の内訳等を記載した薬剤ノートを作成し、これに基 づいて、看護師又は准看護師は被施術者に使用する薬剤を製造していた。 15 同薬剤ノートには、各行の左端に日付及び被施術者を特定する情報が記載 され、各行について、左から「血液」「ガナハ」「フィブラスト」「AA PE」「イントラ」「メルス」「抗」の順に列が設けられ(ただし、令和 3年2月23日までの記載においては「抗」の列がない。)、それぞれ数 値等が記載されている。また、薬剤ノートの2枚目末尾には、「★ガナハ20 イントラをくだいてまぜた人」との記載があって、被施術者を特定する情 報の右に「★」が記載されていることがある。(甲29、乙60、62) オ 被控訴人が作成した説明資料等 (ア) 本件クリニックのウェブサイトには、本件手術について、「無細胞プ ラズマジェル」、「カップ吸引固定」及び「バウンド強化EMS」の三25 つの手順による「3WAY血液豊胸」である旨が紹介され、「注入薬剤」 については「術後のしぼみのリスクを回避するため、当院では無細胞プ ラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤を組み合わせております。」と 記載されていた。(甲3、4、9) (イ) 被控訴人が、被施術者に交付して署名を求めていた「注入式豊胸手術 承諾書および申込書(誓約書)」には、「自己の血液を200ccある5 いは400cc採取し、血球成分を除去したものをジェル化し、胸に戻 し豊胸する手術です。」、「充填剤として成長因子と一部ヒアルロン酸 製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」、「今回の手術で注入でき るのは片側100ccあるいは200cc、両側併せて200ccある いは400ccです。」、「乳房再生豊胸ではトラフェルミン○を使用 R10 しますが、この薬剤に含まれるエデト酸によるアレルギーがあります。 また、イントラリポスには大豆蛋白質は含まれていませんが、卵黄から の脂質が含まれ、アレルギーを起こすことが知られています。乳房再生 豊胸時には薬剤アレルギー、卵アレルギーの問診を行い、乳房再生豊胸 溶液注入時には血中酸素分圧を監視して行っています。」などと記載さ15 れている。(甲6) (2) 前記(1)の認定事実によると、①被控訴人の指示により、本件手術の被施術 者に投与する薬剤を製造する際に、本件クリニックの看護師又は准看護師に よって作成され、その記載に基づいて看護師又は准看護師が実際に薬剤を製 造していたと認められる薬剤ノートには、「血液」、「ガナハ」(ヒアルロ20 ン酸製剤)、「フィブラスト」、「AAPE」(成長因子を含む製剤)、「イ ントラ」(イントラリポス)、「メルス」(メルスモンという商品名のプラ センタ剤)、「抗」(抗生物質)と、被施術者に投与された成分の量が記載 されているが、被控訴人のいうA剤(「フィブラスト」等)とB剤(「イン トラリポス」等)に対応する区別がされていない上、薬剤ノートの2枚目末25 尾には「★ガナハ イントラをくだいてまぜた人」との記載があって、この ような記載は、「ガナハ」や「イントラ」を合わせて薬剤に混ぜることが前 提になっているともうかがわれること、②本件クリニックのウェブサイトに は、注入薬剤について「無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤を 組み合わせております」と記載され、被施術者に交付されていた「注入式豊 胸手術承諾書および申込書(誓約書)」にも「充填剤として成長因子と一部5 ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」等の記載と共に、 トラフェルミン及びイントラリポスのアレルギーリスクについての説明があ ること、他方、いずれの記載においても、薬剤が分けて投与される旨をうか がわせる記載は存在しないことなどが認められる。 これらの点に加え、モニターとして募集していた者を対象としていた期間10 及び一般募集をした者を対象としていた期間を通じて、被控訴人が本件手術 において被施術者に投与した薬剤の内容や投与方法を変更したことをうかが わせる事情が全くないことに照らすと、被控訴人は、これらの期間を通じて、 被施術者から採取した血液から血漿を製造し、これにフィブラストスプレー、 イントラリポスを含む、薬剤ノートに記載された各成分を全て混合させた薬15 剤を製造した上で、これを本件手術において被施術者に投与していたと合理 的に推認できる。 (3) これに対し、被控訴人は、被控訴人が本件手術に先立ち製造していた薬剤 は、NCPと成長因子(トラフェルミン)その他の薬剤を混合した「A剤」 と、乳化剤(イントラリポス)や栄養剤等を混合した「B剤」であって、本20 件手術では、まずA剤を胸の奥の方に投与し、次にB剤を胸の皮膚表面近傍 に投与し、更にその中間の区間にA剤、B剤を交互にグラデーション状に投 与したなどと主張する。 しかし、前記(2)の説示のとおり判断される上に、被控訴人は、当審で実施 した本人尋問において、医師である自身の判断として被施術者に各成分をど25 の程度使用するかを決定し、これを看護師や准看護師に伝えてA剤及びB剤 を製造させ、本件手術に際してこれらの薬剤をどのように管理、使用するか という一連の過程について、具体的、合理的な説明をすることができていな い。すなわち、被施術者の属性や体質によって適宜選択されるという成分の 選択が薬剤ノートの記載に反映されている箇所を具体的に特定することがで きず、A剤に含まれる成分とB剤に含まれる成分が混在して薬剤ノートに記5 載されている点については看護師らが意図なくなぜかそのような順で記載し たとし、また、院内での薬剤の呼ばれ方については「A、B」 「血漿、 、 白」、 「赤、白」などと質問の中で変遷し、施術の三段階目でA剤とB剤とを臨機 応変に投与する際の薬剤の交換方法は、看護師等に指示すると言ったり自分 で交換すると言ったりと、具体的状況が判然としない。このような被控訴人10 本人の供述内容、供述態度に加えて、本件において、被控訴人が看護師又は 准看護師に指示して、手術に際してA剤、B剤と薬剤を分けて製造させた上、 管理及び使用していたならば、当然に存在すべきといえる、そのことをうか がわせる客観的証拠が提出されていないことに照らすと、被控訴人の供述を 採用することはできない。 15 また、被控訴人は、被控訴人による実験結果(乙12、13)に依拠して、 血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを被施術者の体外で全て混合する と、薬剤が凝固し、被控訴人の用いる機器では投与できないし、仮にできた としても施術後にしこりが生じるから、被控訴人は上記成分を被施術者の体 外で全て混合してはいないと主張する。 20 しかし、被控訴人による実験は、採取した血液を遠心分離して上層の画分 を医療用バットに投入し、イントラリポスとフィブラストを投入して1分間 程度適度に揺らしたというものであり、製造方法や管理条件において、本件 明細書の実施例に記載されたものと異なっているし、実際に施術する際のも のと同一とも限らない。したがって、被控訴人による実験結果をもって直ち25 に、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを被施術者の体外で全て混合 した場合に薬剤が凝固し、投与自体が困難になるなどと認めることはできな い。 (4) 上記(2)及び(3)のとおり、被控訴人は、被施術者から採取した血液から血 漿を製造し、これにフィブラストスプレー、イントラリポスを含む、薬剤ノ ートに記載された各成分を全て混合させた薬剤を製造したと合理的に推認で5 きるところ、被控訴人による主張等を考慮しても、同推認を覆すには至らな い。 したがって、被控訴人は、モニターとして募集していた者を対象としてい た期間及び一般募集をした者を対象としていた期間を通じて、上記三成分を 含む組成物を製造したと認められるところ、同組成物は、豊胸手術である本10 件手術に用いるために製造されたものであるから、被控訴人は、本件発明の 技術的範囲に属する組成物を生産したと認められる。 3 争点2-1(本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条 1項柱書き)に違反した無効理由があるか)について (1) 被控訴人は、本件発明は「豊胸用組成物」に係る発明であるが、これを製15 造するには医師が被施術者から血液を採取して「自己由来の血漿」を得る必 要がある上、製造された組成物は、医師がそのまま被施術者の皮下に投与す ることが前提となっているから、本件発明は、実質的には、採血、組成物の 製造及び投与という連続して行われる一連の行為、すなわち豊胸手術のため の方法の発明と異なるものではないとの主張を前提として、医療行為は「産20 業上利用することができる発明」に当たらないから、本件発明に係る特許は 無効とされるべき旨主張する。 (2) 法29条1項柱書きは、「産業上利用することができる発明をした者は、 次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と するのみで、本件発明のような豊胸のために使用する組成物を含め、人体に25 投与する物につき、特許の対象から除外する旨を明示的に規定してはいない。 また、昭和50年法律第46号による改正前の法は、「医薬(人の病気の 診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ。)又は二以 上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」を、特許を受けること ができない発明としていたが(同改正前の法32条2号)、同改正において この規定は削除され、人体に投与することが予定されている医薬の発明であ5 っても特許を受け得ることが明確にされたというべきである。 したがって、人体に投与することが予定されていることをもっては、当該 「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であって、「産 業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。 (3) 次に、本件発明の「自己由来の血漿」は、被施術者から採血をして得て、 10 最終的には被施術者に投与することが予定されているが、人間から採取した ものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行わ れるものとは限らず、採血、組成物の製造及び被施術者への投与が、常に一 連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえない。むしろ、再生医療や遺 伝子治療等の先端医療技術が飛躍的に進歩しつつある近年の状況も踏まえる15 と、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造するなどの技術の 発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発が寄与 するところが大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでも あるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要性が認 められる。 20 そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその 人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことを もって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみ ると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらない などということはできない。 25 (4) 以上によると、本件発明が「産業上利用することができる発明」に当たら ないとする被控訴人の主張を採用することはできず、本件発明に係る特許は、 法29条1項柱書きの規定に違反してされたものということはできない。し たがって、同無効理由の存在により本件特許権を行使することができないと する被控訴人の抗弁には理由がない。 4 争点2-2(本件発明に係る特許は、サポート要件(法36条6項1号)に5 違反した無効理由があるか)について (1) 被控訴人は、本件発明の「自己由来の血漿」について、文理上あらゆる血 漿を含むように記載されているが、出願人は、「自己由来の血漿」は「乏血 小板血漿(PPP)」である旨を主張していたから、本件発明の技術的範囲 を、「乏血小板血漿(PPP)」以外の血漿を構成要素とする組成物全般に10 ついてまで拡張ないし一般化することはできないとして、本件発明は、発明 の詳細な説明に記載されたものではなく、本件発明に係る特許は、サポート 要件の規定(法36条6項1号)に違反してされたものであると主張する。 (2) しかし、前記1(2)アのとおり、本件発明の「自己由来の血漿」は、「被施 術者から採取した血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体成分」15 という意義を有すると解するのが相当であるところ、本件明細書等の発明の 詳細な説明には、「自己由来の血漿」について、「自己由来の血液成分の中 でも、その半数を占める液体成分である血漿」(【0010】)との記載や、 発明を実施するための形態として「自己由来の血漿としては、自己の血液を 採取し、常法、遠心分離して得た血漿であり、血液の約55%を占める液体20 成分である」(【0025】)との記載があり、これを得るための実施例も 記載されている(【0037】)。これらによると、本件発明は、発明の詳 細な説明に記載されたものといえる。 被控訴人が指摘する出願審査過程における出願人の主張は、前記1(2)イ のとおり、審査官による拒絶理由に対し、血小板をほとんど含まない「自己25 由来の血漿」は、血小板が豊富に含まれる引用文献1のPRPとは区別でき る旨を述べたものにすぎず、発明の詳細な説明で開示された発明と、特許請 求の範囲に記載された発明とが異なることを示すものとはいえない。なお、 本件発明の「自己由来の血漿」にPRPを含まないことは、本件明細書等の 「PRPとして分離される血漿は採血した血液量の十分の一から二十分の一 程度であり、…数十から数百mLを必要とする豊胸には実用的でな(い)」5 (【0009】)、「本発明者は、かかる現状下のもとに、自己由来の血液 成分の中でも、その半数を占める液体成分である血漿に着目し、」(【00 10】)との記載に接した当業者であれば容易に理解できる事項である。 (3) 以上によると、本件発明は、本件明細書等の発明の詳細な説明に記載され たものと認められるから、本件発明に係る特許は、法36条6項1号の規定10 に違反してされたものということはできない。したがって、同無効理由の存 在により本件特許権を行使することができないとする被控訴人の抗弁には理 由がない。 5 争点2-3(本件発明に係る特許は、明確性要件(法36条6項2号)に違 反した無効理由があるか)について15 (1) 被控訴人は、本件発明の「自己由来の血漿」は、その構造又は特性が明記 されていないところ、これを製造する時点で、被施術者が誰であるかは医師 の内心にしかなく、その物の構造又は特性を客観的に判断することができな いから、本件発明に係る特許は、明確性要件の規定(法36条6項2号)に 違反してされたものであると主張する。 20 (2) しかし、本件明細書等には、「自己由来の血漿」について、「具体的には、 本発明の豊胸用組成物を用いて豊胸を行おうとするヒトの血液(自己血液) を採取し、…遠心分離して血漿を分離し、…自己由来の血漿を調製すること ができる。」(【0026】)等の記載があるし、本件明細書等に接した当 業者であれば、「自己由来の血漿」が、豊胸用組成物を用いて豊胸を行おう25 とする被施術者から採取した血液を用いて製造されたものであることは容易 に理解でき、独占権の範囲について予測可能性を奪うなど第三者に不測の不 利益を及ぼすおそれもないというべきである。 (3) したがって、本件発明に係る特許が、法36条6項2号の規定に違反して されたものということはできない。したがって、同無効理由の存在により本 件特許権を行使することができないとする被控訴人の抗弁には理由がない。 5 6 争点3-1(本件特許権の効力が、試験又は研究のための実施の免責規定 (法69条1項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について (1) 前記2(1)の認定事実のとおり、被控訴人は、令和2年5月頃まで、血液豊 胸術を行うための研究として、自身から採取した血液を使用した試験管内等 による生体外実験を行うなどしていたところ、このような行為が、法69条10 1項によって本件特許権の侵害行為とならないことは、当事者間に争いがな い(控訴人は、上記行為を本件請求の対象に含めていない。)。 (2) 被控訴人は、令和2年5月頃から同年11月頃までは、本件手術の効果を 検証するためにモニターを募集し、モニターには料金割引、ウェブサイト掲 載への了承、複数回の通院等を依頼したほか、本件クリニックではデータ収15 集、解析等のために追加人件費を支払っていたことなどを理由に、同期間に おける本件発明の実施は、試験又は研究のためにする実施であって、本件特 許権の効力が及ばない旨主張する。 (3) 法69条1項の趣旨は、試験又は研究のためにする特許発明の実施は、通 常は特許権者の有する経済的利益を害することはなく、このような実験にま20 で特許権の効力を及ぼすことは、かえって技術の進歩を阻害し、産業の発達 を損なう結果となるため、産業政策上の見地から、特許権者と一般公共の利 益との調和を図ることにあると解される。 ここで、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するとこ ろ(法68条本文)、対価を取得して特許発明を実施する行為は、特許権者25 の有する経済的利益を害することになり、特許権者と一般公共の利益との調 和を図るとの法69条1項の趣旨からすると、同行為に研究目的が併存して いるとしても、特段の事情がない限り、「試験又は研究のためにする特許発 明の実施」には当たらないと解すべきである。 これを本件についてみると、前記2に認定説示したとおり、被控訴人は、 本件クリニックにおいて、令和2年5月27日以降、顧客から対価を得て本5 件手術を提供し、本件手術に用いるために、本件発明の技術的範囲に属する 組成物を製造(生産)していたと認められる。 そして、証拠(乙45、47、52~58)によると、被控訴人が本件手 術の対価として顧客から受領していた金額は、値引きがされていることが多 いものの、その値引額は一様ではなく、また、被控訴人が主張するモニター10 期間(令和2年5月~11月)であっても値引きしていない例や、モニター 期間後であっても多額の値引きをしている例があって、少なくとも、モニタ ー期間であることを理由に、実質的にみて対価とはいえないような低廉な金 額で本件手術が提供されたということはできない。そうすると、上記の特段 の事情を認めることはできず、被控訴人による本件発明の実施は、「試験又15 は研究のためにする特許発明の実施」には当たらないというべきである。 (4) したがって、法69条1項の規定により、令和2年5月頃までの被控訴人 による生体外実験等については本件特許権の効力は及ばないが、他方、同年 5月27日から同年11月頃までのいわゆるモニター期間につき、同項によ り、本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。 20 7 争点3-2(本件特許権の効力が、調剤行為の免責規定(法69条3項)に より、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について (1) 被控訴人は、本件特許権の効力は、法69条3項の規定により、被控訴人 の行為に及ばないと主張する。 (2) 法69条3項は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防25 のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することによ り製造されるべき医薬の発明」を対象とするところ、本件発明に係る組成物 は、特許請求の範囲の記載からも明らかなとおり「豊胸のために使用する」 ものであって、その豊胸の目的は、本件明細書等の段落【0003】に「女 性にとって、容姿の美容の目的で、豊かな乳房を保つことの要望が大きく、 そのための豊胸手術は、古くから種々行われてきた。」と記載されているよ5 うに、主として審美にあるとされている。このような本件明細書等の記載の ほか、現在の社会通念に照らしてみても、本件発明に係る組成物は、人の病 気の診断、治療、処置又は予防のいずれかを目的とする物と認めることはで きない。 (3) これに対し、被控訴人は、本件発明は美容医療に関するところ、美容医療10 は、身体的特徴の再建、修復又は形成による心身の健康や自尊心の改善に寄 与する分野であり、治療並びに身体の構造又は機能に影響を及ぼすものであ るとして、本件発明が法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治 療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を 混合することにより製造されるべき医薬についての発明」に当たると主張す15 る。 しかし、一般に「病気」とは、「生物の全身または一部分に生理状態の異 常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象」(甲25: 広辞苑(第7版))、「生体がその形態や生理・精神機能に障害を起こし、 苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態」(甲26:大辞泉(第20 1版・増補・新装版))という意味を有する語であって、上記のとおり主と して審美を目的とする豊胸手術を要する状態を、そのような一般的な意味に おける「病気」ということは困難であるし、豊胸用組成物を「人の病気の… 治療、処置又は予防のため使用する物」ということも困難である。 また、法69条3項は、昭和50年法律第46号による法改正により、特25 許を受けることができないとされていた「医薬(人の病気の診断、治療、処 置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ)又は二以上の医薬を混合し て一の医薬を製造する方法の発明」に関する規定(同改正前の法32条2号) が削除されたことに伴い創設された規定であるところ、その趣旨は、そのよ うな「医薬」の調剤は、医師が、多数の種類の医薬の中から人の病気の治療 等のために最も適切な薬効を期待できる医薬を選択し、処方せんを介して薬5 剤師等に指示して行われるものであり、医療行為の円滑な実施という公益の 実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図る ことにあると解される。しかるところ、少なくとも本件発明に係る豊胸手術 に用いる薬剤の選択については、このような公益を直ちに認めることはでき ず、上記のとおり一般的な「病気」の語義を離れて、特許権の行使から特に10 これを保護すべき実質的理由は見当たらないというべきである。 (4) したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造され るべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんによ り調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、法69条3項の 規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がな15 い。 8 争点3-3(本件特許権の行使は権利の濫用等に当たり許されないか)につ いて 被控訴人は、控訴人による本件特許権の行使は、被控訴人が医師として被施 術者から血液を採取してNCPを製造し、これらを用いて製造した薬剤を被施20 術者に投与する一連の医療行為に対する特許権の行使にほかならないし、身体 的コンプレックスで精神を病む場合もあるので、豊胸手術も医療行為といえ、 これに用いられる混合薬剤の製造に特許権の効力が及ばないとすることは公共 の利益、福祉にも合致するとして、控訴人による本件特許権の行使は、権利の 濫用として許されないか、端的に医療行為には特許権の行使が及ばないと主張25 する。 しかし、被施術者からの採血、豊胸用組成物の製造及びこれの被施術者への 投与が、常に一連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえないことは、前 記3のとおりである。また、主として審美を目的とする豊胸手術を要する状態 を「病気」ということが困難であることや、少なくとも本件発明に係る豊胸手 術に用いる薬剤の選択について、医療行為の円滑な実施という公益を直ちに認5 めることができないことは、前記7のとおりである。 このような前提に立つと、本件で特許発明の実施行為とされている行為が豊 胸用組成物の製造であって、被控訴人が医師であるとしても、その行為に対し て本件特許権を行使することが権利の濫用に当たるということはできないし、 他に特許権の効力が及ばないとすべき理由はない。 10 したがって、権利の濫用等をいう被控訴人の抗弁には理由がない。 9 争点4-1(本件の損害額の算定に当たり、法102条2項を適用できる か)について (1) はじめに 前記2(1)の認定事実によると、被控訴人は、本件手術に用いる薬剤を製造15 したことにより、業として本件発明を実施したといえ、そのことにつき少な くとも過失が認められる。そこで、以下、被控訴人の損害賠償義務について 検討する。 (2) Aから損害賠償請求権の譲渡を受けたとの主張について ア 控訴人は、控訴人が本件特許権につきAに対して独占的通常実施権を設20 定していたところ、Aから被控訴人に対する独占的通常実施権侵害を原因 とする損害賠償請求権の譲渡を受けたとして、Aが受けた損害の額の算定 に当たり法102条2項が適用されるべきと主張する。 しかし、控訴人がAに対して本件特許権についての独占的通常実施権を 設定したことを認めるに足りる証拠はない。かえって、証拠(乙42)に25 よると、控訴人は、平成30年2月から令和3年12月にかけて、控訴人 のウェブサイトにおいて、「乳腺再生豊胸注射の特許貸与について」と題 して、本件特許権を明記して、通常実施権者又は専用実施権者を募集して いたことが認められるところ、このような控訴人の立場は、同一の範囲に おいて第三者に重複する内容の実施権を許諾しないことを内容とする独 占的通常実施権の設定と両立しない。 5 イ これに対し、控訴人は、特許権者は、独占的通常実施権を設定した場合 でも、独占的通常実施権者の同意があれば、第三者に対して更に実施権の 許諾が可能であり、控訴人が通常実施権設定の募集をしていたことをもっ て、Aが本件特許権の独占的通常実施権の設定を受けていたことと矛盾す るものではないと主張する。しかし、前記アのとおり、控訴人は、通常実10 施権者だけでなく、専用実施権者についても募集していたものであって、 控訴人の主張は採用することができない。 ウ したがって、Aが本件特許権についての独占的通常実施権を有していた 事実は認められないから、控訴人がAから損害賠償請求権の譲渡を受けた とする控訴人の主張は前提を欠き、採用することができない。 15 (3) 「控訴人グループ」としての利益を得ていたとの主張について 次に、控訴人は、本件特許権の侵害により控訴人が受けた損害の額の算定 に当たり法102条2項が適用されるべきとし、その理由として、控訴人と Aとは経済的に一体の関係にあり、控訴人はAを通じて本件発明を実施して 利益を得ているといえるから、控訴人には、被控訴人による特許権侵害行為20 がなかったならば利益が得られたであろう事情があると主張する。 しかし、控訴人が、本件発明を実施しているとか、競合品や競合役務を提 供しているといった事実関係を認めるに足りる証拠はない。控訴人とAはそ れぞれ独立した法人格であるところ、Aが事業により得た利益が必然的に控 訴人に配分される体制となっているなどの事実関係を認めるに足りる証拠も25 ない。 したがって、控訴人には、被控訴人による特許権侵害がなかったならば利 益が得られたであろう事情は認められないから、控訴人が受けた損害額を算 定するに当たり、法102条2項を適用することはできない。 10 争点4-2(損害額)について 前記9のとおり、控訴人が受けた損害の額を算定するに当たり、法1025 条2項を適用することはできないから、同条3項により控訴人が受けた損害 の額を算定する。 (1) 実施料率について ア まず、本件発明について控訴人が現実に第三者に対してその実施を許諾 し、実施料を受領していた実績を認めるに足りる証拠はない。 10 そこで、一般的な実施料の動向をみると、「知的財産の価値評価を踏ま えた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」 (帝国データバンク・ 平成22年)(甲34)において、国内企業・ロイヤルティ料率アンケー ト調査の結果として、「医薬・バイオ」分野のロイヤルティ料率が6.0% とされていること、「特許権等の実施料相当額算定手法について」(日本15 知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム・平成30年)(乙 44)には、「我国産業界において特許ライセンス契約交渉において提示 される実施料率としては、一般製造業では3%、医薬品では6%前後の率 に「松竹梅」などと称してそれぞれに上下1~2%程度を増減した率が大 方の相場であるとの認識が一般的に存在することは否定できない。」とさ20 れており、これらによると、医薬・バイオ分野における一般的な実施料と しては、6%が一つの目安になるということができる。 イ 次に、本件発明の内容等について検討する。 本件発明は、豊胸のために使用する組成物に係る発明であるところ、こ れを実際に用いて豊胸手術を行い、所望の効果を得るためには、当該組成25 物を得て被施術者の皮下に単純に投与すれば足りるというものではなく、 実際に施術を担当する医師の手技が重要な役割を果たすであろうことは自 明である。また、審査段階で引用文献1(甲8)として示された従来技術 には、多血小板血漿(PRP)と塩基性線維芽細胞成長因子(b-FGF) とを組み合わせた物が開示され、そこには豊胸に用いることへの示唆も記 載されている。そうすると、従来技術とは異なる本件発明の特徴としては、 5 豊胸に用いるのに十分な量の組成物を確保するため、用いる血液成分を多 血小板血漿(PRP)ではなく「自己由来の血液成分の中でも、その半数 を占める液体成分としての血漿」とした点や、より脂肪組織を生成、増大 させるために脂肪乳剤を加えた点にあるというべきである。加えて、本件 発明の課題であるところの安全で自然な方法による自己組織の回復、容貌10 の回復が得られる皮下組織増加促進用組成物である豊胸用組成物の提供と いう観点から、本件発明に係る豊胸のための組成物が、どの程度安全で自 然な方法による豊胸を提供できているかは、判然としないというほかはな い。 ウ 本件特許権を侵害した被控訴人の行為態様やその他の事情について検討15 する。 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、①被控訴人は、本件クリニック において、令和2年5月27日からモニターとして募集した者を、次いで、 同年12月から一般募集をした者を対象として、対価を得て本件手術をし ていたが、そのうち、法112条の3第2項1号の規定により本件特許権20 の効力が及ばない期間(令和3年7月26日~令和5年1月9日)の始期 の前日である令和3年7月25日までの間の本件手術の実績件数は多数回 であったこと(乙45、47、52~58)、②被控訴人は、令和4年9 月22日に医療法人を設立し、同年11月1日に同医療法人による診療所 開設届を提出し、同日以降、同医療法人が運営する診療所として本件手術25 が行われ、その売上げは同医療法人の収入となったこと(乙40、41) が認められる。 これらの事実に加え、前記2(1)の認定事実及び証拠(甲3、4、9)に よると、被控訴人は、本件特許の存在を認識し、これに関する弁理士の見 解書を取り付けた上で(なお、本件特許に無効理由があるとか、被控訴人 の行為に本件特許権の効力が及ばないとする見解が採用できないことは、 5 既に述べたとおりである。)、本件発明の実施に踏み切っており、その侵 害期間は令和2年5月27日から令和3年7月24日(特許権侵害となる 本件手術の最終施術日)までの約1年2か月間であるが、この間、「血液 豊胸」を全面的に打ち出した広告展開をして、豊胸手術のみの代金でも後 述するとおり約1億7000万円を売り上げたこと、被控訴人による本件10 発明の実施は、「自己由来の血漿」を「細胞成分を完全に除いた血漿(N CP)」とし、ヒアルロン酸やプラセンタ等を加えたほかは、本件明細書 等に実施例として記載されている方法を用いており、公開された本件発明 を特許権者に無断で実施する意図がうかがわれることなどが認められる。 他方、前記のとおり、本件発明に係る組成物を被施術者に投与するに際15 しては、医師である被控訴人の手技が重要となり、本件手術の対価のうち には、このような技術への対価も相応に含まれるものとみるべきこと、被 控訴人は、令和2年10月から同年12月までの約3か月間のみをみても 広告宣伝費に約2000万円を費やすなど、相応の販売促進により顧客を 得たこともうかがわれること(乙37~39、51)、血漿や線維芽細胞20 を使用した豊胸術を実施しているクリニックが他にも存在していること (乙64)が認められる。 エ 以上のとおり、一般的な実施料率の動向、本件発明の特徴や効果、被控 訴人による特許権侵害の態様等の事情に加えて、法102条3項により損 害の額を算定するに際しては、特許権の侵害があったことを前提として侵25 害者との間で実施許諾料の合意をする場面を仮定することができること (同条4項)、実施許諾料を定めるに際しては消費税相当額を考慮するこ とがあり得ること、その他本件に表れた諸般の事情を総合考慮すると、法 102条3項により算定される損害額は、被控訴人が本件手術の対価(豊 胸代金)として得た売上高に8%を乗じた額と認めるのが相当である。 (2) 豊胸代金の売上高と法102条3項による損害額について5 ア 証拠(乙45、47、52~58)及び弁論の全趣旨によると、本件発 明に係る特許権の侵害行為が行われたと認められる令和2年5月27日か ら令和3年7月24日にかけて、被控訴人が本件手術の対価として得た金 額(売上伝票に「血液マンマ」又は「HYマンマ」との記載があるものな ど本件手術の対価と認められるものから値引き額を控除した額)は、別紙10 1認容額一覧表の各「売上高」欄に記載のとおりであり、各月の売上高に 上記(1)の8%を乗じた額(小数点以下切捨て)は、同別紙の各「認容額」 欄に記載のとおりである。法102条3項により算定される損害額の合計 は、1363万2196円となる。 控訴人による損害賠償請求の対象期間のうち、上記期間を除く期間につ15 いては、本件全証拠をもっても、損害が発生したと認めることはできない。 イ なお、売上高の計算に際して考慮し又は考慮しない事項について補足し て次に説明する。 控訴人は、本件手術における豊胸代金のみならずオプション料金も含め るべきと主張するが、オプション料金は、静注麻酔や腫れ止め等、被施術20 者の要望に応じて提供される役務の対価であって、本件発明の実施に不可 避的に発生するものではないから、売上高の計算において考慮しない。 控訴人は、値引き分を考慮すべきではないと主張するが、被控訴人は、 ほとんどの被施術者に対して値引きを実施しており、正規の料金といった ものをほぼ観念できないことからすると、被控訴人が本件手術の対価とし25 て現実に受領した金額を計算の対象とするのが相当であるので、伝票に記 載された豊胸代金の額から、「値引割引金額」として記載された金額を控 除した額を計算の対象とする。 被控訴人は、代金を後に返金した分については控除すべきと主張するが、 既に本件発明を実施した後の事情であるから、売上高の計算において考慮 しない。 5 (3) 消費税相当額について 前記(1)エのとおり、法102条3項により損害額を算定するに当たり、実 施許諾料を定めるに際しては消費税相当額を考慮することがあり得ることを 含めた本件に表れた諸般の事情を総合考慮して、被控訴人が本件手術の対価 (豊胸代金)として得た売上高に8%を乗じた額とするのが相当であるとす10 るものであるから、更に消費税相当額を考慮する必要は認められない。 (4) 弁護士費用相当損害金について 本件における諸事情に照らすと弁護士費用相当額は140万円とするのが 相当である。なお、同額に係る遅延損害金の起算日は、侵害の最終月である 令和3年7月の翌月の初日(同年8月1日)を請求しているものと解される。 15 (5) まとめ 以上によると、当審により拡張された控訴人の請求は、1503万219 6円及び別紙1認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金額に対する「遅延損 害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金 の支払を求める限度において理由がある。 20 11 結論 そうすると、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人の原審に おける1000万円及びこれに対する遅延損害金の請求は理由があるから認 容すべきところ、これを棄却した原判決は失当であって、本件控訴は理由が あるから、原判決を取り消して控訴人の上記請求を認容し、また、控訴人の25 当審における拡張請求も一部理由があってこれを認容すべきであるが、その 余の拡張請求には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり 判決する。 なお、本件の審理において、法105条の2の11の規定に基づき、いわ ゆる第三者意見募集を実施した。裁判所に提出された意見書は、いずれも、 医療と特許との関係についての実情を踏まえた貴重な意見を含み、裁判所の5 審理及び判断に有益なものであった。関係者各位に深く御礼申し上げる。 |
|
| 追加 | |
| 10裁判長裁判官本多知成15裁判官宮坂昌利20裁判官清水響25 5裁判官中平健10裁判官天野研司 (別紙1)認容額一覧表集計年集計月売上高認容額遅延損害金起算日令和25132,000\10,560令和2年6月1日62,024,548\161,963令和2年7月1日71,862,093\148,967令和2年8月1日84,323,003\345,840令和2年9月1日92,376,366\190,109令和2年10月1日10668,183\53,454令和2年11月1日114,134,547\330,763令和2年12月1日1213,286,822\1,062,945令和3年1月1日令和3121,665,929\1,733,274令和3年2月1日220,247,043\1,619,763令和3年3月1日322,435,482\1,794,838令和3年4月1日422,398,142\1,791,851令和3年5月1日525,639,393\2,051,151令和3年6月1日617,226,683\1,378,134令和3年7月1日711,982,300\958,584令和3年8月1日弁護士費用相当損害金\1,400,000令和3年8月1日合計170,402,534\15,032,196 (別紙2)請求額一覧表集計年集計月豊胸代金豊胸代金各月請求額遅延損害金起算日(オプション込)令和25300,000370,000\166,144令和2年6月1日63,100,0003,498,500\1,570,963令和2年7月1日72,918,4003,048,200\1,368,760令和2年8月1日85,600,0006,080,000\2,730,157令和2年9月1日93,190,9103,195,910\1,435,088令和2年10月1日101,100,0001,290,000\579,260令和2年11月1日114,200,0004,433,000\1,990,590令和2年12月1日1216,700,00017,468,000\7,843,814令和3年1月1日令和3127,854,54629,044,637\13,042,176令和3年2月1日228,409,09129,669,091\13,322,581令和3年3月1日325,643,63727,543,637\12,368,169令和3年4月1日424,380,00026,767,000\12,019,428令和3年5月1日529,510,00131,215,301\14,016,889令和3年6月1日621,760,91023,181,310\10,409,314令和3年7月1日715,028,18215,893,182\7,136,659令和3年8月1日合計209,695,677222,697,768\99,999,992 (別紙3)略語一覧本件特許特許第5186050号の特許(出願日:平成24年2月24日、登録日:平成25年1月25日)5本件特許権本件特許に係る特許権本件明細書等本件特許の願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面(その内容は甲2記載のとおり)本件クリニック被控訴人が令和元年頃から令和4年頃まで東京都内に設置し、豊胸手術等の美容医療サービスを提供していた10「Y’」との名称のクリニック本件発明本件明細書等の特許請求の範囲の請求項4記載の発明のうち、請求項1記載の発明を引用する発明A、出願人医師、本件発明の発明者、本件特許の出願人(以下、第三者の氏名は、記号で表記する。)15本件手術被控訴人が「無細胞プラズマジェル」を用いて本件クリニックで提供していた「3WAY血液豊胸」という名称の血液豊胸手術NCP細胞成分を完全に除いた血漿薬剤ノート本件クリニックにおいて作成されていた本件手術に用いた20成分等を記録する手書きのノート(甲29、乙60、62)B令和3年4月8日及び同月26日に本件クリニックで本件手術を受けた者C本件クリニックで勤務していた看護師25D本件クリニックで勤務していた准看護師 |