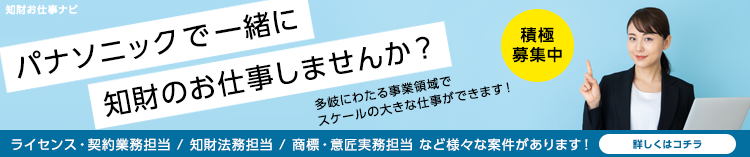| 関連審決 |
無効2022-800025 |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行ケ)
10043号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
5 原告 大和ハウス工業株式会社 同訴訟代理人弁護士 山上和則 雨宮沙耶花 10 大林良寛 同訴訟代理人弁理士 芝哲央 小菅一弘 森林克郎 15 被告 NextInnovation 合同会社 同訴訟代理人弁護士 鮫島正洋 高橋正憲 20 石橋茂 藤田達郎 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/03/12 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 25 事実及び理由第1 請求1特許庁が無効2022−800025号事件について令和6年3月28日にした審決のうち、特許第5667716号の請求項1、2、4、5、7〜20に係る部分を取り消す。 第2 事案の概要5 1 特許庁における手続の経緯等(1) 被告は、平成24年12月14日に出願した特許出願(特願2012−273962号(優先日平成23年12月16日、優先権主張国日本)の一部を分割して、平成26年6月17日、発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明について、新たな特許出願(特願2014−124689号。 「本件出願」以下 という。)10 をし、同年12月19日、特許権の設定登録(特許第5667716号。請求項の数は20。以下、この特許を「本件特許」という。)を受けた。(甲18)(2) 原告は、令和4年3月25日、本件特許の請求項1〜20に係る発明の特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した(無効2022−800025号)。被告は、同年7月22日付けで、本件特許の特許請求の範囲及び明細書を訂正15 する旨の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した(甲80の1・2)。 特許庁は、令和6年3月28日、本件訂正を認めた上で、 「特許第5667716号の請求項1、2、4、5、7〜20に係る発明についての本件審判の請求は成り立たない。特許第5667716号の請求項3、6に係る発明についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同20 年4月8日、原告に送達された。 (3) 原告は、令和6年5月1日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1〜20の記載は、別紙1「本件訂正後の特許請求の範囲」記載のとおりである。なお、本件審決の記載に合わせて、請求項25 1のみ分説記号を用いて記載している。以下、本件訂正後の請求項1、2、4、5、 7〜20に係る発明を「本件訂正発明1」等といい、本件訂正発明1、2、4、5、 27〜20を併せて「本件訂正発明」という。 また、本件訂正後の明細書及び図面(以下、これらを併せて「本件明細書」という。)は、別紙2「本件明細書(本件訂正後)」のとおりである。 (甲18、80の1・2)5 3 本件審決の理由の要旨(1) 無効理由本件審決の理由の要旨は、本件訂正を認めた上で、原告主張の下記ア〜クの無効理由1〜8は、いずれも理由がないというものである。 ア 無効理由110 甲1(特開2007−51452号公報)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)を主引用発明とし、甲2(特開2011−64028号公報)に記載された構成及び甲3(特開2009―47193号公報)に例示されるような選択的事項に基づいてする請求項1、3、6、7、8及び10に係る発明の進歩性の欠如イ 無効理由215 甲1発明を主引用発明とし、甲4(実願昭50−30814号(実開昭51−111715号)のマイクロフィルム)、甲5(加藤勉著「鉄骨構造」(建築構造学大系18)彰国社・昭和46年10月発行)及び甲6(特開2000−297498号公報)に記載された周知の構成に基づいてする請求項1、3、6、7、8及び10に係る発明の進歩性の欠如20 ウ 無効理由3請求項1、2、3、6、7、8及び10に係る発明は甲12(特開2010−121384号公報)に記載された発明(以下「甲12発明」という。)と同一であるとする新規性の欠如、又は甲12発明を主引用発明とし、甲13(特開2007−239241号公報)に記載された発明(以下「甲13発明」という。)に基づいて25 する進歩性の欠如エ 無効理由43甲2に記載された発明(以下「甲2発明」という。)を主引用発明とし、甲1、甲12及び甲14(特開2000−73603号公報)に記載された周知の構成と、 甲12に記載された構成に基づいてする請求項1、3、6、7、8及び10に係る発明の進歩性の欠如5 オ 無効理由5(サポート要件違反)カ 無効理由6(明確性要件違反)キ 無効理由7(実施可能要件違反)ク 無効理由8(分割要件違反、進歩性の欠如)(2) 本件審決が認定した甲1発明と本件訂正発明1との一致点・相違点10 ア 甲1発明本件審決が認定した甲1発明は以下のとおりである。 「剪断変形する矩形平板の金属薄板2と、その形状を維持するために金属薄板2の周囲を囲う枠3(フランジ)とから形成される、金属薄板2の面内方向に荷重が作用するエネルギー吸収部材1であって、 15 金属薄板2は直列に2枚備え、 枠3は、直列の2枚の金属薄板2の間と両端に設けた枠3と、対向する上下の2辺に設けた端部板3’からなり、 2枚の金属薄板2と左右両端の枠3とは直交しており、 建築構造物の梁5や柱6にボルトで締結するものであって、間柱4の一部として、 20 構造物の間柱4及び壁部材7の双方の中間的な部材として、壁部材7として取り付けたり、梁5や柱6の接合位置や、斜材8(梁リンク部材)の間であって梁5の一部として、柱6と柱6の間の梁5の一部の境界梁として配置することもできる、 エネルギー吸収部材1。」イ 本件訂正発明1と甲1発明との対比25 本件審決が認定した本件訂正発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 4(一致点)建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって、 一対の第一補強部と、 前記一対の第一補強部を連結した板状の一対の剪断部と、 前記一対の剪断部は、連結部を介して一連に設けられ、 5 前記一対の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一対のプレートとを備え、 前記剪断部は、前記第一補強部に対して傾斜を成し、 前記剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行う弾塑性履歴型ダンパ。 (相違点1)連結部を介して一連に設けられる板状の一対の剪断部について、本10 件訂正発明1は、互いの向きを異ならせて設けられたものであるのに対し、甲1発明は、金属薄板2が2枚、直列に備えられている点。 (相違点2)第一補強部は、剪断部に、第一補強部と剪断部とのなす角を、本件訂正発明1は、鋭角になるように形成されるのに対し、甲1発明は、金属薄板2と枠3とは直交している点。 15 (3) 本件審決が認定した甲12発明と本件訂正発明1との一致点・相違点ア 甲12発明本件審決が認定した甲12発明は以下のとおりである。 「左右の鉄筋コンクリート(以下「RC」という。)造の柱14、16とRC造の上下の梁18、20(水平部材)によって構成される建物10の架構12において、 20 梁18の下面から下向きに突出して設けられている上連結部40Aと、梁20の上面から上向きに突出して設けられている下連結部40Bと、の間に配置された波形耐震部材26であって、 波形耐震部材26は波形鋼板28(鋼板)と枠体30とを備えており、 波形鋼板28は、材料として普通鋼や低降伏点鋼等が用いられる鋼板を波形形状に25 折り曲げ加工して構成され、その折り筋を横(折り筋の向きを横方向)にして架構12の構面に配置されており、 5波形鋼板28の左右の端部には、プレート状に形成されている縦フランジ32A、 32Bがそれぞれ設けられ、波形鋼板28の左右の端部に沿って溶接固定されており、 波形鋼板28の上下の端部には、プレート状に形成されている鋼製の横フランジ34A、34Bがそれぞれ設けられ、波形鋼板28の上下の端部に沿って溶接固定され5 ており、 これらの縦フランジ32A、32B及び横フランジ34A、34Bは、各々の端部同士が溶接等によって接合されており、これによって波形鋼板28の外周部を囲む枠体30が構成され、縦フランジ32A、32B及び横フランジ34A、34Bはそれぞれ波形耐震部材26の縦辺、横辺に相当し、 10 波形鋼板28の上下の端部は、波形鋼板28の上下方向に延びており、該端部と横フランジ34A、34Bとは直交しており、 横フランジ34A、34Bはそれぞれ上連結部40Aの内壁42A(開口部の上の内壁)、下連結部40Bの内壁42B(開口部の下の内壁)に固定されており、これによって上連結部40Aと下連結部40Bとが波形耐震部材26によって連結されて15 おり、 これらの上連結部40A、下連結部40B、及び波形耐震部材26によって間柱が構成されており、 風や地震等によって架構12の面内方向に水平力が作用し、架構12に層間変形が生じると、波形鋼板28のアコーディオン効果によって上下の梁18、20の曲げ変20 形が阻害されないため、架構12がラーメン構造としての耐震性能を発揮し、また、 上連結部40A及び下連結部40Bから水平力が波形耐震部材26に伝達され、波形鋼板28がせん断変形することにより、波形鋼板28が水平力に抵抗して耐震効果を発揮し、また、水平力に対して波形鋼板28が降伏するように設計することで、鋼板の履歴エネルギーによって振動エネルギーが吸収され、制振効果を発揮し、 25 波形鋼板28は、鋼板を波形形状とすることで、せん断座屈耐力・変形性能を向上させることができ、通常の鋼板を用いる場合よりもせん断座屈防止手段としての補剛6リブを減らすことができ、 波形鋼板28を、その折り筋を縦(折り筋の向きを上下方向)にして開口部42等に設置しても良い、 波形耐震部材26。」5 イ 本件訂正発明1と甲12発明との対比本件審決が認定した本件訂正発明1と甲12発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 (一致点A)建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって、 10 一対の第一補強部と、 前記一対の第一補強部を連結した剪断部と、 前記一対の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一対のプレートとを備え、 前記剪断部は、前記第一補強部に対して傾斜を成し、 前記第一補強部は、前記剪断部に、該第一補強部と該剪断部とのなす角が所定の角15 度となるように形成され、 前記剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行う弾塑性履歴型ダンパ。 (相違点A−1)剪断部について、本件訂正発明1は「前記一対の第一補強部を連結し、互いの向き20 を異ならせて設けられた板状の一対の剪断部と、前記一対の剪断部は、連結部を介して一連に設けられ」とあるように、互いの向きを異ならせて設けられた一対(二つ)備えるものであり、そして、該一対の連結部を介して設けられているのに対し、甲12発明は、そのような構成を備えるものではない点。 (相違点A−2)25 第一補強部は、剪断部に、該第一補強部と該剪断部とのなす角について、本件訂正発明1は、鋭角となるように形成されているのに対し、甲12発明は、左右方向に延7びる端部と縦フランジ32A、32Bとが直交している点。 第3 当事者の主張(本訴において、原告は、本件審決における無効理由1、3及び5について取消事由を主張する。また、本件訂正により、請求項3及び6は削除されたところ、本訴において、原告は、本件訂正を争っていないから、請求項35 及び6に係る発明についての取消しの主張は失当となる。)1 取消事由1(甲1発明を主引用発明とし、甲2に記載された構成及び甲3に例示されるような選択的事項に基づいてする請求項1、3、6、7、8及び10に係る発明の進歩性の欠如)(1) 原告の主張10 ア 相違点1に係る構成の容易想到性の判断の誤りについて(ア) 甲1には、せん断型エネルギー吸収部材(せん断パネル型ダンパー)が、建築構造物の垂直構面(柱と梁で構成される垂直な平面)に設置され、構面内の一方向の動きに対してダンパー機能を奏することが記載されている。他方、橋梁等の二次元的な動きに対応させるために、建設構造物に用いられるせん断パネル型ダン15 パーを複数の方向に配置することは、甲2の記載(甲2の【0002】【0004】【0005】)から明らかなとおり、従前から知られていたから、甲1発明に甲2発明の配置を適用する動機付けは存在しないとの本件審決の判断には誤りがある。 (イ) 発明の容易想到性を考慮する上での「阻害要因」とは、通常、対象発明に対して、他の発明を適用すると、当該対象発明が予定していた課題解決手段が機能す20 ることを阻害し、発明としての意義を滅してしまうことを意味する。本件では、甲1発明に甲2発明を適用した場合、2枚の金属薄板の一方には面外方向の力が加わることになるが、甲1発明の金属薄板は面外変形が許容されるのであるから、エネルギー吸収部材としてはより挙動が安定することになる。そうすると、甲1発明に甲2発明を適用することに上記意味での阻害事由があるどころか、逆にその課題解25 決手段の機能が活かされることになるから、阻害要因があるとの本件審決の判断は誤りである。 8(ウ) 本件審決は、建築物に用いられるせん断パネル型ダンパーは一方向の動きのみを考慮すればよいから、建築物を対象とした甲1発明に、複数の入力に対応するための甲2発明を適用する動機付けはないとしている。一方、本件特許に係る特許権の別件侵害訴訟において、被告が、建築物に用いられ、一方向からの力のみ入力5 される原告の製品が、複数方向の入力に対応するための本件訂正発明に係る特許権を侵害すると主張していることを前提とすると、甲1発明においても複数の入力に対応する場面があるといえることになるから、甲1発明に甲2発明を適用する動機付けがある。したがって、本件審決の上記判断は誤りである。 イ 相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤りについて10 本件訂正発明1について、剪断部と第一補強部は何らかの角度を持って配置する必要があるところ、当該角度を鋭角とすることに何らの意義もなく、その設定は当業者の単なる設計事項というべきである。そして甲3にも、せん断パネル(剪断部)と端縁補強体15(第一補強部)を任意の角度にしてもよいとされているように、 その角度を鋭角とすることは単なる選択的な事項として知られていたことが裏付け15 られる。したがって、相違点2に係る構成とすることは容易である。 また、甲1発明において、 「金属薄板2」と「枠3」について、何らかの角度を設定する必要があるところ、これに対応する甲3の「パネル体」と「端縁補強体」の角度について鋭角にしてもよいとされているのであるから、この記載事項を参考にすることに何らの問題はない。 20 (2) 被告の主張ア 相違点1に係る構成の容易想到性の判断の誤りについて(ア) 動機付けの有無の判断要素の一つである引用発明の内容中の示唆は、主引用発明の記載中に、副引用発明を適用することの示唆があるか否かを判断するのであって、副引用発明の記載により判断するのではない。 25 本件審決が認定したとおり、甲1は、そもそも構面内の一方向の動きに対してダンパー機能を奏する構成なのであるから、対象物である建築構造物の二次元的な動9きに対応するためのせん断パネルダンパーの設置等に係る示唆は記載されていない。 (イ) 本件審決は、甲1の図2、 【0046】及び【図17】〜【図18】を根拠として、金属薄板を安定的に変形させる方向(想定されるエネルギーの入力方向)は、 一つの方向であって、複数の方向を設けることは想定されておらず、甲2発明にお5 いて、複数の金属薄板2の面内方向を異ならせることには阻害要因がある、と判断しているが、上記判断は正当なものである。 (ウ) 本件審決が述べた動機付けの有無は、甲1発明及び甲2発明に基づくものであり、本件訂正発明が複数方向の入力を前提とするか否か、原告の製品のダンパが一方向の力のみ入力されるか否かといった事項とは全く関係がない。原告の主張は、 10 充足論と無効論を混同するものであって失当である。 イ 相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤りについて本件訂正発明は、そもそもH字形ダンパとは異なり、異なる方向を有する一対の剪断部によりエネルギーを吸収するのであるから、一対の剪断部のなす角度に自由度があり、剪断部と補強部がなす角度も、鋭角が望ましい場合も鈍角が望ましい場15 合もあり得る(乙3)。したがって、H字形ダンパのように、剪断部と補強部が直交していなければ十分な強度が得られないということはない。甲1発明ないし甲3発明(H字形ダンパ)と本質的に異なる発明である本件訂正発明に係る明細書の記載をもって、パネル体と端縁補強体とのなす角度が選択的事項であることの根拠とすることはできない。 20 2 取消事由2(請求項1、2、3、6、7、8及び10に係る発明は甲12発明と同一であるとする新規性の欠如、又は甲12発明を主引用発明とし、甲13発明に基づいてする進歩性の欠如)(1) 原告の主張ア 相違点A−1について25 (ア) 相違点A−1の認定の誤り本件審決は、本件訂正発明1は、一対すなわち二つの剪断部を有するのに対し、 10波形鋼板はそのような構成ではないとして相違点を認定している。 しかしながら、本件訂正発明1(請求項1)に従属する本件訂正発明2(請求項2)は、 「前記剪断部は、傾斜方向が互いに異なる部分が交互に並ぶ波形を成すことを特徴とする請求項1記載の弾塑性履歴型ダンパ。」と特定されているところ、「交5 互に」とは、 「かわるがわる。たがいちがいにするさま。」(甲77)を意味しており、 傾斜方向が互いに異なる部分が、2回以上現れることが必要である。すなわち、板状の剪断部が一対あるのみでは、「傾斜方向が互いに異なる部分が交互に並ぶ波形を成す」との構成とすることはできないから、本件訂正発明1における「板状の一対の剪断部」とは、「弾塑性履歴型ダンパが板状の一対の剪断部のみから成る構成」10 を意味するのではなく、 板状の一対の剪断部があること」「 を意味するものであって、 二対以上の剪断部を有する波形の構成も含まれると解するのが相当である。 そうすると、まず、甲12発明の「波形鋼板28」も、少なくとも一対の剪断部を含む構成であるといえるから、その点で本件訂正発明1に含まれる。また、本件審決は、「甲12発明の「波形鋼板28」が、「波形」をしているから、甲12発明15 は、本件訂正発明1のように、 「前記一対の第一補強部を連結し、互いの向きを異ならせて設けられた板状の一対の剪断部と、前記一対の剪断部は、連結部を介して一連に設けられ」るとの構成を備えていない」と認定するが、その認定は、本件訂正発明1(請求項1)を引用する本件訂正発明2(請求項2)の特定に矛盾する。 したがって、本件訂正発明1(請求項1)を引用する本件訂正発明2(請求項2)20 の特定を勘案すると、本件審決において「本件訂正発明1と甲12発明との相違点A−1」と認定した相違点の構成は、本件訂正発明1と甲12発明との一致点であり、相違点ではない。 (イ) 相違点A−1に係る構成の容易想到性の判断の誤り甲13発明は、甲12発明と同様に波型の鋼板を用いたせん断パネルダンパーに関25 する発明であり、波形鋼板という以上波形が前提となるものであって、平板状の中に一つだけ小さな窪みが存在する構成を意味しないことは明らかであり、甲13には11「窪み26は少なくとも1つあればよく」(甲13の【0020】)との記載があるとおり設定する幅に合わせて波の数を調整してもよいことが示されていると解される。 甲13は、あくまでも波形鋼板であることが前提であり、本件訂正後の請求項2について、一対の剪断部のみであっても「波形」と呼称するのであれば、この点から5 しても本件審決の判断は誤りである。 イ 相違点A−2の認定の誤りについて甲12によると、波形鋼板28について、折り筋を縦にしてもよいと記載され(【0071】 、波形形状について図23の(C)に三角波の形状が示されている。 )この形状では、三角波の一辺と隣接する一辺とは、 「互いの向きを異ならせて設けら10 れた板状の一対」の部分を形成していることになり、当該部分を複数有するものといえる。そして、原告が甲12発明として主張した発明は、上記のように波形鋼板として図23の(C)の三角波の形状の波形鋼板を用いた発明であるから、波形鋼板の波形の水平方向に延びた部分は存在しない。この場合、水平方向に延びた個所が存在しないから、必然的に傾斜した板部の頂部で横フランジに接続された構成と15 なるので、波形鋼板と横フランジの接続部は鋭角となる。 したがって、三角波の波形鋼板と横フランジとは、なす角が鋭角となることは明らかであり、甲12発明において、折り筋を縦にした場合に「(縦フランジと剪断変形する部位のなす角が)鋭角」は当然に認定できる。 仮に、 「三角波の波形鋼板と横フランジとは、なす角が鋭角となる」技術を、甲120 2に記載された事項として導き出せないとしても、横フランジと波形鋼板との接合は必ず存在する。その接合角度は直交、鋭角、鈍角のいずれかにせざるを得ないのであり、本件訂正発明1のように鋭角とすることに何らかの意義があるわけではないから、少なくとも鋭角とすることは当業者にとって単なる選択事項にすぎないというべきである。 25 (2) 被告の主張ア 相違点A−1について12(ア) 相違点A−1の認定の誤りについて原告は、本件訂正発明1の「板状の一対の剪断部」の意義を、本件訂正発明2に係る請求項2の「交互に」の文言を根拠に、 「二対以上の剪断部を有する波形の構成も含まれる」と解釈する。 5 この原告による解釈手法は、従属請求項である請求項2に「前記剪断部」と記載があるにもかかわらず、請求項2が引用する請求項1(独立請求項)に記載の「一対の剪断部」における「一対」という文言と明らかに矛盾する読み方(「二対以上」と読むこと)をするものであり、特許請求の範囲の文言解釈として明らかに誤っている。 10 そして、本件審決は、本件訂正発明2の「「前記剪断部」の「前記」が指し示すものは、請求項1における「一対の剪断部」における(一つの)「剪断部」である」とする。これは、従属請求項の「前記」が付された文言(剪断部)の意味を、当該請求項が引用する独立請求項に記載された同じ文言(剪断部)と同じ意味(一対の剪断部)に解釈するという、特許請求の範囲の文言解釈として極めて正しい解釈をし15 たものである。 したがって、原告による「板状の一対の剪断部」の解釈は誤っており、本件審決が認定するように、甲12の波形鋼板28は 「板状」「 とはいえない」のであるから、 相違点A−1において、甲12発明に「板状の一対の剪断部」を認定しなかった本件審決に誤りはない。 20 (イ) 相違点A−1に係る構成の容易想到性の判断の誤り本件審決は、甲12の「形鋼板28は、鋼板を波形形状とすることで、せん断座屈耐力・変形性能を向上させることができ、通常の鋼板を用いる場合よりもせん断座屈防止手段としての補剛リブを減らすことができる。 (」 【0047】)という記載を根拠に、甲12発明は「鋼板を…波形形状とすることに意義がある」として、波25 の数を一つにすると、せん断座屈耐力・変形性能の向上に反するから、阻害要因があると結論付けたのである。これに対し、原告の主張は、単に「理由になっていな13い」とだけ述べるものであり、本件審決が示した上記の論理について何ら具体的な反論を行っておらず、主張自体失当である。 イ 相違点A−2の認定の誤りについて原告の主張は、甲12に開示されていない内容を勝手に作図して「鋭角」を認定5 しようとするものにすぎず、甲12においてこのような構成は記載も示唆もされていないから失当である。 3 取消事由3(サポート要件違反)(1) 原告の主張本件訂正発明1は、「入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を10 行う」とのみ特定され、どの方向からの荷重にも対応し得るかのように機能的に特定しているが、本件審決は、本件訂正発明1が全ての方向からのエネルギー吸収を行うことができるものではないことを認識していながらサポート要件に違反しないと判断しており、この点において本件審決には誤りがある。 (2) 被告の主張15 原告は、 「様々な(角度や大きさの)入力を減衰させることができる」ことは、 「全ての方向からのエネルギー吸収を行うことができる」ことを意味するという趣旨の主張を繰り返すのみであり、サポート要件の判断基準に従ったサポート要件違反の主張を行っておらず、主張自体失当である。 「様々な(方向の)入力を減衰させることができる」とは、あれこれ異なった方20 向、すなわち「複数の方向の入力を減衰させることができる」ことを意味する。したがって、 「全ての方向からのエネルギー吸収を行うことができる」との上記の原告の理解は、「様々」の語義に照らして明らかに誤っている。 第4 当裁判所の判断1 本件明細書の記載事項について25 本件明細書には、本件訂正発明に関し、次のような技術的思想及び技術的意義が記載されているものと認められる。 14従来の剪断パネル型ダンパは、建築物や橋梁等において、上部構造物と下部構造物との間における下部構造物に固定設置され、常時や所定レベルまでの地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定レベル以上の地震に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能するものであるが(【0005 2】、剪断部を一つしか有しておらず、一方向からの水平力に対してしかダンパと)して機能しないため、例えば、橋軸方向の水平力に対してダンパとして機能するように設置された場合に、橋軸方向以外の方向からの水平力が加わると、入力のあった水平力を十分に減衰させることができず(【0004】 、また、その設置に際して)は、想定される入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角10 度設定が必要とされるという課題があった(【0005】 。 )そこで、本件訂正発明1は、所定レベル以上の地震の際に、複数の方向からの入力に対してダンパとして機能し得る弾塑性履歴型ダンパを提供することを目的とし(【0006】 、 ) この課題を解決するために、一対の第一補強部と、これらを連結し、 互いの向きを異ならせて設けられ、連結部を介して一連に設けられた板状の一対の15 剪断部と、一対の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一対のプレートとを備え、 剪断部は、第一補強部に対して傾斜を成し、第一補強部は、剪断部に、第一補強部と剪断部とのなす角が鋭角となるように形成され、剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行うように構成した(【0007】 。 )本件訂正発明1では、二つの剪断部が設けられているので、所定レベル以上の地20 震の際に、剪断部が直接又は間接に上部構造物のストッパに突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部が剪断弾塑性変形することにより減衰させることができ、また、二つの剪断部を連結部で連結してなるので、より大きな地震時の振動を吸収することができ、さらに、二つの剪断部の向きを異ならせることで、一方向だけでなく複数の方向からの地震時の振動を吸収することができる(【0014】 。 )25 2 取消事由1(甲1発明を主引用発明とし、甲2に記載された構成及び甲3に例示されるような選択的事項に基づいてする請求項1、3、6、7、8及び10に15係る発明の進歩性の欠如に関する認定、判断の誤り)について(1) 甲1発明甲1によると、前記第2の3(2)アに記載の発明(甲1発明)が記載されていると認められる。 5 (2) 本件訂正発明1と甲1発明との対比本件訂正発明1、本件明細書及び甲1によると、本件訂正発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、前記第2の3(2)イに記載のとおりであると認められる。 (3) 相違点1に係る構成の容易想到性ア 甲1発明の金属薄板2の技術的意義10 甲1によると、 「本発明のエネルギー吸収部材においては、図1及び図2に示す矢印方向に荷重が作用する。(甲1の【0038】」 )との記載があり、図1及び図2に示された構成によると、甲1に記載のエネルギー吸収部材は、建築物の架構の構面に沿って荷重が作用することを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように金属薄板を配置することで、地震などによるエネルギーを吸収するもので15 あると認められる。この理解は、甲1の【0046】、図17及び図18において、 金属薄板2を複数枚備える構成例において、それらの金属薄板2が面内方向を一致させる向きで配置されていることからも裏付けられる(甲1の【0046】、図17及び図18)。 イ 甲2発明20 甲2によると、甲2には次の発明(甲2発明)が記載されていると認められる。 「パネル部11、載荷部材12、及び荷重伝達抑制手段20を備えた、橋梁上部構造と橋梁下部構造との間に設置されるせん断パネル型ダンパー10であって、 パネル部11は、極低降伏比鋼により形成された板状部材であって、 パネル部11の橋梁下部構造102への固定構造は、パネル部11の下辺と橋梁25 下部構造102の上面との間に連結板等を設け、この連結板等を介して、パネル部11と橋梁下部構造102とを間接的に固定しており、 16ブロック状の載荷部材12は、その側面12aがパネル部11の側辺11bの上方と対向するように、橋梁上部構造105の下面に設けられており、 載荷部材12の側面12aとパネル部11の側辺11bとの間には、載荷部材12にかかる荷重のうち、Y方向(橋軸と垂直な方向)の荷重成分がパネル部11に5 伝達することを抑制する荷重伝達抑制手段20が設けられ、この荷重伝達抑制手段20は、転動体21、及びこの転動体21を保持し、パネル部11の側辺11b上方に設けられた保持部材22を備えており、載荷部材12の側面12aとパネル部11の側辺11bとの間に略球状の転動体21を転動自在に保持しており、荷重200の面外方向成分202がパネル部11に伝達されることを抑制できるため、パ10 ネル部11が面内方向にうまく変形することができ、橋梁下部構造と橋梁上部構造とを相対的に移動させるエネルギーを吸収することができるものであって、 パネル部11の側辺11bにリブ13を設けてもよく、これにより、パネル部11の面外方向の剛性が向上し、パネル部11の面外方向への変形をより抑制することができるものであり、 15 パネル部11とリブ13とは直交しており、 せん断パネル型ダンパーの設置位置については、 橋梁上部構造と橋梁下部構造とが平面視において二次元的に相対移動可能な橋梁支承構造の場合、設置されるせん断パネル型ダンパー10の一部は、その面内方向(下辺長手方向に同じ)がX軸方向(橋軸方向)となるように設置され、設置さ20 れるせん断パネル型ダンパー10の残りの一部は、その面内方向がY軸方向(橋軸方向と垂直な方向)となるように設置され、両せん断パネル型ダンパー10の設置位置や設置数は任意であって、 また、せん断パネル型ダンパー10の面内方向がX軸にもY軸にも向かないようにせん断パネル型ダンパー10を設置してもよい、 25 せん断パネル型ダンパー10。」ウ 甲2発明の甲1発明への適用について17上記イによると、甲2発明のせん断パネル型ダンパー10は、橋梁上部構造と橋梁下部構造とが平面視において二次元的に相対移動可能な橋梁支承構造の場合に、 互いの向きを異ならせて複数設置され得るものである。これに対し、甲1発明のエネルギー吸収部材1は、建築物の架構の構面に沿って一方向から荷重が作用するこ5 とを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように2枚の金属薄板2を直列に配置するものであるから、甲1発明に甲2発明のせん断パネル型タンパー10の配置を適用する動機付けがない。 また、甲1発明の2枚の金属薄板2の向きを互いに異ならせるとすると、少なくとも一方の金属薄板2は荷重が面内方向に入力されない配置となるから、建築物の10 架構の構面に沿って荷重が面内方向に入力されることを前提とした甲1発明においてこのような構成の変更には阻害要因があるといえる。 したがって、甲1発明に甲2発明を適用することにより上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。 エ 原告の主張について15 (ア) 原告は、橋梁等の二次元的な動きに対応させるために、建設構造物に用いられるせん断パネル型ダンパーを複数の方向に配置することは従前から知られていたから、甲1発明に甲2発明の配置を適用する動機付けが存在しないとの本件審決の判断には誤りがある旨を主張する。 しかしながら、建築物の架構の構面に沿って作用する荷重が入力されるダンパに、 20 橋梁等の二次元的な動きに対応させるための複数方向の配置を適用する動機付けはないから、原告の主張は理由がない。 (イ) 原告は、甲1発明に甲2発明を適用した場合、2枚の金属薄板の一方には面外方向の力が加わることになるが、甲1発明の金属薄板は面外変形が許容されるのであるから、エネルギー吸収部材としてはより挙動が安定することになり、甲1発25 明に甲2発明を適用することに阻害事由があるどころか、逆にその機能が活かされると主張する。 18しかしながら、甲1発明は、建築物の架構の構面に沿った一方向からの荷重の入力を想定するものであるところ、甲1発明が面内方向の入力による面外変形を許容しているとしても、甲1発明は、面外方向の入力によりその機能が活かされるものとは認められず、原告の主張は理由がない。 5 (ウ) 原告は、本件特許に係る特許権の別件侵害訴訟において、被告が「建築物に用いられる原告の製品が、複数方向の入力に対応するための本件訂正発明に係る特許権を侵害する」と主張することを前提とすると、甲1発明においても複数の入力に対応する場面があるといえることになるから、甲1発明に甲2発明を適用する動機があると主張する。 10 しかしながら、本件における進歩性の判断は、本件特許の出願前に当業者が甲1及び甲2の記載に基づいて本件訂正発明1を容易に発明できたかを判断するものであり、この判断は上記ウのとおりである。そして、別件侵害訴訟における被告の主張によって、甲1発明の理解が一義的に決まるものではないから、原告の主張は失当である。 15 (4) 小括以上によると、相違点2に係る構成の容易想到性について判断するまでもなく、本件訂正発明1及び本件訂正発明1を引用する本件訂正発明7、8及び10は、甲1発明及び甲2発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、原告の取消事由1は理由がない。 20 3 取消事由2(請求項1、2、3、6、7、8及び10に係る発明は甲12発明と同一であるとする新規性の欠如、又は甲12発明を主引用発明とし、甲13発明に基づいてする進歩性の欠如)について(1) 甲12発明甲12によると、前記第2の3(3)アに記載の発明(甲12発明)が記載されている25 と認められる。 (2) 本件訂正発明1と甲12発明との対比19ア 上記(1)によると、本件訂正発明1と甲12発明との一致点及び相違点は、前記第2の3(3)イのとおりであると認められる。 イ 相違点の認定について原告は、本件訂正発明1(請求項1)に従属する本件訂正発明2(請求項2)が、 5 「前記剪断部は、傾斜方向が互いに異なる部分が交互に並ぶ波形を成すことを特徴とする請求項1記載の弾塑性履歴型ダンパ。」と特定されていることからすると、本件訂正発明1における「板状の一対の剪断部」には二対以上の剪断部を有する波形の構成も含まれると解するのが相当であり、甲12発明の「波形鋼板28」も本件訂正発明1に含まれるから、相違点A−1は生じないと主張する。 10 しかしながら、請求項2における「前記剪断部」の「前記」が指し示すものは、請求項1における「一対の剪断部」のうちの一つの「剪断部」をいうものと理解でき、 甲12発明は、そのような剪断部が互いの向きを異ならせて一対(二つ)配置された構成を備えるものとは認められないことから、相違点A−1の認定に誤りがあるとはいえない。 15 また、原告は、甲12の図23(C)に示された三角波の形状の波形鋼板を用いた波形耐震部材を甲12発明とすれば、甲12発明は左右方向に延びる端部と縦フランジ32A、32Bとが鋭角で交わる構成を有することとなるため、相違点A−2は生じないと主張する。 しかしながら、甲12の図23(C)は波形鋼板の端部の形状を示すものではなく、 20 波形耐震部材26に図23(C)の波形鋼板28を用いてもよい旨の記載(甲12の【0071】)があることをもって、当該波形鋼板28の端部とフランジとが鋭角で交わる構成が甲12に記載されているとまでは認められないから、原告の主張は採用できない。 ウ 相違点A−1に係る構成の容易想到性25 (ア) 甲13技術事項甲13によると、次の技術事項(以下「甲13技術事項」という。)が記載されて20いるものと認められる。 「建物10の上下の梁14、16に、これらの梁から下方及び上方へそれぞれ伸びる鉄筋コンクリート製の上下のブラケット18を介して取り付けられ、その上下両端部22、24の一方からその他方に向けて上下に伸びる複数の窪み26を有する金属5 製の板状体20からなる弾塑性ダンパ12において、 板状体20は、上端部22及びその下端部24においてそれぞれ両ブラケット18に埋め込まれており、 窪み26を有する板状体20は、矩形の平面形状を有する金属板にプレス加工を施すこと、すなわち前記金属板に折り曲げ加工を施すことにより形成することができ、 10 このような窪み26を設けることにより、板状体20に高い曲げ剛性を与えることができ、これにより、建物10に取り付けられた板状体20が地震動により水平方向への剪断力を受けて変形(剪断変形)するときの座屈及びこれに伴う急激な耐力低下の発生を効果的に防止することができ、 窪み26は少なくとも一つあればよく、また窪み26の数量は任意に定めることが15 できること。」(イ) 甲12発明への甲13技術事項の適用について甲13によると、鋼板の表面に縦リブを溶接する従来技術の課題(甲13の【0003】〜【0004】)を解決すべく、上下両端部の一方から他方に向けて上下に伸びる少なくとも一つの窪みを有する板状体を採用したものであり(同【0007】 、 )20 窪みを横切る横断面の形状が波形を呈するものとすることは一つの構成例であると認められる(同【0008】)。したがって、甲13技術事項が示す「窪み」を一つだけとすることは、周囲よりも凹んでいる部位を一つとする構成であり、一つの「窪み」と、その余の部分が面内方向を向いた平板状の部分となるものであって、相違点A−1に係る構成の開示があるとはいえず、甲12発明に甲13技術事項を適用する前提25 を欠く。 よって、甲12発明に甲13技術事項を適用することにより上記相違点A−1に係21る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。 (ウ) 原告の主張について原告は、甲13は、波形鋼板という以上波形が前提となるものであって、平板状の中に一つだけ小さな窪みが存在する構成を意味しないことは明らかであること、甲15 3には「窪み26は少なくとも1つあればよく」(甲13の【0020】)との記載があるとおり、設定する幅に合わせて波の数を調整してもよいことが示されていると解されると主張する。 しかしながら、上記(イ)のとおり、甲13には縦リブに代えて上下に伸びる窪みを採用した発明が記載されているのであり、窪みを横切る横断面の形状が波状を呈するも10 のとすることは一つの構成例にとどまるというべきであって、必ずしも波形が前提となるものではない。そして、「窪み26は少なくとも1つあればよく」(甲13の【0020】 との記載は、 ) その文言どおり窪みの数についての記載というべきであって、 技術常識を踏まえても、波形を前提としてその波の数を一つにしてもよいという記載であるとは認められないから、原告の主張は採用できない。 15 (3) 小括以上によると、相違点A−2に係る構成の容易想到性について判断するまでもなく、本件訂正発明1及び本件訂正発明1を引用する本件訂正発明2、7、8及び10は、甲12発明と同一ではなく、また、甲12発明と甲13技術事項に基づいて、 当業者が容易に発明をすることができたものではないから、原告の取消事由2は理20 由がない。 4 取消事由3(サポート要件違反)について(1) 検討特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明25 が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載22や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。 本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、発明が解決しようとする課題について、従来の剪断パネル型ダンパは、「剪断部を一つしか有しておらず、所定レベル5 以上の地震に対して、一方向からの水平力に対してしかダンパとして機能しない」(【0004】)こと、これに起因して、「橋軸方向の水平力に対してダンパとして機能するように剪断パネル型ダンパを設置した場合に、橋軸方向以外の方向からの水平力が加わると、剪断パネル型ダンパは、入力のあった水平力を十分に減衰させることが出来ない」(【0004】)ことや、「剪断パネル型ダンパの設置に際しては、想定さ10 れる入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要とされる」(【0005】)ことが記載されている。 これに対し、本件訂正発明1の弾塑性履歴型ダンパは、互いの向きを異ならせて設けられた板状の一対の剪断部を備えるものであり、本件明細書には、「二つの剪断部の向きを異ならせることで、一方向だけでなく複数の方向からの地震時の振動を吸収15 することが出来る」(【0014】)ことが記載されている。 そうすると、当業者は、本件明細書の記載から、本件訂正発明1が、剪断部を一つしか有していないことに起因する上記課題を解決できると認識できるものと認められる。 (2) 原告の主張について20 原告は、本件訂正発明1は、「入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行う」とのみ特定され、どの方向からの荷重にも対応し得るかのように機能的に特定しているが、本件審決は、本件訂正発明1が全ての方向からのエネルギー吸収を行うことができるものではないことを認識していながらサポート要件に違反しないと判断しており、この点において本件審決には誤りがあると主張する。 25 しかしながら、本件明細書の記載によっても、本件訂正発明1が全ての方向からの荷重に対して最大限のエネルギー吸収を行うことまで求めるものとは認められないか23ら、原告の主張は前提において誤っており、理由がない。 (3) 小括以上のとおり、本件訂正発明1及び本件訂正発明1を引用する本件訂正発明2、4、 5、7〜20につき、サポート要件に違反するとの原告の取消事由3は理由がない。 5 第5 結論以上のとおり、原告が主張する取消事由はいずれも理由がない。 よって、原告の請求には理由がないから本件請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部10裁判長裁判官本 多 知 成15裁判官遠 山 敦 士20裁判官天 野 研 司2524別紙1 本件訂正後の特許請求の範囲【請求項1】(A)建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって、 (B)一対の第一補強部と、 (C)前記一対の第一補強部を連結し、互いの向きを異ならせて設けられた板状の一対の剪断部と、 (K)前記一対の剪断部は、連結部を介して一連に設けられ、 (D)前記一対の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一対のプレートとを備え、 (E)前記剪断部は、前記第一補強部に対して傾斜を成し、 (F)前記第一補強部は、前記剪断部に、該第一補強部と該剪断部とのなす角が鋭角となるように形成され、 (G)前記剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とする(H)弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項2】前記剪断部は、傾斜方向が互いに異なる部分が交互に並ぶ波形を成すことを特徴とする請求項1記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項3】(削除)【請求項4】前記一対のプレートは、入力により互いに異なる方向に変位する第一構造物と第二構造物とにそれぞれ接合されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項5】前記剪断部は、平面状を成すことを特徴とする請求項1、2及び4の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項6】(削除)【請求項7】前記連結部は、前記剪断部と一体又は別体であることを特徴とする請求項1、2、4及び5の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項8】前記一対の剪断部の間隔は、前記連結部側から反対側の端部に向かって鋭角状に漸次広がるように形成されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項9】前記一対の剪断部の間隔は、前記連結部側から反対側の端部に向かって鈍角状に漸次広がるように形成されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項10】前記剪断部は、前記連結部と反対側の端部に前記第一補強部を有することを特徴とする請求項1、2、 4、5及び7−9の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項11】前記第一補強部は、前記剪断部に対して一連に設けられていることを特徴とする請求項10記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項12】前記第一補強部は、前記剪断部と一体又は別体であることを特徴とする請求項11記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項13】前記剪断部及び前記連結部は、前記プレートを介して、基盤上に固設されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7−12の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項14】25前記剪断部及び前記連結部は、前記プレートを介して、相対する基盤間に固設されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7−12の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項15】前記連結部は、第二補強部によって補強されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7−14の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項16】前記剪断部と前記連結部は、曲げ加工によって一連に形成されていることを特徴とする請求項1、2、 4、5及び7−15の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項17】前記剪断部と該剪断部を補強する前記第一及び/又は第二補強部は、曲げ加工によって一連に形成されることを特徴とする請求項10又は11に記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項18】前記剪断部には、孔部が形成されていることを特徴とする請求項1、2、4、5及び7−17の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項19】前記孔部は、前記剪断部の外周部に形成されていることを特徴とする請求項18記載の弾塑性履歴型ダンパ。 【請求項20】前記孔部は、前記剪断部の外周部の内側に形成されていることを特徴とする請求項18又は19記載の弾塑性履歴型ダンパ。 26別紙2本件明細書(本件訂正後)【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、 建築物や橋梁等において上部構造物と下部構造物との間に設置され、 常時や所定レベルまでの地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定レベル以上の地震に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能する弾塑性履歴型ダンパに関する。 【背景技術】【0002】下記特許文献1−3には、橋梁の支承構造に用いられる低降伏点鋼を用いた剪断パネル型ダンパが記載されている。 この剪断パネル型ダンパは、建築物や橋梁等において上部構造物と下部構造物との間において、下部構造物に固定設置され、 常時や所定レベルまでの地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定レベル以上の地震に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能する。具体的に、この剪断パネル型ダンパは、水平変位に対し剪断変形が生じるとき、剪断部の履歴減衰を利用して地震時の振動を低減させる。 【先行技術文献】【特許文献】【0003】【特許文献1】 特許第3755886号公報【特許文献2】 特許第4192225号公報【特許文献3】 特開2007−198002号公報【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら、何れの特許文献の剪断パネル型ダンパにおいても、剪断部を一つしか有しておらず、 所定レベル以上の地震に対して、 一方向からの水平力に対してしかダンパとして機能しない。 したがって、例えば、橋軸方向の水平力に対してダンパとして機能するように剪断パネル型ダンパを設置した場合に、橋軸方向以外の方向からの水平力が加わると、剪断パネル型ダンパは、入力のあった水平力を十分に減衰させることが出来ない。地震の際に何れの方向から所定レベル以上の水平力の入力があるのかは、予測困難である。 【0005】また、剪断パネル型ダンパの設置に際しては、 想定される入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要とされる。 【0006】本発明は、 所定レベル以上の地震の際に、複数の方向からの入力に対してダンパとして機能し得る弾塑性履歴型ダンパを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】【0007】本発明に係る弾塑性履歴型ダンパは、建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって、一対の第一補強部と、前記一対の第一補強部を連結し、互いの向きを異ならせて設けられた板状の一対の剪断部と、 前記一対の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一対のプレートとを備え、 前記一対の剪断部は、 連結部を介して一連に設けられ、前記剪断部は、前記第一補強部に対して傾斜を成し、 前記第一補強部は、前記剪断部に、該第一補強部と該剪断部とのなす角が鋭角となるように形成され、 前記剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行う。 例えば、前記剪断部は、平面状を成す。また、前記連結部は、前記剪断部と一体、別体の何れであっても良い。 【0008】27また、前記剪断部は、傾斜方向が互いに異なる部分が交互に並ぶ波形を成すようにしても良い。 更に、 前記一対のプレートは、入力により互いに異なる方向に変位する第一構造物と第二構造物とにそれぞれ接合されているようにしても良い。 【0009】連結部により一体化された一対の剪断部の形状は、前記一対の剪断部の間隔を前記連結部を鋭角又は鈍角として、前記連結部と反対側の端部に向かって漸次広がるようにした、略V字状としても良い。 【0010】前記剪断部は、前記連結部と反対側の端部に第一補強部を設けるようにしても良い。この場合、前記第一補強部は、前記剪断部に対して一連に設けられていても良く、更に前記剪断部と一体(例えば曲げ加工)又は別体(例えば溶接接合)であっても良い。 【0011】また、前記剪断部及び前記連結部は、基盤上に固設し、下部構造物に固定するようにしても良い。更に、基盤と相対してプレートを設け、 前記剪断部の先端部や前記第一補強部が上部構造物側のストッパに直接突き当たるのではなく、前記プレートの端面が上部構造物側のストッパに突き当たるようにしても良い。 【0012】更に、前記連結部は、第二補強部によって補強されていても良い。 【0013】更に、前記剪断部には、貫通した孔部を一つ又は複数形成することも出来る。一つ又は複数の孔部を設けることによって、低降伏点鋼を用いなくても、 通常の鋼材で同様な低降伏点を実現することが出来る。勿論、低降伏点鋼に前記孔部を形成して、降伏点や座屈点を調整するようにしても良い。また、衝撃によって、前記剪断部が剪断弾塑性変形した際に、剪断部にクラック等が発生することを防止出来、 更に、前記剪断部の前記基盤との接合部に形成したときには、溶接箇所を少なくすることも出来る。前記孔部は、前記剪断部の外周部や、その内側に、貫通孔やスリットによって形成することが出来る。 【発明の効果】【0014】本発明では、二つの剪断部が設けられているので、所定レベル以上の地震の際に、剪断部が直接又は間接に上部構造物のストッパに突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部が剪断弾塑性変形することにより減衰させることが出来る。また、二つの剪断部を連結部で連結してなるので、より大きな地震時の振動を吸収することが出来る。更に、二つの剪断部の向きを異ならせることで、一方向だけでなく複数の方向からの地震時の振動を吸収することが出来る。 【図面の簡単な説明】【0015】【図1】本発明を適用した弾塑性履歴型ダンパが用いられる橋梁を示す図であり、 (A)は橋軸方向の模式的な断面図、(B)は橋軸直角方向の斜視図である。 【図2】本発明を適用した弾塑性履歴型ダンパの斜視図である。 【図3】上記弾塑性履歴型ダンパに中心軸線方向から所定レベル以上の入力があったときの状態を示す図であり、(A)は入力方向を示す平面図であり、(B)は斜視図である。 【図4】上記弾塑性履歴型ダンパに中心軸線方向に対して斜めの方向から所定レベル以上の入力があったときの状態を示す図であり、(A)は入力方向を示す平面図であり、 (B)は斜視図である。 【図5】馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、 (A)は、 (B)の高さ方向中間部の横断面図であり、(B)は斜視図である。 【図6】U字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、 (A)は、 (B)の高さ方向中間部の横断面図であり、(B)は斜視図である。 【図7】連結部が鋭角のV字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、 (A)は、(B)の高さ方向中間部の横断面図であり、(B)は斜視図である。 【図8】連結部が鈍角のV字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、 (A)は、(B)の高さ方向中間部の横断面図であり、(B)は斜視図である。 【図9】剪断部の先端部に形成された補強部が円筒状に形成された例を示す図であり、 (A)は断面図、 (B)は斜視図である。 28【図10】剪断部の先端部に形成された補強部が十字状に形成された例を示す図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図11】(A)−(E)は、剪断部の先端部に形成された補強部の更なる変形例である。 【図12】直角の連結部を示す図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図13】連結部の外側に補強部を設けた図であり、 (A)は断面図、 (B)は斜視図である。 【図14】連結部の内側に補強部を設けた図であり、 (A)は断面図、 (B)は斜視図である。 【図15】剪断部の基端部を離間させ連結片で連結した図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図16】連結部を円筒状にした図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図17】連結部の外側に二つの補強片を設けた図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図18】矩形状を成す連結部を示す図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図19】剪断部の基端部を離間させ連結片で連結した図であり、 (A)は断面図、(B)は斜視図である。 【図20】馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図であり、 (A)は横断面図、 (B)は斜視図である。 【図21】Π 型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図であり、 (A)は横断面図、(B)は斜視図である。 【図22】連結部が鋭角のV字型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図であり、 (A)は、横断面図であり、(B)は斜視図である。 【図23】連結部を鈍角とし、更に、剪断部と補強部との成す角も鈍角とした弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、(A)は、断面図であり、(B)は斜視図である。 【図24】連結部を円筒状とし、剪断部の先端部にも円筒状の補強部を設けた弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、(A)は、断面図であり、(B)は斜視図である。 【図25】剪断部に貫通した凹字型の孔部を形成した例を示す図であり、 (A)は側面図、(B)は正面図である。 【図26】剪断部に貫通したスリット状の孔部を形成した例を示す図であり、 (A)は側面図、(B)は正面図である。 【図27】剪断部のコーナ部に貫通した孔部を形成した例を示す図であり、 (A)は側面図、(B)は正面図である。 【図28】剪断部の中央部に貫通した孔部を形成した例を示す図であり、 (A)は側面図、(B)は正面図である。 【図29】剪断部の全体に複数の貫通した孔部を形成した例を示す図であり、 (A)は側面図、(B)は正面図である。 【図30】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角のハ字型に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、 (A)は、横断面図であり、 (B)は斜視図である。 【図31】連結部を設けずに、二つの剪断部を鈍角のハ字型に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図32】連結部を設けずに、二つの剪断部をT字型に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図33】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図34】連結部を設けずに、二つの剪断部を馬蹄状に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図35】連結部を設けずに、二つの剪断部をU字状に配置するとともに、補強部によって剪断部の両端形状をT字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図36】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角又は鈍角のハ字型に配置するとともに、補強部によって各剪断部をクランク状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図37】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によって各剪断部をクランク状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 29【図38】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角又は鈍角のハ字型に配置するとともに、補強部によって各剪断部をコ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図39】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によって各剪断部をコ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。 【図40】一方の剪断部が第一のベースプレートと第一のプレート間に固設され、他方の剪断部が第二のベースプレートと第二のプレート間に固設された弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図であり、(A)は、一方の剪断部の長手方向が第一のベースプレートの長手方向と異なるように設けるとともに、他方の剪断部の長手方向が第二のベースプレートや第二のプレートの長手方向と異なるように設けた横断面図であり、(B)は、略一致するように設けた横断面図である。 【図41】第一のベースプレートと第二のベースプレートがベースプレートに固設され、第一のプレートと第二のプレートがプレートに固設された弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図であり、(A)は、一方の剪断部の長手方向が第一のベースプレートの長手方向と異なるように設けるとともに、他方の剪断部の長手方向が第二のベースプレートや第二のプレートの長手方向と異なるように設けた横断面図であり、(B)は、略一致するように設けた横断面図である。 【図42】弾塑性履歴型ダンパの設置例を示す図であり、(A)は、側面図であり、 (B)は斜視図である。 【発明を実施するための形態】【0016】以下、本発明に係る弾塑性履歴型ダンパについて図面を参照して説明する。なお、以下、弾塑性履歴型ダンパについて、以下の順に沿って説明する。 【0017】1.橋梁の説明2.弾塑性履歴型ダンパの説明3.弾塑性履歴型ダンパの変形例1の説明(馬蹄状)4.弾塑性履歴型ダンパの変形例2の説明(U字状)5.弾塑性履歴型ダンパの変形例3の説明(鋭角V字状)6.弾塑性履歴型ダンパの変形例4の説明(鈍角V字状)7.弾塑性履歴型ダンパの変形例5の説明(剪断部先端の補強部の変形例)8.弾塑性履歴型ダンパの変形例6の説明(連結部の変形例)9.弾塑性履歴型ダンパの具体的な構成例の説明10.剪断部に貫通した孔部及び/又はスリットを設けた変形例の説明11.弾塑性履歴型ダンパの変形例7の説明(連結部の省略)12.弾塑性履歴型ダンパの設置例の説明【0018】[1.橋梁の説明]図1(A)及び(B)に示すように、一般に、橋桁等の上部構造物1は、橋脚や橋台といった下部構造物2上に設置された支承装置3に支承されている。図1に示すように、支承装置3には、一般に、固定支承装置3aと可動支承装置3bとがあり、固定支承装置3aは、一般に、上部構造物1の回転変形に対応して鉛直荷重を支持しつつ、水平・鉛直方向の変位を拘束して制限する。可動支承装置3bは、 一般に、上部構造の回転変形と水平変位に対応している。ところで、新設橋梁では、橋脚等の下部構造物2の耐震性能が高められ、また、反力分散構造や免震構造の採用などが図られている。既設橋梁においても、下部構造物2の補強や支承取り替えや落橋防止システムの付加などの耐震補強工事が行われている。 【0019】例えば、耐震補強工事では、例えば下部構造物2の水平反力を分散するため、固定支承装置3aを、 積層ゴム支承や、支承板支承やローラ支承といった金属支承等の可動支承装置3bに交換する作業が行われる。しかし、固定支承装置3aを可動支承装置3bに交換したときには、上部構造物1の移動量が増大する等の問題が生じ、移動量を制限する必要がある。本発明に係る弾塑性履歴型ダンパ10は、 例えば、可動支承装置3bとの組で、建築物や橋梁等において、上部構造物1と下部構造物2との間に設置され、下部構造物2に対する上部構造物1の移動量を制限するようにしている。 30【0020】例えば、上部構造物1となる桁は、一対の主桁1a,1aと横桁1bとを有している。そして、既設橋梁において、固定支承装置3aの下部工耐力が不足している際には、主桁1a,1aの下部フランジ4と下部構造物2である橋脚との間に、それまで上部構造物1の鉛直荷重を支持するために設置されていた固定支承装置3aに替えて可動支承装置3bが設置される。この際、下部構造物2には、可動支承装置3bと組で弾塑性履歴型ダンパ10が設置される。主として橋軸方向の所定レベル以上の水平力に対して弾塑性履歴型ダンパ10を設置するときには、弾塑性履歴型ダンパ10を上部構造物1の横桁1bに設けられるストッパ16,16で囲むように下部構造物2に設置される。これにより、弾塑性履歴型ダンパ10は、大きな減衰性能により所定レベル以上の水平力を低減する他、 高い剛性によりゴム支承や免震支承のみの弾性支持に比べ水平変位を小さく抑えることが出来る。 これにより、弾塑性履歴型ダンパ10は、下部構造物2を縮小出来、また、下部工耐震補強の縮小が可能となる。また、水平変位が小さくなることで桁遊間を小さくすることが可能となり、伸縮装置などの形状も小型化出来る。 【0021】なお、詳細は後述するが、弾塑性履歴型ダンパ10は、必ずしも、可動支承装置3bとの組で用いる必要があるものではない。また、図1のような桁形式の橋梁だけでなく、アーチ橋、トラス橋などの特殊な構造を有する橋梁の端支点、ブレース材の端部や中間部等にも適用することが出来る。 【0022】[2.弾塑性履歴型ダンパの説明]図2に示すように、本発明が適用された弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11を連結部12で連結して全体が一連となるように形成されている。このような弾塑性履歴型ダンパ10には、 剪断部11,11に、一般構造用鋼材に比べ延性に富み、降伏点に対して上下限の規格値を有するため性能安定性に優れた構造用鋼材である低降伏点鋼を用いることが出来る。 また、弾塑性履歴型ダンパ10には、地震エネルギを塑性歪エネルギによって吸収させるものであるため、 地震時には確実に塑性化し、履歴挙動のバラツキが小さく、降伏点の許容範囲が狭い低降伏点鋼が好適である。 【0023】低降伏点鋼で形成される剪断部11,11は、例えば矩形板状を成し、平面状を成している。そして、 一端部は、平面板状の連結部12に溶接接合等で固定されている。なお、連結部12も、低降伏点鋼が用いることが可能である。また、剪断部11,11と連結部12とは、一連の低降伏点鋼板を曲げ加工で形成するようにしても良い。剪断部11,11の他端部は、剪断部11,11の端部を外側に広げるようにコーナ部を介して補強部13,13が曲げ加工によって形成されている。勿論、補強部13,13は、剪断部11,11に対して溶接接合でも良い。補強部13,13は、ここでは外側にほぼ90度折曲されているが、剪断部11,11に対して外側に広がっていれば、剪断部11,11と成す角が鋭角であっても鈍角であっても良い。このように、平面板状の連結部12と一体化された二つの剪断部11,11は、連結部12の側から補強部13,13側に向かって漸次広がり、略V字状を成し、ここでは、剪断部11,11の延長線の交点が鋭角となるように形成されている。なお、剪断部11及び連結部12に、低降伏点鋼を用いることに限定されるものではなく、一般構造用鋼材等を用いるようにしても良い。 【0024】一体化された剪断部11,11と連結部12は、下部構造物2との取付部の基盤となるベースプレート14に溶接接合等で固設される。このベースプレート14は、一体化された剪断部11,11と連結部12より大きな鋼板であり、矩形状を成す。そして、略V字状を成す一体化された剪断部11,11と連結部12は、ベースプレート14の幅方向中心線と剪断部11,11間の中心線とがほぼ一致する位置に固定される。また、このベースプレート14は、下部構造物2に対してアンカーボルト等で固定される。 【0025】更に、一体化された剪断部11,11と連結部12を挟んでベースプレート14の反対側にも、プレート15が設けられ、プレート15には、一体化された剪断部11,11と連結部12が溶接接合等で固定される。このプレート15は、上部構造物1側に位置するものであり、ベースプレート14と同様なものであっても、異なるものであっても良い。ここでは、ベースプレート14と同じものが用いられ31る。そして、プレート15には、一体化された剪断部11,11と連結部12が剪断部11,11間の中心線とプレート15の幅方向中心線とがほぼ一致する位置に固定される。このプレート15の短辺側端面、すなわち橋軸直角方向と平行な端面15a,15aは、上部構造物1のストッパと突き当たる部分となる。 【0026】一方、上部構造物1側は、図1(B)及び図2に示すように、上部構造物1の横桁1bにストッパ16,16が設けられている。ストッパ16,16は、橋軸方向に離間して設けられ、これらストッパ16,16の間に、下部構造物2に固定された弾塑性履歴型ダンパ10が配設される。弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11間の中心線を橋軸方向にして、下部構造物2にアンカーボルト等で固定される。かくして、弾塑性履歴型ダンパ10は、主として橋軸方向の所定レベル以上の水平力の入力があったとき、上部構造物1のストッパ16,16とプレート15の橋軸直角方向と平行な端面15a,15aとが突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部11, 11や連結部12が剪断塑性変形することにより減衰させる。 【0027】具体的に、図3(A)に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、橋軸方向の入力があったとき、図3(B)に示すように、連結部12のベースプレート14側の角近傍の剪断部11,11及び連結部12が塑性変形して振動を減衰させる。なお、連結部12のベースプレート14側の角近傍の剪断部11,11及び連結部12の変形の程度は、橋軸方向の入力の場合、入力の大きさによって異なることになる。 【0028】また、図4(A)に示すように、橋軸に対して斜めの方向から所定レベル以上の入力があったときには、図4(B)に示すように、入力のあった方向と近い剪断部11が大きく塑性変形し振動を減衰させる。なお、図4の例では、橋軸に対して10°傾いた方向から入力があった状態を示している。連結部12のベースプレート14側の角近傍の剪断部11, 11及び連結部12の変形の程度は、入力の角度や入力の大きさによって異なることになる。 【0029】以上のような弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11を有しているので、剪断部が一つの場合に比べ、より大きな振動を吸収することが出来る。また、剪断部11,11がV字状に開くように形成されているので、例えば、剪断部11,11間の中心線が橋軸方向となるように設置されたときにも、橋軸方向からの入力だけでなく、橋軸に対して斜めの方向からの振動も減衰させることが出来る。 【0030】更に、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11を有し、剪断部11,11間の中心線(橋軸方向)に対して斜めの方向からの振動も減衰させることが出来、剪断部が一つの場合に比べ、入力の許容範囲及び許容角度が広く、入力に対して尤度があるので、 弾塑性履歴型ダンパ10を橋梁に取り付ける際に、例えば、剪断部11,11間の中心線が橋軸方向に対してずれ及び/又は傾いていても、振動を減衰させることが出来る。したがって、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部が一つの場合に比べ、 据付誤差を吸収することが出来、施工性が良い。よって、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部が一つの場合に比べ、例えば、既設橋梁に後付けする場合や、斜角のついた桁や曲線桁や支点部に斜角の付いた桁等に用いる場合に有効である。 【0031】更に、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11を有しているので、剪断部が一つの場合に比べ、剪断部11の高さを低くすることが出来る。更に、剪断部11の高さを低くすることが出来るので、基部に生じる曲げモーメントを少なくすることが出来、ベースプレート14、プレート15及びアンカーボルト等に対する負荷を低減することが出来る。したがって、弾塑性履歴型ダンパ10は、ベースプレート14及びプレート15の厚さを薄くすることが出来、アンカーボルトの径を小さくすることが出来る。更に、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11の高さを低くすることが出来、ベースプレート14及びプレート15の厚さを薄くすることが出来るので、 剪断部が一つの場合に比べ、全高を低くすることが出来る。これにより、弾塑性履歴型ダンパ10は、上部構造物1や下部構造物2等の狭い隙間にも配置することが出来、狭隘部での作業性が良く、施工性が良い。更に、下部構造物2に例えばブラケット等を配置する場合も、下部構造物2の付近に設けることが出来る。 【0032】32なお、以上の例では、主として橋軸方向の振動を減衰させる弾塑性履歴型ダンパ10の設置例を説明したが、 弾塑性履歴型ダンパ10は、橋軸直角方向の振動を減衰させるためにも使用することが出来る。 この場合、 弾塑性履歴型ダンパ10は、 橋軸直角方向に上部構造物1に離間して設けられたストッパ16,16間に、剪断部11,11間の中心線が橋軸直角方向となるように設置される。これにより、弾塑性履歴型ダンパ10は、 橋軸直角方向の振動を減衰させることが出来る他に、 橋軸直角方向に対して斜めの方向の振動も減衰させることが出来る。更に、弾塑性履歴型ダンパ10の設置に際しては、想定される入力方向に対して高精度に弾塑性履歴型ダンパ10の剪断変形方向を合わせる設置角度に自由度を持たせることが出来る。 【0033】更に、弾塑性履歴型ダンパ10としては、ベースプレート14やプレート15を省略しても良い。ベースプレート14を省略したときには、 下部構造物2に一体化された剪断部11, 11と連結部12を固定するようにすれば良い。また、プレート15を省略したときには、剪断部11,11の先端部や補強部13,13が直接ストッパ16,16に突き当たるようにすれば良い。このようにすることで、弾塑性履歴型ダンパ10の部品点数の削減を図ることが出来る。 勿論、ベースプレート14やプレート15を用いた方が、性能の安定性が向上する点で好ましい。 【0034】[3.弾塑性履歴型ダンパの変形例1の説明(馬蹄状) ]図2−図4に示す例では、剪断部11,11と連結部12とがV字状を成す場合を説明したが、図5に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11と連結部12とが馬蹄状を成していても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、図5の例では、剪断部11,11の間隔が連結部12側に比し、連結部12とは反対側の端部の間隔の方が短くなるように形成されている。この場合、二つの剪断部11,11は、平面板状であっても良いし、曲面板状を成していても良い。また、この例では、一枚の低降伏点鋼板を曲げ加工して、馬蹄状に形成するようにしても良い。曲げ加工の場合には、剪断部11,11と連結部12とを溶接する必要がなくなり、生産効率の向上を図ることが出来る。また、連結部12は、ここでは、湾曲しているが、図2−図4のように平板状であっても良い。 【0035】[4.弾塑性履歴型ダンパの変形例2の説明(U字状) ]図6(A)及び(B)に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11と連結部12とがU字状を成していても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、図6(A)及び(B)の例では、 二つの剪断部11,11の間隔が一定となっており、連結部12が湾曲して形成されている。特に、U字状の場合には、 剪断部11,11が二つ設けられているので、 より大きな振動吸収することができる。 また、橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部11,11と連結部12とで減衰させることが出来る。 勿論、連結部12は平板状であっても良い。 このような図6 (A)及び(B)の例にあっても、 U字状の剪断部11,11と連結部12は、曲げ加工によって形成することが出来る。 [5.弾塑性履歴型ダンパの変形例3の説明(鋭角V字状) ]【0036】図7(A)及び(B)に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、全体を略V字状に形成し、剪断部11,11を連結する連結部12を鋭角としても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、剪断部11,11は、連結部12から先端部に向かって漸次広がるように形成される。このような図7の例にあっても、剪断部11,11と連結部12は、曲げ加工によって形成することが出来る。特に、剪断部11, 11を略V字状としたときには、 橋軸に対して斜めの方向からの入力を効果的に減衰させることが出来る。なお、この例では、連結部12が鋭角を成していれば、剪断部11,11は、平面でなく曲面であっても良い。 【0037】[6.弾塑性履歴型ダンパの変形例4の説明(鈍角V字状) ]図8(A)及び(B)に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、全体を略V字状に形成し、剪断部11,11を連結する連結部12を鈍角としても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、剪断部11,11は、連結部12から先端部に向かって漸次広がるように形成される。このような図8(A)及び(B) の例にあっても、剪断部11,11と連結部12は、 曲げ加工によって形成することが出来る。 特に、剪断部11,11を略V字状としたときには、橋軸に対して斜めの方向からの入力を効果的に減33衰させることが出来る。そして、連結部12の角度の設定によって、効果的に減衰出来る入力の方向を設定することが出来る。なお、この例では、連結部12が鈍角を成していれば、剪断部11,11は、 平面でなく曲面であっても良い。 【0038】[7.弾塑性履歴型ダンパの変形例5の説明(剪断部先端の補強部の変形例) ]ところで、図2−図4に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部の補強部13,13が略90度外側に開いた場合を説明したが、この補強部13,13は、図9(A)及び(B)に示すように、円筒状であっても良い。また、図10(A)及び(B)に示すように、補強部13,13は、 剪断部11,11の先端部とほぼ直角に交差する補強片13aで形成し、十字状としても良い。この場合、 補強片17,17は、剪断部11,11の先端部の相対する面のそれぞれに溶接接合される。 勿論、 前述の交差部は、必ずしも直角である必要はなく、剪断部が剪断変形する際に、剪断部の先端部が面外変形を来したり、座屈することを防止することが出来るように構成されていれば特に限定されるものではない。 【0039】更に、図11(A)に示すように、補強部13,13は、剪断部11,11の先端部に、剪断部11,11の厚さ方向の両側に張り出すように、補強部13,13を構成する平板状の補強板を溶接接合し、 先端形状がT字状を成すようにしても良い。また、図11(B)に示すように、補強部13,13は、 平板状の補強板を外側にのみ張り出すように溶接接合し、先端形状がL字状を成すようにしても良い。 なお、図11(B)の補強部13,13は、剪断部11,11の先端部を折り曲げて形成するようにしても良い。更に、図11(C)に示すように、剪断部11,11の先端部よりやや基端側に、補強部13, 13を構成する補強板を外側に張り出すように溶接接合するようにしても良い。 更に、図11(D)に示すように、補強部13,13は、外側に張り出すように形成される際、剪断部11,11と成す角が、図11(A)−(D)の直角の場合と異なり、鋭角となるようにしても良い。勿論、この例の変形例として、補強部13,13と剪断部11,11とが成す角を鈍角とすることもできる。更に、図11(E)に示すように、補強部13,13と剪断部11,11とが成す角を円弧面で構成するようにしても良い。 【0040】[8.弾塑性履歴型ダンパの変形例6の説明(連結部の変形例) ]図2−図4に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、 剪断部11,11を連結する連結部12が平板状に形成されているが、図12(A)及び(B)に示すように、連結部12を略直角に形成するようにしても良い。 すなわち、連結部12は、平板状に形成しても良いし、曲面で形成しても良いし、更に、 (A)図7及び(B)に示すように、鋭角を成すように形成しても良いし、図8(A)及び(B)に示すように、 鈍角を成すように形成しても良い。 【0041】更に、剪断部11,11を連結する連結部12にも、補強部17を形成するようにしても良い。図13(A) (B)及び に示す例では、連結部12の外側に補強部17となる補強片17aを形成している。 この場合、補強片17aは、剪断部11,11間の中心線の延長線上となるように形成すると良い。この補強片17aは、例えば、剪断部11,11で構成される連結部12に対して溶接接合等で固定される。この例において、剪断部11,11を連結する連結部12は、鋭角、直角、鈍角の何れであっても良い。また、図14(A)及び(B)に示すように、補強部17は、連結部12の内側に、二つの剪断部11,11の基端部に架け渡すように形成しても良い。すなわち、補強片17bは、二つの剪断部11,11の連結部12側に補強片17bを架け渡すように溶接接合される。 【0042】更に、図15(A)及び(B)に示すように、連結部12は、剪断部11,11の互いの基端部を離間させて、連結片12aで連結するようにしても良い。この場合、連結片12aは、各端部が各剪断部11,11の内側の面に溶接接合される。更に、連結部12は、図16(A)及び(B)に示すように、 円筒体12bで構成し、円筒体12bの外周面に、剪断部11,11の基端部を溶接接合するようにしても良い。更に、連結部12は、図17(A)及び(B)に示すように、一方の剪断部11の基端部と他方の剪断部11の基端部とが交差するように十字状に形成するようにしても良い。 この場合、例えば、 一方の剪断部11aの基端部に、他方の剪断部11bの基端部を溶接接合する。この際、一方の剪断部3411aの端面よりやや内側に他方の剪断部11bの基端部を溶接接合し、 ここを連結部12とする。そして、一方の剪断部11aの先端に形成され補強片12cと同じ長さの補強片12dを、 一方の剪断部11aに溶接接合して他方の剪断部11の延長線上に形成する。更に、図18(A)及び(B)に示すように、連結部12は、連結部12を平板状に形成し、また、互いの剪断部11,11が平行になるようにして、連結部12が矩形状を成すようにしても良い。すなわち、この場合、一体化された剪断部11,11と連結部12は、矩形状を成すことになる。更に、図19(A)及び(B)に示すように、剪断部11,11は、基端部を平板状の連結部12に離間させて、外側に開くように溶接接合しても良い。 この場合、連結部12に形成された剪断部11,11の基端部より外側が補強部17,17として機能する。 【0043】[9.弾塑性履歴型ダンパの具体的な構成例の説明]図20(A)及び(B)の例は、図5に示した馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパ10の剪断部11,11の先端部に、先端よりやや基端側に、外側に張り出すように平板状の補強板を形成し、補強部13,13としても良い(図11(B)参照)。図21(A)及び(B)の例は、平板状の連結部12に、剪断部11,11を略平行に形成し、剪断部11,11の基端部から先端部に亘って間隔を一定にしても良い。この際、剪断部11,11の先端部には、外側に張り出す補強部13,13を溶接接合によって形成しても良い。勿論、補強部13,13は、溶接ではなく、剪断部11,11の先端部を折り曲げて形成しても良い。また、連結部12は、剪断部11,11の基端部より外側にはみ出した部分が補強部17,17となる。なお、補強部13,13と剪断部11,11とが成す角は、直角だけでなく、鋭角でも鈍角でも良い。図22(A)及び(B)の例は、全体を略V字状に形成し、剪断部11,11を連結する連結部12を鋭角とし、剪断部11,11の先端部に、外側に張り出すように補強部13,13を形成している。ここでの補強部13,13は、溶接接合でも良いが、曲げ加工によって形成されている。 【0044】図23(A)及び(B)の例は、剪断部11,11が連結される連結部12を曲面で形成し、剪断部11,11が成す連結部12の角を鈍角にしている。更に、剪断部11,11の先端部の補強部13,13は、外側に、剪断部11,11に対して一連の弧状の曲面を成すように形成されている。更に、図24(A)及び(B)の例に示すように、本発明の弾塑性履歴型ダンパは、連結部12を円筒状に形成し(図16参照)、剪断部11,11が成す角が鈍角となるようにし、更に、剪断部11,11の先端部に円筒状の補強部13,13を形成するようにしても良い(図9参照) 。 【0045】[10.剪断部に貫通した孔及び/又はスリットを設けた変形例の説明]ここでは、剪断部11,11に貫通した孔部を設けた変形例を、図2−図4で示した弾塑性履歴型ダンパ10を例に説明する。一つ又は複数の孔部を設けたときには、低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で同様な低降伏点を実現することが出来る。勿論、低降伏点鋼に前記孔部を形成して、降伏点や座屈点を調整するようにしても良い。 【0046】図25(A)及び(B)の例では、二つの剪断部11,11に、剪断部11,11とベースプレート14との接合部及び/又は剪断部11とプレート15との接合部となる側縁部を切り欠いた孔部21が断続して複数形成されている。剪断部11,11は、ベースプレート14との接合部及び/又はプレート15との接合部に形成されることで、ベースプレート14との接合部及び/又はプレート15との溶接部分を減らすことが出来る。また、剪断部11,11は、複数の孔部21が形成されることによって、例えば剪断部11,11に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部21の形状は、凹字型、半円型等どの様な形状であっても良い。 また、孔部21の数や大きさは、用途に応じて適宜決定すればよい。また、孔部21は、剪断部11,11の連結部12及び/又は補強部13との境界の部分に形成するようにしても良い。 【0047】図26(A)及び(B)は、図25の変形例であり、剪断部11,11とベースプレート14との接合部及び/又は剪断部11とプレート15との接合部となる側縁部に、スリット状の孔部22を形成するようにしている。また、剪断部11,11は、連結部12及び補強部13との境界の部分にもスリット状の孔部22を形成することも出来る。 このような図26の例によっても、ベースプレート14と35の接合部及び/又はプレート15との溶接部分を減らすことが出来、また、剪断部11,11に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部22を設ける位置は、これら四カ所の内少なくとも一カ所に設けるようにすれば、 特に限定されるものではない。例えば、スリット状の孔部22は、縦二本でも良いし、横二本でも良い。また、各スリット状の孔部22は、長手方向の両側が円弧状を成していても良い。 【0048】図27(A)及び(B)も、図25及び図26の変形例であり、剪断部11,11とベースプレート14との接合部及び/又は剪断部11とプレート15との接合部の一部となるコーナ部に、スリット状の孔部23を形成するようにしている。このような図27の例によっても、 ベースプレート14との接合部及び/又はプレート15との溶接部分を減らすことが出来、また、剪断部11,11に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部23を設ける位置は、これら四カ所のうち少なくとも一カ所に設けるようにすれば、 特に限定されるものではない。例えば、上二個でも良いし、下二個であっても良いし、前面側二個でも良いし、背面側二個でも良い。また、孔部23の形状は、扇状に限定されるものではなく、例えば矩形状であっても良い。 【0049】図28(A)及び(B)は、剪断部11,11の略中央部に、貫通した孔部24を形成することも出来る。このような図28の例によっても、剪断部11,11に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部24の形状としては、円形の他、三角形、四角形、五角形等の多角形であっても良いし、十字状、×字状のスリットであっても良い。 【0050】図29(A)及び(B)は、剪断部11,11の全体に、貫通した孔部25を形成する。このような図29の例によっても、剪断部11,11に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。特に、剪断部11,11の全体に複数の孔部25を形成したときには、剪断変形に伴う座屈屈曲によるクロスクラックの発生を防止することが出来る。なお、孔部25のそれぞれの形状としては、円形の他、三角形、四角形、五角形等の多角形であっても良いし、十字状、 X字状等のスリットであっても良いし、これらの組み合わせであっても良い。 【0051】更に、図25や図26に示すように、剪断部11とベースプレート14との接合部及び/又は剪断部11とプレート15との接合部となる側縁部に、孔部21,22を設けた上で、更に、図28のような孔部24を中央部に設けても良いし、図29に示すように、剪断部11,11の全体に亘って複数の孔部25を設けるようにしても良い。 【0052】[11.弾塑性履歴型ダンパの変形例7の説明(連結部の省略) ]図2−図29に示した弾塑性履歴型ダンパ10は、 二つの剪断部11,11を連結部12で連結して全体が一連となるように形成されているが、図30〜図39に示すように、連結部12を省略して、剪断部11,11の基端部を離間させるようにしても良い。 【0053】具体的に、図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が二つ設けられており、二つの剪断部11,11の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状に漸次広がるように形成されている。すなわち、図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられている。更に、図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部及び基端部に、剪断部11,11の厚さ方向の両側に張り出すように、補強部13,13を構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部11,11の両端形状がT字状を成すように形成されている。更に、 図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11, 11が相対するベースプレート14とプレート15間に固設されている。 【0054】以上のような図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10であっても、 剪断部11,11が二つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図30に示す弾塑性履歴型ダンパ10では、 二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられているので、 橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部11,11で減衰させることが出来る。 36【0055】なお、図31に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11の間隔が基端部側から先端部側に向かって鈍角状に漸次広がるように形成しても良い。更に、図32に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が略直交してT字状を成すように形成しても良い。 【0056】更に、図33に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられることに限定されるものではなく、二つの剪断部11, 11の基端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。 【0057】また、図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が二つ設けられており、二つの剪断部11,11の間隔が基端部側に比して先端部側の方が狭くなるとともに、 先端部側が内側に湾曲して、剪断部11,11が馬蹄状を成すように形成されている。すなわち、図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられている。更に、図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部及び基端部に、剪断部11,11の厚さ方向の両側に張り出すように、補強部13,13を構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部11,11の両端形状がT字状を成すように形成されている。更に、図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が相対するベースプレート14とプレート15間に固設されている。 【0058】以上のような図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10であっても、 剪断部11,11が二つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図34に示す弾塑性履歴型ダンパ10では、 二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられているので、 橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部11,11で減衰させることが出来る。 【0059】なお、図35に示すように、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11の基端部側の平行で間隔が一定となっているとともに、先端部側が内側に湾曲して、剪断部11,11がU字状を成すように形成しても良い。 【0060】また、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が二つ設けられており、二つの剪断部11,11の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状又は鈍角状に漸次広がるように形成されている。すなわち、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられている。更に、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部に、外側にのみ張り出すように、補強部13b,13bを構成する平板状の補強板が溶接接合されて、 剪断部11,11の先端形状がL字状を成すように形成されている。更に、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の基端部に、内側にのみ張り出すように、補強部13c,13cを構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部11, 11の基端形状がL字状を成すように形成されている。更に、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が相対するベースプレート14とプレート15間に固設されている。 【0061】以上のような図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10であっても、 剪断部11,11が二つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図36に示す弾塑性履歴型ダンパ10では、 二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられているので、 橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部11,11で減衰させることが出来る。 【0062】なお、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられることに限定されるものではなく、図37に示すように、二つの剪断部11,11の基端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。 【0063】また、図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が二つ設けられており、二つの剪断部11,11の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状又は鈍角状に漸次広がるように形成されている。すなわち、図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異37ならせて設けられている。更に、図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部及び基端部に、外側にのみ張り出すように、補強部13,13を構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部11,11がコ字状を成すように形成されている。更に、図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が相対するベースプレート14とプレート15間に固設されている。 【0064】以上のような図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10であっても、 剪断部11,11が二つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。 また、図38に示す弾塑性履歴型ダンパ10では、 二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられているので、 橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部11,11で減衰させることが出来る。 【0065】なお、弾塑性履歴型ダンパ10は、二つの剪断部11,11が向きを異ならせて設けられることに限定されるものではなく、図39に示すように、二つの剪断部11,11の基端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。 【0066】なお、図30〜図39に示した弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11が同一のベースプレート14とプレート15間に固設されることに限定されるものではなく、例えば、図40(A)及び図40(B)に示すように、一方の剪断部11が相対する第一のベースプレート14bと第一のプレート15b間に固設され、他方の剪断部11が相対する第二のベースプレート14cと第二のプレート15c間に固設されるようにしても良い。 【0067】この際、図40(A)に示すように、一方の剪断部11の長手方向が第一のベースプレート14bや第一のプレート15bの長手方向と異なるように設けるとともに、他方の剪断部11の長手方向が第二のベースプレート14cや第二のプレート15cの長手方向と異なるように設けるようにしても良く、図40(B)に示すように、略一致するように設けるようにしても良い。 【0068】更に、図41(A)及び図41(B)に示すように、図40(A)及び図40(B)に示した弾塑性履歴型ダンパ10は、更に、第一のベースプレート14bと第二のベースプレート14cがベースプレート14に固設され、第一のプレート15bと第二のプレート15cがプレート15に固設されるようにしても良い。 【0069】更に、図30〜図41に示す弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11,11の先端部及び基端部がT字状やL字状を成すように形成されることに限定されるものではなく、例えば、図9(A)及び図9(B)、図10(A)及び図10(B)、図11(A)〜図11(E)に示すように、他の形状及び形成方法で形成するようにしても良い。 【0070】[12.弾塑性履歴型ダンパの設置例の説明]弾塑性履歴型ダンパ10は、図1及び図2に示した桁橋の他に、ビル鉄骨、橋梁、鉄道橋等にも用いることが出来る。例えば、図42(A)及び(B)に示すように、構造物のフレーム横梁や橋梁の横支材等51と、ブレース材53の一端が取り付けられ、 鉄骨構造の節点に集まる部材相互の接合に用いるガセットプレート52との間 (ダンパー配置箇所)に弾塑性履歴型ダンパ10を取り付けることが出来る。この場合、弾塑性履歴型ダンパ10は、剪断部11, 11の間の方向からの水平力を、剪断部11,11が剪断塑性変形することにより減衰させることが出来る。 【符号の説明】【0071】1 上部構造物、1a 主桁、1b 横桁、2 下部構造物、3 支承装置、3a 固定支承装置、3b 可動支承装置、4 下部フランジ4、10 弾塑性履歴型ダンパ、11(11a,11b) 剪断部、12 連結部、12a 連結片、12b 円筒体、12c 補強片、12d 補強片、13 補強部、13a 補強片、13b 補強部、13c 補強部、14 ベースプレート、15 プレート、15a 端面、16 ストッパ、17 補強部、17a 補強片、17b 補強片、21−25 孔部、 51 構造物のフレーム横梁や橋梁の横支材等、52 ガセットプレート、53 ブレース材38【図1】39【図2】【図3】 【図4】40【図5】 【図6】【図7】 【図8】41【図9】 【図10】【図11】【図12】 【図13】【図14】 【図15】42【図16】 【図17】【図18】 【図19】【図20】 【図21】43【図22】 【図23】【図24】44【図25】【図26】【図27】【図28】【図29】45【図30】 【図31】【図32】 【図33】【図34】 【図35】46【図36】 【図37】【図38】 【図39】【図40】 【図41】47【図42】48 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
|