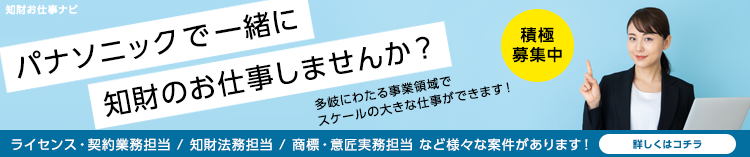| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(ネ)
10032号
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
|
|---|---|
|
令和7年2月27日判決言渡 令和6年(ネ)第10032号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第28332号) 口頭弁論終結日 令和6年11月20日 5判決 控訴人 株式会社DAPリアライ ズ 10 被控訴人 株式会社NTTドコモ 同訴訟代理人弁護士 大野聖二 同 小林英了 同訴訟代理人弁理士 松野知紘15 同補佐人弁理士 榊間城作 被控訴人補助参加人 シャープ株式会社 同訴訟代理人弁護士 生田哲郎20 同佐野辰巳 被控訴人補助参加人 大和管財株式会社 同訴訟代理人弁護士 田中成志25 同山田徹 同 澤井彬子 1 同 沖達也 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/02/27 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 5 事 実 及 び 理 由(注)本判決で用いる略語の定義は、別に本文中で定めるもののほか、次のとおりである。 原告 :控訴人(1審原告)被告 :被控訴人(1審被告)10 本件特許 :原告を特許権者とする特許第4555901号本件発明 :本件特許の特許請求の範囲・請求項1に係る発明本件明細書:本件特許に係る明細書及び図面(甲2)本件優先日:本件特許の原々出願(特願2005-367373号)の優先日(優先権主張番号:特願2004-372558号、優先権15 主張国:日本)である平成16年(2004年)12月24日被告各製品:原判決別紙「被告製品目録」記載の各製品丙B9文献:特開2001-197167号公報(丙B9)丙B9発明:丙B9文献に記載された発明第1 控訴の趣旨20 1 原判決を取り消す。 2 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和3年12月8日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパ25 ーソナルコンピュータシステム」とする本件特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、被2告による被告各製品の販売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法709条、損害額につき特許法102条3項)に基づき、損害額合計115億5700万円の一部である1000万円の損害賠償及びこれに対する令和3年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法5 所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原審が、本件発明は丙B9発明に技術常識を適用することにより容易に発明することができたものであるから、本件発明に係る本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し、原告は本件特許権を行使することができないとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。 10 1 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審における当事者の補足的主張を加えるほか、原判決の「事実及び理由」中、第2の2、3及び第3(原判決1頁26行目から55頁4行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原告は、丙B9発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如(争点 2-4-6)に係る主張について、当審における原15 告の補足的主張において変更した内容は、当審における主張を優先するとしている。)。なお、引用文中の「別紙」は「原判決別紙」と読み替える。 2 当審における当事者の補足的主張(丙B9発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如(争点 2-4-6)について)(原告の主張)20 ? 丙B9発明の認定について丙B9発明は、以下の理由から、本判決別紙「認定・主張対照表(控訴審)」の「原告の主張」欄記載のとおり認定されるべきである(同表の「原判決」欄中の太字部分は原告が原判決の認定に誤りがあると主張する部分であり、同表の「原告の主張」欄中の下線部は原判決の認定を変更すべき部分25 として原告が特定した部分である。)。 ア 丙B9文献(以下の【 】内の番号は、同文献の段落番号を示す。)に3は、「通信部12からCPU11に何らかの信号を送信する」こと(原判決認定の丙B9発明の構成6b)について、開示も示唆もされていない。 イ 構成6d1、6d2、6g’2については、丙B9文献において、「表示データ」という用語は、「表示すべき表示データのコンテンツ」、「表5 示データのコンテンツ」、「表示すべき表示データ」と記載されることが多いことから(【0004】~【0007】、【0011】、【0013】~【0017】)、「表示装置に表示されるコンテンツを含むデータ」という広い意味で使用されているのに対し、【0013】の「その表示データ(ドットデータ)をモニタ端子25へ同期信号と共に送出する。」との10 記載は、「モニタ端子25」へ送出する場合に限って「ドットデータ」という形式をとることを開示しているから、「表示データ」と「ドットデータ」は同義ではなく、「ドットデータ」が送信されるのは「モニタ端子25」のみである。 ウ 丙B9文献には、「ドットデータを画像メモリ22に記憶させること」15 (同6d2、6g’2、6h’)について、開示も示唆もされていない。 【0011】の「入力された表示データ」は、その前後の段落の記載からみて、「電話番号や各種の機能データ」(【0010】)や「登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」(【0013】)であり、これらはドットデータではなくテキストデータと解される。 20 エ 丙B9文献には、「通信部12が、画像情報を受信して復調」すること(同6g’1)について、開示も示唆もされていない。 【0015】の「外部から受信した情報量の多い表示データ」の記載が、 別の段落である【0013】における「外部から取り込んだ画像情報」を指していると解すべき理由はない。 25 ? 一致点及び相違点の認定についてア 前記?の原告の主張に従って丙B9発明を認定したときは、本件発明の4構成要件B、D、G’、H’、Jは、それぞれ、丙B9発明の構成6b、 6d1、6d2、6g’1、6g’2、6h’と相違するから、これらが一致すると認定することはできない。 イ また、丙B9文献には、「画像情報」について記載されている【0015 3】には「画像情報」の「本来解像度」についての記載が一切なく、「画像」の「解像度(画素数)」や、「簡易型液晶表示パネル23」「CRT表示器24」等の「表示装置」の「解像度(画素数)」について一切記載がないから、丙B9発明の「大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作する10 ことなく)表示」できるようにしたもの(6h’、6j)が、本件発明の「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」(H’、J)であると解すべき理由はない。このことは、本件特許に係る別件審決取消訴訟における知財高裁判決(令和3年(行ケ)第10139号、甲17)の判示からも明らかであり、同知財高裁判決が、「簡易型液15 晶表示パネル23では明瞭に表示できない表示データ」が「本来解像度が前記ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」と一致するとは解釈していないにもかかわらず、この点が一致すると判断することは誤りである。 ウ 【0013】記載の「外部から取り込んだ(画像情報)」が【0003】20 記載の「ウェブサイトから特定の画面を取り込んで」に当たるとしても、 【0013】記載の画像情報はHTMLデータであって「画像データ」ではないし、仮に「画像データ」を含むとしても、当該「画像データ」は、 本件発明の「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」(G’)ではない。 25 エ 以上より、本件発明と丙B9発明を対比すると、相違点は以下のとおりとなる(< >内のアルファベットは、該当する本件発明の構成要件を示5す。)。 【相違点①】本件発明では、無線通信手段が、「<B>無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信」しており、当該無線信号5 は、「<G’>『本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ』を伝達する無線信号」であり、中央演算回路が、 「<D>前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い」、「<G’>該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理」するのに対して、丙B9発明では、通信部1210 (無線通信手段)は、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信しておらず、CPU11(中央演算回路)にデジタル信号を送信しておらず、CPU11(中央演算回路)は、通信部12(無線通信手段)からデジタル信号を受信しておらず、したがって、当然、「通信部12(無線通信手段)15 から受信したデジタル信号が伝達する画像データ」の処理を行っていないこと【相違点②】本件発明では、グラフィックコントローラが、「<D><G’>単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、 20 『該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号』を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信」する機能(以下「本件基本G機能」という。)を有し、特に、「<H’>前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAMから『前記25 ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ』を読み出し、『該読み出したビットマップデータを伝達す6るデジタル表示信号』を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能(以下「本件付加G機能?」という。)と、 前記単一のVRAMから『前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ』を読み出し、『該読み5 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号』を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能(以下「本件付加G機能?」という。)と、を実現」するのに対して、丙B9発明では、表示制御回路21(グラフィックコントローラ)は、ドットデータ(ビットマップデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレ10 イに接続されたモニタ端子25に送信するものの、画像メモリ22(単一のVRAM)に対してドットデータ(ビットマップデータ)の書き込み/読み出しを行うものではないこと【相違点③】本件発明では、「<J>前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディス15 プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした」のに対して、丙B9発明では、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、「簡易型液晶表示パネル23の画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示することができるようにしたものではないこと20 ? 相違点の容易想到性以下のとおり、少なくとも、相違点①及び相違点②に係る構成は、容易想到とはいえない。 ア 相違点①について携帯情報通信装置において、「無線通信手段が画像データを伝達する25 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が7伝達する画像データを処理すること」までは周知技術であるとしても、 「無線通信手段が『本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ』を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル5 信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理すること」は、本件特許の優先日当時の周知技術ではない。 したがって、相違点①に係る本件発明の構成は、容易想到とはいえない。 イ 相違点②について10 携帯情報通信装置において、「グラフィックコントローラが、本件基本G機能を有すること」までは周知技術であるとしても、「グラフィックコントローラが、本件付加G機能?と本件付加G機能?を有すること」は、 本件特許の優先日当時の周知技術ではない。 ましてや、携帯情報通信装置が、「高解像度画像受信・処理・表示機能」15 (構成要件G’)を有した上で、「携帯情報通信装置が、前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、グラフィックコントローラが、 本件付加G機能?と本件付加G機能?を実現すること」は、本件優先日当時の周知技術ではない。 したがって、相違点②に係る本件発明の構成は、容易想到とはいえない。 20 ウ 原判決認定の相違点6’について仮に、原判決の相違点6’の認定(本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信する機能を有するのに対し、丙B9発明は、そのような機能を有するとはいえないこと)25 を前提としても、以下のとおり、相違点6’に係る本件発明の構成は、容易想到とはいえない。 8(ア) 丙B9文献には、【0003】、【0014】を含め、①「画像」の「解像度(画素数)」や「表示装置」の「解像度(画素数)」について一切記載がなく、②画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合に、 簡易型液晶表示パネル23においてスクロール操作で全画面を見る必要5 があることについて記載がなく、③携帯電話機の簡易型液晶表示パネルと同じ解像度の表示データを生成することについては開示も示唆もされていない。 したがって、丙B9文献に基づいて、原判決認定の「携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネルの解像度より大きい表示データを10 表示する場合に、大きい表示データから上記表示パネルと同じ解像度の表示データを生成して前記簡易型液晶表示パネルに表示し、スクロール操作を行うことで全画像を見ることができること」(原判決76頁13行目から17行目まで)が技術常識であったと認定することはできない。 (イ) 仮に前記の技術常識が認められるとしても、相違点6’に係る本件発15 明の構成は「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出す」ことであり、前記の技術常識とは文言上明らかに異なる。 また、前記の技術常識における「表示データ」は、「画像データ」が含まれることまでは認められるとしても、「ビットマップデータ」は20 「画像データ」の一般的な総称ではないのであるから、「表示パネルと同じ解像度の表示データを生成する」ことと、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出す」ことは明らかに異なる。 (ウ) さらに、相違点6’には、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実25 現する場合に」との限定がある。本件発明における「高解像度画像受信・処理・表示機能」は、①無線通信手段が画像データを伝達する無線信9号を受信すること、②無線通信手段がこの無線信号をデジタル信号に変換の上、中央演算回路に送信し、中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理すること、③グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のV5 RAMに対して書き込んだビットマップデータであることを含むところ(構成要件G’)、前記?のとおり、これらの構成は、丙B9文献に開示も示唆もされていない。 (被告の反論)? 丙B9発明の認定について10 ア 「通信部12からCPU11に何らかの信号を送信する」構成については、丙B9文献の「通信部12は、アンテナ12aを有し、送信信号の変調および受信信号の復調機能を有する。」(【0008】)及び【図1】の記載に加え、通信部において受信した無線信号をデジタル信号に変換してCPUに送信すること及びCPUから受信したデジタル信号を無線信号15 に変換して通信部に送信することが出願時の技術常識であったこと(乙3、 4、9、丙B11、13、14)から、丙B9文献に実質的に開示されていることは明らかである。 イ 「ドットデータを画像メモリ22に記憶させること」の構成(同6d2、 6g’2、6h’)については、画像メモリには、画像データが記憶され20 ることは字義から明白であり、丙B9文献の「外部から受信した情報量の多い表示データ」(【0015】)も、当然に画像メモリ22に記憶される。また、【0013】には、「表示データ(ドットデータ)」と記載があるところ、これが特定の場面(モニタ端子25へ送出する場合)に限定されると理解すべき合理的な理由はない。 25 ウ その他、原判決の丙B9発明の認定に誤りはない。 ? 相違点の認定について10丙B9文献(【0004】、【0011】、【0014】)には、「表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に表示データのすべてを欠落なく表示できない(表示データ5 のすべてを欠落なく表示できない、またはスクロール操作によらなければ全画像を見られない)ように表示する機能」という構成が明確に開示されているから、原判決認定の相違点6’は存在しない。 その余の相違点が存在しないことは、原判決が認定するとおりである。 ? 相違点の容易想到性の判断について10 「CPU11と相互に信号の送受信を行う通信部12」が丙B9文献に明示的に開示されていない点が相違点を構成するとしても、当該構成は技術常識であり(乙3、4、9、丙B11、13、14)、通信部12を備えた丙B9発明に対して当該技術常識を適用することは、当業者において極めて容易に想到できたものである。 15 また、本件特許の優先日当時、携帯通話端末において、受信した画像データをCPUが処理してディスプレイに画像表示を行うことは、丙B47、乙30から33まで、あるいは丙B17、48、50に記載されている技術常識である。 第3 当裁判所の判断20 1 当裁判所も、本件発明に係る本件特許は、丙B9発明に基づく進歩性欠如の無効事由を有するものと判断する。 その理由は、以下のとおりである。 2 本件明細書の記載事項本件明細書の記載の内容は、原判決「事実及び理由」第4の1?(55頁825 行目から67頁8行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。 3 丙B9文献の記載事項及び丙B9発明11? 丙B9文献の記載の内容は、原判決「事実及び理由」第4の1?ア(67頁10行目から71頁9行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。 ? 丙B9文献の上記各記載によれば、丙B9文献には、本判決別紙「認定・5 主張対照表(控訴審)」の「当裁判所の判断」欄のとおりの丙B9発明の記載があると認められる(原判決の認定から変更した部分に下線を、原告の主張を採用しない部分に二重下線を付した。)。 このうち、争いのある部分に係る認定の理由は、以下のとおりである。 ア 構成6b10 「通信部12からCPU11に何らかの信号を送信する」構成について、 被告は、丙B9文献(【0008】、【図1】)及び本件優先日の技術常識に照らし、実質的に開示されていると主張し、原告はこの点を争っている。 しかし、仮に被告主張の技術常識があったとしても、丙B9文献には、 15 被告指摘の上記箇所を含め、「通信部12からCPU11に何らかの信号を送信する」ことの記載はないから、構成6bの当該部分は「CPU11に制御される通信部12」の限度で認められるというべきである(通信部12からCPU11に対する送信に関し、構成6g’1中の当該部分についても同様である。)。 20 イ 「表示データ(ドットデータ)」の送信先等(構成6d1、6d2、6g’1、6g’2)原告は、丙B9文献の記載において、「表示データ」と「ドットデータ」は同義ではなく、「ドットデータ」が送信されるのは「モニタ端子25」のみである旨主張する。 25 しかし、まず、【0011】には「また、表示制御回路21は、CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させると12ともに、該画像メモリ22に記憶させた表示データを電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23に表示させる。また、本実施形態では、特に、表示制御回路21が、前記表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23に対応する場合、または、表示データの送出先が簡5 易液晶表示パネル23を指示する場合には、該簡易型液晶表示パネル23に表示データを送らせ、一方、表示すべき表示データのコンテンツがモニタ端子25に接続されたCRT表示器24に対応する場合、または、表示データの送出先がCRT表示器24を指示する場合には、モニタ端子25へ表示データを送らせるようにしている。」との記載がある。同記載によ10 れば、表示制御回路21は、CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、該画像メモリ22に記憶させた表示データを、モニタ端子25へ送らせるようにしているのであるから、 モニタ端子25に送信される表示データは、画像メモリ22に記憶させた表示データであることは明らかである。 15 次に、【0013】には「表示データ(ドットデータ)」をモニタ端子25へ送出することが記載されている。 丙B9文献のこれらの記載に接した当業者は、モニタ端子25に送信される表示データ(ドットデータ)は画像メモリ22に記憶させた「表示データ」であり、簡易型液晶表示パネル23及びモニタ端子25を経由して20 CRT表示器24に送信される「表示データ」であると理解すると認められる。 ウ 「画像メモリ22に記憶させた表示データ」の内容について(構成6d2、6g’2、6h’)(ア) 原告は、【0011】の「入力された表示データ」は、その前後の段25 落の記載から、「電話番号や各種の機能データ」(【0010】)や「登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」13(【0013】)であり、これらはドットデータではなくテキストデータと解されるから、「画像メモリ22に記憶させた表示データ」はドットデータではない旨主張する。 (イ) しかし、そもそも、電話番号や氏名、メッセージなどのデータであっ5 ても、「画像メモリ22」に記憶されるのは画像データであると解するのが自然である。 前記イのとおり、丙B9文献において、「画像メモリ22」に記憶されるデータは、簡易型液晶表示パネル23及びモニタ端子25を経由してCRT表示器24に送信される「表示データ」である。同文献【0010 13】によれば、RAM13に記録されている電話番号、氏名又はメッセージは、通話前に読み出され、表示制御回路21に出力される。表示制御回路21は、これらのデータを一旦画像メモリ22に記憶させた上、 簡易型液晶表示パネル23に表示させるものとされている。そして、 「表示データ」のうち、「電話番号や簡単なメッセージなどのように表15 示すべき情報量が少なく、全てを同時に表示できる場合」には、簡易型液晶表示パネル23に表示データを送って表示させるが、「外部から取り込んだ画像情報などのように一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない表示データ」については、 画面表示領域の大きいCRT表示器24に表示することができるように、 20 その表示データをモニタ端子25へ送出することとされ、続く【0014】では、「従って、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合」には、CRT表示器24を使うことで必要とする表示データのすべてを欠落なく表示することができるとされている。これらの点に照らすと、 簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24のいずれに表示する場25 合も、画像メモリ22に記録された「画像を形成する画面上の表示データ」の型式は画像データであり、「画像メモリ22」に記憶される電話14番号や氏名、メッセージなどのデータも、テキストファイルではなく、 画像データ(ドットデータ)であることが前提になっているものと解される。 (ウ) 加えて、例えば、本件優先日前に公開された、携帯情報処理装置等に5 関する発明に係る特開2000-66649号公報(乙2)には、以下の記載(この項においてのみ、【 】内の番号は同文献の段落番号を示す。)がある(下線は当裁判所が付した。)。このような先行公知文献の記載からみても、当業者は、VRAMのような表示(画像)メモリには、画面の画像データ(ビットマップデータ、ドットデータ)が記憶さ10 れるのであり、丙B9文献においても、入力された電話番号や登録してある電話番号、氏名、あるいはメッセージなどのテキストデータもまた、 画像データに変換されて画像メモリ22に記憶されると理解するものと認められる。 ① 本実施形態における携帯機器2は、CPU10、システムメモリ15 (DRAM)12、ROM14、入力装置16、表示メモリ(VRAM)18、表示コントローラ20、及び内部表示装置22を有して構成されている。また、携帯機器2は、表示コントローラ20を介して、 外部表示装置24(図1中に示す外部表示デバイス4)を接続して表示させることができる(【0012】)。 20 ② 表示メモリ18は、内部表示装置22及び外部表示24において表示させる表示データの記憶領域として使用される。…(【0015】)③ アプリケーションプログラム35は、内部表示装置22と外部表示装置24において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージと外部表示イメージの2種類を、それぞれの表示装置の解像度に合わせ25 て、表示メモリ18上にライトする(【0037】)。 ④ 表示コントローラ20は、アプリケーションプログラム35によっ15てライトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示装置22と外部表示装置24に対して、それぞれに応じた描画イメージを表示させる【0038】。 ⑤ なお、同文献の【図2】、【図3】には、符号18が「表示メモリ5 (VRAM)」あるいは「VRAM」に付されている。 エ 構成6g’1原告は、丙B9文献には、「通信部12が、画像情報を受信して復調」することについて、開示も示唆もされていない旨主張する。 しかし、丙B9文献の「携帯電話機本体のメモリからまたはウェブサイ10 トから特定の画面を取り込んで、使用目的のテキストや画像に重ねて表示する機能」(【0003】)との記載において、「取り込む」という用語は、携帯電話機本体のメモリからの「読出」及びウェブサイトからの「受信」 の両者に対して用いられていること、【図1】には、外部から画像情報を受信あるいは取り込む構成として、アンテナ12aを有する「通信15 部12」のみが記載されていることからすると、「外部から取り込んだ画像情報」(【0013】)は、「外部から受信した画像情報」という意味であると解される。 そして、通信部12が受信信号の復調機能を有することについては、 【0008】に「通信部12は、アンテナ12aを有し、送信信号の変調20 および受信信号の復調機能を有する」と記載されている。 したがって、丙B9文献のこれらの記載に接した当業者は、「通信部12が、画像情報を受信して復調する」ものであることを理解することができると認められる。 4 一致点及び相違点について25 ? 一致点ア 本件発明と丙B9発明を対比すると、本件発明の構成要件A、C、E、 16F、I、J及びKと丙B9発明の構成6a、6c、6e、6f、6i、6j及び6kは、一致すると認められる。 イ このうち、原告は、本件発明の構成要件Jと丙B9発明の構成6jは一致しておらず、次の【相違点③】があると主張する。 5 「 本件発明では、「<J>前記外部ディスプレイ手段に、『前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像』を表示できるようにした」のに対して、丙B9発明では、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、『簡易型液晶表示パネル23の画面解像度より大きい解像度を有する画像』を表示できるようにしたものではないこと」10 原告の主張は、丙B9発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、本件発明の「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」と同一ではないと解することを前提としている。しかし、構成6jの「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、丙B9文献の【0013】、【0014】の15 記載によれば、「画像を形成する画面上の表示データ量が多い」ため簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示することができないが、「CRT表示器24等の大型ディスプレイ」であればすべてを欠落なく表示することができ、全画像を表示するためスクロール操作の必要がなくなるものである。本件発明の「画面解像度」とは、本件明細書の記載(【0032】、 20 【0112】、【0117】等)に照らし、「水平画素数×垂直画素数(画素数)」を意味すると解されるところ、一般に、ディスプレイの画面解像度が低い場合には、当該画面解像度を超える画素数を有する表示データのすべてを一画面で表示することができず、当該表示データに係る全画像を表示するためにはスクロール等の操作が必要になることを踏まえると、 25 丙B9文献における「画像を形成する画面上の表示データ量が多い」ため「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」とは、画17像の解像度が「簡易型液晶表示パネル23の画面解像度より大きい」画像情報と同趣旨であると解される。 なお、原告は、丙B9文献には「画像情報」の「本来解像度」についての記載が一切ないとも主張するが、本件明細書の段落【0032】によれ5 ば、本件発明の「本来解像度」とは、「本来画像」の解像度であり、「十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段」等により適切に表示される、外部から受信する等した画像データ自体の解像度(画素数)という程度の意味であると解されるから、本来解像度自体は「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度」の場合もあるし、そうでない場合も10 あるというだけである。 以上によれば、丙B9発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、「簡易型液晶表示パネル23」(本件発明における前記ディスプレイに相当する。)の画面解像度より大きい解像度を有する画像と同じ意味と解されるから、原告主張の相違点③は認められず、 15 本件発明の構成要件Jと丙B9発明の構成6jは一致すると認められる。 これに反する原告の主張は、いずれも採用することができない。 ? 相違点についてア 以上を踏まえ、本件発明と丙B9発明を対比すると、次の点で相違すると認められる。 20 【相違点6BDG’】本件発明では、無線通信手段が、無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理する(前記中央演算回路が前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行う)25 (構成要件B、D、G’)のに対し、 丙B9発明では、通信部12(無線通信手段) は、CPU11(中央18演算回路)に復調した信号(デジタル信号)を送信し、前記CPU11(中央演算回路)が該復調した信号(デジタル信号)を受信して、該復調した信号(デジタル信号)が伝達する画像データを処理しているか明らかではないこと。 5 【相違点6’】本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能(構成要件G’参照)を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信する機能を有する(構成要件H’)のに対し、 10 丙B9発明は、そのような機能を有するか明らかでないこと。 イ これに対し、原告は、相違点①、相違点②(前記第2の2(原告の主張)?エ)が存在すると主張する。 ウ しかし、原告主張の相違点①については、丙B9発明において、「通信部12が、画像情報を受信して復調」していると認められることは前記315 ?エのとおりであり、また、本来解像度が大きく構成6g’1の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」であるときは、それが「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」の画像情報に当たることは、前記?イと同様である。 したがって、丙B9発明では、通信部12(無線通信手段)は、「本来20 解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信する構成を有していると認められ、これに反する原告の主張は、採用することができない。 他方、丙B9発明が、CPU11(中央演算回路)にデジタル信号を送信する構成を有しているかどうか明らかでないことは前記3?アのとおり25 であるから、原告が主張する相違点①については、前記の相違点6BDG’の限度で認められることになる。 19エ 原告主張の相違点②については、丙B9発明は、本判決別紙「認定・主張対照表(控訴審)」の「当裁判所の判断」欄及び前記3?イ、ウで認定したとおり、表示制御回路21(グラフィックコントローラ)が画像メモリ22(単一のVRAM)に対して表示データ(ドットデータ)の書き込5 み/読み出しを行い(構成6d2、6g’2)、読み出した表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23(ディスプレイ制御手段)又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25(インターフェース手段)に送信し(構成6d2、6g’2)、携帯電話機が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示することができない画像10 情報を表示する機能(高解像度画像受信・処理・表示機能)を実現する場合に、表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する機能(原告主張の「本件付加G機能?」)を有する(構成6h’)ものであるから、これに反する原告の主張は理由がない。 15 なお、原告の主張する相違点②の内容に照らしても、「表示データ(ドットデータ)」は「ビットマップデータ」と異なるものではないと認められる。 そうすると、原告が主張する相違点②は、前記の相違点6’の限度で認められることになる。 20 オ 被告は、相違点6’は存在しない旨主張するが、被告の指摘する丙B9文献の記載(【0004】、【0011】、【0014】)を考慮しても、 丙B9文献に相違点6’に係る構成が開示されているとまでは認められない。 5 相違点の容易想到性について25 ? 相違点6BDG’についてア 被告は、相違点6BDG’に係る構成は、本件優先日当時の技術常識で20ある旨主張する。 そこで検討するに、いずれも本件優先日前に頒布された刊行物である被告指摘の各文献には、例えば次の記載があると認められる。 (ア) 特開2002-95056号公報(乙30、発明の名称:携帯情報端5 末機および携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム)には、 施設内画像情報提供サイトS1から送信されてきた店舗内の画像情報をアンテナ20及び送受信回路21によって受信した携帯電話機10は、 この画像情報をデータ処理回路22において復調してその画像信号をCPU30に入力させ、CPU30において、入力された復調された画像10 信号に対して圧縮解凍等の必要な処理が行われた後、LCDドライバ31に出力され、ディスプレイパネル12に表示させる旨の記載がある(【0106】、【0108】、【図3】)。 (イ) 特開2003-319043号公報(乙31、発明の名称:折り畳み型携帯電話機)には、携帯電話機10において、発呼先から送信されて15 きた画像データは、RF回路105を介して、変復調回路106に供給され復調されて、ベースバンド処理回路107に供給され、ベースバンド処理回路107は、供給された信号から、キャラクタデータなどの送信されてきたデータを取り出して、これを制御部109に供給し、CPUを含んで構成される画像処理回路115が、ベースバンド処理回路120 07から供給されるデータに基づいて、画像信号を形成し、表示部11に表示する旨の記載がある(【0073】~【0076】、【図5】)。 (ウ) 特開2003-244301号公報(乙32、発明の名称:携帯情報端末)には、携帯電話機において、アンテナ19から入力された通話先から送られたテレビ電話の画像データは、受話回路21を介してCPU25 を含む制御回路17に入力され(受話回路21は受信したアナログデータの復調処理を行い、その後、制御回路17に復調したデータを入力21し)、制御回路17に入力された画像データは、メモリ23をワークエリアとして利用し、画像データを表示可能なように展開し、展開が終了すると、制御回路17は展開された画像データの保存領域を示すアドレスを表示制御部20に送り、表示制御部20は事前設定でさだめられた5 条件で、固定表示部4、可動表示部12の一方又は双方に画像を表示する旨の記載がある(【0016】、【0038】、【0048】、【0049】、【図7】)。 イ 前記ア(ア)から(ウ)までの刊行物の記載から、携帯情報通信装置の無線通信手段が、画像データを伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換10 の上、中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理することは、本件優先日当時の当業者の技術常識であったと認められる。 そうすると、丙B9発明においても、このような技術常識に沿った画像処理をしているのであれば、そもそも相違点6BDG’は実質的な相違点15 ではないし、仮に相違点があるとしても、丙B9発明に、この技術常識を適用することに何ら阻害事由は認められないから、当業者において当該技術常識を適用することにより、相違点6BDG’に係る本件発明の構成を想到することは容易であったと認められる。 ? 相違点6’について20 ア 当業者において、丙B9発明に技術常識(「携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネルの解像度より大きい表示データ(ドットデータ)を表示する場合に、大きい表示データ(ドットデータ)から上記表示パネルと同じ解像度の表示データ(ドットデータ)を生成して前記簡易型液晶表示パネルに表示し、スクロール操作を行うことで全画像を見ることがで25 きること」。以下「本件技術常識」という。)を適用することにより相違点6’に係る本件発明の構成を想到することは容易であったと認められる22ことは、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第4の1?イ(ア)(76頁3行目から77頁5行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正)5 前記3?イ、ウのとおり、構成6h’において画像メモリ22に記憶され、送信されるのは「表示データ(ドットデータ)」であり、丙B9文献【0014】及び同記載から認められる技術常識の「表示データ」も同様と認められるから、原判決76頁14、15、23、24行目の各「表示データ」をいずれも「表示データ(ドットデータ)」に改める。 10 イ 原告は、相違点6’に係る本件発明の構成は容易想到とはいえない旨主張するが、以下のとおり、いずれも採用することができない。 (ア) 原告は、丙B9文献には、①「画像」の「解像度(画素数)」や「表示装置」の「解像度(画素数)」について一切記載がないこと、②画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合に、簡易型液晶表示パネル15 23においてスクロール操作で全画面を見る必要があることについて記載がないこと、③携帯電話機の簡易型液晶表示パネルと同じ解像度の表示データを生成することについて開示も示唆もないことから、本件技術常識は認められない旨主張する。 しかし、①の点については、丙B9文献に「画像」の「解像度(画素20 数)」や「表示装置」の「解像度(画素数)」の文言の記載がなくとも、 丙B9文献に「当該表示パネルの解像度より大きい表示データを表示する」ことが記載されていると認められることは、前記4?ウと同様である。そもそも、画像をディスプレイに表示させる方法を検討する場合に、 画像及びディスプレイの各解像度(画素数)が重要な要素になることは、 25 丙B9文献に記載されるまでもなく明らかなことであるから、これらの文言自体の記載がないことは、丙B9発明を主引用例とする容易想到性23を認めることの妨げになるものではない。 ②の点については、丙B9文献の【0003】、【0014】の各記載は、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合には、これをそのまま簡易型液晶表示パネル23で表示するとスクロール操作をしない5 限り全画面を見ることができなくなる場合があることを前提にしているものと認められる。したがって、当該各記載からは、「画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合には、簡易型液晶表示パネル23においてスクロール操作で全画面を見る必要があること」を容易に読み取ることができる。 10 ③の点については、そもそも、表示パネルより大きい解像度の表示データであっても、その一部を当該表示パネルと同じ解像度で表示することは可能である(スクロール操作をすれば、その全画像を見ることができる。)ということは、本件発明や丙B9発明の前提になっていた技術常識であったというべきであるから、丙B9文献に「携帯電話機の簡易15 型液晶表示パネルと同じ解像度の表示データを生成すること」について直接記載がないことは、本件技術常識を認める妨げとはならない。 (イ) 原告は、相違点6’に係る本件発明の構成は「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出す」ことであり、本件技術常識とは文言上明らかに異なる、本件技術常識に20 おける「表示データ」は「ビットマップデータ」ではないと主張する。 しかし、既に述べたとおり、本件技術常識における「表示データ」はドットデータ(ビットマップデータ)である(前記のとおり、原判決をこのように補正した。)。 (ウ) 原告は、本件発明の「高解像度画像受信・処理・表示機能」に係る、 25 ①無線通信手段が画像データを伝達する無線信号を受信すること、②無線通信手段がこの無線信号をデジタル信号に変換の上、中央演算回路に24送信し、中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理すること、③グラフィックコントローラが、 該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対して書き込んだビットマップデータであることが丙B9文献に開示されていない旨主5 張する。 しかし、①、③の点が丙B9文献に開示されていると認められることは、前記第3の3?のとおりである。また、②の点は本件発明と丙B9発明の前記相違点6BDG’を構成するとした場合でも、本件技術常識を適用することにより容易想到であると認められることは、前記?のと10 おりである。 6 進歩性についての結論以上より、本件発明は、丙B9発明に、本件優先日当時の技術常識を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、進歩性欠如(特許法29条2項)の無効理由を有する。 15 したがって、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものであり、 原告は被告に対し本件特許権を行使することができないから(同法104条の3第1項)、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求には理由がない。 7 結論よって、原告の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない20 から、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部25 裁判長裁判官清 水 響25裁判官5 菊 池 絵 理裁判官10 頼 晋 一26(別紙)認定・主張対照表(控訴審)原判決 原告の主張 当裁判所の判断本件発明 丙B9発明 丙B9発明 丙B9発明ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力 6a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータを 一致点 6a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータ 一致点 6a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータ 一致点A し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力 CPU11に送信する操作部20と; をCPU11に送信する操作部20と、 をCPU11に送信する操作部20と、 手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記 6b アンテナ12aを有し、送信信号の変調および受信信 一致点 6b アンテナ12aを有し、送信信号の変調及び受信信号 相違点① 6b アンテナ12aを有し、送信信号の変調及び受信信号 相違点6BDG’中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路 号の復調機能を有し、CPU11と相互に信号の送受信を行 の復調機能を有し、CPU11に制御される通信部12と、 の復調機能を有し、CPU11に制御される通信部12と、 Bから受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信 う通信部12と;する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中 6c CPU11 が 実 行 す る 各 種 プ ロ グ ラ ム を 格 納 す る 一致点 6c CPU11が実行する各種プログラムを格納する 一致点 6c CPU11が実行する各種プログラムを格納する 一致点C 央演算回路で処理可能なデータファイルとを格納する ROM14及びユーザ設定データ等を格納するRAM13と; ROM14及びユーザ設定データ等を格納するRAM13 ROM14及びユーザ設定データ等を格納するRAM13記憶手段と; と、 と、 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に 6d1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力さ 一致点 6d1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力 相違点① 6d1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力さ 相違点6BDG’格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段 れた表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、 された表示データ(外部から取り込んだ画像情報) 相違点② れた表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リア ドットデータとして簡易型液晶表示パネルやCRT表示 を、(注:「ドットデータとして」は削除)簡易型液 ドットデータとして簡易型液晶表示パネル23やCRT表ルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自 器24等の大型ディスプレイに送信するよう制御する 晶表示パネルやCRT表示器24等の大型ディスプレイに 示器24等の大型ディスプレイに送信するよう制御するらが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に CPU11と、 送信するよう制御するCPU11と、 CPU11と、 一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のDVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み 6d2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画像 一致点 6d2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画 6d2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画像出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝 メモリ22に記憶させると共に、画像メモリ22に記憶させ 像メモリ22に記憶させると共に、(注:「画像メモリ メモリ22に記憶させると共に、画像メモリ22に記憶させ達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示 た表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けら 22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を」は削 た表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けら信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インター れた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大 除)電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 れた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大フェース手段に送信するグラフィックコントローラ 型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する 又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続された 型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信すると、から構成されるデータ処理手段と; 表示制御回路21と; モニタ端子25に送信し、特に、モニタ端子25へはドッ 表示制御回路21と;トデータとして送信する表示制御回路と、 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより 6e 表示制御回路21から送られてきた表示データを表 一致点 6e 表示制御回路21から送られてきた表示データを表 一致点 6e 表示制御回路21から送られてきた表示データを表 一致点画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラ 示する簡易型液晶表示パネル23と; 示する簡易型液晶表示パネル23と、 示する簡易型液晶表示パネル23と、 フィックコントローラから受信したデジタル表示信号Eに基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディ 6f CRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されて 一致点 6f CRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されて 一致点 6f CRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されて 一致点スプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該 おり、表示制御回路21から送られてきた表示データを おり、表示制御回路21から送られてきた表示データを おり、表示制御回路21から送られてきた表示データを周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラか CRT表示器等の大型ディスプレイに送信するモニタ端 CRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するモニタ CRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するモニタFら受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号 子25とを備え、 端子25とを備え、 端子25とを備え、 を送信するインターフェース手段と;を備え、 27原判決 原告の主張 当裁判所の判断本件発明 丙B9発明 丙B9発明 丙B9発明前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレ 6g’1 通信部12が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭 一致点 (丙B9発明は、6g’1の構成を有しない。) 相違点① 6g’1 通信部12が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭 相違点6BDG’イパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達 に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11 相違点② に表示できない画像情報を受信して復調の上、(注:する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前 に送信し、CPU11が、ドットデータとして簡易型液晶表 「CPU11に送信し、」は削除)CPU11が、ドットデー記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジ 示パネルやCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信 タとして簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等のタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像 するよう表示制御回路21を制御し、 大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21を制データを処理し、前記グラフィックコントローラが、 御し、 該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み 6g’2 CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示 一致点 6g’2 CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示 6g’2 CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示G’出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝 データを画像メモリ22に記憶させると共に、画像メモ データを画像メモリ22に記憶させると共に、(注: データを画像メモリ22に記憶させると共に、画像メモ達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示 リ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話 「画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデー リ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インター 機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRT タ)を」は削除)電話機本体に設けられた簡易型液晶 機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRTフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は 表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端 表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイ 表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以 子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表 に接続されたモニタ端子25に送信し、特に、モニタ端 子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記す 示器24等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を 子25へはドットデータとして送信して、簡易型液晶表 示器24等の大型ディスプレイに画像を表示する機能をる)を有する、携帯情報通信装置において、 有する、携帯電話機において、 示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに 有する、携帯電話機において、 画像を表示する機能を有する、携帯電話機において、 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通 6h’ 携帯電話機が、外部から受信した情報量の多い表 相違点6’ 6h’ 携帯電話機が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭 相違点② 6h’ 携帯電話機が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭 相違点6’信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実 示データ(簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示で に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場 に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場現する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプ きない画像情報)を表示する機能を実現する場合に、 合に、表示制御回路21は、ドットデータとしてCRT表 合に、表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させたレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像の 表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示 示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子 表示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型ビットマップデータ」を読み出し、「該読み出した データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型ディ 25に送信し、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、 ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、 ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を スプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、CRT表 簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像 CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表H’ 生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御 示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネ 情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表 示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記 ル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく 示する機能を実現し、 なく(スクロール操作することなく)表示する機能をディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を (スクロール操作することなく)表示する機能を実現 実現し、 有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該 し、 読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコ 6i モニタ端子25は、表示制御回路21から受信した表 一致点 6i モニタ端子25は、表示制御回路21から受信した表 一致点 6i モニタ端子25は、表示制御回路21から受信した表 一致点ントローラから受信した「ビットマップデータを伝達 示データ(ドットデータ)をCRT表示器24 等の大型 示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型 示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、 ディスプレイに表示できるようにして送信する機能を ディスプレイに表示できるようにして送信する機能を ディスプレイに表示できるようにして送信する機能をI LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方 有する、 有する、 有する、 式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、 ことにより、 6j ことにより、CRT表示器24等の大型ディスプレイ 一致点 6j ことにより、CRT表示器24等の大型ディスプレイ 相違点③ 6j ことにより、CRT表示器24等の大型ディスプレイ 一致点前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイ に、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない に、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない に、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できないJ パネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」 画像情報を、欠落なく(スクロール操作することな 画像情報を、欠落なく(スクロール操作することな 画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなを表示できるようにした、 く)表示できるようにした、 く)表示できるようにした、 く)表示できるようにした、 K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 6k 携帯電話機 一致点 6k 携帯電話機 一致点 6k 携帯電話機 一致点28 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
|