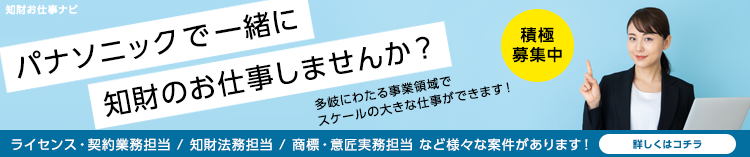| 関連審決 |
異議2022-701091 |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行ケ)
10053号
特許取消決定取消請求事件
|
|---|---|
|
5 原告大建工業株式会社 同訴訟代理人弁理士 前田亮 同 佐敷京子 10 同藤本知志 被告 特許庁長官 同 指定代理人西田秀彦 同 居島一仁 15 同土屋真理子 同 海老原えい子 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/02/20 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 20 事 実 及 び 理 由(注)本判決で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、次のとおりである。 本件決定 :特許庁が異議2022-701091号事件について令和6年5月2日にした決定本件特許 :原告を特許権者とする特許第7064552号(発明の名25 称:木質ボード。甲5)本件発明 :本件特許に係る発明の総称。各請求項に係る発明は、請求項1の番号に対応して「本件発明1」などという。 本件訂正 :原告の令和5年10月23日付け訂正請求書(甲14)による訂正本件明細書 :本件特許に係る明細書及び図面(甲5)5 甲1公報 :特開平11-58332号公報(甲1)甲1発明 :甲1公報に記載された発明(発明の名称:木質板)甲3公報 :特開2003-94411号公報(甲3)本件出願日 :令和2年10月30日第1 請求10 本件決定のうち、特許第7064552号の請求項1、2及び4に係る特許を取り消した部分を取り消す。 第2 事案の概要本件は、特許異議の申立てに対する特許取消決定の取消訴訟である。争点は、 進歩性の判断の誤りである。 15 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)? 原告は、発明の名称を「木質ボード」とする発明について、令和2年10月30日(本件出願日)、特許出願をし、令和4年4月26日、本件特許に係る特許権の設定登録を受けた(請求項の数4)。 ? 本件特許につき、同年11月10日、特許異議の申立てがなされ、特許庁20 は、同事件を異議2022-701091号事件として審理した。 ? 原告は、令和5年10月23日、本件特許の特許請求の範囲の訂正(請求項3の削除を含む。)を求める本件訂正を請求した。 ? 特許庁は、令和6年5月2日、「特許第7064552号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項25 〔1-4〕について訂正することを認める。特許第7064552号の請求項1、2及び4に係る特許を取り消す。特許第7064552号の請求項32に係る特許についての特許異議申立てを却下する。」との本件決定をし、その謄本は、同月13日、原告に送達された。 ? 原告は、同年6月10日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件発明の内容等5 ? 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数3)の記載は、以下のとおりである(下線部は訂正箇所)。 【請求項1】繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードであって、 10 上記木質ボードの密度が500kg/?以上800kg/?以下であり、 上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.05㎜以上0.35㎜以下、上記繊維方向に沿った長さが10㎜以上35㎜以下、上記繊維方向と直交する方向に沿った幅が0.5㎜以上15㎜以下の細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節部分がなく、且つ上記繊維方向がランダムに配向さ15 れていることを特徴とする木質ボード。 【請求項2】請求項1の木質ボードにおいて、 木質ボードの木質小薄片は、厚さが0.15~0.25㎜、長さが20mm 以下、幅が5mm 以下の細長形状であることを特徴とする木質ボード。 20 【請求項3】(削除)【請求項4】請求項1又は2の木質ボードにおいて、表面における二乗平均平方根高さSqが0.005~0.015μm又は表面における算術平均高さSa25 が0.002~0.007μmであることを特徴とする木質ボード。 ? 本件明細書3本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲5)の【発明の詳細な説明】及び各図面のとおりである。 3 本件決定の理由等? 本件決定は、本件訂正を認めた上で、別紙「異議の決定」(写し)のとお5 り、本件発明1は甲1発明に基づき、本件発明2は甲1発明に甲3公報記載の技術事項を適用することにより、本件発明4は甲1発明に基づき、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであると判断した。 原告は、本件訴訟において、本件決定の認定・判断のうち、次の点を争っている。①甲1発明と本件発明1、2及び4に共通する相違点1及び2の認10 定、②これらの相違点に係る容易想到性の判断、③甲1発明と本件発明2との相違点1’の容易想到性の判断。 他方、原告は、?甲1発明の認定、?甲1発明と本件発明1,2及び4に共通する一致点の認定、?前記相違点1’の認定については争っていない。 以下においては、本件決定のうち、甲1発明の認定と相違点1、2及び1’15 に関する認定・判断部分の要旨についてのみ記載する。 ? 甲1発明の認定甲1公報には、以下の甲1発明が記載されている。 「 木材薄片がバインダー樹脂により接着一体化された木材薄片集成板からなる木質板であって、 20 木材薄片は、厚さの絶対値が0.05~0.50㎜、厚さの平均値が0.10~0.45㎜のものが用いられ、 木材薄片の長さは、絶対値が20.0~150.0㎜、平均値が40.0~115.0㎜の範囲内であることが好ましく、 木材薄片の幅は、絶対値が1.00~50.00㎜、平均値が10.0025 ~35.00㎜の範囲内であることが好ましく、 木材薄片集成板をなす木材薄片の配列は、木目方向をほぼ一方向に揃えて4配列されたものであってもよく、木材薄片の木目方向はランダムにしてもよく、 密度が0.40~0.65g/?であり、 木材薄片の厚みの絶対値が0.05~0.50㎜と狭い範囲であるのでバ5 ラツキが小さく、従って表面及び木口面の平滑性が優れており、木質板の角部を削って孔が生じることを低減できるので木口面上に化粧板を貼着し易く、 しかも化粧板に凹部が現出するのを低減できる、 木質板。」? 一致点及び相違点の認定10 【一致点】繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードであって、 上記木質ボードの密度が500kg/?以上800kg/?以下であり、 上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.05㎜以上0.35㎜以下、 15 上記繊維方向と直交する方向に沿った幅が0.5㎜以上15㎜以下の細長形状であり、繊維方向がランダムに配向されている木質ボード。 【相違点1】「木質小薄片」の「繊維方向に沿った長さ」について、本件発明1では、 「10㎜以上35㎜以下」であるのに対して、甲1発明では、「40.0~20 115.0㎜の範囲内」である点。 【相違点2】「木質小薄片」について、本件発明1では、「細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節部分がな」いのに対して、甲1発明では、そのような特定がされていない点。 25 【相違点1’】「木質ボードの木質小薄片」について、本件発明2は、「長さが10mm5以上20mm 以下」、「幅が0.5mm 以上5mm 以下」であることを特定しているのに対し、甲1発明は、「木材薄片の長さ」の「平均値」が「40.0~115.0mm の範囲内」であり、「木質薄片の幅」の「平均値」が「10.00~35.00mm の範囲内」である点5 ? 各相違点の容易想到性ア 相違点2について事案に鑑み相違点2から検討する。 (ア) 相違点2に係る本件発明1の構成のうち、「木質小薄片」が「細長形状に大きさと形状が均質に揃っている」ことの技術的意味は、本件10 明細書【0013】及び【0056】(以下、特記しない限り、【 】内の数字は、本件明細書の段落を表すものとする。) の記載から、 「木質小薄片」が「細長形状に大きさと形状が均質に揃っている」こととは、「厚さt」、「繊維方向寸法d1(長さ)」及び「繊維直交方向寸法d2(幅)」が、「狭い範囲内に収まってい」ることや、 15 「ばらつきが小さ」いことなど、「一定範囲内にある」ことをいうものと理解することができる。 (イ) 甲1発明において、木材薄片は厚さ、長さ及び幅それぞれの絶対値の範囲が規定されていることに照らすと、厚さ、長さ及び幅それぞれの平均値は、前記(ア)の「一定範囲内」に収まっていることは明らかで20 ある。 そうすると、甲1発明の木材薄片の厚さの絶対値が0.05~0.50㎜であり、長さの絶対値が20.0~150.0㎜であり、幅の絶対値が1.00~50.00㎜であることは、本件発明1の「木質小薄片」が、「細長形状に大きさと形状が均質に揃っている」ことに25 相当する。 (ウ) 特開平11-58330号公報(甲4)に、木材小片を木目方向に6略配向させて積層・接着した配向ストランドボード(OSB)や、長尺 木 細 片 を 配 向 さ せ て 積 層 ・ 接 着 し た O S L ( Oriented StrandLumber)、PSL(Parallel Strand Lumber)等の、細片化木材を用いた再構成材は、原木を細片化してこれを再構成するために、原木から5 切り出した製材品のように節等による欠陥が存在しないことが記載されているとおり、細片化木材を用いた再構成材(OSB、OSL、PSL等)は、原木を細片化してこれを再構成するため、原木から切り出した製材品のように節等による欠陥が存在しないことは技術常識である。 10 甲1発明の「木材薄片」は、厚さ、長さ及び幅の絶対値及び平均値の範囲が規定されており、このような木質薄片を用いた木質板であれば、 前記の公報記載の細片化木材を用いた再構成材と同様に、節等による欠陥が存在していないといえる。 (エ) 以上を踏まえれば、相違点2は実質的な相違点ではない。 15 イ 相違点1について(ア) 本件発明1に記載された厚さ、長さ及び幅に係る数値範囲は、【0017】に「木質小薄片の厚さ、長さ及び幅はいずれも平均値である。」と記載されているように、平均値の範囲である。 (イ) 一般に、数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創20 作能力の発揮である。そして、甲1発明は表面の平滑性の向上を課題の一部としているところ、木材薄片を利用した木質板は、構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板の表面が平滑になるものであるから、平滑性等、所望の特性を得るよう、「繊維方向に沿った長さ」の数値範囲を好適化して、すなわち、「木質小薄片」の「平均値」25 を小さくして、「10mm~35mm以下」と特定することは、当業者が通常の創作能力を発揮してなし得た程度のことである。 7(ウ) 【0022】、【0056】等をみても、長さを「10㎜以上35㎜以下」に限定したことにより奏される特段の効果が認められないから、 本件発明1が、長さを「10㎜~35㎜以下」とした点で、甲1発明と比較して、進歩性を推認できる顕著な効果を持つとはいえない。 5 また、甲1公報において、長さの数値範囲を変更することの阻害要因となる特段の記載や示唆はなく、また、甲1公報【0003】には、 木質板の製造にあたって、構成要素の寸法を小さくすることによる利点があることが示唆されている。 (エ) そうすると、相違点1に係る本件発明1の構成による作用効果は、格10 別顕著なものとはいえず、甲1発明において、長さを変更することを阻害する要因があるともいえないから、甲1発明において、木質小薄片の長さのバラツキを小さくするにあたって、相違点1の本件発明1の数値範囲とした点は、適宜なし得る設計事項程度のものである。 ウ 相違点1’について15 (ア) 本件発明2において「長さが10mm 以上20mm 以下」、「幅が0.5mm 以上5mm 以下」としたことによる作用効果の程度が格別顕著なものとはいえないから、相違点1’に係る本件発明2の構成は、適宜なし得る設計事項程度のものである。 (イ) 甲3公報の木質板(1)において、木片の「厚さ0.2~0.2520 mm」、「長さ10~12mm」及び「幅0.5~2.5mm」が使用されることは、それぞれ、本件発明2の木質ボードの木質小薄片の「厚さ0.15~0.25mm」、「長さ20mm 以下」及び「幅が5mm 以下」であることに相当し、甲3公報の木片の長さが幅に比べて長いことは、 本件発明2の「細長形状」に相当する。 25 (ウ) 甲1発明と甲3公報に記載された技術とは、いずれも多数の木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードに関する8もので、属する技術分野が共通する。甲1公報【0003】の記載を踏まえると、表面の平滑性を高めることを目的として、甲1発明の木質板において、表面の平滑性を高めるために、寸法が小さい甲3公報記載の木片を適用し、相違点1’に係る本件発明2の構成となすこと5 は、当業者が容易になし得たことである。また、本件発明2の作用効果は、甲1発明及び甲3公報の技術事項から予測しうる範囲のものである。 ? したがって、本件発明1、2及び4は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明2は、甲1発明及び甲10 3公報記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 取消事由原告主張の取消事由は、甲1発明に基づく本件発明の進歩性判断の誤りであり、具体的には、本件発明の進歩性判断について、以下の誤りがあると主張す15 るものである。 ? 相違点1、2の認定の誤り? 相違点1の容易想到性判断の誤り? 相違点2の容易想到性判断の誤り? 相違点1’の容易想到性判断の誤り20 第3 当事者の主張1 相違点1、2の認定の誤り(原告の主張)? 本件発明1の「上記木質ボードの密度が500kg/?以上800kg/?以下であり、」との構成(以下「密度に係る構成」という。)、及び「上記木25 質小薄片は」「上記繊維方向がランダムに配向されている」との構成(以下「配向に係る構成」という。)は、相違点1に係る「木質小薄片の繊維方向9に沿った長さが10㎜以上35㎜以下」である構成(以下「寸法に係る構成」という。)及び相違点2に係る「細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節部分がない」構成(以下「形状等に係る構成」といい、「寸法に係る構成」と併せて「寸法・形状等に係る構成」という。)と合わせ、これらすべての5 発明特定事項の組み合わせにより、高強度で寸法安定性や表面性に優れる木質ボードという、本件発明の技術的課題の解決手段として重要な技術的意義を有している(以下、本件発明1を含む本件発明2、4についても同じ)。 この点を否定する本件決定の判断は、いずれも誤りである。 ア 本件明細書の【図6】(以下、単に【図6】という。)には、「密度に10 係る構成」、「寸法・形状等に係る構成」及び「配向に係る構成」の奏する効果が記載されている。 また、【0018】、【0056】、【0058】及び【図6】には、 高強度かつ表面性に優れることは、「寸法・形状等に係る構成」と「密度に係る構成」を兼ね備えることにより達成されることが記載されている。 15 さらに、高強度かつ寸法安定性に優れる木質ボードとは、【0046】に「木質小薄片1によって木質ボードAの均質性と強度とを兼ねている」と記載のとおり、高強度で寸法安定性に優れた上でさらに均質なものと判断できる。ここで、「高強度で寸法安定性に優れた上でさらに均質な」木質ボードとは、「吸放湿による反りが発生し難く」い(吸放湿時の長さ変20 化率が小さい)こと(【0018】、【0056】、【0058】)に加えて、「曲げヤングが縦横に均一であり、寸法安定性での異方性」の無い木質ボード(【0058】、【図6】)といえるから、「木質小薄片」の繊維方向が一方向に配向されているものでは達成されず、「ランダムに配向されている」ことが必要である。 25 このように、「寸法・形状等に係る構成」、「配向に係る構成」、 「密度に係る構成」を組み合わせることでしか、本件発明の目的とする10「木質ボード」が得られないと理解することができる。 イ 実験成績証明書?(甲17)によれば、木質小薄片の繊維方向を基準方向に配向した「比較実験例2」は、木質小薄片の繊維方向がランダムに配向されている「実験例1」と比較して寸法安定性(変化率及び異方性)に5 劣ることから、「配向に係る構成」は木質ボードの「異方性」の有無に影響し、寸法安定性の向上に寄与することが示されている。 また、「密度に係る構成」の範囲外とした「比較実験例3」は、本件発明1の構成を有する「実験例1」と比較して、強度及び表面性に劣る。このことは、「寸法・形状に係る構成」を有した上で「密度に係る構成」と10 することは、本件発明の技術的課題と直接関係することを示している。 このように、実験成績証明書?(甲17)は、本件発明1の発明特定事項を併せ持つ実験例1(本件発明1)の効果に対して、いずれかの発明特定事項を有しない比較実験例1-1、1-2、2及び3では同様の効果が得られないことを示している。 15 ? 以上のとおり、本件決定において認定された相違点1、2に係る「寸法・形状等に係る構成」は、「密度に係る構成」及び「配向に係る構成」とともに、互いに関連し、ひとまとまりの手段として機能し、相乗効果を奏するものであるから、ひとまとまりの相違点として認定して判断しなければならないものであって、前記各構成の技術的意義の判断を誤り、相違点1、2を個20 別に認定した本件決定の認定は誤りである。 このような相違点の認定の誤りは、容易想到性が区々に判断され、本来であれば進歩性が認められる発明の進歩性が否定される結果を生じ得るものであるから、結論に影響を及ぼす重大な誤りである。 (被告の主張)25 ? 本件明細書には、課題を解決するための手段(【0014】)において、 「形状等に係る構成」(「細長形状に大きさと形状が均質に揃っていること」11及び「節部分がな」いこと)と「配向に係る構成」の記載がないことから、 これらの構成と課題を解決すべき手段との直接の関係を示す記載も示唆もないことは、本件決定のとおりである。 特に、「節部分がな」いことに関しては「節部分が除去されており」5 (【0046】)と、「配向に係る構成」に関しては「繊維方向がランダムに配向されていてもよい」(【0034】)と記載されているにとどまり、 本件明細書全体をみても、課題を解決すべき手段との技術的関係を合理的に理解させる記載はない。 「密度に係る構成」に関しても、本件明細書の記載から、原告主張の技術10 的意義を有することを理解することができない。 したがって、相違点1、2の「寸法・形状等に係る構成」に「配向に係る構成」と「密度に係る構成」を加えたひとまとまりの手段と、本件発明の技術的課題の解決手段との直接の関係が示されているとはいえない。 ? 実験成績証明書?(甲17)については、特許法が先願主義を採用し、発15 明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨から、当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、 進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、 出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。 20 仮にこれを参酌したとしても、各発明特定事項と得られる木質ボードの物性は理解することができるとしても、各発明特定事項相互間の技術的関係は何ら理解することはできず、「寸法・形状等に係る構成」、「配向に係る構成」と「密度に係る構成」がひとまとまりとして機能し、相乗効果を奏していると理解することはできない。 25 ? したがって、本件決定の相違点の認定に誤りはない。 2 相違点1の容易想到性判断の誤りについて12(原告の主張)? 甲1公報には、木材薄片の長さを、好ましい範囲である「平均値が40.0~115.0㎜」(甲1公報【0012】)よりも小さい「10㎜以上35㎜以下」とすることについて、何ら記載も示唆もない。 5 ? 甲1公報は、「構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり、表面も平滑になるが、強度、剛性は低下し、密度は増加する傾向がある。逆に構成要素の寸法を大きくすると、木材本来が持っている強度、 密度に近づいて行くが、そのような木質板は不均質で、表面の凹凸も大きくなる傾向がある」(甲1公報【0003】)とした上で(すなわち、長さ等10 の寸法を小さくすることによる欠点も考慮した上で)、木質板に要求される特性を持たせるために、種々の検討を重ねた結果(甲1公報【0004】~【0007】)、「木材薄片の長さは、絶対値が20.0~150.0㎜、 平均値が40.0~115.0㎜の範囲内であることが好ましい」(甲1公報【0012】)ことに到達したものといえるから、甲1公報に接した当業15 者が、木材薄片の長さを、好ましい範囲の「平均値が40.0~115.0㎜」からそれよりも小さい「10㎜以上35㎜以下」とすることをあえて試みる動機付けの存在が認められず、相違点1に係る構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在しないばかりか、その推測すら成り立たない。 20 ? 甲1公報には、甲1発明の構成による実施例1(甲1公報【0020】)と比較して、作用効果が劣る比較例1として「①芯層をなす木材薄片として、 長さの絶対値が70~80㎜(長さの平均値が75㎜)」及び「②表面層をなす木材薄片として、長さの絶対値が70~80㎜」が記載されている(甲1公報【0022】)ことから、甲1発明において、木材薄片の長さの平均25 値を75㎜よりもさらに小さい「10㎜以上35㎜以下」(相違点1)に構成することは、当業者が通常考えないから、阻害要因がある。 13? 相違点1に係る、木質小薄片の長さを「10㎜~35㎜以下」と限定する構成は、実験成績証明書?(甲17)のとおり、木質ボードの「強度」、 「寸法安定性」及び「表面性」の向上に寄与するという有利な効果を奏する。 加えて、実験成績証明書?(甲17)のとおり、本件発明1の構成を有す5 る「実験例1」と、木質小薄片の長さを甲1発明の範囲の構成とした「比較実験例1-1」及び「比較実験例1-2」とを対比すると、強度(MOE)は全て「〇」で相違がない一方で、表面性(平滑性)に関しては、「比較実験例1-1」及び「比較実験例1-2」が「×」で、「実験例1」の「〇」よりも劣ることが理解できる。すなわち、木質小薄片の長さを小さくした本10 件発明1では、表面性(平滑性)は「×」から「〇」に推移するが、強度(MOE)は「〇」のままに維持され、前記の甲1公報【0003】の記載と異なり、強度(MOE)が低下しない。 したがって、相違点1に係る本件発明の構成には、特段の効果が認められ、 進歩性を推認できる顕著な効果を持つといえる。 15 (被告の主張)? 甲1公報は、木材薄片の厚さ及び幅に着眼しているものであって(甲1公報【0001】、【0009】、【0012】)、長さについては「平均値が40.0~115.0mm の範囲内であることが好ましい。」(甲1公報【発明の実施の形態】【0012】)と記載されているものの、【課題を解20 決するための手段】としては記載されていないし、長さを当該範囲にすることの技術的意義についても記載されていない。原告指摘の各記載をみても、 木材薄片の長さに着目した検討を重ねたことは窺われない。 また、木質板の製造に当たり、構成要素の寸法を小さくすることによる「得られる木質板は均質になり、表面も平滑になる」との利点も記載されて25 いる(甲1公報【0003】)。 ? 特開平10-249817号公報(甲2)には、「板状に成形」される14「配向性ストランドマットSM」に、「長さが24㎜」のストランド(木質薄片)を用いた点が記載されており(甲2の【0009】、【0034】)、 甲3公報には、木質板に使用される木片の好適なサイズとして、芯層において「長さ1~50㎜」が、表裏層において「長さ1~30㎜」が示され、 5 「長さ1~30㎜」の木片が木質板の芯層においても表裏層においても好適に用いられること(甲3公報【0006】、【0008】)が記載されているように、当該技術分野においては、木質板の構成要素の長さを本件発明1のものと同程度のものとすることは、周知の事項である。 ? したがって、甲1発明において、木質板の均質性や表面の平滑性の観点か10 ら、「木材薄片の長さ」を寸法が小さくなるよう変更することは、当業者が容易に想到しうることであるし、前記の周知の事項を併せ考えれば、木質薄片の長さを、好ましい範囲の「平均値が40.0~115.0㎜」から、それよりも小さい「10㎜以上35㎜以下」とする動機付けは十分に認められる。 15 ? 本件明細書には、木質小薄片の長さを「10㎜以上35㎜以下」とすることにより、木質ボードの「強度」、「寸法安定性」及び「表面性」が向上するという効果は何ら記載されていないことは、前記のとおりである。 したがって、これらの点について、実験成績証明書?(甲17)に基く主張は採用されるべきではないが、仮に参酌したとしても、木質小薄片の平均20 値が「10㎜~35㎜以下」であることによる効果は、通常想定されるものと異なるものではなく、顕著な効果が奏されるとはいえない。 3 相違点2の容易想到性判断の誤りについて(原告の主張)? 本件発明1の「木質小薄片」は「10㎜以上35㎜以下」(公差25㎜)25 であるのに対し、甲1発明の「木材薄片」は「40.0~115.0㎜の範囲内」(公差75.0㎜)であり、本件発明1の「木質小薄片」よりも公差15(スケール)が3倍以上大きいため、「狭い範囲内に収まってい」るとはいえず、「ばらつきが小さ」いともいえないから、「細長形状に大きさと形状が均質に揃」っているとはいえない。 ? 甲1発明の「木材薄片」は、本件発明1の「木質小薄片」と比較して、前5 記の公差に加え、長さの中央値(目標値)も大きく相違するから、節等による欠陥が存在している。 実験成績証明書?(甲19)のとおり、木質小薄片の厚さ、長さ及び幅の寸法を本件発明1の構成とした「実験例2」は節部分がないのに対し、長さのみを60㎜とした「比較実験例5」、長さのみを100㎜とした「比較実10 験例6」では節部分のある不良薄片が含まれているから、長さが「40.0~115.0㎜の範囲内」である甲1発明の木材薄片に「節部分」がないとはいえない。 ? したがって、相違点2は実質的な相違点ではないとする本件決定の判断は誤りである。 15 (被告の主張)? 木質小薄片(木材薄片)の長さの平均値が「10㎜以上35㎜以下」(本件発明1)、あるいは「40~115㎜以下」(甲1発明)であるということは、複数の集合体である木質小薄片の全体の平均値を算出した値が上記範囲の中にあるということを意味するのであり、上記範囲の上限値と下限値の20 差(原告主張の「公差」)と、各木質小薄片の個々の長さに着目した場合のばらつきや長さの幅との間に、何らの技術的関係も見出せない。 ? 本件明細書には「節部分が除去されており」(【0046】)と記載されているのみで、「節部分」がどのようなものであるかの説明はなく、「新版木材工業ハンドブック」(乙1)によれば、「節」とは「枝が幹に巻き込ま25 れてできるもので、節の周囲では材の繊維が錯走しており目切れ材をつくり、 また死節では節の繊維と周囲の材の繊維が連続していないから乾燥に際して16この部分に緩み、干裂を生じ強度低下の原因となる」ものであるから、「節部分」とは、かかる「節」の部分を意味すると解するのが合理的である。 そして、実験成績証明書?(甲19)の[節部分のある不良薄片の例]とされる写真には、上記の「節」の部分があることを確認することができない5 から、そのようなものが比較実験例5、6において含有されていたとしても、 そのことをもって、甲1発明において、実質的な節部分はないものとはいえないと理解することはできない。 4 相違点1’の容易想到性判断の誤りについて(原告の主張)10 本件発明2が甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、甲1発明及び甲3公報の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの判断については、誤りがある。 (被告の主張)争う。原告は本件発明2について実質的な主張をしていない。 15 第4 当裁判所の判断1 本件発明について本件明細書の記載(別紙「特許公報」参照)によれば、本件発明について、 次の記載があると認められる。 ? 技術分野20 本発明は、木質ボードに関するものである。(【0001】)? 背景技術一般に、既存の木質ボードとしてラワン合板等の南洋材合板はよく知られており、広く利用されているが、近年入手が難しくなってきている。配向性ストランドボード(OSB)、パーティクルボード(PB)及びMDFには、 25 それぞれ、配向性ストランドボード(OSB)は強度が高いものの表面性が不足している、パーティクルボード(PB)は価格が安いが強度が不足して17いる、MDFは表面性がよいものの寸法安定性が十分ではないとの問題がある上、いずれも南洋材合板と比較して密度が大きい難がある。(【0002】、【0004】)このように、原料の安定性に加え、強度、重量、表面性、さらに寸法安定5 性といった複数の要素を満足する木質ボードが存在していないのが現状である。(【0005】)? 発明が解決しようとする課題先行技術文献に示される木質ボードには、それぞれ、木材薄片の厚さや大きさを表面層と芯層とで異ならせているため、製造時には2種類の木材薄10 片を用意する必要があり、製造や管理に手間がかかる、木質ボードの表面に凹凸が生じ、表面平滑性を確保できない、基材を2次加工するために手間がかかるだけでなく、基材と繊維層との2重構造となるために、ボードの厚さを小さくすることに限度があり、吸湿による寸法変化を抑制することもできない等の問題がある。(【0010】~【0012】)15 本発明の目的は、多数の木質薄片を積層する構造の木質ボードに改良技術を施すことにより、1種類の大きさの木質薄片のみを用いて、高強度で寸法安定性や表面性に優れ、製造の容易な木質ボードが得られるようにすることにある。(【0013】)? 課題を解決するための手段20 ア 上記の目的を達成するために、この発明では、配向性ストランドボード(OSB)の構成材料として通常使用される切削片に対し、厚さを含む大きさを微小な範囲に限定した木材薄片を用い、この木材薄片の大きさをさらに微小な範囲に限定した木質小薄片を構成材料とし、その多数の木質小薄片を集合状態で積層して木質ボードとするようにした。(【0014】)25 なお、「切削片」は、配向性ストランドボード(OSB)用途に原木から切削され、構成材料として通常使用されるものをいい、「木質薄片」18は、「切削片」と同様に原木から切削されるものであるが、「切削片」の通常一般の厚さの範囲外でそれよりも薄くて小さい薄片をいい、本発明に係る「木質小薄片」は、「木質薄片」と同じ厚さ範囲で「木質薄片」よりも小さい薄片をいう。(【0015】)5 実施例でみると、本発明に係る木質小薄片1,1,…は、通常一般の配向性ストランドボード(OSB)の構成材料として使用される切削片が一般的には長さが110㎜(長いものでは150~250㎜程度)、 幅が15~25㎜(長いものでは長さの1/3程度)であるのに対し、 それよりも寸法の小さい薄片(好ましくは長さ35mm 以下、幅15mm 以10 下)である。(【0028】)イ 第1の発明は、繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードが対象であり、この木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.05㎜以上0.35㎜以下、上記繊維方向に沿った長さが10㎜以上40㎜以下、上記繊維方15 向と直交する方向に沿った幅が0.5㎜以上15㎜以下であることを特徴としている。この第1の発明では、前記寸法の細長形状の多数の木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化により構成されている。木質小薄片の厚さ、長さ及び幅はいずれも平均値である。このように木質ボードは、 後述のP1工程で得られる特定の厚みを有する木質薄片を、同じく後述の20 P2工程において木質薄片の繊維方向及び繊維直交方向に粉砕した1種類の大きさの木質小薄片のみで構成され、その木質小薄片は厚さが極めて薄く、0.05~0.35㎜という狭い範囲内に収まっているので、多数の木質小薄片は厚さのばらつきが小さくて均一な厚さに揃ったものになり、 木質小薄片の長さ及び幅も一定範囲内にある。(【0016】~【00125 8】)ウ 第2の発明は、第1の発明の木質ボードにおいて、その木質小薄片は、 19厚さが0.15~0 .25㎜、長さが20㎜以下、幅が5㎜以下の細長形状であることを特徴とする。(【0019】)エ 第3の発明は、第1又は第2の発明の木質ボードにおいて、密度が500~800kg/?であることを特徴とする。(【0020】)5 オ 〔注:実施例〕本件明細書の【図3】は、木質小薄片を概略的に示す拡大斜視図である。木質小薄片1は、導管や仮導管等による繊維1a,1a,…を有し、その繊維1aに沿った方向の繊維方向寸法d1が、繊維方向と直交する方向に沿った繊維直交方向寸法d2よりも長い細長形状(短冊形状)である。繊維方向寸法d1を長さとし、繊維直交方向寸法d2を幅と10 すると、長さd1は40㎜以下、好ましくは35㎜以下、より好ましくは30㎜以下、より一層好ましくは25㎜以下、さらに好ましくは10~20㎜(10㎜以上かつ20㎜以下)である。また、幅d2は40㎜以下、 好ましくは15㎜以下、より好ましくは0.5~5㎜(0.5㎜以上かつ5㎜以下)である。木質小薄片1の長さd1及び幅d2はいずれも平均値15 とする。(【0023】、【0028】)【図3】20カ 〔注:実施例〕上記木質ボードA内において、多数の木質小薄片1,1,…は、その繊維1a,1a,…に沿った方向である繊維方向(長さ方向)が基準方向に配向されていてもよいが、この繊維方向の配向性は必須ではなく、繊維方向がランダムに配向されていてもよい。(【0034】)5 ? 発明の効果ア 第1の発明は、木質小薄片の厚さのばらつきが小さくて均一な厚さに揃ったものになり、長さ及び幅も一定範囲内にあるので、木質ボードは大きさが一定範囲内に揃った木質小薄片が集合して均質なものとなる。そのため、木質ボードの強度が高くなるだけでなく、吸放湿による反りが発生し10 難くなり、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性が得られる。また、多数の木質小薄片が均一な大きさに揃っているので、通常の配向性ストランドボード(OSB)のように木質ボードの表面に大きな凹凸は生じず、木質ボードは表面性に優れたものとなる。また、均一な大きさの多数の木質小薄片を集合させて積層するので、その製造も容易となる。(【00115 8】)イ 第2の発明は、第1の発明よりも木質小薄片の厚さ、長さ及び幅をさらに限定することにより、木質ボードの寸法安定性及び表面性がさらに向上する。(【0019】)ウ 第3の発明は、木質ボードの密度を限定することにより、木質ボードの20 強度がさらに高くなる。(【0020】)エ 以上説明したように、本発明によると、多数の木質小薄片はばらつきの小さい均一な大きさに揃ったものになり、木質ボードの強度を高くすることができるとともに、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性及び表面性が得られ、木質ボードを容易に製造することができる。(【0022】)25 オ 〔注:実施例〕また、木質小薄片1,1,…は、節部分が除去されており、ばらつきがなくて細かい範囲内の大きさのものに保たれているので、 21マットA1全体で均質になり、このことによって木質ボードAの強度のばらつきがなくなる。つまり、大きなストランド(切削片)を用いるストランドボードでは、例えば節部分を含む不均一なマットにより部分的(スポット的)に薄くて低強度部分が生じ、強度のばらつきがでるが、それがな5 くなる。しかも、木質小薄片1,1,…も薄い方がマットA1の均質性が高くなり、木質ボードAの強度が出易くなる。一般に大きなストランド(切削片)を用いるストランドボードは強度を大きくできるのに対し、本発明では切削片よりも薄くて小さい木質薄片(切削後木質薄片)を粉砕によりさらに小さくした木質小薄片1によって木質ボードAの均質性と強度10 とを兼ねている。(【0046】)カ 〔注:実施例〕本発明に係る単層の木質ボードAは、1種類の木質小薄片1,1,…のみで構成され、その木質小薄片1,1,…の厚さtが極めて薄く、0.05~0.35㎜という狭い範囲内に収まっているので、多数の木質小薄片1,1,…は厚さtのばらつきが小さくて均一な厚さtに15 揃ったものになる。また、木質小薄片1,1,…の繊維方向寸法d1(長さ)及び繊維直交方向寸法d2(幅)も一定範囲内にあるので、木質ボードAは大きさが一定範囲内に揃った木質小薄片1,1,…が集合して均質なものとなる。そのため、木質ボードAの強度が高くなるだけでなく、吸放湿による反りが発生し難く、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性が20 得られる。また、多数の木質小薄片1,1,…が均一な大きさに揃っているので、通常の配向性ストランドボード(OSB)のように木質ボードの表面に大きな凹凸が生じることはなく、木質ボードAは表面性に優れたものとなる。また、均一な大きさの多数の木質小薄片1,1,…を集合させて積層するので、その製造も容易となる。(【0056】)25 【図6】は、本発明に係る木質ボードAの特性を他の材料のボードと比較して例示したものであり、木質ボードAは、曲げヤング、吸放湿時22の長さ変化率、平滑性がラワン合板程度に大きく、ラワン合板に比べ寸法安定性での異方性や表面性における色調・色均質性が優れている。また、木質ボードAは、配向性ストランドボード(OSB)に比べ、曲げヤングが縦横に均一であり、寸法安定性での異方性や表面性における平5 滑性、色調・色均質性が良好である。すなわち、木質ボードAは、高強度で寸法安定性や表面性に優れる。(【0058】)【図6】2 甲1発明及び本件発明との相違点の認定について10 証拠(甲1、5,10、14、15)及び弁論の全趣旨によれば、甲1発明の内容及び本件発明との相違点1、2及び1’については、本件決定が認定したとおりであると認められる。 3 相違点1、2の認定の誤りについて? 原告は、本件決定において個別に認定された相違点1、2に係る本件発明15 1の各構成(「寸法に係る構成」及び「形状等に係る構成」、併せて「寸法・形状等に係る構成」)、「密度に係る構成」及び「配向に係る構成」は、 発明の技術的課題の解決手段として、互いに関連するひとまとまりの手段と23して機能し、相乗効果を奏するものであるから、併せて一つの相違点として判断しなければならない旨主張する。 ? しかし、本件明細書には、前記1の各記載を含め、「高強度で寸法安定性や表面性に優れ、製造の容易な木質ボード」という発明の技術的課題の解決5 手段(前記1??ア)として、①「寸法に係る構成」を含む木質小薄片の厚さ、長さ及び幅の数値範囲の構成が本件発明1とほぼ同じである「第1の発明」の木質ボード(前記1?イ)とその奏する効果(前記1?ア、エ)、②「第1の発明」の木質ボードが本件発明2の厚さ、長さ及び幅の数値範囲の構成を有する「第2の発明」の木質ボード(前記1?ウ)とその奏する効果10 (前記1?イ、エ)、③「第1の発明」又は「第2の発明」の木質ボードが「密度に係る構成」を有する「第3の発明」の木質ボード(前記1?エ)とその奏する効果(前記1?ウ、エ)、④「密度に係る構成」及び「寸法・形状等に係る構成」を含む本件発明1の木質小薄片の厚さ、長さ及び幅の数値範囲の構成を有するが、「配向に係る構成」については繊維方向の配向性は15 必須ではなく、繊維方向がランダムに配向されていてもよい木質ボードA(前記1?オ、カ)とその奏する効果(前記1?オ、カ)については記載されている。しかし、「配向に係る構成」の効果は、本件発明の効果として示されておらず、「密度に係る構成」、「寸法・形状等に係る構成」及び「配向に係る構成」が、それぞれ単独で奏する効果を超えて、互いに関連して機20 能することを示す記載や相乗効果を奏することを示す記載はなく、そのように機能することが想定可能とみるべき作用機序等の記載も認められない。 ? また、本件明細書における発明の効果の記載がこのようなものである場合に、本件訴訟提起後である令和6年8月9日付けで作成された実験成績証明書?(甲17)を参酌すべきか否かという点を措くとしても、実験成績証明25 書?(甲17)には、実験結果として、本件発明1に含まれる実験例1と比べて、 24① 木質小薄片の長さを本件発明1の範囲よりも長い60㎜とした比較実験例1-1では表面性1(平滑性)に劣ること、 ② 木質小薄片の長さを本件発明1の範囲よりも長い100㎜とした比較実験例1-2では強度(曲げヤング)及び寸法安定性1(変化率)に係る物5 性のばらつきが大きく、表面性1(平滑性)に劣ること、 ③ 比較実験例2として木質小薄片がランダムではない配向をしたものは、 配向と直交方向で強度と変化率が異なる異方性があること、 ④ 比較実験例3として木質ボードの密度が低いものでは、寸法安定性1(変化率)に係る物性のばらつきが大きいこと、強度及び表面性1(平滑10 性)が劣ること、 ⑤ 比較実験例4-1及び4-2として、木質小薄片の長さが本件発明1の範囲よりも長く、木質小薄片がランダムではない配向をしたものは、配向と直交する方向での強度及び寸法安定性1(変化率)が劣り、寸法安定性2(異方性)があり、表面性1(平滑性)に劣ること、 15 が示されているにとどまる。 これらの実験結果によれば、木質小薄片の長さ、木質ボードの密度又は木質小薄片の配向性を異ならせて比較した場合、これらの要素が強度、寸法安定性又は平滑性に影響を与えることが分かるものの、「密度に係る構成」、 「寸法・形状等に係る構成」及び「配向に係る構成」が単独で奏する効果と20 その重なり合いを超えて、各構成が互いに関連して機能し、組合せによる相乗効果を奏することまでは認められない。 「実験の結論(考察)」として記載されている内容をみても、各構成が奏する上記の効果とその理由は述べられているが、各構成が互いにどのように関連して相乗効果を奏しているのかについての説明はない。 25 ? 以上のとおり、本件明細書の記載のほか、実験成績証明書(甲17)を参酌したとしても、相違点1、2に係る本件発明1の各構成が、「密度に係る25構成」、「配向に係る構成」とともに、互いに関連して相乗効果を奏するものとは認められない。 したがって、原告の前記主張は、その前提が認められないから採用することはできず、本件決定の相違点の認定に誤りがあるとはいえない。 5 4 相違点1の容易想到性判断の誤りについて? 原告は、木質小薄片の繊維方向に沿った長さについて、甲1発明の木質ボードの「40.0~115.0mm の範囲内」から本件発明の「10mm 以上35mm 以下」とすることは当業者が適宜なし得たとする本件決定の判断は、 誤りである旨主張する。 10 ? そこで、まず、甲1発明における木質薄片の長さが有する技術的意義について検討する。 甲1公報には、発明が解決しようとする課題は「木質薄片を原料とする木質板において、製造工程の簡略化が可能であり、表面と木口面の平滑性を向上でき、芯部の強度及び剛性を向上でき、木材薄片のカールや折れ曲がりに15 起因するボイドの発生を低減でき、密度を低く設定でき、耐水性を向上させて寸法安定性を向上できることのうち、少なくとも製造工程の簡略化と、表面と木口面の平滑性の向上と、強度及び剛性の向上を実現できる木質板を提供すること」(甲1公報【0008】)であって、その解決手段は「厚さの絶対値が0.05~0.50㎜の木材薄片がバインダー樹脂により接着一体20 化」及び「木材薄片の幅の絶対値が1.00~50.00㎜であること」を含むこと(甲1公報【0009】)が記載されている一方、木質薄片の長さについて、長さの絶対値の範囲が課題を解決する手段に含まれることは記載されていない。 また、発明の実施の形態における記載では、厚さの数値範囲は、強度、剛25 性、生産性、成形後の密度及び表面の平滑性の観点により(甲1公報【0011】)、また、幅の数値範囲は、接着不良による強度低下、木材薄片の変26形によるバインダーの付着困難性、ボイド(泡)発生による木材薄片の剥離や表面の平滑度の低下の観点により、それぞれ選択されること(甲1公報【0012】)が記載されているところ、長さについては「絶対値が20.0~150.0㎜、平均値が40.0~115.0㎜の範囲内であることが5 好ましい」と記載されているにすぎず(甲1公報【0012】)、その数値範囲内外で課題解決や効果に差異があることは記載されていない。 原告が指摘する記載箇所(甲1公報【0004】~【0007】)をみても、木材薄片の長さについての言及はなく、前記の好ましい数値がどのような根拠に基づき選択された数値なのかは明らかではない。 10 これらの甲1公報の記載に照らすと、甲1発明における木質薄片の長さに係る数値範囲は、少なくとも厚さ及び幅に関するものと同様の技術的意義を有するものとまでは認められないから、木質薄片の長さを記載された数値範囲外とすることが、甲1公報から認定される技術思想(甲1発明)を逸脱し、 又は齟齬を生じさせるものとはいえない。 15 ? 他方、甲1公報には、木質薄片を用いた木質板について「構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり、表面も平滑になるが、 強度、剛性は低下し、密度は増加する傾向がある。逆に構成要素の寸法を大きくすると、木材本来が持っている強度、密度に近づいて行くが、そのような木質板は不均質で、表面の凹凸も大きくなる傾向がある」こと(甲1公報20 【0003】)、「木質板を床材に応用するには、その木質板に強度、剛性、 さらに表面平滑性を持たせる必要がある」こと(甲1公報【0004】)が記載されているところ、これらの記載から把握される、木質板における木質薄片の寸法と、これを使用して得られる木質板の均質性、平滑性、強度、剛性及び密度の定性的な関係や、床材への応用における必要な特性は、木質板25 の技術分野に属する当業者であれば当然認識している技術常識であると認められる。 27このような技術常識に照らせば、甲1発明において、木質薄片の寸法を木質板の用途に応じて調整、最適化し、その「繊維方向に沿った長さ」を甲1発明の寸法よりも小さくし、相違点1に係る本件発明1の構成である「10㎜以上35㎜以下」とすることは、当業者が有する通常の創作能力の発揮と5 いえるから、当業者が容易に想到することができたものである。 なお、本件明細書の記載をみても、「寸法に係る構成」の数値範囲が臨界的意義を有するとは認められない。 ? 前記?の認定を争う原告の主張は、以下のとおり、いずれも採用することができない。 10 ア 原告は、甲1公報に、木質薄片の長さを前記の好ましい範囲よりも小さい「10㎜以上35㎜以下」とすることについての記載も示唆もないから、 容易想到とはいえない旨主張する。 しかし、既に述べたとおり、「10㎜以上35㎜以下」とすることは、 発明に係る物の用途に応じた数値範囲の好適化であるから、甲1公報に15 原告指摘の記載や示唆がなくとも、当業者には容易に想到することができたと認められる。 イ 原告は、甲1公報には長さ等の寸法を小さくすることによる欠点も記載され、種々の検討を重ねた結果、木材薄片の長さを前記の好ましい数値の範囲内とすることに到達したものであるから、動機付け等が認められ20 ない旨主張する。 しかし、前記?のとおり、甲1発明における木質薄片の長さに係る数値範囲は、課題解決手段として幅や厚さの数値と同様の技術的意義を有するものではなく、当該数値範囲が選択された具体的根拠は明らかにされていないから、当業者において、前記技術常識に基づき、これと異なる25 長さに係る数値を選択することは通常の創作能力の発揮であるというべきである。 28ウ 原告は、甲1公報に記載された実施例、比較例1とその比較結果からみて、甲1発明において、比較例1で採用された木材薄片の長さの平均値75㎜よりもさらに小さいものとすることには阻害要因がある旨主張する。 5 しかし、甲1公報記載の比較例1は、木質薄片の長さのみならず、厚さ、 幅とも、絶対値の範囲及び平均値が実施例1と異なり、芯層と表面層でも厚さが異なるものであり(甲1公報【0020】、【0022】)、 比較例1は表面及び木口面の平滑性が実施例1の木質板に比べて劣り、 実施例1よりも密度が大きく、曲げ強さ及び曲げヤング係数がやや小さ10 い(甲1公報【0020】、【0023】)との比較結果は、木材薄片の厚さ、幅及び長さの寸法を調整した結果生ずる一つのパターンを示したものにすぎず、甲1公報に接した当業者が、これらの比較結果及び前記?の技術常識を踏まえ、長さを含む木質薄片の寸法を木質板の用途に応じて調整、最適化することを妨げるものとはいえない。例えば、木質15 板及びその製造方法の発明である甲3公報の実施形態において、芯層に使用される木片は「好ましくは」長さ1~50mm、「更に好ましくは」長さ20~25mm(甲3公報【0006】)、表裏層に使用される木片は「好ましくは」長さ6~12mm(甲3公報【0008】)とされていることも踏まえると、甲1発明の木材薄片の長さを本件発明1(10mm20 以上35mm 以下)と同様のものにすることに、阻害要因があると認めることはできない。 エ 原告は、実験成績証明書?(甲17)の実験例1(本件発明1の構成としたもの)と比較実験例1-1及び比較実験例1-2(木質小薄片の長さを甲1発明の範囲としたもの)を対比すると、いずれも強度(MOE)が25 「〇」であるから、本件発明1は、木質小薄片の長さが小さくても強度が低下しないという、前記?の技術常識とは異なる特段の効果、顕著な効果29を奏する旨主張する。 しかし、実験成績証明書?(甲17)の記載によれば、上記実験結果が示すのは、実験例1、比較実験例1-1及び比較実験例1-2とも、強度(曲げヤング:MOE)が「〇」とされる「3.5GPa以上7.05 GPa未満」の範囲であったことであって、当該範囲内で実験例1の強度が低下していないことまでは示されていない。 ? したがって、相違点1に係る構成は、長さ以外の木質小薄片の寸法部分も含め、甲1発明及び技術常識に基づいて当事者が容易に想到することができるものであり、本件決定の容易想到性判断に誤りはない。 10 5 相違点2の容易想到性判断の誤りについて? 原告は、相違点2の「形状等に係る構成」が実質的な相違点ではないとする本件決定の判断は、誤りである旨主張する。 ? しかし、本件発明の木質小薄片の「細長形状に大きさと形状が均質に揃う」とは、本件明細書の記載(【0013】~【0018】、【0054】)に15 よれば、木質小薄片の厚さが「狭い範囲内」にあって「ばらつきが小さくて均一な厚さに揃」い、長さ及び幅が「一定範囲内にある」ことであり、「狭い範囲内」の具体的内容は特定されていない。 そして、本件発明1の「寸法に係る構成」のほか、厚さ及び幅に関する数値範囲はいずれも平均値であり(【0017】、【0027】、【00220 8】)、この「平均値」の計算対象となる寸法の数値範囲を示すものではなく、また、平均値と寸法の数値範囲の相関関係は本件明細書に記載がないことから、木質小薄片の各寸法が収まる範囲を限定するものではないといえる。 そして、甲1発明において、木質薄片の各寸法の数値の範囲は、平均値、 絶対値ともその範囲内に多数の木質薄片の寸法が収まっていることから、 25 「狭い範囲内」にあって「ばらつきが小さくて均一な厚さに揃」い、長さ及び幅が「一定範囲内にある」といえる。 30? さらに、前記4?のとおり、甲1発明の木質薄片の長さについては、技術常識に照らし、木質板の用途に応じて調整、最適化し、本件発明1の構成である「10㎜以上35㎜以下」とすることは、当業者が容易に想到することができたものであり、この点は、厚さ及び幅を本件発明1の構成と全く同じ5 ものとすることについても同様といえる。 そして、本件明細書の記載(【0013】~【0017】、【0054】)によれば、少なくとも、本件発明1の各平均値の数値範囲内であれば、「細長形状に大きさと形状が均質に揃」うものであることは明らかである。 ? また、「節部分がない」との構成については、特開平11-58330号10 公報(甲4)の「…OSL(Oriented StrandLumber)、PSL(ParallelStrand Lumber)等の木質系再構成材を木質系構造用材として活用することが多くなりつつある。これらの細片化木材を用いた再構成材は、原木を細片化してこれを再構成するために、原木から切り出した製材品のように節等による欠陥が存在せず、性能が安定してより均質な強度が得られるという有用15 な特徴を持つ。」(【0003】)との記載から、原木を細片化した細片化木材を用いた再構成材が通常有する構成であると認められる。 また、本件明細書の記載(【0046】、前記1?オ)によれば、「節部分がない」ことは、木質小薄片の寸法を本件発明1の各平均値の数値範囲内とすることによる効果であって、少なくとも本件発明1の各平均値の数値範20 囲内であれば、「節部分がない」構成を備えるものといえる。 ? そうすると、相違点2に係る本件発明の構成は、実質的な相違点ではないか、そうでなくとも、実質的に相違点1と異なる相違点ではないといえるから、甲1発明及び技術常識に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。 25 原告の主張は、いずれも、以上の認定を左右するものではない。 ? したがって、相違点2に係る本件発明の構成は、実質的に相違点ではない31か、甲1発明及び技術常識に基づいて当事者が容易に想到できるものであり、 本件決定の容易想到性判断に誤りはない。 6 相違点1’の容易想到性判断の誤りについて前記したところによれば、本件発明2に係る「長さ10mm 以上20mm 以下、 5 幅0.5mm 以上5mm 以下」の形状を選択し、相違点1’に係る本件発明2の構成とすることも、当業者が通常の創作能力を発揮することにより容易に想到することができたものと認めるのが相当であるから、相違点1’が容易想到であるとする本件決定の判断は、結論において誤りはない。 7 結論10 以上のとおり、本件決定の甲1発明に基づく本件発明の進歩性判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は認められないから、原告の請求は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部15裁判長裁判官清 水 響20 裁判官菊 池 絵 理裁判官25 頼 晋 一32(別紙特許公報写し、異議の決定書写し省略)33 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
|