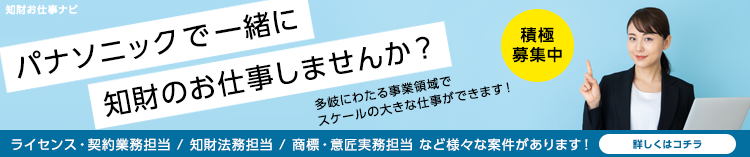| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(ネ)
10058号
損害賠償請求控訴事件
|
|---|---|
|
令和7年2月13日判決言渡 令和6年(ネ)第10058号 損害賠償請求控訴事件 (原審・大阪地方裁判所令和4年(ワ)第8785号) 口頭弁論終結日 令和6年11月13日 5判決 控訴人X 同訴訟代理人弁護士 浅田隆幸10 同堀井秀知 被控訴人徳島県 同訴訟代理人弁護士 田中浩三15 同坂田知範 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/02/13 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
20 (注)本判決で用いる略語の定義は、別に本文中で定めるもののほか、次のとお りである。 原告 :控訴人(1審原告) 被告 :被控訴人(1審被告) 甲2契約 :平成27年10月1日に原被告間で締結された「水車を利用25 した青ノリの採苗技術の開発」に関する共同研究契約(甲 2)。 1 本件共同研究:甲2契約に基づいて実施された研究(平成28年9月から平 成29年7月31日までを研究期間として行われた再度の 共同研究を含む。) 支援センター:徳島県立農林水産総合技術支援センター 5 本件公表行為:支援センターが、平成29年度の事業報告書において、「水 車を利用した青ノリ類の効率的な採苗技術の開発」と題す る記事を掲載し、同内容を支援センターのウェブサイトに 掲載した行為(甲3、乙13) 本件公表内容:本件公表行為に係る記事の内容10 本件特許 :原告を特許権者とする特許第6878720号(甲6) 徳島県漁連 :徳島県漁業協同組合連合会 講習会資料 :「スジアオノリ講習会資料」「平成10年3月 徳島県水産 試験場鳴門分場」と記載された講習会資料(乙5は被告が 原審で提出した抜粋であり、甲26は原告が当審で提出し15 た全文である。) 本件記載部分:講習会資料のうち、乙5において黄色でマーキングされた 「2) 水車採苗の技術が開発されれば、芽数の調整がで きる」、「やはり、水車採苗で付着を確認しながら採苗す るのが理想であろう。」との各記載部分20 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する令和4年10月21日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要25 本件は、被告との間で「水車を利用した青ノリの採苗技術の開発」に関する共 同研究契約(甲2契約)を締結した原告が、①被告による本件公表行為は、甲2 2 契約に反し、原告の承諾なく本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たる、 ②被告は本件特許に係る原告の特許権取得を妨害し、研究成果の特許出願に係る 甲2契約上の義務に違反したと主張して、各債務不履行に基づき、損害賠償金1 億円(明示的一部請求)及びこれに対する令和4年10月21日(訴状送達日の 5 翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め る事案である。 原審が、①本件公表行為は本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たると は認められず、②被告に原告の特許権取得を妨げる行為があったとは認められな いとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。 10 1 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける原告の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の 3、4及び第3(原判決2頁15行目から9頁12行目まで)に記載のとおり であるから、これを引用する。なお、引用文中の「別紙」は「原判決別紙」と 読み替える。 15 2 当審における原告の補足的主張 ? 争点1(本件公表行為が承諾を得ない公表行為であって、甲2契約におけ る被告の債務不履行となるか)について ア 講習会資料について 原判決は、水車を用いて青ノリの人工採苗をすることができるとの技術20 思想自体は本件共同研究以前に存在し公知となっていたと認定した。 しかし、その認定の根拠とされた講習会資料(乙5)は、本件記載部分 が、他の箇所の字体、書式と異なっていること等から、改ざんされた疑い が濃いものである。 また、原告が情報開示請求手続を通じて入手した資料全文(甲26)を25 みると、①乙5の本件記載部分に対応する箇所の字体が乙5のものと異な っていること、②全体的に、手書きの部分があったり、字体が不統一であ 3 ったり、段落番号やページ番号その他に多数の不備があること、③タンク 式人工採苗の講習会において、「今後の課題」などとして水車採苗に言及 することはあり得ないこと、④水車採苗による「芽数の調整」の方法が不 明であること等から、やはり、改ざんされた疑いが濃いものである。 5 甲26及び乙5が改ざんされたものであることは、同資料を作成したA (以下「A氏」という。)の話からも裏付けられる。 また、被告がその後行った青ノリの養殖技術の研究(甲27~29)を みても、タンク式の方法を研究しており、水車採苗への言及がないことか ら、前記講習会で水車採苗について言及されたとは考えられない。 10 イ 青ノリの水車採苗の周知性について 青ノリの水車採苗について、A氏は研究をしておらず、黒ノリ、青ノリ を養殖している各県の業者においても知識はなく、実際に行われていない のであるから、周知の技術ではない。 ウ 本件公表内容について15 本件公表内容は、平成28年の本件共同研究の成果である。 本件公表内容のうち、1時間に40枚のノリ網への胞子付着が可能であ る旨の記載は、平成28年の本件共同研究の成果を元に、平成29年に原 告が独自に行った研究結果を、被告の担当者が原告から聞き取り、そのま ま記載したものである。 20 なお、被告は、本件共同研究のデータを原告に開示していないし、被告 が本件共同研究の結果として主張する内容は、A氏によれば「平成9年の 公開特許公報時にすでに解明されており、何ら研究成果でもない」とのこ とであるから、実際の本件共同研究の結果ではない。 エ 事前の了解等について25 被告は、原告との間で共同研究契約を締結した以上、青ノリ水車採苗に 関してウェブサイトに掲載するのであれば、原告に告知し、了解を求める 4 べきである。 ? 争点2(被告に、原告が本件特許権を取得するにあたっての妨害行為があ ったか、あったとして甲2契約の債務不履行となるか)について ア 本件共同研究においては、水車採苗によりノリ網に青ノリの胞子が付く 5 かどうかが最重要点であった。この点さえ分かれば、青ノリのタンク式人 工採苗の技術・知識を有するものであれば、原告が特許権を取得した本件 発明を導き出すことができる。 イ 本件特許が「種網を50反以上重ねて積層させる工程」という範囲に限 定されることとなったのは、本件公表行為のためである。 10 原告は、本件公表行為があったため、本件特許取得のためにあらゆる研 究成果を公表することになったが、被告が甲2契約の義務を履行していれ ば、青ノリの水車採苗が可能であることのみで特許権を取得することがで きたのである。 第3 当裁判所の判断15 1 当裁判所も、本件公表行為は本件共同研究の研究成果を公表する行為に当た るとは認められず、被告に特許権の取得を妨げる行為があったとは認められな いから、原告の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、後記2の とおり当審における原告の補足的主張に対する判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」第4の1から3まで(原判決9頁13行目から16頁4行目20 まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 2 当審における原告の補足的主張に対する判断 ? 争点1(本件公表行為が承諾を得ない公表行為であって、甲2契約におけ る被告の債務不履行となるか)について ア 講習会資料について25 原告は、青ノリの水車採苗について言及された平成10年3月付けの講 習会資料(甲26、乙5)は、改ざんされた疑いがある旨主張する。 5 しかし、甲26及び乙5をみても、原告が指摘する講習会資料中の本件 記載部分が、前後の文章と比較して字体や書式が異なるとも、甲26と乙 5で字体が異なるとも認められない。 原告は、講習会資料の様々な不備等を指摘するが、いずれも、原告の憶 5 測を述べたものにすぎず、講習会資料中の本件記載部分が改ざんされたこ とを合理的に疑わせるに足りるものではない。被告がその後行った青ノリ の養殖技術の研究(甲27~29)に水車採苗への言及がないからといっ て、これにより本件記載部分が改ざんされたことを推認することはできな い。さらに、原告の主張する「A氏の話」を前提としても、A氏は、甲210 6は手書き部分の筆跡や資料の内容からしてA氏本人の資料であるが、3 0年も前の講習会の資料に言及されている水車採苗の中身の詳細は覚えて いないと述べているにすぎず、講習会資料が改ざんであることを認めてい るわけではない。したがって、「A氏の話」は、本件記載部分が改ざんさ れたものであることを疑うべき根拠とならない。 15 以上によれば、原告の指摘する点を考慮しても、講習会資料の本件記載 部分が改ざんされたものと認めることはできず、平成10年3月当時にお いて、青ノリ(スジアオノリ)について水車採苗を行うという着想自体は 既に存在していたことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。 イ 青ノリの水車採苗の周知性について20 原告は、青ノリの水車採苗が当業者に周知の技術ではなかった旨主張す る。確かに、本件全証拠によっても、本件公表行為の当時、青ノリの水車 採苗のための技術が当業者に広く知られていたことを認めるに足りない。 しかし、前記アのとおり、青ノリについて水車採苗を行うという着想自体 は、既に平成10年当時から知られていたと認められる。また、共同研究25 契約書(甲2)及び再度の共同研究に係る共同研究申込書(案)(甲11) によれば、本件共同研究の研究課題は、「水車を利用した青ノリの採苗技 6 術の開発」であり、具体的な研究内容は、①母藻から遊走子を放出させる 条件の解明、②水車の操作方法の確立、③のり網への遊走子付着の確認で ある。そして、本件共同研究が開始された当時、黒ノリについては既に水 車採苗技術が確立していたこと(乙2、13、14、原審証人B1~2頁) 5 を踏まえると、青ノリについて水車採苗を行うという着想自体は、格別想 起することが困難なものであったとは考えられないから、それは本件共同 研究の前提ではあっても、本件共同研究の成果ではないというべきである。 そうすると、結局、被告が「青ノリについて水車採苗を行うこと」を公表 したことにより、本件共同研究の成果を公表したことになると認めること10 はできない。 ウ 本件公表行為について 原告は、本件公表内容は本件共同研究の成果である旨主張するところ、 前記引用した原判決の第4の2?(原判決14頁8行目から18行目まで) のとおり、本件公表内容は、本件共同研究の成果である水車による採苗の15 際の好適な状況や条件を述べるものではない。本件公表内容は、本件共同 研究の研究課題(前記イ)について、甲7の研究成果資料に記載されてい るような具体的な技術内容を明らかにするものではないから、本件共同研 究の成果ということはできない。 その上、原告の主張によっても、本件公表内容の少なくとも一部は、本20 件共同研究終了後に原告が独自に行った研究結果であるというのであるか ら、当該部分は、そもそも本件共同研究の成果自体ではないことは明らか である。 その他、原告は、原告主張の「A氏の話」に基づき、被告の主張する本 件共同研究の結果は、平成9年当時既に解明されていた事実であって、実25 際の研究成果ではない旨主張するが、これを裏付ける証拠はないから、同 主張を採用することはできない。 7 エ 事前の了解等について 原告は、原告との間で甲2契約を締結した以上、被告は、青ノリ水車採 苗のことに関してウェブサイトに掲載するのであれば、原告に告知し、了 解を求めるべきであった旨主張する。 5 しかし、甲2契約においては、共同研究に係る研究成果を公表する場合 にあらかじめ相手方に通知し承諾を得なければならないことは規定されて いるが(甲2・8条2項)、研究成果以外の事項、例えば青ノリの水車採 苗が可能であること自体を秘匿すべき旨の規定はなく、原被告間でそのよ うな合意がなされたことを窺わせる証拠もない。 10 かえって、原告は、遅くとも令和2年1月に本件公表行為があったこと を知りながら(原告本人)、当時既に被告と紛争状態にあったにもかかわ らず、原告及びその代理人弁護士が、本件公表行為が本件共同研究の成果 の公表に当たると主張したのは、同年8月11日に原告が単独で本件特許 を出願し、同年12月3日付けの拒絶理由通知書の理由3(進歩性)にお15 いてスジアオノリの葉片を水車式採苗装置に投入することにより胞子を網 に付着させることが可能であることが周知である根拠として本件公表内容 (拒絶理由書の引用文献2)が引用され(乙11)、補正を経て令和3年 5月7日に本件特許が登録に至った(甲6)後の同年9月2日である(乙 6の11)。 20 これらの点に照らすと、原告自身においても、甲2契約を締結した当時、 本件公表内容が秘匿すべきものであると考えていたとはにわかに認め難い。 オ 以上によれば、本件公表行為が甲2契約に違反する旨の原告の主張は、 いずれも採用することができない。 ? 争点2(被告に、原告が本件特許権を取得するにあたっての妨害行為があ25 ったか、あったとして甲2契約の債務不履行となるか)について ア 原告は、本件共同研究においては、水車採苗によりノリ網に青ノリの胞 8 子が付くかどうかが最重要点であったから、その旨を公表した本件公表行 為は甲2契約の債務不履行となる旨主張する。 しかしそもそも、本件公表行為において「スジアオノリの葉片を水車式 採苗装置に投入することにより胞子を網に付着させることが可能」である 5 ことが明らかにされたからといって、直ちに本件共同研究の具体的内容を 明らかにしたことにならないのは、前記?ウのとおりである。 イ 原告は、本件公表行為により、本件特許の特許請求の範囲が限定される ことになった、本件特許を取得するに当たり、青ノリの水車採苗が可能で あることにとどまらず原告のあらゆる研究結果を公表せざるを得なくなっ10 た旨主張する。 しかし、前記のとおり、「青ノリについて水車採苗を行う」という着想 自体は、平成10年頃から周知であったと認められるところ、現実に「青 ノリについて水車採苗を行うことが可能になったこと」については、当該 可能になったことを示す具体的な技術的裏付けや実施例が開示されない限15 り、通常、単に「可能になった」と述べるだけで特許が付与されることは ないはずである。本件公表行為が、本件共同研究の結果である技術の具体 的内容を公表するものではないことは、前記のとおりであるから、原告が 本件特許権を取得するためには、本件公表行為の有無にかかわらず、自分 の研究結果である具体的技術内容を開示しなければならなかったと考えら20 れる。そうすると、本件において、本件公表行為により、原告の特許取得 が妨害されたという関係にあるものとは認められない。すなわち、本件公 表行為が本件特許の審査過程において引用されたからといって、本件公表 行為が原告による本件特許権の取得にあたっての妨害行為に当たり、甲2 契約の債務不履行となると評価することはできない。 25 3 なお、原告は、本件口頭弁論終結後、令和6年12月16日付け準備書面? 及び意見書(甲30)の提出とともに口頭弁論再開を申し立てたが、その実質 9 的な内容は、原審における主張や前記の当審における補足的主張を繰り返すも のであり、口頭弁論再開の必要性があるとは認められない。 4 結論 よって、原告の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない 5 から、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 |