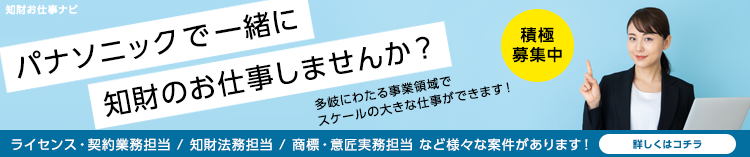| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行コ)
10006号
出願却下処分取消請求控訴事件
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/01/30 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
|
判例全文
令和7年1月30日判決言渡 令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第5001号) 口頭弁論終結日 令和6年11月11日 5 判 決 控 訴 人 X 同訴訟代理人弁護士 佐 藤 安 紘 同 小 西 絵 美 10 同 末 吉 亙 同補佐人弁理士 中 島 崇 晴 同 設 楽 修 一 同 藤 田 健 同 山 口 真 紀 15 同 高 須 甲 斐 同 石 田 理 同 田 中 宏 明 被 控 訴 人 国 20 処 分 行 政 庁 特 許 庁 長 官 同 指 定 代 理 人 小 西 俊 輔 同 井 坂 景 子 同 坂 本 千 鶴 子 25 同 大 谷 恵 菜 同 中 島 あ ん ず 1 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付 5 加期間を30日と定める。 事 実 及 び 理 由 (注)本判決の本文中で用いる略語の定義は、別に定めるほか、次のとおりである。 原告 :控訴人(1審原告) 被告 :被控訴人(1審被告) 10 AI発明 :人工知能(AI)が自律的にした発明 国内書面 :特許法184条の5第1項所定の書面 特許協力条約:千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力 条約(昭和53年条約第13号) TRIPS協定:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(平成6年条約 15 第15号) 本件出願 :原告が特許協力条約に基づき行い特許法184条の3第1項 の規定により特許出願とみなされた特願2020-5430 51に係る国際出願 本件国内書面:原告が本件出願に係る国内手続において提出した国内書面 20 (発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明し た人工知能」との記載がある。) 本件処分 :特許法184条の5第3項の規定に基づき本件出願を却下し た特許庁長官の処分 なお、「AI発明」の略語の定義は、便宜上、原告の主張に基づいて定める 25 が、本件において、特許出願に係る発明を人工知能(AI)が自律的にした事 実の有無は、争点となっていない。また、「AI発明」の略語は、人工知能 2 (AI)の成果物が特許法の定める「発明」に当たり得ることをあらかじめ前 提とするものではない(この点は、後記のとおり、本件の争点の一つであ る。)。 第1 控訴の趣旨 5 1 原判決を取り消す。 2 特許庁長官が特願2020-543051号について令和3年10月13日 付けでした出願却下の処分を取り消す。 第2 事案の概要 原告は、本件出願をした上、本件出願に係る国内手続において、特許庁長官に 10 対し、本件国内書面を提出した。特許庁長官は、原告に対し、国内書面に発明者 の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたが、原告がこれに従った 補正をしなかったため、本件処分をした。 本件は、原告が被告に対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであ り、AI発明に係る特許出願の手続において発明者の氏名は必要的記載事項では 15 ないから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求める事案である。 原審は、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られると解するのが相当で あるから、国内書面に「発明者の氏名及び住所又は居所」を記載するよう定める 特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者の氏名を記載 しなかったことにつき、特許庁長官が同条2項3号に基づき補正を命じた上、同 20 条3項の規定に基づき本件処分をしたことは適法であるとして、原告の請求を棄 却したところ、原告がこれを不服として控訴した。 1 関連法令の定め 別紙「関連法令の定め」のとおり 2 前提事実(争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる 25 事実) ? 原告は、令和元(2019)年9月17日、特許協力条約に基づき、発明 3 の名称を「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」(注 :明細書の翻訳文(甲1の3)による。)とする発明について、世界知的所 有権機関の国際事務局を受理官庁として、外国語(英語)により本件出願 (PCT/IB2019/057809)をした。本件出願は、同条約4条 5 ?(ⅱ)の指定国に日本を含むものであり、特許法184条の3第1項の規定 により、同日にされた特許出願とみなされた(甲1の3、甲8の2)。 ? 原告は、令和2年8月5日、特許庁長官に対し、本件出願(特願2020 -543051)に係る国内手続として、本件国内書面及び特許法184条 の4第1項所定の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文 10 を提出した。その際、原告は、本件国内書面における【発明者】の【氏名】 欄(特許法施行規則・様式第53参照)に、「ダバス、本発明を自律的に発 明した人工知能」と記載するとともに、「本出願に係る発明は、人工知能 (AI)によって自律的になされたものであり、発明者として、『ダバス、 本発明を自律的に発明した人工知能』と明記しております。」と記載した上 15 申書を提出した(甲1の1~9)。 ? 特許庁長官は、令和3年7月30日、原告に対し、国内書面には発明者の 氏名を記載しなければならず(特許法184条の5第1項2号)、発明者と して記載をすることができる者は自然人に限られるが、本件国内書面の発明 者の氏名欄には発明者として自然人でない者が記載されているものと認めら 20 れるから、発明者の氏名欄に自然人の氏名を記載する補正を行わなければな らないとして、同条2項の規定により、手続補正指令書(方式)の発送日 (同年8月3日)から2月以内に、本件国内書面の発明者の氏名欄に自然人 の氏名を記載する補正をすべきことを命じた(甲2)。 ? 原告は、同年9月30日、特許庁長官に対し、特許法にはAIを発明者と 25 することを禁ずる規定は存在しないから、発明者は自然人に限られるとの解 釈に根拠はなく、AIによる発明を特許権により保護する必要性もあること 4 から、補正による応答は不要である旨を記載した上申書を提出し、指定され た期間内に補正をしなかった(甲3)。 ? 特許庁長官は、同年10月13日、前記?で指定した期間内に本件国内書 面に係る提出手続の補正がなかったとして、特許法184条の5第3項の規 5 定に基づき、本件出願を却下する本件処分をした(同月19日発送、甲4)。 ? 原告は、令和4年1月17日付けで、本件処分について、行政不服審査法 に基づく審査請求をし、審査庁(特許庁長官)は、同年10月12日、上記 審査請求を棄却する旨の裁決をした(甲5~8の2)。 ? 原告は、令和5年3月27日、本件処分は違法である旨主張して、本件処 10 分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 3 争点 ? 特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られ るか ? 国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必 15 要的記載事項であるか 第3 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の従前からの主張は、別紙「当事者の主張」のとおりで ある。また、当審における原告の補足的主張は、次のとおりである。 1 特許法上の「発明」に関する最高裁判決(最高裁第三小法廷昭和44年1月 20 28日判決・民集23巻1号54頁、最高裁第一小法廷昭和52年10月13 日判決・民集31巻6号805頁、最高裁第三小法廷平成12年2月29日判 決・民集54巻2号709頁、最高裁第一小法廷昭和28年4月30日判決・ 民集7巻4号461頁)をみても、客観的な反復可能性など客体の面を重視し ており、発明が自然人によって創作されたか否かという主体の面は重視されて 25 いない。 2 発明が自然人による発明に限定された場合には、AI発明を生み出す意欲が 5 減退する、生み出されても公開されず秘匿される等の弊害も生ずることになり、 発明の保護及び利用を図ることにより産業の発達に寄与するという特許法の目 的にも反することになる。 3 なお、欧州特許庁を含む諸外国の判断は、あくまでも「発明者」の該当性に 5 ついてAIは「発明者」に該当しないと判断しているに留まり、いずれの判決 も、AI発明の「発明」の該当性についての解釈に基づいて出願を却下したも のではない。 第4 当裁判所の判断 当裁判所も、本件処分は適法であり、原告の請求は理由がないと判断する。 10 その理由は、以下のとおりである。 1 争点?(特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに 限られるか)について ? 特許法上の「発明」と特許を受ける権利について ア 特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、も 15 って産業の発達に寄与することを目的とし(同法 1 条)、特許権は、同法 所定の出願、審査の手続を経て、設定の登録により発生する(同法66 条1項)と規定している。すなわち、特許権は、特許法により創設され、 付与される権利であり、特許を受ける権利もまた、同法により創設され、 付与される権利である。特許法は、特許権及び特許を受ける権利の実体 20 的発生要件や効果を定める実体法であると同時に、特許権を付与するた めの手続を定めた手続法としての性格を有する。 イ 特許法29条1項柱書は、「産業上利用することができる発明をした者 は、…その発明について特許を受けることができる。」と規定しており、 同項の「発明をした者」は、特許を受ける権利の主体となり得る者すなわ 25 ち権利能力のある者であると解される。 また、同法35条1項にいう「従業者等」が自然人を指すことは、文 6 言上、同項の「使用者等」に法人、国又は地方公共団体が含まれている のに対し、「従業者等」には法人等が含まれていないことから明らかで ある。そして、同条3項は、「従業者等がした職務発明」について、一 定の場合に特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属する場合がある 5 ことを定めているが、同項の規定も発明をするのは自然人(従業員等) であることを前提にしている。特許法上、「特許を受ける権利」の発生 及びその原始帰属者について定めた規定は、上記の同法29条1項柱書 及びその例外を定める同法35条3項以外には、存在しないから、特許 法上、「特許を受ける権利」は、自然人が発明者である場合にのみ発生 10 する権利である。そして、本件で問題となっている国際出願に係る国内 書面のほか、特許出願の願書(特許法36条1項2号)、出願公開に係 る特許公報(同法64条2項3号)、国際出願の国内公表に係る特許公 報(同法184条の9第2項4号)、設定登録に係る特許公報(同法6 6条3項3号)については、いずれも「発明者の氏名」を記載又は掲載 15 するものとされ、それぞれ、特許出願人、出願人又は特許権者について 「氏名又は名称」を記載又は掲載するものとされていることと対比して も、発明者については自然人の呼称である「氏名」を記載又は掲載する ことを規定するものであって、職務発明の場合も含め、発明者が自然人 であることが前提とされている。 20 ウ そうすると、特許法は、特許を受ける権利について、自然人が発明をし たとき、原則として、当該自然人に原始的に特許を受ける権利が帰属する ものとして発生することとし、例外的に、職務発明について、一定の要件 の下に使用者等に原始的に帰属することを認めているが、これら以外の者 に特許を受ける権利が発生することを定めた規定はない。また、同法に定 25 める「特許を受ける権利」以外の権利に基づき特許を付与するための手続 を定めた規定や、自然人以外の者が発明者になることを前提として特許を 7 付与するための手続を定めた規定もない。したがって、同法に基づき特許 を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られる と解するのが相当である。 エ(ア) これに対し、原告は、特許法29条1項柱書は「AI発明については 5 特許を受ける権利が発生しない」などと規定しているわけではなく、法 人が発明者とならないとの解釈についても同法35条3項と併せて初め て導き出されるものであり、同項に相当する規定がないAI発明につい て、同法29条1項柱書のみから、特許を受ける権利が発生しないと解 することはできない旨主張する。 10 しかし、特許を受ける権利は、特許権と同じく特許法により創設され、 付与される権利であるから、権利能力のない存在が発明した発明につい て特許を受ける権利が発生する旨の規定や、その場合の権利の帰属者を 定める規定がないのに、これを否定する規定がないことだけを理由に、 特許法上、権利能力のない存在が行った「発明」について特許を受ける 15 権利が発生するとは認められない。 そもそも、特許法が予定している「特許を受ける権利」の解釈は、特 許法29条1項柱書の文言、同法の他の規定の文言との整合性を検討し た上でされるべきものであり、検討した結果、同項柱書にいう「発明を した者」が自然人をいうものと解されることは、前記ウのとおりである。 20 したがって、原告の前記主張は理由がない。 (イ) 原告は、前記各最高裁判決を引用し、発明が自然人によって創作さ れたか否かという主体の面は重視されていない等と主張する。しかし、 これらの最高裁判決は、いずれも発明の要件としての技術的完成度や 自然法則の利用等が問題となった事案であって、「発明」の主体が争 25 点となった事案ではない。確かに、特許法2条1項の規定する「発明」 の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)中 8 には、発明者が誰であるかという点は明示的に含まれてはいないけれ ども、特許法上、特許を受けるための手続については、これまで検討 したとおり、権利能力のない存在を発明者とする発明について特許を 付与するための手続は定められていない。したがって、仮に、原告が 5 主張するように特許法上の「発明」の概念自体は自然人を発明者とす る場合に限られないと解したとしても、権利能力のない存在を発明者 とする「発明」について、同法に基づく手続により特許権を付与する 余地がないことに変わりはない。 (ウ) 原告は、AIであるダバスがした発明について、善意の占有者(民法 10 189条1項、205条)又は所有者(同法206条、89条1項)の 果実取得権に基づき、本件出願に係る発明についての特許を受ける権利 を有していると主張する。 しかし、発明という情報を客体として保護する場合の財産権の具体的 内容は、特許法その他の個別の法律により決まるべき性質のものである。 15 AIは有体物ではないから、所有権の対象にはならず、仮に、AIの使 用者が民法205条の規定にいう財産権を行使している者に該当すると 考えた場合でも、「AI発明について特許を受ける権利」は、「物の用 法に従い収取する産出物」又は「物の使用の対価として受けるべき金銭 その他の物」(民法88条1項及び2項)のいずれにも該当しない。前 20 記のとおり、AI発明について特許を受ける権利が発生する根拠規定自 体存在しないのであるから、現行法上、これを財産権の行使に係る果実 に該当するものと解することはできない。そもそも、AIに係る当該財 産権の内容として、いかなるものを考えるべきかどうかということ自体、 今後の検討課題と言わざるを得ない。特許法が認めていない特許を受け 25 る権利が、これらの民法の規定に基づいて発生すると解することはでき ず、本件において、民法89条を適用し、又は準用することもできない 9 というべきであるから、原告の主張は失当である。 (エ) 原告は、日本の特許法は、英国、オーストラリア又はニュージーラン ドのように特許を受ける権利の原始的帰属を発明者に限定する趣旨の条 文も、米国のように特許出願人となり得る主体を限定する趣旨の条文も 5 定めていないから、特許を受ける権利の原始的帰属や特許出願人となり 得る主体が限定されていないと主張する。 しかし、特許法の解釈として、自然人が発明者となる発明の場合に特 許を受ける権利の発生及び原始的帰属が限定されていると解すべきこと は、これまで述べたとおりである。 10 (オ) 原告は、特許法の制定当時、AI発明という概念やこれに伴う法律問 題は存在しておらず、特許法が自然人による発明のみを前提にして制定 されたことは明らかであるから、特許法がAI発明に関する規定を設け ていないことは、AI発明の保護を一律に否定する理由にはならないと 主張し、また、AI発明は現に誕生して利用され、今後も増加が予想さ 15 れるから、産業の発達に寄与するという特許法の目的に照らし、できる 限り保護を認めるよう解釈運用すべきであって、自然人による発明に限 定した場合には、AI発明を生み出す意欲が減退する、生み出されても 公開されず秘匿される等の弊害も生ずることになり、産業の発達に寄与 するという特許法の目的にも反する等と主張する。 20 特許法の制定当初から直近の法改正に至るまで、近年の人工知能技術 の急激な発達、特にAIが自律的に「発明」をなし得ることを前提とし た立法がなされていないことは、原告が主張するとおりである。 しかし、特許権は天与の自然権ではなく、「発明を奨励し、もって産 業の発達に寄与する」ことを目的とする特許法に基づいて付与されるも 25 のであり、その制度設計は、国際協調の側面も含め、一国の産業政策の 観点から議論されるべき問題である。 10 例えば、次世代知財システム検討委員会報告書(平成28年4月、知 的財産戦略本部検証・評価・企画委員会、次世代知財システム検討委員 会、乙10)においては、人工知能による自律的な創作(AI創作物) について、「『情報量の爆発的な増大』という形で、人間による創作活 5 動を前提としている現在の知財制度や関連する事業活動に影響を及ぼし ていくと考えられる。人工知能は、人間よりはるかに多くの情報を生成 し続けることが可能と考えられるからである。」、「AI創作物が自然 人の創作物と同様に取り扱われるとなると、それは即ち、人工知能を利 用できる者(開発者、AI所有者等)による、膨大な情報や知識の独占、 10 人間が思いつくような創作物はすでに人工知能によって創作されてしま っているという事態が生じることも懸念される。」等の指摘がされてい る。 すなわち、AI発明に特許権を付与するか否かは、発明者が自然人で あることを前提とする現在の特許権(原則として、特許権は特許出願の 15 日から20年の存続期間を有し、特許権者は業として特許発明を実施す る権利を独占し(特許法68条本文)、侵害者に対する差止請求権(同 法100条)及び損害賠償請求権を有する等)と同内容の権利とすべき かを含め、AI発明が社会に及ぼすさまざまな影響についての広汎かつ 慎重な議論を踏まえた、立法化のための議論が必要な問題であって、現 20 行法の解釈論によって対応することは困難である。原告が主張する発明 者を自然人に限定した場合の弊害等も、これらの立法政策についての議 論の中で検討されるべき問題である。 そうすると、本件処分時点(及び現時点)で特許法がAI発明の存在 を前提としていないことは、特許権付与によりAI発明を保護するとい 25 う立法的判断がなされていないことを意味し、この場合において、単純 にAI発明を現行制度の特許権の対象とするような法解釈をすることが、 11 直ちに「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ことにつながる ということはできない。 (カ) 原告は、TRIPS協定27条1項は、新規性、進歩性及び産業上の 利用可能性のある発明について、自然人がしたか否かにかかわらず、特 5 許法上の保護を与える義務を規定しているから、特許法がAI発明の保 護を排除していると解釈することは、同協定の規定に反することになる 旨主張する。 しかし、TRIPS協定には、原告の指摘する27条1項を含め、同 項にいう「発明」についての定義はなく、前記(オ)のとおり、近年に至 10 るまで、AIが自律的に「発明」をなし得るという事態は生じていなか ったことからすると、同協定がAI発明に特許法上の保護を与える義務 を規定していると解することはできない。 オ 以上のとおり、原告の主張は、いずれも採用することができない。 ? 小括 15 したがって、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受 ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、 AI発明については、同法に基づき特許を付与することはできない。 そうすると、AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かにつ いて判断するまでもなく、特許法に基づきAI発明について特許付与が可能 20 である旨の原告の主張は、理由がない。 2 争点?(国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」 は必要的記載事項であるか)について ? 特許法は、国際特許出願の国内手続において、発明者の氏名を記載した国 内書面を提出しなければならないと規定し(同法184条の5第1項柱書、 25 2号)、特許庁長官は、国内書面の提出に係る手続が経済産業省令で定める 方式に違反しているときは、相当の期間を指定して手続の補正を命ずること 12 ができ(同条2項柱書、3号)、これを受けた特許法施行規則38条の5第 1号は、国内書面の方式として、発明者の氏名を含む特許法184条の5第 1項各号に掲げる事項が記載されていることを規定し、特許庁長官は、指定 した期間内に手続の補正がなされないときは、当該国際特許出願を却下する 5 ことができると規定しているのであるから(同条3項)、国内書面において 「発明者の氏名」が必要的記載事項として規定されていることは明らかであ る。 ? 原告は、AI発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではな いと主張する。 10 しかし、原告の主張は、権利能力のない存在が行ったAI発明について、 特許法上、特許を付与することができると解することを前提とするものであ って、この前提において誤っているから、採用することができない。 なお、原告が指摘する、氏を持たない個人の場合については、名を記載す れば足りると解すべきことはあまりにも当然であるし、法人名を記載した出 15 願の実体審査がなされた事例は、必要的記載事項の要件を看過してなされた 事例があるというだけであり、当然ながら、これらの事例が存在するからと いって、特許出願手続上、「発明者の氏名」が必要的記載事項ではないと解 することはできない。 また、現行特許法上、発明者は自然人であることが前提とされている以上、 20 出願書類等に記載すべき「発明者の氏名」が自然人であることは当然の論理 的帰結である。これと異なる前提に立って、AI発明の出願において「発明 者の氏名」を必要的記載事項と解することが憲法14条に違反するとの原告 の主張は、採用することができない。 ? 原告は、AI発明の出願において発明者の氏名を必要的記載事項とした場 25 合、発明者でない自然人を発明者として記載した出願の増加を招く問題点が ある旨主張し、さらに、このような冒認出願に係るAI発明の特許は、冒認 13 を理由とする無効審判の請求権者である利害関係人が存在せず、無効となら ない問題点がある旨主張する。 原告が指摘するこれらの問題は、AI発明の存在を前提としていない現行 法の問題点の一つといえるが、発明者の氏名欄の記載を必要的記載事項でな 5 いと解すれば解決するものではない。原告の指摘する問題点は、前記のとお り、AI発明に関する立法政策の議論の中で検討されるべき問題であって、 現行法の解釈として、発明者の氏名欄の記載が必要的記載事項ではないと解 する根拠にはならない。 なお、原告指摘の冒認出願については、特許の拒絶の査定をする理由にな 10 る(特許法49条7号)ほか、侵害訴訟において特許無効の抗弁として主張 することは可能である(同法104条の3第1項、3項)。AI発明におい て同法123条2項の利害関係人(特許を受ける権利を有する者)として同 条1項6号に該当することを理由に特許無効審判を請求する者が存在しない としても、それは現行法が予定していなかった事態が生じたというだけで、 15 特許法上、自然人を発明者とする発明についてのみ特許付与が可能である旨 の前記解釈を変更する理由にはならない。 ? 原告は、AI発明の出願において発明者の氏名を必要的記載事項と解する ことは、欧州特許庁の判断と整合しないと主張する。 しかし、原告指摘の説示(甲10・段落4.4.1)は、欧州特許出願に 20 発明者を表示すべき旨定めた欧州特許条約81条第1文の解釈について、欧 州特許庁が示した判断であって、かつ、結論として発明者適格を有するのは 自然人のみであるとした判断の理由の一部であるにすぎず、我が国の特許法 の解釈として、国内書面の「発明者の氏名」が必要的記載事項であることを 否定する根拠とはならない。 25 ? したがって、国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者 の氏名」は必要的記載事項である。 14 3 結論 以上のとおり、本件処分は適法であるから、原告の請求を棄却した原判決は 相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文の とおり判決する。 5 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 10 清 水 響 裁判官 15 菊 池 絵 理 裁判官 20 頼 晋 一 15 (別紙) 関係法令の定め 1 特許法 5 (目的) 第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産 業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の 10 ものをいう。 2~4 略 (特許の要件) 第二十9条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、そ の発明について特許を受けることができる。 15 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又 は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各 20 号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、 同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 (特許を受ける権利) 第三十3条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 25 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ ば、その持分を譲渡することができない。 16 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ ば、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設 定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 (職務発明) 5 第三十5条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従 業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその 性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使 用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」とい う。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継し 10 た者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有す る。 2 略 3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらか じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受け 15 る権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 4~7 略 (特許出願) 第三十6条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官 に提出しなければならない。 20 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2~7 略 (特許権の設定の登録) 第六十6条 特許権は、設定の登録により発生する。 25 2 第百7条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はそ の納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 17 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされてい るときは、この限りでない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 5 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四~七 略 4 略 (特許権の効力) 10 第六十8条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、そ の特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施 をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (国際出願による特許出願) 第百八十4条の3 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約 15 (以下この章において「条約」という。)第十1条(1)若しくは(2)(b)又は 第十4条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四 条(1)(ⅱ)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、そ の国際出願日にされた特許出願とみなす。 2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。) 20 については、第四十3条(第四十3条の2第2項(第四十3条の3第3項において準 用する場合を含む。)及び第四十3条の3第3項において準用する場合を含む。)の 規定は、適用しない。 (書面の提出及び補正命令) 第百八十4条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項 25 を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 18 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこ とを命ずることができる。 5 一、二 略 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四、五 略 3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定 により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下すること 10 ができる。 (手数料) 第百九十5条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけ ればならない。 一~七 略 15 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令 で定める額の手数料を納付しなければならない。 3~13 略 別表(第百九十5条関係) 一~三 略 20 [納付しなければならない者] [金額] 四 第百八十4条の5第1項の規定により 一件につき一万六千円 手続をすべき者 五~二十 略 25 2 特許法施行規則 (書面の様式) 19 第三十8条の4 特許法第百八十4条の5第1項の書面は、様式第五十三により作成し なければならない。 (書面の提出手続に係る方式) 第三十8条の5 特許法第百八十4条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、 5 次のとおりとする。 一 特許法第百八十4条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。 二 前条に規定する様式により作成されていること。 20 3 特許協力条約 第4条 願書 (1) 願書には、次の事項を記載する。 5 (i) 国際出願がこの条約に従つて処理されることの申立て (ⅱ) 国際出願に基づいて発明の保護が求められている一又は二以上の締約国の指 定(このように指定される締約国を「指定国」という。)。指定国について広域特 許を受けることが可能であり、かつ、出願人が国内特許ではなく広域特許を受ける ことを希望する場合には、願書にその旨を表示する。広域特許に関する条約により 10 出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場 合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望す る旨の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。指定国の国内法令に基 づきその国の指定が広域特許の出願としての効果を有する場合には、その国の指定 は、広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなす。 15 (ⅲ)~(v) 略 (2)~(4) 略 第十1条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件 として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 21 (i) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由によ り明らかに欠いている者でないこと。 (ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。 (ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。 5 (a) 国際出願をする意思の表示 (b) 少なくとも一の締約国の指定 (c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示 (d) 明細書であると外見上認められる部分 (e) 請求の範囲であると外見上認められる部分 10 (2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていな いと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をするこ とを求める。 (b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合 には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。 15 (3) 第六十4条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(i)から(ⅲ)ま でに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められた国際出願は、国際出願日か ら各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定 国における実際の出願日とみなす。 (4) 略 20 第十4条 国際出願の欠陥 (1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうか を点検する。 (i) 規則の定めるところによる署名がないこと。 (ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。 25 (ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。 (ⅳ) 要約が含まれていないこと。 22 (v) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。 (b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所 定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、そ の国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。 5 (2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合に は、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にそ の図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合に は、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、その 図面への言及は、ないものとみなす。 10 (3)~(4) 略 第二十2条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払 (1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出 願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出 し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が 15 発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めてい るが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それ らの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国の ために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月を経過する時までにそれらの事 項を届け出る。 20 (2) 国際調査機関が第十7条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しな い旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期 間と同一とする。 (3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又 は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。 25 以 上 23 (別紙) 当事者の主張 1 争点?(特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られ 5 るか)について (原告の主張) 特許法が、特許の実体的要件において、AI発明の保護を殊更に排除していないこ とは、明らかである。 ? 特許法における「発明」の概念 10 特許法2条1項は、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高 度のものをいう」と定義しており、このうち「技術的思想」は、一定の課題を解決す るための具体的手段が反復可能であることを意味し、「創作」は、自ら作り出すこと が必要であるものの、既存のものを見つけ出す発見は創作には含まれないという程度 の意味であるから、同項の文言上、「発明」は自然人により生み出されたものに限定 15 されていない。 これ以外の特許法の規定をみても、AI発明が特許法上の「発明」の概念から排除 されることを根拠付ける規定は存在しない。 ? 特許要件について ア 特許要件についてみても、特許法29条は、産業上の利用可能性(同条1項柱 20 書)、新規性(同条1項)及び進歩性(同条2項)を充足する発明には特許が付与 されると規定し、同法32条は、消極要件として、公序良俗又は公衆衛生を害する おそれがある発明については特許すべきではないと規定するにとどまるように、特 許付与の実体的要件として、自然人がした発明であることには限定されていない。 イ 原告は、AIであるダバスを創作した者であり、ダバスをアクセス制限等によっ 25 て自己のために排他的に管理しているから、善意の占有者(民法189条1項、2 05条)又は所有者(同法206条、89条1項)の果実取得権に基づき、本件出 24 願に係る発明についての特許を受ける権利を有している。 なお、特許を受ける権利を有しないことは、拒絶理由(特許法49条7号)とな るが、出願却下の理由とはならず、本件処分の適法性には影響しない。 ? 「発明」が自然人による発明に限定されることの問題点 5 仮に、特許法上の「発明」が自然人による発明に限定されると解釈した場合、AI 発明は特許法29条1項各号が定める公知の発明、公然実施発明等にも含まれないこ とになるから、現実に存在するAI発明と同一の発明をした者の特許出願は、新規性 要件で拒絶されることがないということになる。これは、新規の発明を公開した者に 対して独占権を付与するという特許制度の根幹を揺るがすものであり、このような不 10 合理な結果を招来する解釈は誤っている。 ? TRIPS協定との整合性 TRIPS協定27条1項は、特許の対象について、「(2)及び(3)の規定に従うこ とを条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のある全ての技術 分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。」と規定 15 している。この日本語の訳文では「特許は…与えられる」と訳出されているが、原文 は「patents shall be available」であり、法律用語の「shall」は、通常、立案者 が義務を課す趣旨で使用する用語であるから(甲9)、正確には「特許は…与えられ なければならない」という趣旨である。 そして、同条2項(上記の「(2)の規定」)は公序良俗等に反する発明について、 20 同条3項(上記の「(3)の規定」)は診断方法や生物学的な方法について、それぞれ 加盟国が特許の対象から除外し得ることを定めているにとどまるから、同条1項は、 結局のところ、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のある発明については、自然 人がしたか否かにかかわらず、特許法上の保護を与える義務を規定していることにな る。 25 このように、特許法がAI発明を保護の対象から排除していないと解釈することは、 TRIPS協定の規定にも整合する一方、特許法がAI発明の保護を排除していると 25 解釈することは、TRIPS協定の規定に反することになる。 ? 欧州特許庁の判断との整合性 欧州特許庁は、欧州における本件出願に係る発明の対応特許出願について、「第一 に、EPC(注:欧州特許条約)52条(1)に基づき、新規であり、産業上利用可 5 能であり、進歩性を有する発明は、特許を受けることができる。審判請求人は、この 規定の対象は人為的発明に限定されないと主張している。審判部はこれに同意する。 発明がどのようにしてなされたかは欧州特許制度において明らかに何の役割も果たさ ない。(中略)したがって、AI生成発明もEPC52条(1)に基づいて特許を受 けることができると論じることが可能である。」と述べている(甲10・段落4.6. 10 2)。 上記説示のとおり、発明が自然人、AIのいずれにより生成されたものであるかと いうことは、特許を付与する上で何ら重要な事実ではない。 ? 被告の主張に対する反論 ア AI発明における特許を受ける権利の発生について 15 (ア) 特許法29条1項は、発明者(自然人)は特許を受けることが「できる」という、 当然のことを規定しているだけであって、「AI発明については特許を受ける権利 が発生しない」などと規定しているわけではない。 例えば、法人については、自然人ではない法人は発明者になることができず、同 項柱書に基づいて特許を受ける権利を取得することはできないと解釈されているが、 20 このような解釈は、同項柱書の文言から当然に導き出されるものではなく、職務発 明について特許を受ける権利の帰属の例外を定める同法35条3項と併せて、初め て導き出されるものである。同項に相当する規定がないAI発明については、同法 29条1項柱書の文言のみから、特許を受ける権利が発生しないなどと解釈するこ とはできない。 25 (イ) 英国、オーストラリア又はニュージーランドのように特許を受ける権利の原始的 帰属を発明者に限定する趣旨の条文も、米国のように特許出願人となり得る主体を 26 限定する趣旨の条文も定めていない日本の特許法においては、特許を受ける権利の 原始的帰属や特許出願人となり得る主体が限定されていないことが明らかである。 (ウ) そもそも、特許法の制定当時、AI発明という概念やそれに伴う法律問題は存在 しておらず、特許法が自然人による発明のみを前提にして制定されたことは明らか 5 であるから、特許法がAI発明に関する規定を設けていないことは、AI発明の保 護を一律に否定する理由にはならない。 従来は想定もされていなかったAI発明は、現に誕生し利用されており、今後も 増えていくことが確実に予想される。このため、旧来の発明者主義に関する見解を 無批判に採用し、AI発明に対するインセンティブという観点を殊更に捨象したの 10 では、「産業の発達に寄与する」(特許法1条)という特許法の目的に反する事態 が招来されることは明らかであり、現行法の解釈として認められるものについては、 できる限りの保護を認めるように解釈運用すべきである。 イ 知的財産基本法2条1項について 知的財産基本法2条1項の文言は、「その他」と「その他の」を厳密に使い分けて 15 おらず、「その他の」という文言により「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物」 が「人間の創造的活動により生み出されるもの」に包含されることを規定するとは解 されないし、仮にそうでないとしても、同項は「発明」が人間の創造的活動により生 み出されることを必ずしも前提としていないと解釈するのが自然である。 同法の立法経緯からみても、当時の技術水準ではAI発明は現実に存在していなか 20 ったのであり、「発明」は自然人がしたものに限定されるといった議論はなされてお らず、同法が国家戦略として知的財産を可能な限り広く積極的に保護しようとして制 定された法律であることからも、同法から「発明」の定義を限定的な範囲にとどめる 解釈を導くことは不合理である。 (被告の主張) 25 特許法において特許権の付与により保護される「発明」は、自然人によってなされた ものに限られ、これを満たさないAI発明は、特許の対象とならない。 27 ? AIにより生成された成果物は「発明」に包含されないと解するのが相当であるこ と ア 特許法2条1項は、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち 高度のものをいう」と定義しているところ、ここにいう「技術的思想の創作」とい 5 う文言は、何らか自然人の精神活動が介在することが当然に前提とされていると解 される。また、この定義は、ドイツの法学者であるコーラーが提唱した「技術的に 表示された人間の精神的創作であり、自然を制御し自然力を利用して一定の効果を 生ぜしめるもの」との定義を、実質的にそのまま踏襲したものと理解されている。 イ 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」(同条2項により特許権が含まれる。) 10 を「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生 み出されるもの(中略)をいう。」と定義しており、「発明」につき、特許法と同 様に「人間の創造的活動により生み出される」ものであると位置づけている。 ウ 以上のとおり、特許法における「発明」の定義や沿革等に照らせば、現行特許法 で特許権の付与により保護され得る「発明」は、自然人の創作活動により生み出し 15 たものであることを要するものであって、自然人の創作活動を介在させずに生成さ れるAI発明については、同法2条1項の「発明」に包含されないと解するのが相 当である。 ? AI発明のように自然人たる発明者が観念できないような場合に「特許を受ける権 利」が発生し得ると解することは極めて困難であること 20 ア 特許法29条1項柱書は、「産業上利用することができる発明をした者は、(中 略)その発明について特許を受けることができる」と規定している。これは、当該 「発明をした者」に「特許を受ける権利」が原始的に帰属するという発明者主義の 考え方を採用したものであり、特許法は、これにより「発明を奨励し、もって産業 の発達に寄与」(同法1条)しようとするものである。 25 このような「特許を受ける権利」の発生ないし帰属に関する規律等に照らすと、 同法29条1項の「発明をした者」とは、権利義務の帰属主体となり得るとともに、 28 「発明」の定義が想定しているような何らかの創作活動ないし精神的活動をするこ とができるもの、すなわち自然人であることが当然の前提とされていることは明ら かである。 また、発明者は人格権としての発明者名誉権を取得するとされていることも、 5 「発明をした者」が人格的利益の享有主体である自然人であることを前提にしてい るといえる。 イ 特許法上、AI発明のように自然人たる発明者を観念できない場合を念頭に、 「特許を受ける権利」が発生し、それが何人かに原始的に帰属することを定めた規 定は存在しない。 10 ? 原告の主張に対する反論 ア 特許法が、実体的要件として、AI発明の保護を殊更に排除していないとの主張 について 原告も認めるように、特許法は自然人による発明のみを特許権の対象とすること を前提に制定されており、同法の立法者は、自然人でないものが生み出した成果物 15 に特許権を付与するとの政策判断をしていない。 また、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされてお り(特許法68条本文)、このような強力な権利の発生を法律上の根拠なく認める という解釈は相当でない。 AI発明について、明文の規定がないから現行特許法の下でも特許権付与が認め 20 られるべきであるという原告の主張は、解釈論の域を超えた立法論といわざるを得 ない。 イ TRIPS協定に基づく主張について TRIPS協定27条1項が適用対象である発明を積極的に定義するものでない ことは、その文言から明らかである。AIのような自然人でないものによる成果物 25 につき、新規性、進歩性、産業上の利用可能性さえあれば特許として保護すべきこ とを義務付けているというのが、同項の一般的な解釈であるなどと解すべき的確な 29 根拠は見当たらない。現に、TRIPS協定の加盟国のうち複数の国において、A Iを発明者とすることはできない旨の司法判断が示されているところである。 ウ 欧州特許庁審判部の判決を援用する主張について そもそも日本はEPCの締約国ではないから、原告が援用する欧州特許庁審判部 5 の判決(甲10)は、日本の特許法の解釈において直ちに参照し得るものではない。 しかも、上記判決は、発明者適格を有するのは自然人のみであるとして、同旨の 理由により発明者をAIとする出願を却下した原処分を維持したものであって、原 告が引用する部分は、審決の結論に対する想定反論等に検討を加える説示から、想 定反論等への部分的な賛意を述べた箇所を殊更に抜き出すものにすぎず、特許法の 10 解釈において参照すべき価値に乏しい。 2 争点?(国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必 要的記載事項であるか)について (原告の主張) AI発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではないと解すべきであ 15 る。したがって、国内書面の【発明者】の【氏名】の欄に自然人ではないものの名称 が記載されていることを根拠に、本件国内書面に方式違反があるとした本件処分は、 違法である。 ? AI発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではないこと 特許法184条の5第2項3号、特許法施行規則38条の5第1号が発明者の氏 20 名の記載を求めている趣旨は、自然人が発明をした場合において、その自然人には 発明者名誉権が帰属することから、その権利関係を明確にするためのものにすぎな い。 そして、自然人が介在することなくAIが自律的に生成したAI発明の場合、財 産権としての特許出願権は発生するものの、人格権としての発明者名誉権は発生し 25 ないから、その帰属を明確にする必要はなく、国内書面に発明者の氏名の記載が要 求される趣旨が妥当せず、また、発明者の氏名の記載がなくとも真の発明者や第三 30 者との関係で何らかの不合理な事態を招来することもないから、結局、発明者の氏 名の記載は何らの意味も持たないことになる。 したがって、AI発明の出願手続においては、国内書面の発明者の氏名の記載は 必要的記載事項ではないと解すべきである。 5 ? 〔当審における補足的主張〕国内書面に発明者の氏名の記載を求める特許法18 4条の5第1項第2号の規定は、同条2項、同法施行規則38条の5の規定の文言 からみて、常にどのような場合にも記載しなければならないという不可侵のルール ではない。このことは、姓を持たない者を発明者とする特許登録が認められた事例 (甲28)や、発明者として法人の名称を記載した特許出願の実体審査がなされた 10 事例(甲29、30)があることからも裏付けられる。 AI発明について、記載ができない「発明者の氏名」の記載という形式要件違反 のみを理由として特許出願を却下することは、実体要件において特許法上の保護の 対象に含まれるAI発明を保護の対象から除外し、形式要件が実体要件を上書きし て新たな実体要件を作り出すのと同じでことあり、法令解釈として誤っている。 15 また、前記の各事例と比較して、発明者の氏名にAIの名称を記載した原告のみ、 本件出願を却下して実体審査を受けさせないことは、憲法14条が定める平等原則 に違反する。 ? 必要的記載事項と解することの問題点 ア 冒認出願の増加を招くこと 20 仮に、AI発明の出願においても発明者の氏名は必要的記載事項であると解し た場合、AI発明を活用する企業は、①AI発明については保護を受けることを 断念するか、②発明者の氏名欄に適当な自然人を特定して特許を受けようとする かのいずれかの行動を取るものと考えられるが、本来特許法上の保護を受け得る 発明の保護を断念すること(上記①)は考え難いから、経済合理性を踏まえた上 25 で、上記②の行動を取る可能性が高い。 この場合、そのAI発明が特許要件を充足する限り、発明者でない自然人が 31 発明者として記載されることになるが、これは、特許庁が、本来発明者名誉権 を有しない者に対して発明者名誉権を付与したかのような外観を作出すること を助長し、かつ、本来特許を受ける権利を有しない者による特許出願を正当な 出願として奨励するようなものであって、AI発明について冒認出願を事実上 5 容認、助長、奨励することにつながり、特許法の冒認出願に関する定めを無意 味にするものといえる。 イ 無効にできない特許が発生すること さらに、このような冒認出願に係るAI発明の特許については、冒認出願に該 当することを理由として無効審判を請求することができる者が特許を受ける権利 10 を有する者に限定されていることから(特許法123条2項)、AI発明につい て誤って特許が付与された場合に特許を受ける権利を「発明者」から承継した者 が存在しないため、冒認出願に該当することを理由として無効審判を請求できる 者が存在しないことになり、本来無効であるはずの特許が残り続けることになる。 ? 欧州特許庁の判断との整合性 15 欧州特許庁は、EPC(欧州特許条約)81条第一文の定め(「The European patent application shall designate the inventor.」(欧州特許出願は、発明者 を指定しなければならない。))について、「予備的請求は、出願が人為的発明に 関連しない場合にはEPC81条第一文が適用されないという主張に依拠している。 審判部はこのアプローチに同意する。発明者の表示に関する規定は発明者に特定の 20 権利を付与するために起草されたものである。自然人の発明者を特定できない場合 には、EPC81条第一文の法理は適用されないと議論することは可能である。」 と述べている(甲10・段落4.4.1)。 EPC81条第一文は、特許法184条の5第2項3号と同旨であるから、上記 の説示は、AI発明の出願手続において国内書面の発明者の氏名の記載は必要的記 25 載事項ではないとする解釈と整合する。 (被告の主張) 32 国内書面の発明者の氏名欄には、発明者たる自然人の氏名を記載すべきであって、 自然人の氏名でない名称等の記載によってこの要件が満たされる余地はなく、このよ うな記載がある本件国内書面は、形式要件違反があるものとの評価を免れない。 ? 発明者の氏名は必要的記載事項であること 5 国内書面は、様式第53により作成し(特許法施行規則38条の4、38条の5 第2号)、特許法184条の5第1項各号所定の事項(2号に「発明者の氏名」が 規定されている。)を記載しなければならない(特許法施行規則38条の5第1号) と定められていることから、発明者の氏名は、国内書面における必要的記載事項で ある。 10 特許法上、発明者は自然人に限られると解されることは前記1(被告の主張)の とおりであり、この「氏名」が自然人たる発明者の氏名を指すことは明らかである。 そして、発明者の氏名欄の記載について、一定の場合にこれを省略したり、自然人 たる発明者の氏名以外の名称等で代替したりすることが可能であることをうかがわ せる規定は、特許法には存在しない。 15 ? 原告の主張に対する反論 ア AI発明について発明者の氏名が国内書面の必要的記載事項ではないとする原 告の主張は、いずれも、AI発明が特許権を付与され得ることを前提とするもの であり、前提において誤っている。 イ 欧州特許庁審判部の判決を援用する主張については、前記1(被告の主張)? 20 ウに同じ。 以 上 33 |