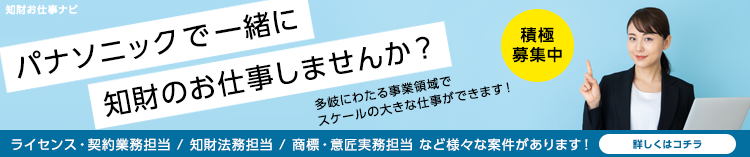| 関連審決 |
異議2021-700022 無効2022-800049 |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
5年
(行ケ)
10098号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
5 原告ザ プロクターアンド ギャンブル カンパニー 同訴訟代理人弁護士 宮嶋学 10 同高田泰彦 同 柏延之 同 二枝翔司 同訴訟代理人弁理士 反町洋 同 小島一真 15 被告ライオン株式会社 同訴訟代理人弁理士 服部智 同 川越雄一郎 20 同内田洋平 同訴訟代理人弁護士 三縄隆 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2024/05/14 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
1 特許庁が無効2022−800049号事件について令和5年4月20日にした審決のうち、特許第6718777号の請求項1及び25 3ないし5に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 1事 実 及 び 理 由第1 請求主文同旨第2 事案の概要5 1 特許庁における手続の経緯等? 被告は、出願日を平成28年9月5日とし(以下「本件出願日」という。 、 )発明の名称を「衣料用洗浄剤組成物」とする発明について特許出願(特願2016−172763号)をし、令和2年6月17日、特許権の設定登録(特許第6718777号。請求項の数6。以下、この特許を「本件特許」とい10 い、本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)を受けた。(甲7)? 本件特許に対し、令和3年1月8日に特許異議の申立てがされ(異議2021−700022号)、同年4月20日付けで取消理由が通知された。被告は、同年6月18日、意見書を提出するとともに、特許請求の範囲の訂正請求をした。特許庁は、同年10月27日、上記訂正を認め、請求項1ない15 し6に係る特許を維持する旨の異議決定をした。(甲8、9)? 原告は、令和4年6月8日、本件特許(上記?の異議事件において認められた訂正後の請求項1ないし6)につき、無効審判請求をした(無効2022−800049号事件。以下「本件審判」という。)。被告は、同年8月25日、審判事件答弁書を提出するとともに、特許請求の範囲の訂正請求を20 した(以下「本件訂正」という。)。上記?の異議事件において認められた訂正後の請求項1ないし6のうち、請求項2及び6は本件訂正により削除された。(甲21〜23)? 特許庁は、令和5年4月20日、本件訂正を認めた上で、「特許第6718777号の請求項2、6に係る発明についての本件審判の請求を却下する。 25 特許第6718777号の請求項1、3〜5に係る発明についての本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、 2その謄本は、同年5月9日、原告に送達された(付加期間90日)。 ? 原告は、令和5年9月1日、本件審決のうち、本件特許の請求項1及び3ないし5に係る部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載5 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(下線部は本件訂正による訂正部分である。以下、本件訂正後の請求項1、3ないし5に記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」「本件発明3」ないし「本件発明5」といい、 、 これらを併せて「本件各発明」という。。 ) (甲23)【請求項1】10 (A)成分:アニオン界面活性剤(但し、炭素数10〜20の脂肪酸塩を除く)と、 (B)成分:4,4’−ジクロロ−2−ヒドロキシジフェニルエーテルを含むフェノール型抗菌剤と、 (C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレ15 ート剤0.02〜1.5質量%と、 (G)成分としてノニオン界面活性剤を含み、 (G)成分の含有量が、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%であり、 (G)成分が、 20 下記一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であり、 R2−C(=O)O−[(EO)s/(PO)t ]−(EO)u −R 3 ・・・(I)R4−O−[(EO) v/(PO) w ]−(EO) x −H ・・・(II)(式(I)中、R 2は炭素数7〜22の炭化水素基であり、R 3 は炭素数1〜6のアルキル基であり、sはEOの平均繰り返し数を表し、6〜20の数であり、 25 tはPOの平均繰り返し数を表し、0〜6の数であり、uはEOの平均繰り返し数を表し、0〜20の数であり、EOはオキシエチレン基を表し、POはオ3キシプロピレン基を表す。 式(II)中、R 4は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であり、v、xは、それぞれ独立にEOの平均繰り返し数を表す数で、v+xは3〜20であり、POはオキシプロピレン基を表し、wはPOの平均繰り返し数5 を表し、wは0〜6である。)(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)が10〜100である衣料用洗浄剤組成物(但し、クエン酸二水素銀を含有する組成物を除く)。 【化1】10 式(c1)中、Aは、それぞれ独立してH、OHまたはCOOMであり、Mは、それぞれ独立してH、Na、K、NH 4 またはアルカノールアミンであり、 nは0〜5の整数である。 【請求項3】さらに(D)成分:酵素を含む、請求項1に記載の衣料用洗浄剤組成物。 15 【請求項4】(B)成分/(C)成分で表される質量比が0.02〜1である、請求項1又は3に記載の衣料用洗浄剤組成物。 【請求項5】前記(B)成分の含有量が、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、0.2〜120 質量%である、請求項1、 4のいずれか一項に記載の衣料用洗浄剤組成物。 3、 」3 本件審判で主張された無効理由原告は、本件審判において、次の無効理由を主張した。なお、原告は、本件訂正により削除される前の請求項2及び6についても同一の無効理由を主張し4ていたが、以下、本件各発明(本件訂正後の請求項1、3ないし5)に対する主張の範囲で摘示する。 ? 無効理由1(新規性の欠如)本件 各 発明 は 、 甲1 (IP.com, Biocidal Compositions containing 4,4’-5 dichloro 2-hydroxy diphenylether (DCPP), The IP.com Journal,IPCOM000213522D, 2011年(平成23年)12月20日)に記載された発明であるから、特許法29条1項3号の発明に該当し、特許を受けることができない。よって、本件各発明に係る特許は、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである。 10 ? 無効理由2(進歩性の欠如)本件各発明は、甲1に記載された発明及び甲2ないし6の記載に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。よって、本件各発明に係る特許は、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである。 15 ? 無効理由3(サポート要件違反)「(E)成分:硫酸亜鉛一水和物」の存在が特定されておらず、また、(C)成分が「C−1:メチルグリシン二酢酸三ナトリウム(MGDA)」にまで特定されていない本件各発明は、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものである。 20 したがって、本件各発明は、特許請求の範囲の記載が、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしておらず、本件各発明に係る特許は、同法123条1項4号に該当し、無効とすべきである。 4 本件審決の理由等本件審決の理由は、別紙1審決書(写し)記載のとおりであり、原告の主張25 に対する判断の要旨は次のとおりである。 ? 無効理由1及び無効理由2について5ア 甲1に記載された発明甲1は、4,4’−ジクロロ2−ヒドロキシジフェニルエーテル(DCPP)を含有する抗菌組成物について開示されたものであり、処方LIに係る抗菌性液体洗濯洗剤として、次の発明(以下「甲1発明」という。)が5 記載されていると認められる。 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)であるNaLASが8〜17wt%、 R−(OCH 2CH 2 ) n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)が5〜25wt%、 10 C 12−C 18のアルキルポリエトキシレート(3.0)硫酸塩であるSLES(3EO)が4〜15wt%、 石鹸が0.5〜7wt%、 クエン酸が0.1〜3wt%、 グリセロールが1〜8wt%、 15 プロピレングリコールが0.5〜8wt%、 塩化ナトリウムが0〜4wt%、 トリエタノールアミンが0.5〜5wt%、 香料が0.01〜1wt%、 プロテアーゼが0.001〜0.01wt%、 20 アミラーゼが0.001〜0.01wt%、 リパーゼが0.001〜0.01wt%、 蛍光増白剤が0.02〜0.5wt%、 4,4’−ジクロロ2−ヒドロキシジフェニルエーテルであるDCPPが0.01〜0.5wt%、 25 クメンスルホン酸塩ナトリウムが0wt%、 MGDA(Trilon (R) M)が0.1〜5wt%、 6フェノキシエタノールが0wt%、 水/不純物/微量成分が残部からなる、 抗菌性液体洗濯洗剤。」イ 本件発明1と甲1発明の一致点及び相違点5 〔一致点〕「(A)成分:アニオン界面活性剤(但し、炭素数10〜20の脂肪酸塩を除く)と、 (B)成分:4,4’−ジクロロ−2−ヒドロキシジフェニルエーテルを含むフェノール型抗菌剤と、 10 (C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレート剤と、 ノニオン界面活性剤を含む、 衣料用洗浄剤組成物(但し、クエン酸二水素銀を含有する組成物を除く)。 【化1】15式(c1)中、Aは、それぞれ独立してH、OHまたはCOOMであり、 Mは、それぞれ独立してH、Na、K、NH 4またはアルカノールアミンであり、nは0〜5の整数である。」〔相違点1〕20 本件発明1では、 (C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含む「アミノカルボン酸型キレート剤」の含有量が「0.02〜1.5質量%」であるのに対し、甲1発明では、当該成分に相当する「MGDA(Trilon (R) M)」の含有量が「0.1〜5wt%」である点。 7〔相違点2〕本件発明1では、「ノニオン界面活性剤」である「(G)成分が、 下記一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であり、 R 2 −C(=O)O−[(EO)s/(PO)t ]−(EO)u −R3 ・・・5 (I)R 4 −O−[(EO) v /(PO) w ]−(EO) x−H ・・・(II)(式(I)中、R 2は炭素数7〜22の炭化水素基であり、R 3 は炭素数1〜6のアルキル基であり、sはEOの平均繰り返し数を表し、6〜20の数であり、tはPOの平均繰り返し数を表し、0〜6の数であり、uはE10 Oの平均繰り返し数を表し、0〜20の数であり、EOはオキシエチレン基を表し、POはオキシプロピレン基を表す。 式(II)中、R 4は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であり、v、xは、それぞれ独立にEOの平均繰り返し数を表す数で、v+xは3〜20であり、POはオキシプロピレン基を表し、wはPOの平15 均繰り返し数を表し、wは0〜6である。」「) 、(G)成分の含有量が、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%であ」るのに対し、甲1発明では、 「ノニオン界面活性剤」が「R−(OCH 2 CH 2 )n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO) であり、 」その含有量が「5〜25wt%」である点。 20 〔相違点3〕本件発明1では、(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)「が10〜100である」のに対し、甲1発明では、 (A)成分」に相当す「る「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)であるNaLAS」、 「C12 −C 18 のアルキルポリエトキシレート(3.0)硫酸塩であるSLES25 (3EO)」及び「クメンスルホン酸塩ナトリウム」の合計含有量が(8+4+0)〜(17+15+0)wt%すなわち「12〜32wt%」であ8り、(C)成分」に相当する「MGDA(Trilon(R)「 M)」の含有量が「0.1〜5wt%」である点。 ウ 相違点についての判断(ア) 相違点2について5 a 化合物種の違いについて甲14(本件審判における乙2)の記載より、天然アルコールは偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有するのに対し、合成アルコール(エチレンを原料とするチーグラー法で得られたものを除く)は奇数あるいは分枝のアルキル基を含むことが把握できる。 10 「R 4 は炭素数12及び本件発明1における式(II)の化合物は、 14の天然アルコール由来の炭化水素であ」るから、 4 の炭素数が奇R数(例えば13や15)の場合や、R 4 が分枝のアルキル基の場合は除外されているといえる。 一方、甲15及び16(本件審判における乙3及び4)の記載より、 15 甲1発明の「R−(OCH 2CH 2)n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」は、Neodol(登録商標)25−7(Shell Chemicals)であり、アルキル鎖Rの炭素数分布はC 12 が21%、C 13 が29%、C 14 が25%、C15 が25%と推認される。また、アルキル鎖Rは直鎖に限らず、分枝20 を有するものも含まれていると推認される。 そうすると、本件発明1における式(II)の化合物と、甲1発明の「R−(OCH 2 CH 2 ) n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」は、R 4 の炭素数が偶数の12及び14のみで構成されるか、奇数の13及び15をも含んで構成され25 るかという点、 4 が直鎖のみで構成されるか、 R 分枝を有するものをも含んで構成されるかという点で相違しており、これらは実質的な相違9点である。 そして、 4は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水「R素であ」る点を含め、 「ノニオン界面活性剤」が本件発明1にいう「一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であ」ることは、 5 甲1に記載がなく、甲2ないし6にも記載されていない。 したがって、甲1発明において、 「ノニオン界面活性剤」 「R−を (OCH2CH2)nOH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO) から本件発明1にいう」 「一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種」に代えることは、当業者が容易になし得10 ることではない。 b 含有量の違いについて本件発明1における「ノニオン界面活性剤」である「(G)成分」の含有量(衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%)と、 甲1発明における「ノニオン界面活性剤」である「R−(OCH 2CH15 2 )n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」の含有量(5〜25wt%)は、少なくとも20〜25質量%の範囲で一部重複するが、後者の数値範囲は、前者の数値範囲に完全に包含されるものではなく、前者の含有量を必ず充足するとはいえないため、当該含有量は、実質的な相違点である。 20 また、甲1発明の「R−(OCH 2CH 2)n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」のうち、アルキル鎖Rの炭素数が12又は14であるものは21+25=46%であり、 残る54%は炭素数が13又は15と解される。そうすると、甲1発明において、本件発明1の式(II)の化合物に相当する化合物の含25 有量は、炭素数に着目しただけでも(5×46/100)〜(25×46/100)wt%すなわち2.3〜11.5wt%となり、天然10アルコール由来とはいえない分枝を有するものを差し引けば、その含有量はさらに少なくなるため、本件発明1で規定される含有量(衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%)と全く重複せず、 明らかに相違点である。 5 そして、 「ノニオン界面活性剤」である「(G)成分」の含有量が「衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%であ」ることは、 甲1に記載がなく、甲2ないし6にも記載されていない。 したがって、 「ノニオン界面活性剤」たる「R−(OCH 2 CH 2 )nOH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(710 EO)」の含有量が「5〜25wt%」である甲1発明において、「ノニオン界面活性剤」たる「(G)成分」の含有量を「衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20〜40質量%」に変更することは、当業者が容易になし得ることではない。 (イ) 相違点3について15 甲1発明では、 (A)成分」に相当する「直鎖アルキルベンゼンスル「ホン酸塩(LAS)であるNaLAS」「C 12−C 18 のアルキルポリエ、 トキシレート(3.0)硫酸塩であるSLES(3EO)」及び「クメンスルホン酸塩ナトリウム」の合計含有量が(8+4+0)〜(17+15+0)wt%すなわち「12〜32wt%」であり、 (C)成分」に「20 相当する「MGDA(Trilon(R) M)」の含有量が「0.1〜5wt%」であるから、 (A)成分/(C)成分で表される質量比(A/「C比) は最小で12/5=2. 最大で32/0.」 4、 1=320となり、 本件発明1で規定される数値範囲(10〜100)と重複する。しかし、 この2.4ないし320という数値範囲は、本件発明1で規定される数25 値範囲(10〜100)に包含されない数値範囲(2.4以上10未満及び100超320以下)も含んでおり、本件発明1で規定される数値11範囲(10〜100)を必ず充足するとはいえないため、A/Cの質量比は、実質的な相違点である。 そして、 (A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)が1「0〜100である」ことは、甲1に記載がなく、甲2ないし6にも記載5 されていない。 したがって、 (A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)「 」のとり得る値が最小で2.4、最大で320である甲1発明において、 その質量比を「10〜100」とさらに限定することは、当業者が容易になし得ることではない。 10 (ウ) 相違点1について本件発明1における「(C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレート剤」の含有量(0.02〜1.5質量%)と、甲1発明における「MGDA(Trilon(R) M) の含有量」 (0.1〜5wt%)は、少なくとも0.1〜1.5質量%の範囲で一部重複15 するが、後者の数値範囲は、前者の数値範囲に完全に包含されるものではなく、前者の含有量を必ず充足するとはいえないため、当該含有量は、 実質的な相違点である。 そして、 (C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノ「カルボン酸型キレート剤」の含有量が「0.02〜1.5質量%」であ20 ることは、甲1に記載がなく、甲2ないし6にも記載されていない。 したがって、本件発明1の「(C)成分」に相当する「MGDA(Trilon(R) M)」の含有量が「0.1〜5wt%」である甲1発明において、その含有量を「0.02〜1.5質量%」に変更することは、 当業者が容易になし得ることではない。 25 エ 結論以上のとおり、本件発明1は、甲1発明ではないから、特許法29条112項3号の発明に該当せず、また、本件発明1は、甲1発明及び甲2ないし6の記載に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものではないから、同条2項の規定により特許を受けることができない発明には当たらない。 5 本件発明3ないし5は、本件発明1を直接又は間接的に引用し、さらに特定事項を加えたものであるから、本件発明1と同様である。 ? 無効理由3について本件各発明の課題は、本件明細書の段落【0004】の記載より、 「衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境においても、十分な防臭効果が得られ、 10 防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供すること」と認められる。 そして、本件明細書に記載された、本件発明1で規定される組成を充足する衣料用洗浄剤組成物である実施例と、上記組成を充足しない衣料用洗浄剤組成物である比較例とを用いた防臭効果の評価の結果によれば、当業者は、 (A)成分、 (B)成分及び(C)成分を少なくとも含有することで、上記課15 題が解決できる一方、 (A)成分、 (B)成分、 (C)成分のうち少なくともいずれかの成分を含有しなければ、上記課題が解決できないことを十分認識することができた。 上記実施例で使用される(C)成分は、式(c1)のAがH、MがNa、 nが0の化合物、すなわちメチルグリシン二酢酸三ナトリウム(MGDA)20 に限られているが、当業者であれば、A、M、nに関し他の選択肢を組み合わせた化合物を(C)成分とした場合でも、上記実施例と同様又は類似の防臭効果が得られ、上記課題が解決できることを認識できるといえる。 したがって、本件発明1は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えているとはいえない。また、本件発明3ないし5は、本件発明125 を直接又は間接的に引用し、さらに特定事項を加えたものであるから、本件発明1と同様である。 135 原告の主張する本件審決の取消事由? 取消事由1本件各発明の甲1発明に対する新規性の判断の誤り? 取消事由25 本件各発明の甲1発明に対する進歩性の判断の誤り? 取消事由3本件各発明のサポート要件違反の有無に関する判断の誤り第3 当事者の主張1 取消事由1(本件各発明の甲1発明に対する新規性の判断の誤り)について10 〔原告の主張〕次のとおり、本件審決が認定した本件発明1と甲1発明との相違点は、いずれも形式的な相違点であって、実質的な相違点ではないから、本件発明1は甲1発明と同一の発明である。 ? 相違点2について15 甲1発明の「R−(OCH 2CH2 )n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」に関し、ここでのNIは、ノニオン(非イオン)を表す「Non−Ionic」を意味するものであり、特定の原料や関連する商品名を意味するものではない。本件審決は、甲15及び16を根拠として、甲1発明のNI(7EO)がNeodol25−7であると判20 断し、これを前提に相違点2が実質的な相違点であるとの結論を導いているが、上記判断は誤りであって、NI(7EO)は、アルキル基がC12からC15の範囲であり、EOの付加数の平均値が7程度のアルコールエトキシレートであれば、いずれも使用可能であるものという趣旨と考えるのが合理的である。 25 そして、アルキル基のC12ないしC15という数値範囲は、AE(アルコールエトキシレート)のアルキル基として洗剤などの分野で汎用されてい14る数値を記載したものにすぎず、必ずしもC12ないしC15全てのアルキル基が存在しなければならないことを意味するものではない。従前から、C12ないしC15として、天然由来のアルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)が用いられており、昨今においては、石油由来の高級アルコ5 ール(分岐アルコール)と天然油脂由来の高級アルコール(直鎖アルコール)との価格差が小さくなっていることなども相まって、特に天然由来のアルコールの割合が増えている。 以上によれば、甲1発明のNI(7EO)について、そのアルキル鎖(R)には天然由来のアルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)である10 ものも含まれるから、本件発明1に規定する「式(II)中、R 4 は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であり」という構成は、甲1発明の「RはC12からC15のアルキル鎖」に包含される関係にあるから、 この点は両発明の相違点に該当しない。 また、NI(7EO)の配合量についても、20ないし25質量%の範囲15 で重複している。 したがって、相違点2は形式的な相違点にすぎず、実質的な相違点に該当しない。 ? 相違点1について本件発明1における「(C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含む20 アミノカルボン酸型キレート剤」の含有量(0.02〜1.5質量%)と、 甲1発明におけるMGDA(Trilon M) の含有量」 (0.1〜5wt%)は、少なくとも0.1ないし1.5質量%の範囲で一部重複している。このように本件発明1の範囲が引用発明と一部重複する以上、少なくともその部分に関しては一致点と判断されるべきである。 25 また、甲1の処方XXXIVは、MGDAに関して「3.13%MGDA(Trilon?M、有効成分40%、BASF、納品時に使用)」と記載し15ており、この記載によれば、上記処方はMGDAを1.252質量%(3.13×0.4)配合しているから、本件発明1の「0.02〜1.5質量%」に含まれるといえ、これによってMGDAが4,4’−ジクロロ2−ヒドロキシジフェニルエーテル(DCPP)による殺菌効果を高めることも甲1に5 記載されている。 したがって、相違点1は実質的な相違点に該当しない。 ? 相違点3について甲1発明について、 (A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)は最小で12/5=2.4、最大で32/0.1=320となり、本件発明10 1で規定される数値範囲(10〜100)と重複するのであって、本件発明1の範囲が引用発明と一部重複する以上、少なくともその部分に関しては一致点と判断されるべきである。 また、甲1の処方XXXIVのMGDA1.252質量%を前提とすれば、 A/C比は9.6ないし25.6となり、本件発明1の10ないし100に15 より近接した値になる。 したがって、相違点3は実質的な相違点に該当しない。 〔被告の主張〕? 相違点2について甲1発明に配合されるノニオン界面活性剤成分のNI(7EO)について20 は、 「R−(OCH 2CH 2 )n OH」を指すとされているところ、このRは「C12からC15のアルキル鎖であり」とされている以上の特定はないから、 本件発明1の式(II)に係る、R 4 が炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であるノニオン界面活性剤とは化合物として相違する。 また、甲1発明のNI(7EO)は、甲15の記載(段落【0034】)も25 考慮すれば、甲1の処方V、VIに用いられているNeodol25−7Eである蓋然性が高い。Neodolは、合成アルコールエトキシレートに係16る商品群であること(乙4)からすれば、甲1発明のNI(7EO)におけるアルキル基NIにおいても炭素数が奇数のアルキル基を含む蓋然性が高い。 さらに、甲16の記載(段落【0063】)によれば、「ネオドール25」の代表的特性として、C12アルコール21%、C13アルコール29%、 5 C14アルコール25%、C15アルコール25%等であることが理解できるところ、仮に、炭素数12及び14のアルコールに由来する成分を含む点で本件発明1の(G)成分に係る化合物と重複し得るとしても、甲1発明においてその含有量は、5ないし25質量%のうちの46質量%(上記21%と25%の合計)、すなわち2.3ないし11質量%であり、本件発明1にお10 ける20ないし40質量%とは相違する。 以上のとおり、甲1発明に配合されるノニオン界面活性剤成分のNI(7EO)に相当する化合物種については甲1からは必ずしも明らかではないものの、関連する文献を参照してNI(7EO)中のアルキル基NIの具体的構造について最大限に解釈したとしても、本件発明1の式(II)に係る炭15 素数12及び14のアルコールに由来するR 4とは相違し、また、洗浄剤組成物に対する当該成分の含有量においても相違するといえるのであるから、本件審決において、本件発明1における式(II)の化合物と甲1発明に係るNI(7EO)が実質的に相違し、また、天然アルコール由来成分の含有量においても相違すると判断した点に誤りはない。 20 ? 相違点1について上記?と同様、 (C)成分の含有量に関し、本件発明1に係る数値範囲が引用発明と一部重複するとしても、技術思想を具体化したものとして実質的に相違していると認定すべきである。 原告が指摘する、甲1の処方XXXIVの記載は、MGDAを40%含有25 するTrilonMをMGDAとして3.13%となるように希釈して使用したと読むのが自然である。また、そもそも処方XXXIVは、添加剤とし17てMGDAを混合したDCPP抗菌剤について、その殺菌効果が高まることをEN1276殺菌試験によって確認したものであって、本件発明1のようにMGDAを配合した衣料用洗浄剤組成物によって繊維を処理した場合の防臭効果の程度やその評価について直接参考となるものではない。 5 したがって、相違点1が実質的相違点でないとする原告の主張に根拠はない。 ? 相違点3について原告は、A/C比に関し、本件発明1に係る数値範囲が引用発明と一部重複する以上、その構成に関しては一致点と判断すべきである旨主張するが、 10 この主張が相当でないことは、相違点1及び相違点2と同様であって、相違点3が実質的相違点でないとする原告の主張に根拠はない。 2 取消事由2(本件各発明の甲1発明に対する進歩性の判断の誤り)について〔原告の主張〕? 相違点2について15 本件発明1の一般式(II) 4 −O−[(R (EO)v /(PO)w ]−(EO)x −H)のR 4に関し、本件明細書では、段落【0034】において、 「直鎖又は分岐鎖であってもよい」 「炭素数12〜14の第2級アルコール由来のア、 ルキル基が好ましい」との記載が存在するのみで、 「炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素」に関する記載は存在しない。また、直鎖アル20 コールは第1級アルコールであるから、上記記載内容からすれば、炭素数12及び14の天然アルコール(第1級アルコール)は、むしろ好ましい選択肢ではないことが読み取れる。 本件明細書の実施例を参酌しても、G−3(LMAO。アルキル基が炭素数12及び14の天然アルコール(第1級アルコール) )を用いた実施例8。 25 と、G−4(EOPOノニオン。アルキル基が炭素数12の第2級アルコール及び炭素数14の第2級アルコール)とで全く作用効果の差がみられず、 18本件各発明に関し、式(II)のR 4 について、炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素(直鎖の炭化水素)とするか、石油アルコール由来の炭化水素(分岐のある炭化水素)とするかは、当業者が通常の創作能力の発揮として行う設計事項にすぎない。 5 したがって、「アルキル基が炭素数12及び14の天然アルコール由来のもの」を用いる積極的な動機付けがなくても容易想到と判断されるべきものである。 仮にこの点を措くとしても、石油由来の高級アルコールと油脂由来の高級アルコールとの価格差が少なくなったことに加え、アルキル基が直鎖である10 ことにより、起泡性が高くなり、洗浄性がより高まることや、環境負荷に関し、石油由来の高級アルコール(分岐アルコール)と比較して、天然油脂由来の高級アルコール(直鎖アルコール)の方が生分解性が良好である点を考慮すれば、甲1発明の「RはC12からC15のアルキル鎖」として、天然由来のアルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)を用いる明確な15 動機付けが見出せる。 また、本件発明1の(G)成分の一般式(I)は、本件明細書の実施例においてG−2として用いられているメチルエステルエトキシレート(MEE)であると考えられるところ、洗浄性能や消臭効果の向上などの観点から、甲1発明のアルコールエトキシレート(NI(7EO))に代わって、これと同20 程度のアルキル基ないしEOの付加数を有するメチルエステルエトキシレート(MEE)を用いる動機付けも存在し、相違点2の式(I)についても容易想到と認められる。 さらに、本件明細書の実施例において、非イオン性界面活性剤 (G)( 成分)を用いた実施例は、 (G)成分を用いない実施例と比べて、一貫して優れた防25 臭効果が得られるとは認識できず、本件明細書の段落【0026】においても、 (G)成分は含んでも含まなくてもよい任意成分として位置付けられてい19る。しかも、上記実施例において(G)成分とされている成分のうち、本件発明1に規定する一般式(I)又は一般式(II)に該当するのは、G−2、 G−2’及びG−3のみであるが、実施例6のG−3をG−4に置き換えた実施例8において作用効果に差異が見られないなど、本件発明1において(G)5 成分を一般式(I)又は一般式(II)に限定する技術的意味は不明である。 以上によれば、相違点2に関して、本件発明1は甲1発明に対して進歩性を欠く。 ? 相違点1について仮に相違点1が実質的な相違点であるとしても、本件明細書の段落【0010 23】の記載からも明らかなとおり、防臭効果や酵素安定化効果を得るために(C)成分を一定程度以上配合する必要があるのは、このような化合物の性質上当然のことであり、経済性の観点から一定程度以下にすべきことも当然の設計思想であって、本件各発明の課題解決とは何ら関係がない。 また、他の公知文献である甲30(国際公開2014/109380号公15 報)、甲33(特開2013−136682号公報)、甲34(特開2016−17133号公報)に記載の配合割合の数値範囲は、いずれも本件発明1の0.02ないし1.5質量%に含まれている。 したがって、 (C)成分に該当する化合物につき、本件発明1に規定の0.02ないし1.5質量%の範囲内にすることは極めて容易であり、むしろ1.20 5質量%を超える値にしなければならない理由が見当たらない。 以上によれば、相違点1は、当業者が甲1発明を基に極めて容易に想到し得たものである。 ? 相違点3について本件発明1においては、 (A)成分であるアニオン界面活性剤の配合割合は25 何ら規定されていないところ、アニオン界面活性剤と(C)成分のようなキレート剤の割合さえ規定すれば所望の防臭効果等が得られるということは考20えられない。 また、本件明細書の実施例には、A/C比が10ないし100を充足しない例も数多く含まれており、A/C比が上記範囲を上回る実施例の防臭効果の評価が、A/C比が上記範囲内の実施例の評価よりも良好な値となってい5 るものがある。 以上のことからすれば、本件発明1のA/C比10ないし100という数値範囲は、単なる設計事項にすぎない。 また、公知文献(甲30、33、34)によれば、 (A)成分に相当するアニオン界面活性剤と(C)成分(MGDA)について、A/C比を10ない10 し100の範囲とすることは、当該技術分野における処方において一般的に採用されている範囲にすぎず、これによって良好な消臭効果や酵素安定性といった本件各発明において意図する作用効果も十分に達成されていることが読み取れる。したがって、相違点3が仮に実質的相違点に該当するとしても、 上記各公知文献を適宜参酌することによって、当業者が極めて容易に想到し15 得たといえる。 以上によれば、相違点3は、当業者が甲1発明を基に極めて容易に想到し得たものである。 ? 被告の主張に対する反論甲1で言及されているAATCC100法は、本件明細書の実施例と少な20 くとも同程度の強い異臭が発生するような厳しい条件下における試験である。 また、MGDAのような添加物を加えることによってDCPPによる殺菌効果が向上することも、甲1に記載されている。しかも、本件明細書の実施例は、その防臭効果の評価からすれば、 「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度のものであり、顕著な防臭効果を発揮しているとはいえない。した25 がって、本件発明1が、甲1から予測不可能な顕著な作用効果をもたらすものとはいえない。 21?ア 上記?ないし?のとおり、本件発明1が甲1発明と相違点があるとしても、本件発明1の構成は当業者が極めて容易に想到し得たものにすぎない。 また、本件発明1について予測できない顕著な作用効果は何ら存在しない。 したがって、本件発明1は甲1発明に対して進歩性を欠くものである。 5 イ 本件発明3ないし5が本件発明1と同様に進歩性を有するとした本件審決の判断は、本件発明1が進歩性を充足するとの前提が成り立たないため、 誤りである。また、本件発明3ないし5に特有の構成を基に進歩性を充足するとは認められない。 〔被告の主張〕10 ? 相違点2についてア 相違点2に係るノニオン界面活性剤は、衣類が湿った状態で菌が増殖し、 強い異臭が発生するような厳しい条件下でも優れた防臭効果を奏する衣料用洗浄剤組成物を提供するとの課題を解決するために、他の成分と共に配合した場合の各成分の安定性や洗浄効果、殺菌作用等を考慮しつつ、 (C)15 成分や(A)成分の含有量などと併せて特定されたものである。そして、 本件明細書に記載された実施例、比較例を参照すると、化合物種や含有量等が特定された本件発明1に係る洗浄剤組成物が上記課題を解決し、格別の効果を奏していることが理解できる。 したがって、甲1発明との上記相違点やその適用が当該技術分野におけ20 る単なる設計事項であり、動機付けが無くても容易想到であるとの原告の主張は失当である。 イ 甲1発明におけるノニオン界面活性剤NI(7EO)と本件発明1に係る(G)成分について、その化合物種、含有量のいずれにおいても実質的に相違することは、前記1〔被告の主張〕?のとおりである。 25 また、本件審決が甲1発明と認定した、甲1における「処方LI」は、 洗浄剤組成物における特定の成分の配合割合が一定の範囲をもって示さ22れるのみで、実際には非常に広範な組成物群が想定され、その抗菌性についても、いかなる洗浄剤組成物がどの程度の抗菌作用及び脱臭効果を奏するものかについて開示するものではないから、甲1発明が衣料用洗浄剤組成物としてどの程度の防臭効果を奏するのかは不明である。 5 そして、 (G)成分は、本件発明1に係る他の成分と共に配合した場合の各成分の安定性や洗浄剤組成物全体としての洗浄効果、殺菌作用等を考慮して選択されるものであり、本件発明1が解決すべき課題とした衣類が湿った状態で菌が増殖し、強い臭気が発生するような厳しい条件下での防臭作用については、甲1発明や他の引用文献に記載された技術的事項から認10 識することはできないのであって、甲1発明において、 (G)成分の化合物種や含有量、他の成分の配合量、配合割合に着目し、これらを特定するとの技術思想は見出せない。 また、ノニオン界面活性剤成分として配合されているNI(7EO)に代えて、本件発明1に係る(G)成分を用いることによって、他の洗浄剤15 組成物の成分に係る特定と相俟って、強い異臭が発生するような厳しい条件下でも優れた防臭効果を奏する衣料用洗浄剤組成物が得られていることにも鑑みれば、甲1発明及び他の公知技術から、ノニオン界面活性剤成分として配合されているNI(7EO)に代えて、本件発明1に係る(G)成分を用いることについて当業者が容易に想到し得るとの根拠を見出す20 ことはできない。 経済的な理由や環境負荷への配慮等から(G)成分を選択し得るとの事情のみでは、本件各発明の課題を認識しない甲1発明におけるノニオン界面活性剤成分を本件発明1に係る(G)成分に置き換えた洗浄剤組成物に想到する動機付けとはならない。 25 ウ 仮に、甲1発明のNI(7EO)に代えて本件発明1に係る(G)成分を配合すること、更には配合量において本件発明1の範囲とすることが動23機付けられたとしても、上記イのとおり、甲1発明に係る衣料用洗浄剤組成物がどの程度の防臭効果を奏するのかは不明であり、抗菌や脱臭の程度についてもせいぜい上記AATCC100−2004法で評価される一定の抗菌作用が期待されることを示唆しているにすぎないことに鑑みれ5 ば、本件発明1によって、衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境においても高い防臭効果を奏する洗浄剤組成物が得られるとの効果は、甲1発明において相違点2並びに他の相違点(相違点1、3)に係る発明特定事項を適用した場合に奏するものとして当業者が予測することができた範囲を超える顕著な効果といえるから、当業者が容易に発明をすることがで10 きたものではないというべきである。 ? 相違点1について甲1発明において、 (C)成分の含有量に着目し、これを特定の範囲とするとの技術思想は見出せず、 (C)成分の含有量を一定の範囲内とした本件発明1について、他の成分に係る特定と相俟って、厳しい条件下においても防臭15 効果に優れるとの格別の効果が確認されていることも考慮すれば、甲1発明において(C)成分の含有量を特定することによって本件各発明に係る特定の洗浄剤組成物に至る動機付けはない。 甲1においては、MGDAを含有する処方LIと、MGDAを含有していない処方XLIX、L、LIIが、いずれもAATCC100法による評価20 において優れた抗菌効果を示しており、甲1発明に係る洗浄剤組成物において、本件発明1の(C)成分に相当するMGDAを必須の成分としてその含有量に着目する理由はない。 原告が指摘する甲30、33及び34に記載されている洗浄剤は、いずれも本件発明1に係る(B)成分であるフェノール型抗菌剤を含むものではない。 25 また、甲30及び34に記載された洗浄剤組成物はいずれも酵素を配合したものであり、その保存安定性や活性を良好にすることなどを目的として、ア24ミノカルボン酸が添加されており、甲33に記載された洗浄剤組成物は、本件発明1と同様に消臭効果を狙ったものではあるが、金属とアミノカルボン酸キレート剤の併用でアニオン界面活性剤の存在下でも防臭効果を示すものである。このように、これらの文献に記載された洗浄剤組成物は、本件発明5 1に係る洗浄剤組成物とは主たる成分において異なるものであり、MGDAの配合量がたまたま本件発明1における(C)成分の含有量と一致する部分があるとしても、そのことをもって甲1発明におけるMGDA配合量として採用する動機付けとはならない。 仮に、甲1発明において(C)成分の含有量を本件発明1に係る範囲とす10 ることが動機付けられるとしても、前記?ウのとおり、本件発明1による効果は、甲1発明における相違点1ないし3に係る発明特定事項を適用した場合に奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるから、当業者が容易に発明をすることができたものではないというべきである。 15 ? 相違点3について相違点3が単なる設計事項であるとの原告の主張が失当であることは、相違点2と同様である。 また、相違点2及び相違点1と同様、甲1発明において、 (C)成分の含有量に加えてA/C比についても着目し、これを特定の範囲とするとの技術思20 想は見出せない。そして、本件発明1について格別の効果が確認されていることにも鑑みれば、甲1発明においてA/C比を調整することによって本件発明1に係る特定の洗浄剤組成物に想到する動機付けは見出せない。 甲30、33及び34も、前記?のとおり、洗浄剤組成物としては本件発明1と異なるものであり、これら文献に記載された実施例から算出されるA25 /C比がたまたま本件発明1と一致するものがあるとしても、それを甲1発明に適用する動機付けとはならない。A/C比が最小で2.4、最大で32250である甲1発明において、 「10〜100」とさらに限定することは、当業者が容易に想到することではない。 また、本件明細書の実施例15や22を参照すれば、抗菌剤の含有量が同じ、あるいは多い場合であっても、A/C比が上記範囲を外れるときには防5 臭効果が劣ることから、甲1発明において防臭性の向上に影響し得る指標となり得るA/C比が好適な範囲内である、本件発明1に係る特定の洗浄剤組成物に至る動機付けはない。 仮に、甲1発明においてA/C比を本件発明1に係る範囲とすることが動機付けられるとしても、前記?ウ及び?のとおり、本件発明1による効果は、 10 甲1発明における相違点1ないし3に係る発明特定事項を適用した場合に奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるから、当業者が容易に発明をすることができたものではないというべきである。 ? 以上のとおり、本件発明1は甲1発明に基づく進歩性を満たす。 15 また、本件発明3ないし5は、本件発明1を直接又は間接的に引用し、さらに特定事項を加えたものであるから、本件発明1と同様、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない発明ではない。 3 取消事由3(本件各発明のサポート要件違反の有無に関する判断の誤り)について20 〔原告の主張〕? 本件各発明の構成によりその課題を解決できると認識できないこと本件明細書の実施例による防臭効果の評価によれば、本件各発明の構成によって得られる効果はせいぜい「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度であり、 「衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境においても、十分な25 防臭効果が得られ、防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供する」という本件各発明の課題解決の水準に達していない。 26また、上記防臭効果の評価に用いた臭気評価布について、本件明細書の段落【0055】の記載された条件からは、湿った状態で菌が増殖しやすい環境であることは読み取れず、異臭が発生しやすい条件下で試験が行われたといえる根拠もない。プロテアーゼのような衣類用洗剤の分野で汎用的に使用5 されている成分を含有することのみによって、防臭効果が3. (実施例6)2から2.3(実施例9)へと大きく改善していることも考慮すれば、 「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度の評価しか得られなかったのは、段落【0055】に記載の条件が特別過酷であったからではなく、本来課題解決に不可欠なはずの成分が含まれていなかったことによると考えられる。 10 以上によれば、本件各発明の課題を解決するためには、 (E)成分:硫酸「亜鉛一水和物」の存在が不可欠であると考えるほかない。 ? 本件明細書の効果が(C)成分一般に当てはまらないこと本件各発明がサポート要件を充足することの根拠として本件審決が挙げた甲13(別紙3「文献の記載」9)、甲17(別紙3「文献の記載」10)15 及び甲18(別紙3「文献の記載」11)(本件審決における乙1、5及び6)は、いずれも、本件各発明の課題に関して何ら評価がなされておらず、かつ、 その構成は本件発明1の一般式(c1)とは必ずしも一致しないため、上記根拠となり得るものではない。 また、共通基本骨格がアミノカルボン酸と酷似している「C−3:クエン20 酸三ナトリウム」が用いられた比較例が明らかに実施例よりも効果が劣っていることも考慮すれば、構造の僅かな違いでも本件各発明において重要な意味を持つと考えるのが合理的であり、上記(c1)のnの数が多くなり、かつAがCOOMのようにキレート剤としての機能を有する官能基である場合についてまで、実施例と同様又は類似の防臭効果が得られるとは認識できな25 い。 したがって、仮に本件明細書の実施例から何らかの効果を認識し得るとし27ても、(C)成分としてメチルグリシン二酢酸三ナトリウム (MGDA)以外を用いた場合についてサポートされているとは認められない。 ? (G)成分として「G−1:椰子脂肪酸」が必須であること甲12の記載などに示されているように、椰子脂肪酸などの脂肪酸も消臭5 効果を併せ持つことは技術常識であり、G−1成分が抑泡やすすぎ性の向上のための泡コントロール剤としての効果だけではなく、十分な防臭効果を得る効果も有すると考えられる。したがって、 (G)成分に関し、G−1成分を含まない場合についてまでサポートされているとは認められない。 ? 以上のとおり、本件発明1はサポート要件を充足せず、本件発明1を引用10 する本件発明3ないし5も同様である。 〔被告の主張〕? 本件各発明の構成によりその課題を解決できると認識できること本件各発明は、実施例に記載されているとおり、強い異臭が発生する厳しい条件下における防臭効果の評価を行っていることから、防臭効果の判定が15 「3点:異臭がやや強く感じられる」に相当する例においても、高い防臭効果は得られたと評価することに何ら問題はなく、 (E)成分:硫酸亜鉛一水「和物」を含まない実施例についても、当業者は、本件発明1で特定される洗浄剤組成物によって、衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境においても高い防臭効果を有すること、すなわち、本件各発明の課題が解決できること20 を十分認識できるといえる。 したがって、本件各発明は、発明の詳細な説明において、発明の課題を解決できることを当業者が認識できる範囲内のものである。 ? 本件各発明の効果が式(c1)で表される化合物一般に当てはまること式(c1)で表される化合物は、 「C−1:メチルグリシン二酢酸三ナトリ25 ウム(MGDA)」やグルタミン酸二酢酸塩(GLDA)に代表される洗浄剤に配合されるキレート剤として知られるアミノカルボン酸化合物であり(甲2813、17、18)、これらが洗浄剤組成物におけるキレート剤として好適に用いられることからみて、本件明細書の記載に接した当業者であれば、一般式(c1)で表される化合物の共通の基本骨格を有し、そこに結合する置換基の種類が本件発明1において定めたAの範囲の化合物について、洗浄剤組5 成物に配合されるキレート剤化合物として同等の機能を発揮し、防臭効果に優れた衣料用洗浄剤を提供するとの課題の解決に寄与することが理解できる。 したがって、 「当業者であれば、A、M、nに関し他の選択肢を組み合わせた化合物を(C)成分とした場合でも、実施例6〜7、9〜14、20と同様又は類似の防臭効果が得られ、前記アで示した課題が解決できることを認10 識できるといえる。」との審決の判断に誤りはない。 また、 「C−3:クエン酸三ナトリウム」を配合した実施例が、本件発明1の(C)成分に該当する成分を配合した実施例よりも効果において劣ることが、本件発明1のサポート要件を満たさないことの根拠となることはない。 ? (G)成分として「G−1:椰子脂肪酸」は必須でないこと15 衣料用洗浄剤において、主に抑泡やすすぎ性の向上のための泡コントロール剤として椰子脂肪酸(G−1)に代表される脂肪酸が少量添加されることは、当該技術分野における技術常識であり、本件明細書に接した当業者は、 当該成分が本件各発明の課題である「衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境において、十分な防臭効果」を得るために必要な成分とはいえないこと20 を十分に理解するのであって、全ての実施例に(G−1)が含まれていることのみをもって、当該成分が本件各発明の課題を解決するために必要な成分であるとはいえない。 したがって、本件審決が、 「G−1:椰子脂肪酸」が本件発明1で必須成分として特定されなくても、当業者は、本件発明1の構成を備えることで、本25 件各発明の課題を解決できることを十分認識できるとした点に誤りはない。 ? 以上のとおり、サポート要件に関する本件審決の判断に誤りはない。 29第4 当裁判所の判断1 本件各発明の技術的意義等? 特許請求の範囲本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、前記第2の2に記載のとおりで5 ある。 ? 本件明細書の記載本件明細書の記載は、別紙2特許公報(甲7)の【発明の詳細な説明】のとおりである。 ? 本件各発明の技術的意義10 上記?の特許請求の範囲及び上記?の本件明細書の記載によれば、本件各発明の技術的意義は次のとおりであると認められる。 ア 技術分野本件各発明は、衣料用洗浄剤組成物に関する。(段落【0001】)イ 背景技術15 近年、衛生志向の高まりから、衣料用洗浄剤組成物には、衣類に付着した汚れの除去(洗浄効果)だけでなく、衣類から発生する嫌な臭いの抑制(防臭効果)が求められているが、衣類から発生する嫌な臭い発生の原因として衣類に付着した菌と汚れの関与が考えられており、洗濯時に衣類に残存した菌は、衣類の乾燥過程でタンパク質等の汚れを栄養源に増殖し臭20 いを発生することから、洗濯中および洗濯後の乾燥時において菌を制御することが高い防臭効果に寄与する。(段落【0002】)防臭効果を付与した従来の衣料用洗浄剤組成物には菌の増殖を抑制するためカチオン界面活性剤などの抗菌剤が配合されていたが、衣料用洗浄剤組成物にアニオン界面活性剤と併用すると配合効果が発揮できず、十分25 な菌の抑制効果が得られないといった問題があった。(段落【0002】)そこで、共存するアニオン界面活性剤の影響を受けにくいトリクロサン30などのフェノール型抗菌剤を含む衣料用洗浄剤組成物が提案されている(例えば、特開2001−146681号公報参照。。 )(段落【0002】)ウ 本件各発明が解決しようとする課題しかし、上記特許公報に記載された衣料用洗浄剤組成物では、衣類が湿5 った状態で菌が増殖しやすい環境において、十分な防臭効果が得られなかったことから、本件各発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供することを課題とする。(段落【0004】)つまり、本件各発明の課題は、衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環10 境においても防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供することである。 エ 課題を解決するための手段発明者は、特定のアニオン界面活性剤と、フェノール型抗菌剤と、アミノカルボン酸型キレート剤とを組み合わせることにより上記課題を解決15 できることを見出し、本件各発明を完成するに至った。 (段落【0005】)オ 本件各発明の効果本件各発明によれば、防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供できる。(段落【0007】)カ 発明を実施するための形態20 本件各発明の衣料用洗浄剤組成物は、以下の(A)成分、 (B)成分、 (C)成分及び(G)成分を本件各発明の各請求項に記載の所定量あるいは量比で含有する組成物である。(段落【0008】〜【0034】)(ア) (A)成分:アニオン界面活性剤(但し炭素数10〜20の脂肪酸塩を除く)25 (A)成分は、炭素数10ないし20の脂肪酸塩を除く少なくとも一種のアニオン界面活性剤であり、界面活性剤の種類によらず防臭効果と31酵素安定性を発揮できる。(段落【0009】〜【0012】)(イ) (B)成分:フェノール型抗菌剤(B)成分は、4,4’−ジクロロ−2−ヒドロキシジフェニルエーテル(慣用名:ダイクロサン)を含むフェノール型抗菌剤で、洗濯後の5 衣類等の繊維製品に抗菌性を付与する成分であり、衣料用洗浄剤組成物中においてアニオン界面活性剤と共存させても、アニオン界面活性剤による洗浄性を損なわずに抗菌性を発揮できる。(段落【0013】〜【0018】)(ウ) (C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン10 酸型キレート剤(C)成分は、下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレート剤であり、 (C)成分と(B)成分との併用により高い防臭効果が得られる。さらに、(C)成分により、酵素((D)成分)の安定性を損なうことなく、 (C)成分が寄与する洗浄性能(たとえばプロテ15 アーゼの場合、タンパク汚れに対する洗浄性能)を向上させることができる。 (式(c1)中、Aは、それぞれ独立してH、OHまたはCOOMであり、Mは、それぞれ独立してH、Na、K、NH 4またはアルカノールア20 ミンであり、nは0〜5の整数である。)(C)成分の含有量は、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、0.01ないし2質量%が好ましく、0.02ないし1.5質量%がより好ましく、 (C)成分の含有量が下限値以上であると、十分な防臭および酵素32安定性の効果が得られやすく、上限値以下であると経済的に好ましい。 (段落【0019】〜【0023】)(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)は、5ないし700が好ましく、10ないし560が好ましく、10ないし100が5 さらに好ましい。A/C比を上記数値範囲内とすることにより、十分な防臭及び酵素安定性の効果が得られる。 (エ) (G)成分:一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であるノニオン界面活性剤。 (A)(B)(C)成分の他に、酵素(、 、 (D)成分)、金属化合物((E)10 成分)(A)成分以外の界面活性剤(、 (G)成分)等を含んでよく、 (G)成分としては、炭素数10〜20の脂肪酸塩、ノニオン界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。 このうち、ノニオン界面活性剤としては、下記一般式(I)又は(II)で表されるものが好ましい。 15 R2−C(=O)O−[(EO)s /(PO)t ]−(EO)u−R 3 ・・・(I)R4−O−[(EO) v /(PO) w ]−(EO) x −H ・・・(II)式(I)中、R 2 は炭素数7ないし22の炭化水素基であり、R 3 は炭素数1ないし6のアルキル基であり、sはEOの平均繰り返し数を表し、 20 6ないし20の数であり、tはPOの平均繰り返し数を表し、0ないし6の数であり、uはEOの平均繰り返し数を表し、0ないし20の数であり、EOはオキシエチレン基を表し、POはオキシプロピレン基を表す。 式(II)中、R4は炭素数6ないし22の炭化水素であり、10ない25 し20が好ましく、10ないし18がさらに好ましい。R 4 は、直鎖又は分岐鎖であってもよい。R 4としては、具体的には、炭素数12ないし1334の第2級アルコール由来のアルキル基が好ましい。 式(II)中、vはEOの平均繰り返し数を表し、3ないし20の数であり、wはPOの平均繰り返し数を表し、0ないし6の数であり、xはEOの平均繰り返し数を表し、0ないし20の数であり、EOはオキ5 シエチレン基を表し、POはオキシプロピレン基を表す。 (G)成分としては、ノニオン界面活性剤が、洗浄力、液の安定性の観点から好ましく、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20ないし40質量%であることが好ましい。 (以上、段落【0026】 【0030】〜【0034】 【0039】、 、 )10 ? 本件明細書における実施例及び防臭効果の測定について本件明細書には、 (A)成分、 (B)成分、 (C)成分及び(G)成分として、 それぞれ複数の組成物を調製し、各成分の組成物を様々な割合で配合して得られた実施例1ないし22及び比較例1ないし8の衣料用洗浄剤組成物を用いた防臭効果の評価(以下「本件防臭効果評価」という。)について記載され15 ている。(段落【0046】以下)本件防臭効果評価の方法は、以下のとおりである。 混紡シャツ(綿60%、ポリエステル40%)を30代又は40代の男性11人に14時間着用させた後、各例の洗浄剤組成物を用いて、洗濯機(JW−Z23A型、ハイアール社製)の通常コースで洗濯処理(水温約15℃、 20 硬度約3゜DHの水道水を注水、浴比30倍)を行った。その際、衣料用洗浄剤組成物の洗濯機への投入量を10mL/水道水30Lとし、実施例21、 22のみ、投入量を20mL/水道水30Lとして洗濯処理を行った。 洗浄終了後に、約25℃、相対湿度60%RHの室内にて12時間乾燥後、 洗浄せずに2日間家庭で使用した。家庭での使用中、洗浄は行っていない。 25 2日間使用後、ポリ袋に密封した状態で回収し、25℃の条件で1日間保管したものを臭気評価布とした。 34臭気評価布に対して、6段階臭気強度評価法により11名の専門パネラー臭いを評価した。得られた評価点の平均点数を求め、以下の判定基準により評価した。 ア 防臭効果の評価基準5 0点:異臭が全くしない。 1点:異臭がやっと感知できる程度に感じられる。 2点:異臭が弱く感じられる。 3点:異臭がやや強く感じられる。 4点:異臭が強く感じられる。 10 5点:異臭が強烈に感じられる。 イ 判定基準◎:11名の平均点数が0.0点以上1.5点未満。 〇:11名の平均点数が1.5点以上2.5点未満。 △:11名の平均点数が2.5点以上3.5点未満。 15 ×:11名の平均点数が3.5点以上5.0点以下。 2 取消事由1(本件各発明の甲1発明に対する新規性の判断の誤り)について? 甲1の記載内容は、別紙3「文献の記載」1のとおりである。 この甲1の記載内容によれば、甲1には本件審決が認定した甲1発明(前記第2の4?ア)が記載されていると認められる。この甲1発明が甲1に記20 載されていることについては、当事者間に争いがない。 そして、甲1発明の内容に照らせば、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、本件審決が認定した前記第2の4?イのとおりであると認められる。 ? 相違点2について25 ア 相違点2に係る技術常識について甲10(別紙3「文献の記載」2)、甲11(別紙3「文献の記載」3)35及び甲14(別紙3「文献の記載」4)には、それぞれ別紙3「文献の記載」2ないし4のとおりの記載が存在する。 これらの記載の内容によれば、R−O−(CH 2CH 2 O) n −Hの化学式で表されるAE(アルコールエトキシレート)におけるアルキル基につ5 いて、一般の洗剤に含まれるものはアルキル基「R」がC12ないしC15であるものを主体とし、アルキル基「R」の原料として油脂由来(天然物由来)の高級アルコール(天然アルコール)と石油由来の高級アルコール(合成アルコール)のいずれもが利用されており、天然アルコールは偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有するのに対し、石油由来の合成ア10 ルコール(エチレンを原料とするチーグラー法で得られたものを除く)については、炭素数が奇数であるものを含むか、又は分枝鎖の炭化水素基を有することが、本件出願日当時の技術常識であったものと認められる。 なお、甲1発明のNI(7EO)及び本件発明1の(G)成分の一般式(II)は、AE(アルコールエトキシレート)に該当する(甲10、115 1、31、32、弁論の全趣旨)。 イ 本件発明1の(G)成分と甲1発明のNI(7EO)との対比本件発明1のノニオン界面活性剤である(G)成分のうち、一般式(I「R 4−O−[I) (EO)v /(PO)w]−(EO)x −H」で表される化合物におけるR 4は、 「炭素数12及び炭素数14の天然アルコール由来の20 炭化水素」であるとされているが、これは、上記アの技術常識によれば、 炭素数12及び炭素数14の直鎖の炭化水素であることを意味するものと認められる。そうすると、炭素数が奇数であるか、又は分枝鎖を有する炭化水素基は、上記R 4 に該当せず、このような炭化水素基を有する化合物は、一般式(II)で表される化合物から除外されるものと認められる。 25 他方、甲1発明に含まれるノニオン界面活性剤は「R−(OCH 2CH 2)n OH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)」であるNI(7E36O)である。このNI(7EO)の構造式は、本件発明1の(G)成分の「R」と「R4」一般式(II)においてw=0、v+xが7とした場合と、 との違いを除き、構造式としては共通する(「EO」(オキシエチレン基)は「‐CH 2CH 2O‐」である(甲10、37) )。。 5 しかし、甲1発明のNI(7EO)における「RはC12からC15のアルキル鎖」はその文言以上の特定はなく、炭素数が奇数(13又は15)であるか、又は分枝鎖の炭化水素基を除外するものとは認められず、天然アルコール由来のものに限定されるとは認められない。 そうすると、上記アの技術常識からすれば、当業者は、甲1発明のアル10 キル基「R」につき、 「C12からC15のアルキル鎖」として、偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール由来のものと、炭素数が奇数であるか、又は分枝鎖の炭化水素基を有する合成アルコール由来のものの両方を利用できると認識するものといえる。 以上によれば、相違点2は実質的な相違点であるというべきであり、こ15 れが形式的な相違点にすぎないとは認められない。 ウ 原告の主張に対する判断原告は、前記第3の1〔原告の主張〕?のとおり、相違点2は形式的な相違点であり、本件審決の判断が誤りであると主張する。 この点、本件審決は、甲1のNI(7EO)がNeodol25−7と20 いう特定の商品を指すものとであると認定し、これを前提に相違点2が実質的な相違点であると判断しているが、NI(7EO)がNeodol25−7を指すと認定すべき根拠はないというべきである。すなわち、甲1の処方LIの箇所には、NI(7EO)に関し、 「NI(7EO)はR−(OCH 2 CH 2 ) n OHを指すところ、このRはC12からC15のアルキル25 鎖であり、n=7である。」との記載があるのみであり(別紙3「文献の記載」1?の記載)、商品名は記載されていない。また、甲15(特表201374−529660号公報)の段落【0034】には、 「NI7EOは、C12−15アルコールエトキシレート7EO非イオン性Neodol(登録商標)25−7(Shell Chemicalsから)である。」との記載があるが、これは甲15の実施例においてNI(7EO)として用いる5 具体的な商品を記載したものと解され、NI(7EO)がNeodol25−7を指すものと解すべき根拠とはならない。しかし、上記ア及びイの説示によれば、NI(7EO)がNeodol25−7を指すものではないとしても、相違点2が実質的な相違点であると認められるとの結論は左右されないというべきである。 10 甲1発明のアルキル基Rが、偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール由来のものを利用できるとしても、炭素数が奇数であるか、又は分枝鎖の炭化水素基を有する合成アルコール由来のものも利用できるのであるから、本件発明1の(G)成分の一般式(II)におけるR4が「炭素数12及び炭素数14の天然アルコール由来の炭化水素」に限15 定されていることと相違しているというべきであり、前者が後者を包含しているから形式的な相違点にすぎないと解することはできない。 そして、その他原告が前記第3の1〔原告の主張〕?で主張する内容を検討しても、上記イの結論は左右されない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 20 ? 相違点1についてア 甲1発明におけるMGDA(Trilon M)の含有量「0.1〜5wt%」は、本件発明1における(C)成分の含有量「0.02〜1.5質量%」と一部重複するものの、甲1発明における含有量の割合の範囲は、 本件発明1における含有量の割合の範囲に該当しないものを含んでいる。 25 したがって、本件発明1と甲1発明との相違点1は実質的な相違点であるというべきであり、これが形式的な相違点であるとは認められない。 38イ 原告の主張に対する判断原告は、前記第3の1〔原告の主張〕?のとおり、相違点1は形式的な相違点にすぎないと主張する。 しかし、本件発明1における(C)成分の含有量は0.02ないし1.5 5質量%であり、甲1発明におけるMGDA(Trilon M)の含有量は0.1ないし5wt%(質量%)であって、上記アのとおり、甲1発明における含有量の割合の範囲は、本件発明1における含有量の割合の範囲に該当しないものを含んでいる。そうすると、数値が一部重複しているからといって、相違点1が形式的な相違点にすぎないと解すべきというこ10 とにはならない。 原告が挙げる甲1の処方XXXIVには、 「3.13%MGDA(Trilon ?M、有効成分40%、BASF、納品時に使用)」との記載があるが、この記載は、MGDAを40%含有するTrilon Mを、MGDAとして3.13%となるように希釈して使用したと読むのが自然である15 から、上記処方が、MGDAを1.252質量%配合したものとは認められない。また、甲1発明は甲1の処方LIの配合によるものであって、仮に、甲1において挙げられたLI以外の処方におけるMGDAの含有量が、 本件発明1における(C)成分の含有量の割合に含まれるとしても、そのことによって、本件発明1と甲1発明との相違点1が形式的な相違点にす20 ぎないと解すべきことにはならない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ? 相違点3についてア 本件審決が相違点3の認定において指摘するとおり(前記第2の4?イ)、 甲1発明は、 (A)成分に相当するアニオン界面活性剤である各成分の合計25 が12ないし32wt%であり、 (C)成分に相当するMGDA(Trilon M)の含有量が0.1ないし5wt%であるが、A/C比について39は特定されていない。上記の両成分の含有量の範囲から計算すると、A/C比の値は、最小で2.4、最大で320となる。 他方、本件発明1では、 (A)成分/(C)成分で表される質量比(A「/C比)が10〜100である」とされている。 5 そうすると、甲1発明において算出されるA/C比の範囲は、本件発明1のA/C比の範囲に該当しないものを含むといえる。 したがって、本件発明1と甲1発明との相違点3は実質的な相違点であるというべきであり、これが形式的な相違点であるとは認められない。 イ 原告の主張に対する判断10 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕?のとおり、相違点3は形式的な相違点にすぎないと主張する。 しかし、相違点1に関する原告の主張と同様、甲1発明において算出されるA/C比の範囲と、本件発明1のA/C比の範囲が一部一致することをもって、相違点3が形式的な相違点にすぎないと解すべきことにはなら15 ず、かつ、甲1の処方LI以外の処方に関して算定したA/C比の範囲が本件発明1のA/C比の範囲に含まれるからといって、相違点3が形式的な相違点にすぎないと解すべきことにもならない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ? 以上によれば、本件発明1と甲1発明との相違点1ないし3のいずれも、 20 実質的な相違点であるといえるから、本件発明1と甲1発明が同一であるとは認められない。 また、本件発明3ないし5は、本件発明1を直接又は間接的に引用し、さらに特定事項を加えたものであるから、本件発明1と同様、これらの発明が甲1発明と同一であるとは認められない。 25 したがって、取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(本件各発明の甲1発明に対する進歩性の判断の誤り)について40? 相違点2についてア 相違点2に係る技術常識について前記2?のとおり、甲10、11及び14によれば、AE(アルコールエトキシレート)におけるアルキル基について、一般の洗剤に含まれるも5 のはアルキル基がC12ないしC15であるものを主体としていることが本件出願日当時の技術常識であったと認められるが、さらに、甲10によれば、近年は油脂由来(天然物由来)の高級アルコール(天然アルコール)と石油由来の高級アルコール(合成アルコール)の価格差が少なくなり、天然油脂由来の高級アルコールが多く用いられるようになってきたこ10 とも、本件出願日当時の技術常識であったことが認められる。 また、甲36(別紙3「文献の記載」5)、甲37(別紙3「文献の記載」6)には、それぞれ別紙3「文献の記載」5及び6のとおりの記載が存在し、これらの記載からも、AE(アルコールエトキシレート)における炭素数が12ないし15のアルキル基の原料として、天然アルコールが用い15 られていることが、本件出願日当時の技術常識であったことが認められる。 以上によれば、従前から、洗剤に用いるAE(アルコールエトキシレート)は、C12ないし15(炭素数12〜15)のアルキル基を有するものが主体であって、そのC12ないし15のアルキル基の原料として、油脂由来の偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール20 (炭素数12及び14の直鎖アルコール)が、石油由来の合成アルコールと同様に、一般に用いられており、特に近年は、価格差が少なくなったことなどから、天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)が多く用いられるようになってきたことが、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。 25 他方、天然アルコール由来の炭化水素と合成アルコール由来の炭化水素とで、いずれか一方が他方よりも衣料用洗浄剤の組成物に適しているとの41技術常識があったとは認められない。 イ 本件発明1における(G)成分の技術的意義について本件明細書の段落【0026】は、 (A)成分以外の界面活性剤を(G)成分と称することとしているが、段落【0008】は、 「本発明の衣料用洗5 浄剤組成物は、以下の(A)成分、 (B)成分及び(C)成分を含有する組成物である。」と記載し、同段落では(G)成分は本件各発明の衣料用洗浄剤に必須の組成物とは位置付けられていない。また、段落【0026】の記載によれば、(G)成分は、(A)成分ないし(C)成分のほかに「含んでいてもよい」とされる他の成分の一つとして位置付けられているにすぎ10 ない。 本件発明1は、 (G)成分を一般式(I)又は(II)のいずれか1種と特定しており、一般式(II)のR 4 を「炭素数12及び14の天然アルコ「R 4 は、直鎖又ール由来の炭化水素」であるとするが、本件明細書には、 」「R 4 としては、具体的には、炭素数12〜1は分岐鎖であってもよい。 、 15 4の第2級アルコール由来のアルキル基が好ましい。」との記載はあるものの(段落【0034】、R 4 として炭素数12及び14の天然アルコール)由来の炭化水素が好ましいとの記載は本件明細書に存在せず、本件発明1の(G)成分の一般式(II)においてR 4 が炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であるとされた理由は本件明細書の記載からは20 明らかでない。 また、本件明細書に記載された本件防臭効果評価では、 (A)成分、 (B)成分、 (C)成分及び(G)成分として、それぞれ複数の組成物を調製し、 各成分の組成物を様々な割合で配合して得られた実施例1ないし22及び比較例1ないし8の衣料用洗浄剤組成物が用いられている。本件防臭効25 果評価で用いられた(G)成分は、G−1、G−2、G−2’、G−3及びG−4の5種類であり、このうち本件発明1で特定された(G)成分に該42当するものはG−2、G−2’及びG−3であるが、実施例1ないし22のうち、実施例1ないし5にはG−1ないしG−4のいずれも配合されておらず、実施例6、7及び9ないし20には、G−1が2質量%、G−2、 G−2’又はG−3のいずれか2種類が合計30質量%含まれ、実施例25 1及び22には、G−1が1質量%、G−2及びG−3が各7.5質量%(合計15質量%)含まれている。そして、防臭効果の評価の結果をみると、G−2、G−2’又はG−3のいずれかを合計30質量%含む実施例6、7及び9ないし20が、G−1ないしG−4のいずれの成分も含まない実施例1ないし5並びにG−2及びG−3を合計15質量%含むにと10 どまる実施例21及び22に比べて一貫して優れた防臭効果を得られているとは認められず、実施例6、7、12などは、むしろ、実施例1ないし5、21及び22よりも防臭効果が劣る結果となっている。 以上のとおり、本件明細書の記載からは、 「(A)成分以外の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分15 であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明1で特定された(G)成分に該当するG−2、G−2’及びG−3についても、本件防臭効果評価において、これらの成分を用いた実施例が他の実施例に比べて優れた防臭効果を得られていないのであって、これらのことからすれば、本件発明1において、 (G)成分を一般式(I)又は一般式(II)で表される少な20 くとも1種であるとし、一般式(II)のR 4を炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素と特定したことについて、格別の技術的意義があるとは認められない。 ウ 上記ア及びイによれば、炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素が、甲1発明の「C12からC15のアルキル鎖」に包含されるも25 のであることは当業者に明らかであり、天然アルコール由来の炭化水素と合成アルコール由来の炭化水素とで、いずれか一方が他方よりも衣料用洗43浄剤の組成物に適しているとは認められず、どちらを選択するかについて格別の技術的意義があるとも認められないから、アルコールエトキシレート(AE)のC12ないし15(炭素数12〜15)のアルキル鎖の原料として、近年多く用いられている、油脂由来の偶数の炭素からなる直鎖の5 炭化水素基を有する天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)を用いることは、当業者が当然に想起するものであるといえる。 エ 甲1発明において、NI(7EO)の含有量は「5〜25wt%」とされているところ、特定された範囲内で含有量を規定することは、当業者の設計事項にすぎないというべきである。 10 オ 以上によれば、甲1発明のNI(7EO)において、本件出願日当時の技術常識を考慮し、 「C12からC15のアルキル鎖」として天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)由来の炭化水素を採用し、かつ、ノニオン界面活性剤((G)成分)の含有量を、甲1発明における含有量の範囲内で検討して「20〜25質量%」にすることによって、相違点15 2に係る構成を導くことは、当業者が容易に想到することができたものというべきである。 したがって、甲1発明において、相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、甲1発明並びに甲10、11、14、36及び37に記載された各周知技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであ20 るといえる。 ? 相違点1について前記相違点2に係る判断と同様に、甲1発明の(C)成分に相当するMGDA(Trilon M)の含有量についても、特定された範囲内で含有量を規定することは、当業者の設計事項であるから、その含有量を、甲1発明25 における含有量「0.1〜5wt%」の範囲内で検討し、 「0.1〜1.5質量%」にすること(相違点1に係る構成を導くこと)は、当業者が容易に想44到することができたものといえる。 ? 相違点3について上記?のとおり、甲1発明において、 (C)成分に相当するMGDA(Trilon M)の含有量を、甲1発明における含有量「0.1〜5wt%」5 の範囲内で検討し、 「0.1〜1.5質量%」にすることは、当業者の設計事項にすぎない。 また、甲1発明において、アニオン界面活性剤である(A)成分の含有量についても、その含有量の合計である「12〜32wt%」の範囲内で、当業者が適宜設定し得る事項である。 10 そして、 (A)成分と(C)成分を甲1発明に記載の各含有量の数値範囲内で設定した結果として、A/C比を「最小で2.4、最大で320」の範囲内である「10〜100」とすること(相違点3に係る構成を導くこと)も、 当業者にとって格別の創意工夫を要するものであるとは解されず、当業者が容易に想到することができたものといえる。 15 ? 上記?ないし?のとおり、本件発明1は、甲1発明並びに甲10、11、 14、36及び37に記載された各周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項により特許を受けることができない発明であると認めるのが相当である。 ? 被告の主張に対する判断20 ア 被告は、前記第3の2〔被告の主張〕?アのとおり、相違点2が設計事項であるとは認められない旨主張する。 しかし、前記?イのとおり、本件明細書の記載からは、 (A)成分以外「の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明125 で特定された(G)成分に含まれるG−2、G−2’及びG−3についても、本件防臭効果評価において、これらの成分を用いた実施例が他の実施45例に比べて優れた防臭効果を得られていないことからすれば、本件発明1において、 (G)成分を一般式(I)又は一般式(II)に特定したことに格別な技術的意義があるとは認められず、少なくとも、ノニオン界面活性剤((G)成分)の含有量を、甲1発明における含有量の範囲内で検討し、 5 「20〜25質量%」としたことは、当業者における設計事項であると認められる。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 イ 被告は、前記第3の2〔被告の主張〕?イのとおり、甲1発明におけるノニオン界面活性剤成分を本件発明1の(G)成分に置き換える動機付け10 がない旨主張する。 しかし、甲1発明のNI(7EO)と、本件発明1の(G)成分の式(II)で表される化合物とは、一般式において共通し、R 4(炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素)の部分においてのみ異なるが(前記2?イ) 炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素は、 、 甲115 発明のNI(7EO)のRである「C12からC15のアルキル鎖」に包含されるものであることが明らかであり、かつ、天然アルコール由来の炭化水素と合成アルコール由来の炭化水素とで、いずれか一方が他方よりも衣料用洗浄剤の組成物に適しているとの技術常識があるとは認められないから(前記?ア、ウ)、甲1発明のNI(7EO)において、「C12か20 らC15のアルキル鎖」の原料として、天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)を選択する動機付けがなかったとはいえず、相違点2に係る構成を想到し得ないとも解されない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 ウ 被告は、相違点1に関し、甲1発明において(C)成分の含有量を特定25 することによって本件各発明に係る特定の洗浄剤組成物に至る動機付けはないと主張する。 46この点、甲1発明において(C)成分に相当する成分であるMGDA(Trilon M)について、甲1は、製剤の抗菌効果を向上させる添加剤の一つであるとしており(別紙3「文献の記載」1?)、MGDAのような添加剤の使用はDCPPによる殺菌効果を高めるものであると記載して5 いる(別紙3「文献の記載」1?)。 そうすると、甲1発明において、DCPPによる殺菌効果ないし抗菌効果を高め、臭気の抑制効果を高めるのに十分となるように、その含有量を甲1発明の範囲(0.1〜5wt%)内で設定し、0.1ないし1.5質量%にすることは当業者が適宜なし得たことにすぎないというべきであ10 り、甲1発明の上記数値範囲の中から本件発明1の(C)成分の割合を選択する動機付けがないとはいえず、相違点1に係る構成を想到し得ないとも解されない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 エ 被告は、相違点3に関し、相違点3が設計事項にすぎないとはいえない15 とか、甲1発明においてA/C比を調整することによって本件発明1に係る特定の洗浄剤組成物に想到する動機付けはないなどと主張する。 しかし、上記ウのとおり、甲1の記載によれば、甲1発明において(C)成分に相当するものであるMGDAは、DCPPによる殺菌効果を向上させるための添加剤として配合され、その含有量の範囲が示されているので20 あるから、その含有量の範囲内で数値の範囲を選択することは、当業者の設計事項であるといえる。また、甲1発明には(A)成分に相当するアニオン界面活性剤が配合されているところ、甲31(別紙3「文献の記載」7)、甲33(別紙3「文献の記載」8)には、それぞれ別紙3「文献の記載」7及び8のとおりの記載が存在し、これらの記載によれば、アニオン25 界面活性剤は、衣類の洗浄の成分であり、他の成分による消臭効果を向上させる効果も有することが、本件出願日時点における技術常識であったと47認められるから、甲1発明のアニオン界面活性剤の含有量を、その洗浄等の効果を高めるのに十分なように、甲1発明における範囲内(合計で12〜32wt%)で検討することも、当業者の設定事項であるといえる。 そうすると、 (A)成分と(C)成分を甲1発明に記載の各含有量の数値5 範囲内で設定した結果として、A/C比を最小で2.4、最大で320(前記2?ア)の範囲内である「10〜100」とすることも、当業者にとって格別の創意工夫を要するとはいえず、当業者の設計事項であるといえるし、A/C比を「10〜100」とする動機付けがないともいえないから、 相違点3に係る構成を想到し得ないとは解されない。 10 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 オ 被告は、前記第3の2〔被告の主張〕?ウ、?及び?のとおり、本件発明1による効果は、甲1発明における相違点1ないし3に係る発明特定事項を適用した場合に奏するものとして当業者が予測することができた範囲を超える顕著なものであるから、容易想到性が否定される旨主張する。 15 本件発明1の効果、とりわけその程度が、予測できないものであるかについては、本件出願日当時、本件発明1の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から検討すべきである(最高裁平成30年(行ヒ)第69号令和元年8月20 27日第三小法廷判決・裁判集民事262号51頁参照)。 本件審決が述べるとおり、本件明細書に記載された本件防臭効果評価の実施例1ないし22の組成物のうち、本件発明1で規定された組成を充足するものは、実施例6、7、9ないし14及び20であるが(本件審決書51頁)、これらの実施例の防臭効果の評価結果は、実施例9が「2.3/25 〇」、実施例10が「1.4/◎」、実施例11が「1.2/◎」であるが、 それ以外の実施例は、評価値が2.6ないし3.4であり、いずれも判定48は「△」である。本件防臭効果評価における評価及び判定の基準(前記1?)からすれば、本件発明1の実施例に該当するものの防臭効果は、一定の効果が得られたことは認められるものの、実施例9ないし11を除き、 その効果が明らかに優れたものであるとはいえない。本件発明1の実施例5 に該当しない実施例の評価値は2.8ないし3.4であり、本件発明1の実施例に該当するものの評価が、該当しないものの評価よりも高い(防臭効果がより優れている)とも認められない。 実施例9ないし11のうち、実施例9は(D)成分(プロテアーゼ)が、 実施例10は(E)成分(硫酸亜鉛一水和物)が、実施例11は(D)成10 分及び(E)成分が、それぞれ配合されており、これらの成分が配合されたことによって、他の実施例よりも防臭効果が優れたものになったと考えられる。 以上によれば、本件発明1に規定された組成を充足する組成物である実施例の防臭効果の評価の結果をもって、本件発明1の効果が、本件各発明15 の構成が奏するものとして当業者が予測することのできなかったものである、あるいは当該構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものであるとは認められない。 すなわち、本件発明1による効果が、甲1発明における相違点1ないし3に係る発明特定事項を適用した場合に奏するものとして当業者が予測20 することができた範囲を超える顕著なものであるとは認められない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 ?ア 以上によれば、本件発明1の甲1発明に対する進歩性に関する本件審決の判断は誤りであり、本件発明1は、特許法29条2項により特許を受けることができない発明であると認められる。 25 イ 本件審決は、本件発明3ないし5について、これらの発明が、本件発明1を直接又は間接に引用し、さらに特定事項を加えたものであることを前49提として、本件発明1と同様、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない発明ではないと判断したが、本件発明1の進歩性に関する本件審決の判断が誤りであることは上記アのとおりであるから、本件発明3ないし5に関する上記判断も誤りである。 5 ウ よって、取消事由2は理由がある。 4 取消事由3(本件各発明のサポート要件違反の有無に関する判断の誤り)について? 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載され10 た発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。 15 ? 前記1?ウのとおり、本件各発明の課題は、衣類が湿った状態で菌が増殖しやすい環境においても、防臭効果に優れる衣料用洗浄剤組成物を提供することである。 ? 本件明細書においては、特定のアニオン界面活性剤と、フェノール型抗菌剤と、アミノカルボン酸型キレート剤とを組み合わせることにより、上記本20 件各発明の課題を解決できることが見出されたことが示されている(段落【0005】 。 )そして、本件明細書に記載された本件防臭効果評価では、本件発明1に規定された組成を充足する組成物も実施例の一部で用いられている。本件防臭効果評価の方法は前記1?のとおりであり、衣類が湿った状態で菌が増殖し25 やすい環境における試験条件であると認められる。本件発明1に規定された組成を充足する組成物の防臭効果の評価結果は、前記3?オのとおりであり、 50(D)成分又は(E)成分が含有されていないものも含め、一定の防臭効果が得られたことが認められる。 したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、本件発明1は、当業者が前記?の課題を解決できると認識できる範囲のものであり、か5 つ、発明の詳細な説明に記載されたものといえる。 また、本件発明3ないし5は、本件発明1を直接又は間接的に引用し、さらに特定事項を加えたものであるから、本件発明1と同様、上記?の本件各発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 ? 原告の主張に対する判断10 ア 原告は、前記第3の3〔原告の主張〕?のとおり、本件各発明は、本件各発明の課題を解決できると認識することのできないものであると主張する。 しかし、本件発明1の実施例に該当するものの防臭効果が、 「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度であったとしても、一定の防臭効果が15 得られたことは、本件防臭効果評価の結果によって認められる。 (E)成分を配合した実施例10及び11は、他の実施例に比べてさらに優れた防臭効果が得られているが(前記3?オ) (E)成分を含有しない本件発明1、 の実施例についても一定の防臭効果が得られたといえる。 そうすると、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであったとは20 いえないものの(前記3?オ) サポート要件違反の有無についてみれば、 、 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、本件発明1は、当業者が前記?の課題を解決できると十分に認識できる範囲のものであり、かつ、 発明の詳細な説明に記載されたものということができる。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 25 イ 原告は、前記第3の3〔原告の主張〕?のとおり、本件明細書からは、 本件発明1の(C)成分としてメチルグリシン二酢酸三ナトリウム(MG51DA)以外を用いた場合についてサポートされているとは認められないと主張する。 この点、本件防臭効果評価において本件発明1で規定された組成を充足する組成物の実施例(実施例6、 9ないし14及び20)7、 は全て、 (C)5 成分としてC−1:メチルグリシン二酢酸三ナトリウムが用いられている。 しかし、 (C)成分はアミノカルボン酸型キレート剤であるところ(本件明細書の段落【0019】 、式(c1)で表される化合物の中ではメチル)グリシン二酢酸三ナトリウム(MGDA)が特に望ましいとされているが(段落【0022】 、その他にも、式(c1)中、A、M、nがメチルグ)10 リシン二酢酸三ナトリウムと異なるものも用い得る旨の記載がされている(段落【0021】 【0022】 。 、 )また、甲13(別紙3「文献の記載」9)には、別紙3「文献の記載」9のとおりの記載が存在するところ、この記載からは、式(c1)で表される化合物が広く洗浄剤組成物におけるキレート剤として好適に用いら15 れることが理解される。甲17(別紙3「文献の記載」10)及び甲18(別紙3「文献の記載」11)には、それぞれ別紙3「文献の記載」10、 11のとおりの記載が存在し、これらの記載からも上記同様の理解を得ることができる。 したがって、式(c1)で表される化合物については、A、M、nがメ20 チルグリシン二酢酸三ナトリウムの場合の数値である場合に限らず、キレート剤としての作用効果を奏することは、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。 また、本件防臭効果評価の比較例で用いられた(C−3)成分(クエン酸三ナトリウム)を用いた比較例の防臭効果が各実施例より劣っているこ25 とをもって、式(c1)で表される化合物がメチルグリシン二酢酸三ナトリウムとわずかでも異なれば防臭効果が異なってくるとか、式(c1)の52nの数が多くなると防臭効果が得られなくなると認められることにはならない。 以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明及び本件出願日当時の技術常識に照らし、本件明細書に接した当業者は、本件発明1の(C)成分5 としてメチルグリシン二酢酸三ナトリウム以外を用いた場合であっても、 本件発明1は前記?の課題を解決することができると認識すると認められる。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ウ 原告は、前記第3の3〔原告の主張〕?のとおり、本件発明1の(G)10 成分に関し、G−1(椰子脂肪酸)を含まない場合についてまでサポートされているとは認められないと主張する。 しかし、甲19(別紙3「文献の記載」12)及び甲20(別紙3「文献の記載」13)には、それぞれ別紙3「文献の記載」12及び13のとおりの記載があり、これらの記載によれば、衣料用洗浄剤において、抑泡15 やすすぎ性の向上のための泡コントロール剤として、椰子脂肪酸などの脂肪酸が少量添加されることは、本件出願日当時における技術常識であったと認められる。 そうすると、本件防臭効果評価において本件発明1で規定された組成を充足する組成物の実施例が全てG−1(椰子脂肪酸)を含んでいるとして20 も、本件明細書に接した当業者は、上記技術常識に基づき、椰子脂肪酸が本件発明1の課題の解決のために必要な成分ではないことを理解すると認められる。 原告が指摘する甲12は、著者が明らかでないインターネット上のブログの記載と認められ、その記載の内容が本件出願日当時の技術常識である25 と認めることはできない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 53? 以上によれば、取消事由3は理由がない。 5 結論以上のとおりであり、取消事由1及び3は理由がないが、取消事由2は理由があり、本件審決のうち、特許第6718777号の請求項1及び3ないし55 に係る部分は取り消されるべきものであって、原告の請求は認容されるべきである。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部10裁判長裁判官東 海 林 保15裁判官20 今 井 弘 晃25 裁判官水 野 正 則54(別紙1審決書写し、別紙2特許公報写し省略)55別紙3文献の記載1 甲 1 ( IP.com, Biocidal Compositions containing 4,4’-dichloro 2-hydroxy5 diphenylether (DCPP), The IP.com Journal, IPCOM000213522D、2011年(平成23年)12月20日)? 「4,4’−ジクロロ2−ヒドロキシジフェニルエーテル(DCPP)を含有する抗菌組成物抗菌化合物4,4’−ジクロロ2−ヒドロキシジフェニルエーテル(DCPP)10 は、洗浄剤および消毒剤に配合することができます。これらは、硬質表面の洗浄製品、洗濯用洗剤、布地用コンディショナー、手洗い食器洗い製品、硬質表面の消毒および除菌用製品、万能クリーナー、床用クリーナー、ガラスクリーナー、キッチンクリーナー、バスクリーナー、衛生クリーナー、布地の衛生リンス製品、カーペットクリーナー、家具クリーナー、さらには硬質および軟質15 の表面の調整、シール、ケアまたは処理用製品であり得ます。 それらの洗浄及び殺菌製品は、固体、粉末、顆粒、ケーキ、バー、錠剤、液体、ペースト又はゲルであることができる。また、すぐに使用できる製品である場合もあれば、洗浄、洗濯、処理、調整工程の前または最中に希釈される濃縮物である場合もあります。 20 DCPPを含むこれらの洗浄および消毒製品の目的の中には、製品で処理される硬質および軟質表面上の細菌、真菌、酵母、ウイルス及び藻類のような微生物の死滅、制御および/または増殖の抑制が含まれる。DCPPはまた、これらの表面上の前述の微生物の代謝を操作するという意味でも利点を有し、その結果、臭気を抑制する可能性がある。殺生物効果又は抗菌効果は、処理され25 た物品および/または表面が洗浄/殺菌製剤またはその希釈液と直接接触しているときに起こり、処理期間内に終了する即効性であり得る。しかし、抗菌効56果は、適用後、処理された表面で起こり続ける、より長い持続的な効果であることもできる。以下では、この段落で言及されたこれらの効果すべてを指すために、 『抗菌効果』という語句を用いることにする。 (1頁1〜25行、 「甲第1号証の抄訳」1、2頁)5 ? 「これらの言及された洗浄及び抗菌製品において、DCPPは、DCPPの抗菌効果を強化、改善、延長、復元、増強、支持、加速又は拡大するため、又は製品中のDCPP活性分子を安定化するために、さらなる化学物質、製品、 混合物及び/又はポリマー(下記c−fを参照)と組み合わせることができる。 DCPP活性分子の安定化とは、例えば、洗浄製品中のDCPP自体の化学分10 解の抑制、DCPPを含む製品の変色の抑制、またはDCPPを有する洗浄製品の不快な臭いの抑制を意味する。 ここで開示されているのは、すなわち、以下成分を含む第1段落に記載の洗浄及び消毒剤製品である。 (a)0.01−10% DCPP15 (b)0−80%、例えば0.5−20%の1種以上の界面活性剤(c)0−50%、例えば0.1−10%の1種以上のハイドロプロピック剤(d)DCPPに加え、0−50%、例えば0.01−20%の1種以上の殺菌活性物質(e)0−50%、例えば0.1−20%の、洗浄または殺菌製品の抗菌効果20 を改善し得る1種以上のさらなる添加剤(f)0−10%、例えば0.001−5%の、組成中の活性DCPPを安定化させることができる1種以上の薬剤を含む。 以下、 (b)〜(f)の成分の例について説明する。(3頁10〜29行、 」 「甲第1号証の抄訳」2、3頁)25 ? 「(b)界面活性剤界面活性剤(b)は、通常、アニオン性、カチオン性、ノニオン性又は両性57であってよい少なくとも1種の界面活性剤からなる。 アニオン性界面活性剤は、例えば、硫酸塩、スルホン酸塩、カルボン酸塩の界面活性剤またはそれらの混合物であることができる。しばしば用いられるのは、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸5 塩、オレフィンスルホン酸塩、脂肪酸塩、アルキルおよびアルケニルエーテルカルボン酸塩または α−スルホン脂肪酸塩またはそのエステルである。 しばしば用いられるスルホン酸塩は、例えば、アルキル基中に10〜20個の炭素原子を有するアルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル基中に8〜18個の炭素原子を有するアルキル硫酸塩、アルキル基中に8〜18個の炭素原子10 を有するアルキルエーテル硫酸塩、椰子油または獣脂から得られ、以下を有する脂肪酸塩である。 アルキル部分の炭素原子数は8〜18個である。アルキルエーテル硫酸塩に添加されるエチレンオキサイド単位の平均モル数は、1〜20であり、好ましくは1〜10である。アニオン性界面活性剤におけるカチオンは、アルカリ金15 属カチオンが好ましく、特にナトリウムまたはカリウム、より好ましくはナトリウムである。好ましいカルボキシレートは、式R 19 ’−CON(R 20’)CH 2COOM 1、ここでR 19’はC9 −C17 アルキルまたはC 9 −C17 アルケニル、R20 ’ はC1 −C4 アルキル、M 1 はアルカリ金属、特にナトリウムのサルコシン酸塩である。 20 ノニオン性界面活性剤は、例えば、第1級または第2級アルコールエトキシレート、特に、アルコール基当たり平均1〜20モルのエチレンオキシドでエトキシル化されたC 8 −C 20 脂肪族アルコールであり得る。アルコール基当たり平均1〜10モルのエチレンオキシドでエトキシル化された第1級および第2級C 10 −C 15脂肪族アルコールがより好ましい。非エトキシル化ノニオン性25 界面活性剤、例えばアルキルポリグリコシド、グリセロールモノエーテルおよびポリヒドロキシアミド(グルカミド)も同様に使用することができる。 58アニオン性及び/又はノニオン性界面活性剤に加えて、組成物はカチオン性界面活性剤を含んでもよい。可能なカチオン性界面活性剤には、すべての一般的なカチオン性表面活性化合物、特に織物柔軟化効果を有する界面活性剤が含まれる。 (3頁30行〜4頁17行、 」 「甲第1号証の抄訳」4、5頁)5 ? 「(d)さらなる殺菌活性分子・・・JMアクティケアのような銀化合物、または例えばクエン酸銀(Tinosan SDC ?)のような有機銀複合体、または銀ゼオライトや銀ガラス化合物(例えばイルガガードB500、イルガガードB6000、イルガガードB7000)等、 (WO−A−99/1879、EP1041879B1)に10 記載の無機銀複合体等;Cu、Zn、Sn、Au等の金属の無機または有機複合体・・」(5頁26行、7頁34〜39行、「甲第1号証の抄訳」5頁)? 「(e)製剤の抗菌効果を向上させるさらなる添加剤・・・他の添加剤(e)は、金属キレート剤および錯化剤からなり、例えば、 EDTA、NTA、アラニン二酢酸またはホスホン酸、エチレンジアミン四酢15 酸(EDTA) β−アラニン二酢酸、 (EDETA) ホスホンメチルキトサン、 、 カルボキシメチルキトサン、ヒドロキシエチレンジアミン四酢酸、ニトリル三酢酸(NTA)およびエチレンジアミン二酢酸(S,S−EDDS、R,R−EDDSまたはS,R−EDDS)、トリポリリン酸塩、ポリカルボン酸塩、有機リン酸塩、アミノアルキレンポリ(アルキレンホスホン酸)、MGDA(Tr20 ilon ? M、BASF)、Dissolvine ? GL(AKZO)などのアミノ酸アセテートの他、ベイピュア ? CX(Lanxess)などのアスパラギン酸誘導体などである。(7頁41行、8頁3〜12行、 」 「甲第1号証の抄訳」6頁)? 「処方例25 以下のとおり殺菌性製品の組成物(I〜LXII)が開示されている。以下、 各製剤(I〜XXV)について、各組成番号ごとに、その組成、製造情報、技59術情報、および抗菌性または殺生物性活性を記載する。製剤(I〜XXV)において、Tinosan ? HP100は、DCPP30%と1,2−プロピレングリコール70%との混合物である。」(9頁10〜15行、 「甲第1号証の抄訳」6、7頁)5 ? 「抗菌性液体洗濯洗剤の処方XLIX〜LII(数値は処方中のwt%)これらの組成物において、酵素は純酵素のパーセントで示される。NI(7EO)はR−(OCH 2 CH 2)nOHを指すところ、このRはC12からC15のアルキル鎖であり、n=7である。NaLASは直鎖アルキルベンゼスルホ10 ン酸塩(LAS)を、SLES(3EO)はC 12 −C18 のアルキルポリエトキシレート(3.0)硫酸塩を、SDSはドデシル硫酸塩ナトリウムを指す。 これらの液体洗剤組成物XLIX〜LIIは、例えば肺炎桿菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌および大腸菌に対して、AATCC 100−2004法に従って評価すると、処理した繊維(綿、ポリエステル、ナイロン、ウールな15 ど)に対して非常に優れた長期にわたる抗菌効果を示す。 (36頁1行〜最終」行、「甲第1号証の抄訳」7、8頁)60? 「添加物による向上効果・・・(XXXIV)0.025% DCPP、35% 1,2−プロピレングリコール、3.13% MGDA(Trilon ? M、有効成分40%、BASF、納品時に使用)、水で100%にメスアップしpH=8.0になるように5 クエン酸で調整した抗菌・殺菌性混合物処方XXXIIIとXXXIVは全て80%濃度でEN1276殺菌試験(洗浄条件(0.03%アルブミン) 5分接触、 、 室温、緑膿菌ATCC15442)を行った。処方XXXIIIは2logのLOG減少を示し、処方XXXIVは5log以上のLOG減少を示した。従って、MGDAのような添加剤の使10 用はDCPPによる殺菌効果を高めるものである。 (31頁下から7行、下か」ら3行〜32頁6行、「甲第1号証の抄訳(追加分) )」2 甲10(大矢勝、界面活性剤とは[7]:AE(アルコールエトキシレート)、 2006年(平成18年)9月24日)15 「アルコールエトキシレート(Alchol Ethoxylates,略称AE)はLASと並んで大量に使用されている非イオン界面活性剤です。 ? AEの化学構造AEは一般にR−O−(CH 2 CH 2 O) n −Hの化学式で表されますが、これは第1級AEと呼ばれるタイプです。この界面活性剤はアルキル基の鎖長と20 エチレンオキサイド(CH 2CH 2 O)の付加モル数で非常に多種類のものが製造されます。 一般の洗剤に含まれるものはアルキル基がC12〜C15を主体とし、エチレンオキサイドの付加モル数の平均値が3〜10程度のものが欧州では商業的に重要度の高いものになっており、生態影響評価においては、アルキル基の炭25 素数13.3、エチレンオキサイド付加モル数8.2に標準化して毒性を評価しています。日本では炭素数12〜15のAEがPRTR法の第一種指定化学61物質になっています。 原料として油脂由来の高級アルコールと石油由来の高級アルコールが利用されます。油脂由来の高級アルコールは、油脂を加水分解して脂肪酸または脂肪酸エステルを高圧・高温条件下で水素で還元して得られます。アルキル基は直5 鎖型で、水酸基はアルキル基の末端につながります。天然物由来の高級アルコールは不飽和のオレイルアルコールを含んでいたり、炭素数の大部分が偶数であることが特徴です。天然物由来の脂肪酸の炭素数は、その殆どが偶数であるためです。 石油由来の高級アルコールは、製造法によりチーグラーアルコール、オキソ10 アルコール、そして第2級アルコールがあります。チーグラーアルコールは構造的に天然由来の高級アルコールと同様で、直鎖型で端末に水酸基を有します。 オキソアルコールは炭素鎖の途中にメチル基(−CH 3 )の分岐がある構造です。第2級アルコールは−O−(CH 2CH 2O) n −Hの部分がアルキル基の途中につながって一箇所だけ枝分かれのある形になったタイプを指します。 15 以前は石油由来の高級アルコールが油脂由来の高級アルコールよりもかなり安価でしたが、最近はその価格差が少なくなり、天然油脂由来の高級アルコールが多く用いられるようになってきました。 (1頁左欄1行〜右欄11行)」3 甲11(平成18年度NEDO成果報告資料−アルコールエトキシレート詳細20 リスク評価書−、2007年(平成19年)4月27日、要約−0〜3頁)? 「本書は、アルコールエトキシレート(以後「AE」と略す、別名「ポリオキシエチレンアルキルエーテル」)に関する詳細リスク評価の成果をまとめたものである。 (要約−1頁5〜6行)」? 「2.生産と流通に関する情報25 AEの生産量は2002年から増加する傾向にあり、2003年の生産量(他物質の誘導体原料としての分も含む)は約17万 t で、非イオン系界面活性剤62の3割強を占めている。また、化管法指定範囲のC12〜15の同族体群の流通量は、全AE流通量の6〜8割を占めている。 (要約−3頁8〜11行)」? 「4.国内市販洗浄剤に含まれるAE同族体組成本詳細リスク評価のために実施したAE同族体組成の委託調査の結果、洗浄5 剤製品ごとにAEの同族体組成は異なっていた。また、一般家庭での使用率が高い洗浄剤製品中には、C12〜15EO0〜15の範囲の同族体が多く配合されており、その殆どが偶数のC鎖を持つものであることが分かった。 (要約」−3頁20〜23行)10 4 甲14(加藤秋男編著、パーム油・パーム核油の利用、初版第1刷、1990年(平成2年)7月31日、株式会社幸書房、212〜215頁)「天然の油脂を構成する脂肪酸あるいはアルコールの特徴は、偶数の炭素からなる直鎖の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有することである。したがって、これらを原料として得られる天然高級アルコールも、偶数の炭素鎖を有している。 15 合成アルコールでも、エチレンを原料とするチーグラー法では、天然と同じ偶数の炭素鎖を有する直鎖で飽和の高級アルコールが得られるが、それ以外の方法では奇数あるいは分枝のアルキル基を含んだものしか得られない。 (212頁第1」1〜17行)20 5 甲36(特開平1−174599号公報)「成分B:エチレングリコールエーテル基を2〜4個有する直鎖状1級C 12 −C15 アルコールまたは2位にメチル分枝を有する相当するアルコール10〜15重量%、 成分C:エチレングリコールエーテル基を6〜8個有する直鎖状飽和1級C 1225 −C 15 アルコールまたは2位にメチル分枝を有する相当するアルコール4〜8重量%、 (702頁右上9〜16行)」63「成分Bは、アルコール基中に炭素原子を12〜15個有し、天然または合成のアルコール(オキソアルコール)から誘導し得る。 (702頁右下3〜5行)」「成分Cは、成分Bと同様のアルコールまたはアルコール混合物から誘導し、グリコールエーテル基を平均6.5〜7.5個有することが好ましい。 (702頁」5 右下11〜13行)6 甲37(橋本賀之、界面活性剤の環境配慮と新しい機能追求理想材料を追求するアプローチ、第一工業製薬社報 No.551 2010冬)「環境配慮型のアルコールエトキシレート(AE)は、天然由来またはオキソ法10 由来(主に2−メチル分岐体と直鎖体の混合物)の炭素数12〜15の高級アルコールにエチレンオキサイド(EO)を付加重合させて得られる製品が主流である。 (11頁左欄6〜10行)」7 甲31(洗剤・洗浄百科事典(新装版)、朝倉書店、2011年(平成23年)15 3月10日第2刷)「陰イオン界面活性剤は、衣料用や身体用の洗浄剤をはじめとして、最も多く用いられている界面活性剤である。 (70頁5〜6行)」8 甲33(特開2013−136682号公報)20 「【0016】<(A)成分>(A)成分は、アニオン界面活性剤である。 (A)成分を含有することで、被洗浄物に付着した汚れや臭気成分を良好に除去できると共に、消臭効果の向上が図れる。これは、繊維製品用洗浄剤が洗浄水に分散された洗浄液中で、 (A)成分が、 25 (B)成分と(C)成分とで形成された錯体を取り込むと共に、 (D)成分と会合体を形成し、この会合体が繊維製品に吸着することで、消臭効果を発揮するため64と考えられる。」9 甲13(特表2012−515827号公報)「【技術分野】5 【0001】本発明は、キレート剤のアルカリ土類金属塩、それを含む組成物、並びにそれに関する方法及び使用に関する。本発明は詳細には、良好な酸化安定性を与えるそのような塩、組成物、方法、及び使用に関する。 【0002】10 本発明は、詳細には漂白用途での使用における、重金属及び遷移金属のキレート剤に特に関する。 【背景技術】【0003】過酸化物及び過酸などの化合物を含む活性酸素系漂白組成物は、幅広い種類15 の用途において、例えば洗濯、食器洗浄、及び他の洗浄用組成物において;パルプ及び紙の漂白において;及びパーソナルケア組成物において、一般に使用される。」「【0026】好ましくは、キレート剤は、メチルグリシン二酢酸(MGDA)、グルタミ20 ン酸,N,N−二酢酸(GLDA,glutamic acid,N,N−diacetic acid)、・・・から選択される。・・・【0028】酸性キレート剤は、MGDA、GLDA、・・・から選択されるのが適切である。 25 【0029】好ましくは、酸性キレート剤は、MGDA、GLDA、・・・から選択され65る。 【0030】メチルグリシン二酢酸(MGDA)は式Iに示される構造を有する:【0031】5 【化1】【0032】MGDAはエナンチオマーか又はその混合物として存在してもよい。好ましくはこれはラセミ混合物として存在する。 10 【0033】グルタミン酸N,N−二酢酸(GLDA)は式IIに示される構造を有する:【0034】【化2】」1510 甲17(特表2017−536306号公報)「【0009】本発明は、水溶性洗浄用パウチ、すなわち洗浄組成物を収容するパウチを提供するものである。パウチは、単一の区画又は複数の区画を有することができる。 20 少なくとも1つの区画が液体組成物を含み、その液体組成物はアミノカルボン酸錯化剤を含む。錯化剤は、メチルグリシン二酢酸(MGDA)、グルタミン酸二66酢酸(GLDA)、それらの塩及びそれらの混合物から好ましくは選択される。・・・」11 甲18(特許第3889250号公報)5 「【0020】(a1)成分としては、分子内にCOOM基(MはH、Na、K、NH 4 )を2〜5個、好ましくは3〜5個有する化合物が挙げられる。中でも洗浄性能、環境適性の点で下記一般式(I)で表される化合物が好ましい。 【0021】10 【化1】【0022】〔式中、Rは−(CH 2 )n −Aであり、AはH、OH、COOMであり、MはH、 Na、K、NH 4、好ましくはNaであり、nは0〜5の数を示す。〕」1512 甲19(特開昭61−288000号公報)「本発明(c)成分である炭素数8〜20の脂肪酸は、飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸のどちらでもよく0.5〜3%配合される。この様な脂肪酸としてはラウリン酸を主成分とする椰子酸、オレイン酸を主成分とする牛脂脂肪酸、パーム脂肪20 酸が好ましい。 脂肪酸が0.5%未満ではすすぎ性に対する効果は見られず、3%を越えるとすすぎ性に寄与する効果は変らず、逆に洗濯時における起泡性を悪くするため好ましくない。」(744頁左上12〜右上2行)「本発明の液体洗剤組成物は・・・更に陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性67剤及び脂肪酸を特定量配合したことにより洗浄力は勿論、洗濯中には粉末洗剤に匹敵する豊かな泡立ちを示し、すすぎ時には速やかに泡が消えるという特徴を有する。」(745頁左下5〜14行)5 13 甲20(特許庁公報10(1998)−25〔7159〕周知・慣用技術集(衣料用粉末洗剤)、日本国特許庁、平成10年3月26日)「3.1.1.7 高級脂肪酸塩(石けん)(中略)【原料】10 ・脂肪酸・天然油脂(ヤシ油、牛脂、大豆油、パーム油、パーム核油、綿実油、豚脂等)・天然油脂由来の脂肪酸及びメチルエステル(中略)【物性/特性/特徴】15 (中略)・泡コントロール剤(すすぎ性、低泡性)として配合される。 【配合量】かつては、石けんを主基剤とする粉末洗剤も多く見られたが、cmcが高いため使用量が多くなる上に、低温溶解性や耐硬水性に劣るため、主用途は泡コント20 ロール剤として二次的に添加されることが多い。この目的では最大10%配合される。」(13、14頁)68 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
|